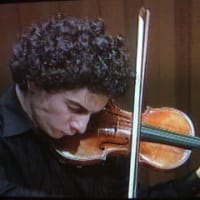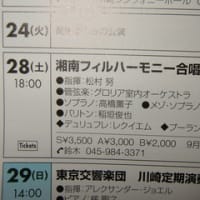先週の土曜日、生まれて初めてマンドリン・オーケストラというものをナマで聴いてきました。
マンドリン・オケというものが、果たして世の中にどの程度認知されているのか定かではないのですが、まず驚いたのが、会場が立ち見がでるほどの 満員御礼
満員御礼 だったこと。そして、オーケストラとも吹奏楽団ともまた違う、独特の“濃ゆい”ノリ(!)がスゴカッタ
だったこと。そして、オーケストラとも吹奏楽団ともまた違う、独特の“濃ゆい”ノリ(!)がスゴカッタ
曲目は、《劇場支配人序曲》(モーツァルト)、《世界名作劇場メドレー》、《白鳥の湖》より抜粋(チャイコフスキー)、などなど。全てマンドリン・オケ編曲版と、マンドリンオケ・オリジナルの曲です。
個人的には、前半のオケメンバー自作のマンドリンオリジナル曲と、後半の《世界名作劇場メドレー》、《白鳥の湖》の演奏がよかったです。
編成は、弦楽器から、1stマンドリン、2ndマンドリン、マンドラテナー、マンドロンセロ、クラシックギター、コントラバスの弦6部。
管・打は、フルート×2、ピッコロ×1、クラリネット×2、ティンパニ、ほか。
という編成でした。これがおおよそのマンドリンオーケストラの通常の形だそうです。
ヴァイオリン属(&ヴィオール属)の弦楽器の配置を少し拡大した感じですねー。変わりに管楽器の編成はかなりこぢんまりしてます。
マンドリンを弾く姿って、ヴァイオリン属やヴィオール属の弦楽器の弾き姿に比べると、アクション自体が少なく、個々の音量も小さく、全体的に見て地味ぃ~なイメージなんです。
このマンドリン奏者たちが、狭いステージに所せましと並んで、姿勢を前傾にして、ジィ~っとタクトに集中して、ピックで弦を書き鳴らす様は、なにか修行中の修行僧が念仏を唱えているような趣をかもし出していて、彼らの集中力とアツイ思いが客席のうしろまでビリビリ伝わってきたのでした。いやぁ~、この人達“青春”してるなぁ~と思いましたデスヨ
ワタシのとなりに座ってた叔母ちゃんなんか常連らしく、ノリノリで聴いておられました(後半の白鳥湖は飽きちゃったのかコックリコックリ眠りこけてましたが(笑))。
このマンドリンオーケストラというものを聴いて、つくづく思ったのが、マンドリンの表現力はかなり制約があるということ。
弦楽器とはいえ、マンドリンは撥弦楽器だから、我々ヴァイオリン属やヴィール属のように弦を“弓”で弾かない分、演奏の大半をトレモロで表現しなければいけない。つまり、我々弦楽器奏者よりも表現のパレットがかなり限定されているのです(弦楽器は、ボーイングによる奏法のほかに、ボウを利用した特殊奏法(例えば、コルレーニョなど)、ピッツィカートで撥弦楽器の奏法もできるし、重音奏法もありますし、その他の特殊奏法もがくさんあります)。
でも、逆に表現の制約があるからこそ、奏者はその制約のなかで多彩な響きを創造して、そして、聴き手も奏者のイマジネーションに呼応して無限の想像力を膨らませるもの。これが、曲に深く没入できるというか、団員が一体になって演奏ができていた秘訣なのではないかと思いました。
社会人オケのはずなのに、まるで高校生の吹奏楽バンドの演奏を聴いているかのような、一生懸命さがヒシヒシと伝わってきましたしね
団員の方々はだいたい20代後半~40代くらいの方々が多いように見えましたが、彼らが一生懸命音楽に青春している様子は、うらやましいことだなぁと素直に思ってしまいましたよ。
ただ、ひとつ思ったのは、管楽器の編成が少し薄かったかなぁと。
いろいろと事情があるのでしょうが、欲を言えば、せめてオーボエは編成に入れて欲しかったなぁと思いました。白鳥の湖の情景のシーンでの有名なオーボエ・ソロもそうですが、他の曲でもオーボエがあるだけでかなり違うのではないかと正直思いました。
マンドリン・オケというものが、果たして世の中にどの程度認知されているのか定かではないのですが、まず驚いたのが、会場が立ち見がでるほどの
 満員御礼
満員御礼 だったこと。そして、オーケストラとも吹奏楽団ともまた違う、独特の“濃ゆい”ノリ(!)がスゴカッタ
だったこと。そして、オーケストラとも吹奏楽団ともまた違う、独特の“濃ゆい”ノリ(!)がスゴカッタ
曲目は、《劇場支配人序曲》(モーツァルト)、《世界名作劇場メドレー》、《白鳥の湖》より抜粋(チャイコフスキー)、などなど。全てマンドリン・オケ編曲版と、マンドリンオケ・オリジナルの曲です。
個人的には、前半のオケメンバー自作のマンドリンオリジナル曲と、後半の《世界名作劇場メドレー》、《白鳥の湖》の演奏がよかったです。
編成は、弦楽器から、1stマンドリン、2ndマンドリン、マンドラテナー、マンドロンセロ、クラシックギター、コントラバスの弦6部。
管・打は、フルート×2、ピッコロ×1、クラリネット×2、ティンパニ、ほか。
という編成でした。これがおおよそのマンドリンオーケストラの通常の形だそうです。
ヴァイオリン属(&ヴィオール属)の弦楽器の配置を少し拡大した感じですねー。変わりに管楽器の編成はかなりこぢんまりしてます。
マンドリンを弾く姿って、ヴァイオリン属やヴィオール属の弦楽器の弾き姿に比べると、アクション自体が少なく、個々の音量も小さく、全体的に見て地味ぃ~なイメージなんです。
このマンドリン奏者たちが、狭いステージに所せましと並んで、姿勢を前傾にして、ジィ~っとタクトに集中して、ピックで弦を書き鳴らす様は、なにか修行中の修行僧が念仏を唱えているような趣をかもし出していて、彼らの集中力とアツイ思いが客席のうしろまでビリビリ伝わってきたのでした。いやぁ~、この人達“青春”してるなぁ~と思いましたデスヨ

ワタシのとなりに座ってた叔母ちゃんなんか常連らしく、ノリノリで聴いておられました(後半の白鳥湖は飽きちゃったのかコックリコックリ眠りこけてましたが(笑))。
このマンドリンオーケストラというものを聴いて、つくづく思ったのが、マンドリンの表現力はかなり制約があるということ。
弦楽器とはいえ、マンドリンは撥弦楽器だから、我々ヴァイオリン属やヴィール属のように弦を“弓”で弾かない分、演奏の大半をトレモロで表現しなければいけない。つまり、我々弦楽器奏者よりも表現のパレットがかなり限定されているのです(弦楽器は、ボーイングによる奏法のほかに、ボウを利用した特殊奏法(例えば、コルレーニョなど)、ピッツィカートで撥弦楽器の奏法もできるし、重音奏法もありますし、その他の特殊奏法もがくさんあります)。
でも、逆に表現の制約があるからこそ、奏者はその制約のなかで多彩な響きを創造して、そして、聴き手も奏者のイマジネーションに呼応して無限の想像力を膨らませるもの。これが、曲に深く没入できるというか、団員が一体になって演奏ができていた秘訣なのではないかと思いました。
社会人オケのはずなのに、まるで高校生の吹奏楽バンドの演奏を聴いているかのような、一生懸命さがヒシヒシと伝わってきましたしね

団員の方々はだいたい20代後半~40代くらいの方々が多いように見えましたが、彼らが一生懸命音楽に青春している様子は、うらやましいことだなぁと素直に思ってしまいましたよ。
ただ、ひとつ思ったのは、管楽器の編成が少し薄かったかなぁと。
いろいろと事情があるのでしょうが、欲を言えば、せめてオーボエは編成に入れて欲しかったなぁと思いました。白鳥の湖の情景のシーンでの有名なオーボエ・ソロもそうですが、他の曲でもオーボエがあるだけでかなり違うのではないかと正直思いました。