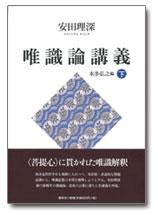すっかり忘れては、ふと思い出すこと。
婚約のとき、夫は結納返しとして懐中時計を所望しました。
名古屋の百貨店を何軒かまわって、品物を決めましたが、
その後で私はひそかに時計の蓋の裏に文字を彫ってもらうように注文しました。
文字はすでに決めてありました。
compassion
9.11のテロ事件のとき、私は1年間佛教大学の専攻科に在籍していました。
事件後の授業で、水谷幸正先生が黒板に書かれた「同悲」という言葉が
とても心にのこりました。
佛大では、私は仏教看護(ビハーラ)を学んでいて、そこでは仏教や哲学の授業もあれば、医学概論という名前の授業やカウンセリングやターミナルケア、病院実習の授業もありました。
(実習で棺桶の中に入ったこともあります。)
学んでいくうちに、
人は自分のこと(気持ち)がわかってもらえた、と感じられたときに(現実世界は変わらなくても)救われた気持ちになるんだな…
ということに気がつきました。
そして、もしかしたら法藏菩薩という人は、すべての人の苦しみや悲しみを知ろう、共にしようとする、という方法で救う人なのかもしれないな、と思いました。
でも、頭ではそのように理解しても
現実にはそのような行動が私にはできません。
できないけれど、忘れてはいけない。
そう思って、最も私が忘れやすいことを 文字として刻み込もうと思ったのでした。

しばらく前に、「話をしたい」とある人から訪問を受け、
何も返事ができないままになっていることが気になっています。
「わかるよ、わかるよ、そういうの。」
「本当につらかったね。」
そう言ってあげられるといい、と頭ではわかっていても
話を聞いて「ふうん。。。それで?」と思ってしまうと、そういう言葉が出てこないのです。
どうして、人の話を重く受け止められないのだろう…??
私の心のヒダは平たん過ぎて、言葉が滑っていってしまいます。
他にも、気になる人がいます。
知人のyasuさんが入院中だということはわかりましたが、様子がわかりません。
おそらく原因のよくわからない痛みに悩まされているのだと推測しています。
前者の人も倒れるほどの疲労があったそうです。
身体の痛み等、そして理解者のいない苦しみ…
辛さはさらに増してしまうのでしょう。
痛みという症状は不思議です。
現実にあるはずなのに、数値ではあらわせないし、人と比較もできません。
婚約のとき、夫は結納返しとして懐中時計を所望しました。
名古屋の百貨店を何軒かまわって、品物を決めましたが、
その後で私はひそかに時計の蓋の裏に文字を彫ってもらうように注文しました。
文字はすでに決めてありました。
compassion
9.11のテロ事件のとき、私は1年間佛教大学の専攻科に在籍していました。
事件後の授業で、水谷幸正先生が黒板に書かれた「同悲」という言葉が
とても心にのこりました。
佛大では、私は仏教看護(ビハーラ)を学んでいて、そこでは仏教や哲学の授業もあれば、医学概論という名前の授業やカウンセリングやターミナルケア、病院実習の授業もありました。
(実習で棺桶の中に入ったこともあります。)
学んでいくうちに、
人は自分のこと(気持ち)がわかってもらえた、と感じられたときに(現実世界は変わらなくても)救われた気持ちになるんだな…
ということに気がつきました。
そして、もしかしたら法藏菩薩という人は、すべての人の苦しみや悲しみを知ろう、共にしようとする、という方法で救う人なのかもしれないな、と思いました。
でも、頭ではそのように理解しても
現実にはそのような行動が私にはできません。
できないけれど、忘れてはいけない。
そう思って、最も私が忘れやすいことを 文字として刻み込もうと思ったのでした。

しばらく前に、「話をしたい」とある人から訪問を受け、
何も返事ができないままになっていることが気になっています。
「わかるよ、わかるよ、そういうの。」
「本当につらかったね。」
そう言ってあげられるといい、と頭ではわかっていても
話を聞いて「ふうん。。。それで?」と思ってしまうと、そういう言葉が出てこないのです。
どうして、人の話を重く受け止められないのだろう…??
私の心のヒダは平たん過ぎて、言葉が滑っていってしまいます。
他にも、気になる人がいます。
知人のyasuさんが入院中だということはわかりましたが、様子がわかりません。
おそらく原因のよくわからない痛みに悩まされているのだと推測しています。
前者の人も倒れるほどの疲労があったそうです。
身体の痛み等、そして理解者のいない苦しみ…
辛さはさらに増してしまうのでしょう。
痛みという症状は不思議です。
現実にあるはずなのに、数値ではあらわせないし、人と比較もできません。