愛新覚羅溥儀
最後の皇帝・ラストエンペラー
プロローグ
1967年10月の新聞に、元満州国皇帝・愛新覚羅溥儀の死亡記事がその簡単な略歴と共に小さく載った。当時を知る者にとっては、感慨深いものがある。彼こそ、清王朝最後の皇帝ラストエンペラーである。今世紀の初頭、僅か三歳で皇帝の地位に就いた溥儀は、革命で追われ、その姿を消していた。歳月が流れ、やがて日本軍が撮ったフィルムに登場した溥儀に、世界はアット驚いた。
1934年 3月(昭和9年)、現在の中国東北部に忽然と出現した幻の帝国・満州国の皇帝として彼が復活したからである。しかし、その後の彼を待っていたのは、関東軍や女スパイ川島芳子の暗躍する日本の謀略と数奇な命運であった。太平洋戦争での日本の敗戦で再び皇帝の座を追われた溥儀の行方は多くの謎を残しながら、歴史の波間に消えて行った。
その後の消息の一端は、彼が名前の代わりに呼ばれていた『981』と言う囚人番号が、如実に物語っている。そして彼が最後に漸く手にした人生とはどんな物であったのか? 1998年 5月、一人の女性が始めてカメラの前に立っ。彼女こそ、最後の皇帝ともう一つの人生を送り、彼の最後を看取った皇帝最後の妻(五人目)『李淑賢』である。彼女は、その夫に関して『彼は過去の、なんでも手にすることの出来た皇帝の暮らしより、貧しくても夫婦共稼ぎの平凡な生活を幸せと感じていた』と証言している。
君臨し、崇拝され、そして裏切り者の汚名を着ながら、二十世紀最大のミステリーを生きたラストエンペラー、歴史の荒波に押し流された果てに、彼が見た真実の人生とは?
1946年 8月、終戦直後の極東軍事裁判で、連合国側の証人として出廷した人物に、内外の報道陣はどよめいた。その証人は『溥儀、本来の満州国の名は愛新覚羅』と名乗った。抑留先のソ連から、連合国側の証人として連れてこられたのである。『私は1909年に、中国皇帝の地位に就きました。…』に始まり、日本の戦争犯罪を証言した溥儀は、遠くを見つめる目差しで、自分の背負わされた運命を辿っているようであった。
[1]運命の前半生
今世紀の幕開けを迎えた清朝の宮廷・紫禁城の奥の院で、一人の奇怪な老婆がその落日を眺めて居た。アヘン戦争以来の中国は、欧米の列強に浸食され、1895年には小国の日本との日清戦争にも敗れ、南からは革命の予兆が伝わって来る、落日はあたかも三百年に及ぶ清朝そのものの様であった。人々がその名を口にすることさえ恐れ慄いたこの老婆こそ、かの恐怖の女帝『西太后』である。しかし、さしもの女帝も寄る年波には勝てなかった。病に伏し、死を悟った彼女に残されたのは、後継者を自ら指名する事であった。 その運命に当たったのは、同じ満州族の血を引き、西太后のかっての愛人であった側近 『永録』の孫『溥儀』三歳であった。その日、いきなり親元から引き離された三歳の乳飲み子は、泣き叫ぶのも構わず輿に乗せられ、死の間際の西太后の前に召し出された。その僅か二日後に西太后の命運は74歳で尽きる。玉座に押し上げられた男の子は、黄昏行く王朝の運命を背負わされたのである。1908年(明治41年)三歳の皇帝即位であった。
紫禁城、高い城壁に囲まれた城内は、二十を越える宮殿、八千を越える部屋があり、多くの家臣たちの仕える富と権力の象徴である。その玉座に座る者は天子であり、神でもあった。しかし、この王朝にも崩壊の日がやてきた。1911年(明治44年)の『辛亥革命』である。君子制打倒を叫ぶ『孫文』らの革命運動は全国に飛び火し、遂に1912年、共和制による新国家『中華民国』の建国を宣言した。この辛亥革命によって、清王朝が地上から消えたのは、皇帝溥儀、五歳の事である。 だが、奇妙な事に革命のうねりは紫禁城には及ばず、皇帝の地位は存続していた。それは市民の間に皇帝への畏敬の念が根強かったので、混乱を避けるためであった。そのため城内は、歴史の空白のように幼い溥儀の下に千人の家臣が仕え、古来からの儀式や祭りごとが続いていたのである。
物心付いた溥儀が最初に覚えた事は命令することであった。一言、腹が空いたと言えば、二百人の料理人が腕を振るい、銀の器に山海の珍味が並べられ、外に行きたいと言えば即座に輿が用意された。毎日衣服が新調され、ボタンも靴紐も自分ですることはなく、便器を持参するだけの召使も居た。彼の日課は、退屈な儀式をしたり、宮殿を巡って母や祖母に挨拶することであった。後に彼は『私には大勢の母がいたが、母性愛と言うものを私は知らなかった』と言っているが、母と呼ばされていたのは、先代や先々代の未亡人、側室等である。つまり大后や大姉たちであった。溥儀が唯一感情を通わせたのは、九歳まで毎晩添い寝し、幼い頃は乳を飲ませてくれた乳母の『王焦氏』だけである。
しかし、溥儀九才の時、この安らかな感情も奪われる。大后たちが、授乳の奴隷にすぎない乳母に、皇帝が肩入れするのを恐れて、追放したのである。
これ以後、彼が覚えたのは家臣に当たり散らし、折檻する事であった。彼は愛情に飢えていたのであるが、皇帝の権威を振るうことしか感情の捌け口を知らないため、下の者に対して怒りっぽくなっていたのである。
そんな或日、蟻やコオロギを唯一の友達にしてきた彼のところに、三人の子供が連れてこられた。溥儀が始めて見るこの子等は、勉強や遊びの相手として連れてこられた、実の弟『溥傑』と貴族の少年逹であった。
この時代、溥儀に大きな影響を与えたのは、英国人家庭教師ジョンストンである。城の外にどんな世界が広がっているのか?ジョンストンの呉れる舶来のキャンディーや雑誌には文明開化の香りが立ち上ぼっていた。とりわけ夢中になったのは自転車であった。お供の者を振り切って自転車を乗り回す事は、ひととき味わう自由の感触であった。しかし、それも決まって門の前で終った。あくまで城壁の内側での自由に過ぎなかったのだ。外側の事を学ぶ事は、自由への憧れを掻き立てるばかりの溥儀は焦燥感の余り、満州族の伝統である辨髪を切ってしまうに及んで、彼の西洋かぶれを恐れる側近たちは、ジョンストンから引き離す策謀を企てた。
ある日、溥儀は、側近から四枚の写真を見せられ、印を付けるように求められた。后選びである。彼が何気なく印を付けたのは二人の娘であった。彼と同い年、十六歳、名家の令嬢『婉容』、そして第二夫人として選ばれた十三歳の『文繍』である。
こうして、溥儀の結婚式は革命から11年も経った1922年(大正11年)五日間に亘り盛大に行われた。しかし、溥儀が皇后や側室の部屋で過ごす事は殆ど無かった。ただ、自分をヘンリー、皇后をエリザベスと呼び、子供のように遊ぶ姿が見られただけであった。
このころ溥儀と一緒の生活をした婉容の実弟の『潤麒』は、溥儀は女性には興味を示さなく、子供もできなかったので、婉容が溥儀と結婚したのは、彼女の悲しい人生の始まりであったと回想している。
自由への憧れが募る一方の溥儀は、外出が自由にできる弟の溥傑に手伝わせて、密かに中国脱出を企てていた。英国領事館に逃げ込み、帝位も特権も全てを捨てて英国留学をしようとしたのである。しかし、彼はオランダ大使やジョンストンと連絡を取って脱出計画を進めていたのであるが、買収していた家臣に密告され、脱出当日に計画は阻止されてしまう。
その頃、外の世界では革命が頓挫し、軍閥たちは勢力争いに凌ぎを削り、全くの無政府状態になっていた。1924年(大正13年)、俄に城門の外が騒然としてくる。北京に入った軍閥の一人『馬玉祥』の軍が紫禁城を囲み、城を明け渡す様に要求した。まさに天変地異の政変に城内は上を下への大騒ぎとなった。皮肉にも溥儀にとっては、思いも掛けぬ形での自由の到来である。この時、溥儀18歳、城の外の世界は溥儀にとって目が眩むようであった。
城を出た溥儀には、三つの道があった。一つは、皇帝の地位も野心も放棄して、平民になる道、二つ目は実権はないがもう一度、城を奪い返す道、三番目が外国の力を借りて革命以前の真の皇帝の座を奪い返す道である。溥儀が選んだのは野望とも言える皇帝復帰の道であった。彼は側近たちから自分が天から遣わされた竜であり、皇帝としての運命を信じ込まされていたのである。財力も武力もない彼の結論は、外国の力を借りることであった。溥儀の心を捕らえた外国、それは大陸進出を目論む日本である。清王朝同様に皇室を貴ぶ国、そして今、満州族の故郷に大きな力を持ち始め、何より溥儀自身を尊重してくれる国に見えたからである。
1925年、始めて北京を離れた溥儀は、欧米列強の特権地帯・天津の日本祖界に入り、日本大使館の保護を受ける身となった。莫大な財産を持ち出していた溥儀は、広大な屋敷で、一族や家臣共々、小さな宮廷生活の体面を保ちながら復活の好機到来を待った。時の人として、各国社交界の名士となった溥儀は、英国製の洋服にダイヤの装飾品をちりばめ、オーデコロンを発散させながら芝居見物やナイトクラブに出入りし、外の世界の妖しい香りに酔い痴れて居た。一方、二人の妻は、互いに張り合うように物を買い込み、散財にエネルギーを費やす。そして、婉容は夫が皇帝ではない今、邸内で第二夫人文繍と顔を合わせる事に苛立ち、一夫一婦制を主張する。片や文繍は、婉容の苛めに耐え兼ね、自殺未遂まで引き起こし、突然、家を飛び出し二度と帰ることはなかった。その後、溥儀に離婚請求を突き付けた彼女は、体面上から承知しない溥儀を裁判所に訴え、遂に自由の身を獲得している。こうして文繍を追い出したものの、見せかけだけの夫婦に絶望して婉容は、夫を嫌悪するようになる。こんな彼女の心を捕らえたは『阿片』を吸うことであった。
こうした彼の生活の水面下で、日本軍の巨大な策謀が進んでいたことなどは、溥儀は知る由も無かった。彼を訪ねてくる日本軍の参謀たちは、誰れもが彼を『陛下』と持ち上げ、彼こそ中国の正当な君主であり、その復活を日本が手助けしたいと言った。
1928年(昭和三年)の張作霖・爆破事件から、日本軍の大陸進出に拍車が掛かっていく。この頃、溥儀にとって衝撃的なニュースがもたらされる。蒋介石が、西太后らの清朝の代々の墓を破壊し、西太后の遺体を切り刻んだ上に、副葬品の財宝を奪ったのである。この瞬間、溥儀の心に恨みと怒りの炎が燃え上がった。自分たちを見捨てた中国に恨みを晴らさなくては、愛新覚羅の子ではないと誓う。この年、日本との関係を深めるため、又、溥傑を軍人として教育するため日本に留学させた溥儀は、最早どんな忠告にも貸す耳を持たなかった。
一方その頃、感情の起伏が激しくなっていた婉容は、何とか結婚生活に終止符を打とうとして躍起であった。しかし日本軍の計画にとって、皇后は何としても欠かせない存在である。その頃から、彼女の許を頻繁に訪れる若い女がいた。満州貴族の血を引き、婉容とも親戚に当たるこの女の中国名は『金碧輝』、隠された日本名は『川島芳子』である。日本の大陸浪人『川島浪速』の養女となった彼女は、日本軍のスパイとして『東洋のマタ・ハリ』と呼ばれることになる。芳子の任務は婉容を操ることであった。
1931年(昭和 6年)、満州事変を期に、日本軍の満州支配の陰謀が仕上げに向かって動き始めた。各国の目が光る天津から溥儀の連れ出しを計った日本軍の特務機関は、深夜、溥儀を車のトランクに隠して脱出させ、港から日本の船に載せ、満州の表玄関の旅順に連れ出す事に成功、そこで溥儀を出迎え、監視役になった工作員の名前は『甘粕正彦』、関東大震災のとき、無政府主義者の大杉栄とその妻・野枝を殺害した悪名高い元憲兵大尉である。その二か月後、脱出を嫌がっていた婉容を、強引に連れ出したのは川島芳子である。1932年、遂に日本は『王道楽土』を旗印に、満州国の建国を宣言し、世界が非難の声を上げる中、溥儀は日の丸と満州国国旗がはためく中、首都・長春駅に降り立つ。溥儀は出迎えの歓呼の声に涙を流し、未来が希望に溢れていることを疑わなかった。
かくして1934年(昭和 9年)3 月、溥儀は満州国皇帝として復活した。当時のニュース映画によると、『満州国は誕生し、かくて日・満共存共栄の基礎は確立し、東洋永遠の平和に向かって邁進するに至った』とあり、溥儀自身も日本が強大であると言う感覚を抱いている。そして彼は自分の運命が日本とは切り離せないと考えるようになる。 この時、28歳、行く手の波瀾を知る由もない。
清朝再興の第一歩であると、溥儀が信じた満州国皇帝への復活ではあったが、彼の満面の笑みが歪むまで時間は掛からなかった。元首とは言うものの実権を握っていたのは日本の現地派遣軍・関東軍であり、彼は飾り物同然であったからである。発言権は勿論なく、終日監視の目が光り、自由に外に出る事も人に会うこともできない。彼は日本の力を利用しようとしたのに、逆に利用されたことに気付いた。日本人の作った檻のなかに自分から入ったのである。考えが幼稚であったと言うより、皇帝に復帰したいと言う気持ちが余りに強かったのである。
しかし、彼はそうした現実からは目を背けたかった。関東軍にお膳立てされた格式張った行事や日本の天皇と並んで自分の写真が崇拝の対象となっている事に自分の価値を見出し夢に酔っていたかったのである。
一方、その頃の婉容は皇后に復帰したとはいえ、再び籠の鳥となり、身も心もささくれ立ち、阿片と縁が切れることはなかった。溥儀の関心は一にも、二にも皇帝復帰の事ばかり何を愛情と言うのか分からなかった。他人に於いては平等な物である夫婦と言うものが、彼等にとっては主人と奴隷の関係であり、道具であった。
1935年の日本訪問で溥儀の錯覚は頂点に達した。東京駅に着いた溥儀を迎えたのは、天皇自らであったからである。宴会やパレード等の歓迎行事が時計仕掛けのように次々と繰り広げられ、日本の役人たちが、恭しく付き従う光景に溥儀は、酔い痴れていた。
そして満州に帰った溥儀を思いも掛けぬ事件が待ち受ける。妻の婉容が欺瞞に満ちた生活に飽き足らず自暴自棄となり一層阿片に蝕まれ、その上、親の知れない子供を宿していたことが発覚したのである。家臣との密通であった。既に臨月は近ずき、婉容は自分を離婚してくれるよう、子供は産みたいと、溥儀に哀願した。しかし、溥儀はおろおろするばかり、溥儀にとっても、関東軍にとっても体面が何よりも優先されなくてはならず、離婚など認めるわけには行かなかった。そして産まれたのは婉容に似た愛らしい女の子であったが、赤ん坊が母親に抱かれたのはほんの瞬間であり、溥儀の命令でその子は暖炉の炎の中に投じられ、たった 30 分しか、この世に居ることを赦され無かった。以後、婉容は最後の抵抗を示すように最早、髪を梳かすことも入浴することもなくなってしまった。彼女を訪ねた関係者は、彼女が既に阿片中毒で話す事もできず、指で空中に『宮中暗黒』の四文字を書くのを見たと言う。
そして妻を生き地獄に追いやりながら、尚も幻想にしがみつく溥儀に冷水を浴びせるような事態が起きた。関東軍による溥儀の側近の粛清である。日本への批判勢力に対する銃と刀による弾圧であった。
1937年、日中が全面戦争に突入した年の一月、ただ一人心を許して来た日本留学中の弟・溥傑が、日本の皇族と血縁関係にある嵯峨侯爵の娘・浩と結婚したことを知らされる。 (彼女のことは、『流転の王妃』として著名になる)これは勿論、軍部による政略結婚である。しかも軍部は皇帝に万一のことがあれば弟に、弟に万一のことがあればその子に、皇位継承権が移る事を通告して来た。彼は軍部が必要としているのは溥儀ではなく、日本の血を引いた皇帝なのだと気付く。溥儀 31 歳のときであり、否応なく突き付けられた現実に、為す術もなく身を震わせていた。尚、嵯峨家は孝明天皇に繋がる家柄である。
関東軍に抹殺されるかも知れないと言う恐怖感が、溥儀の神経を針のように尖らせた。食物を前にしても、栄養剤を注射するときも、何時毒が盛られるか?と怯える。折りしも弟の溥傑が日本人の妻を連れて帰ってきたときも、溥傑の前では思った事も口に出さない、その妻・浩が勧める食物は一口も食べないと決めていた。
この年、1937年(昭和 12 年)、溥儀は自分を裏切った婉容を懲らしめるためと称して、同じ満州貴族の17歳の少女『譚玉齢』と結婚、尚も皇帝の装いを凝らす事に必死となった。譚玉齢はそのための飾りにすぎない。
時は少し流れて1940年、溥儀を露骨に見下し始めた関東軍は、満州国の宗教を日本の『神道』にすることを通告する。溥儀は『清朝復活どころか、自分は、先祖の霊を崇めて来た清朝代々の売国奴になってしまう』と、自分の愚かさを呪わずにはいられなかった。
そして1941年、日本は米・英に対して戦火を開くと、満州の統治にも一層あからさまになり、溥儀にしきりと日本女性との結婚を持ち掛けるようになった。
翌年、追い討ちをかけるように、溥儀に恐ろしい事が起る。体調を崩していた妻の譚玉齢が、関東軍が日本人医師に彼女の治療を命じた直後に、22歳で謎の死を遂げた。 それが謀殺である事は溥儀の目にも明かであった。そして関東軍が溥儀に日本女性との結婚を迫ると溥儀は最後の抵抗を示すようにこれを拒否、1943年に、皮肉を込めて貧しい家の少女『李玉琴』15歳と再婚するが、実体は溥儀の召使同然であった。
最後の皇帝・ラストエンペラー
プロローグ
1967年10月の新聞に、元満州国皇帝・愛新覚羅溥儀の死亡記事がその簡単な略歴と共に小さく載った。当時を知る者にとっては、感慨深いものがある。彼こそ、清王朝最後の皇帝ラストエンペラーである。今世紀の初頭、僅か三歳で皇帝の地位に就いた溥儀は、革命で追われ、その姿を消していた。歳月が流れ、やがて日本軍が撮ったフィルムに登場した溥儀に、世界はアット驚いた。
1934年 3月(昭和9年)、現在の中国東北部に忽然と出現した幻の帝国・満州国の皇帝として彼が復活したからである。しかし、その後の彼を待っていたのは、関東軍や女スパイ川島芳子の暗躍する日本の謀略と数奇な命運であった。太平洋戦争での日本の敗戦で再び皇帝の座を追われた溥儀の行方は多くの謎を残しながら、歴史の波間に消えて行った。
その後の消息の一端は、彼が名前の代わりに呼ばれていた『981』と言う囚人番号が、如実に物語っている。そして彼が最後に漸く手にした人生とはどんな物であったのか? 1998年 5月、一人の女性が始めてカメラの前に立っ。彼女こそ、最後の皇帝ともう一つの人生を送り、彼の最後を看取った皇帝最後の妻(五人目)『李淑賢』である。彼女は、その夫に関して『彼は過去の、なんでも手にすることの出来た皇帝の暮らしより、貧しくても夫婦共稼ぎの平凡な生活を幸せと感じていた』と証言している。
君臨し、崇拝され、そして裏切り者の汚名を着ながら、二十世紀最大のミステリーを生きたラストエンペラー、歴史の荒波に押し流された果てに、彼が見た真実の人生とは?
1946年 8月、終戦直後の極東軍事裁判で、連合国側の証人として出廷した人物に、内外の報道陣はどよめいた。その証人は『溥儀、本来の満州国の名は愛新覚羅』と名乗った。抑留先のソ連から、連合国側の証人として連れてこられたのである。『私は1909年に、中国皇帝の地位に就きました。…』に始まり、日本の戦争犯罪を証言した溥儀は、遠くを見つめる目差しで、自分の背負わされた運命を辿っているようであった。
[1]運命の前半生
今世紀の幕開けを迎えた清朝の宮廷・紫禁城の奥の院で、一人の奇怪な老婆がその落日を眺めて居た。アヘン戦争以来の中国は、欧米の列強に浸食され、1895年には小国の日本との日清戦争にも敗れ、南からは革命の予兆が伝わって来る、落日はあたかも三百年に及ぶ清朝そのものの様であった。人々がその名を口にすることさえ恐れ慄いたこの老婆こそ、かの恐怖の女帝『西太后』である。しかし、さしもの女帝も寄る年波には勝てなかった。病に伏し、死を悟った彼女に残されたのは、後継者を自ら指名する事であった。 その運命に当たったのは、同じ満州族の血を引き、西太后のかっての愛人であった側近 『永録』の孫『溥儀』三歳であった。その日、いきなり親元から引き離された三歳の乳飲み子は、泣き叫ぶのも構わず輿に乗せられ、死の間際の西太后の前に召し出された。その僅か二日後に西太后の命運は74歳で尽きる。玉座に押し上げられた男の子は、黄昏行く王朝の運命を背負わされたのである。1908年(明治41年)三歳の皇帝即位であった。
紫禁城、高い城壁に囲まれた城内は、二十を越える宮殿、八千を越える部屋があり、多くの家臣たちの仕える富と権力の象徴である。その玉座に座る者は天子であり、神でもあった。しかし、この王朝にも崩壊の日がやてきた。1911年(明治44年)の『辛亥革命』である。君子制打倒を叫ぶ『孫文』らの革命運動は全国に飛び火し、遂に1912年、共和制による新国家『中華民国』の建国を宣言した。この辛亥革命によって、清王朝が地上から消えたのは、皇帝溥儀、五歳の事である。 だが、奇妙な事に革命のうねりは紫禁城には及ばず、皇帝の地位は存続していた。それは市民の間に皇帝への畏敬の念が根強かったので、混乱を避けるためであった。そのため城内は、歴史の空白のように幼い溥儀の下に千人の家臣が仕え、古来からの儀式や祭りごとが続いていたのである。
物心付いた溥儀が最初に覚えた事は命令することであった。一言、腹が空いたと言えば、二百人の料理人が腕を振るい、銀の器に山海の珍味が並べられ、外に行きたいと言えば即座に輿が用意された。毎日衣服が新調され、ボタンも靴紐も自分ですることはなく、便器を持参するだけの召使も居た。彼の日課は、退屈な儀式をしたり、宮殿を巡って母や祖母に挨拶することであった。後に彼は『私には大勢の母がいたが、母性愛と言うものを私は知らなかった』と言っているが、母と呼ばされていたのは、先代や先々代の未亡人、側室等である。つまり大后や大姉たちであった。溥儀が唯一感情を通わせたのは、九歳まで毎晩添い寝し、幼い頃は乳を飲ませてくれた乳母の『王焦氏』だけである。
しかし、溥儀九才の時、この安らかな感情も奪われる。大后たちが、授乳の奴隷にすぎない乳母に、皇帝が肩入れするのを恐れて、追放したのである。
これ以後、彼が覚えたのは家臣に当たり散らし、折檻する事であった。彼は愛情に飢えていたのであるが、皇帝の権威を振るうことしか感情の捌け口を知らないため、下の者に対して怒りっぽくなっていたのである。
そんな或日、蟻やコオロギを唯一の友達にしてきた彼のところに、三人の子供が連れてこられた。溥儀が始めて見るこの子等は、勉強や遊びの相手として連れてこられた、実の弟『溥傑』と貴族の少年逹であった。
この時代、溥儀に大きな影響を与えたのは、英国人家庭教師ジョンストンである。城の外にどんな世界が広がっているのか?ジョンストンの呉れる舶来のキャンディーや雑誌には文明開化の香りが立ち上ぼっていた。とりわけ夢中になったのは自転車であった。お供の者を振り切って自転車を乗り回す事は、ひととき味わう自由の感触であった。しかし、それも決まって門の前で終った。あくまで城壁の内側での自由に過ぎなかったのだ。外側の事を学ぶ事は、自由への憧れを掻き立てるばかりの溥儀は焦燥感の余り、満州族の伝統である辨髪を切ってしまうに及んで、彼の西洋かぶれを恐れる側近たちは、ジョンストンから引き離す策謀を企てた。
ある日、溥儀は、側近から四枚の写真を見せられ、印を付けるように求められた。后選びである。彼が何気なく印を付けたのは二人の娘であった。彼と同い年、十六歳、名家の令嬢『婉容』、そして第二夫人として選ばれた十三歳の『文繍』である。
こうして、溥儀の結婚式は革命から11年も経った1922年(大正11年)五日間に亘り盛大に行われた。しかし、溥儀が皇后や側室の部屋で過ごす事は殆ど無かった。ただ、自分をヘンリー、皇后をエリザベスと呼び、子供のように遊ぶ姿が見られただけであった。
このころ溥儀と一緒の生活をした婉容の実弟の『潤麒』は、溥儀は女性には興味を示さなく、子供もできなかったので、婉容が溥儀と結婚したのは、彼女の悲しい人生の始まりであったと回想している。
自由への憧れが募る一方の溥儀は、外出が自由にできる弟の溥傑に手伝わせて、密かに中国脱出を企てていた。英国領事館に逃げ込み、帝位も特権も全てを捨てて英国留学をしようとしたのである。しかし、彼はオランダ大使やジョンストンと連絡を取って脱出計画を進めていたのであるが、買収していた家臣に密告され、脱出当日に計画は阻止されてしまう。
その頃、外の世界では革命が頓挫し、軍閥たちは勢力争いに凌ぎを削り、全くの無政府状態になっていた。1924年(大正13年)、俄に城門の外が騒然としてくる。北京に入った軍閥の一人『馬玉祥』の軍が紫禁城を囲み、城を明け渡す様に要求した。まさに天変地異の政変に城内は上を下への大騒ぎとなった。皮肉にも溥儀にとっては、思いも掛けぬ形での自由の到来である。この時、溥儀18歳、城の外の世界は溥儀にとって目が眩むようであった。
城を出た溥儀には、三つの道があった。一つは、皇帝の地位も野心も放棄して、平民になる道、二つ目は実権はないがもう一度、城を奪い返す道、三番目が外国の力を借りて革命以前の真の皇帝の座を奪い返す道である。溥儀が選んだのは野望とも言える皇帝復帰の道であった。彼は側近たちから自分が天から遣わされた竜であり、皇帝としての運命を信じ込まされていたのである。財力も武力もない彼の結論は、外国の力を借りることであった。溥儀の心を捕らえた外国、それは大陸進出を目論む日本である。清王朝同様に皇室を貴ぶ国、そして今、満州族の故郷に大きな力を持ち始め、何より溥儀自身を尊重してくれる国に見えたからである。
1925年、始めて北京を離れた溥儀は、欧米列強の特権地帯・天津の日本祖界に入り、日本大使館の保護を受ける身となった。莫大な財産を持ち出していた溥儀は、広大な屋敷で、一族や家臣共々、小さな宮廷生活の体面を保ちながら復活の好機到来を待った。時の人として、各国社交界の名士となった溥儀は、英国製の洋服にダイヤの装飾品をちりばめ、オーデコロンを発散させながら芝居見物やナイトクラブに出入りし、外の世界の妖しい香りに酔い痴れて居た。一方、二人の妻は、互いに張り合うように物を買い込み、散財にエネルギーを費やす。そして、婉容は夫が皇帝ではない今、邸内で第二夫人文繍と顔を合わせる事に苛立ち、一夫一婦制を主張する。片や文繍は、婉容の苛めに耐え兼ね、自殺未遂まで引き起こし、突然、家を飛び出し二度と帰ることはなかった。その後、溥儀に離婚請求を突き付けた彼女は、体面上から承知しない溥儀を裁判所に訴え、遂に自由の身を獲得している。こうして文繍を追い出したものの、見せかけだけの夫婦に絶望して婉容は、夫を嫌悪するようになる。こんな彼女の心を捕らえたは『阿片』を吸うことであった。
こうした彼の生活の水面下で、日本軍の巨大な策謀が進んでいたことなどは、溥儀は知る由も無かった。彼を訪ねてくる日本軍の参謀たちは、誰れもが彼を『陛下』と持ち上げ、彼こそ中国の正当な君主であり、その復活を日本が手助けしたいと言った。
1928年(昭和三年)の張作霖・爆破事件から、日本軍の大陸進出に拍車が掛かっていく。この頃、溥儀にとって衝撃的なニュースがもたらされる。蒋介石が、西太后らの清朝の代々の墓を破壊し、西太后の遺体を切り刻んだ上に、副葬品の財宝を奪ったのである。この瞬間、溥儀の心に恨みと怒りの炎が燃え上がった。自分たちを見捨てた中国に恨みを晴らさなくては、愛新覚羅の子ではないと誓う。この年、日本との関係を深めるため、又、溥傑を軍人として教育するため日本に留学させた溥儀は、最早どんな忠告にも貸す耳を持たなかった。
一方その頃、感情の起伏が激しくなっていた婉容は、何とか結婚生活に終止符を打とうとして躍起であった。しかし日本軍の計画にとって、皇后は何としても欠かせない存在である。その頃から、彼女の許を頻繁に訪れる若い女がいた。満州貴族の血を引き、婉容とも親戚に当たるこの女の中国名は『金碧輝』、隠された日本名は『川島芳子』である。日本の大陸浪人『川島浪速』の養女となった彼女は、日本軍のスパイとして『東洋のマタ・ハリ』と呼ばれることになる。芳子の任務は婉容を操ることであった。
1931年(昭和 6年)、満州事変を期に、日本軍の満州支配の陰謀が仕上げに向かって動き始めた。各国の目が光る天津から溥儀の連れ出しを計った日本軍の特務機関は、深夜、溥儀を車のトランクに隠して脱出させ、港から日本の船に載せ、満州の表玄関の旅順に連れ出す事に成功、そこで溥儀を出迎え、監視役になった工作員の名前は『甘粕正彦』、関東大震災のとき、無政府主義者の大杉栄とその妻・野枝を殺害した悪名高い元憲兵大尉である。その二か月後、脱出を嫌がっていた婉容を、強引に連れ出したのは川島芳子である。1932年、遂に日本は『王道楽土』を旗印に、満州国の建国を宣言し、世界が非難の声を上げる中、溥儀は日の丸と満州国国旗がはためく中、首都・長春駅に降り立つ。溥儀は出迎えの歓呼の声に涙を流し、未来が希望に溢れていることを疑わなかった。
かくして1934年(昭和 9年)3 月、溥儀は満州国皇帝として復活した。当時のニュース映画によると、『満州国は誕生し、かくて日・満共存共栄の基礎は確立し、東洋永遠の平和に向かって邁進するに至った』とあり、溥儀自身も日本が強大であると言う感覚を抱いている。そして彼は自分の運命が日本とは切り離せないと考えるようになる。 この時、28歳、行く手の波瀾を知る由もない。
清朝再興の第一歩であると、溥儀が信じた満州国皇帝への復活ではあったが、彼の満面の笑みが歪むまで時間は掛からなかった。元首とは言うものの実権を握っていたのは日本の現地派遣軍・関東軍であり、彼は飾り物同然であったからである。発言権は勿論なく、終日監視の目が光り、自由に外に出る事も人に会うこともできない。彼は日本の力を利用しようとしたのに、逆に利用されたことに気付いた。日本人の作った檻のなかに自分から入ったのである。考えが幼稚であったと言うより、皇帝に復帰したいと言う気持ちが余りに強かったのである。
しかし、彼はそうした現実からは目を背けたかった。関東軍にお膳立てされた格式張った行事や日本の天皇と並んで自分の写真が崇拝の対象となっている事に自分の価値を見出し夢に酔っていたかったのである。
一方、その頃の婉容は皇后に復帰したとはいえ、再び籠の鳥となり、身も心もささくれ立ち、阿片と縁が切れることはなかった。溥儀の関心は一にも、二にも皇帝復帰の事ばかり何を愛情と言うのか分からなかった。他人に於いては平等な物である夫婦と言うものが、彼等にとっては主人と奴隷の関係であり、道具であった。
1935年の日本訪問で溥儀の錯覚は頂点に達した。東京駅に着いた溥儀を迎えたのは、天皇自らであったからである。宴会やパレード等の歓迎行事が時計仕掛けのように次々と繰り広げられ、日本の役人たちが、恭しく付き従う光景に溥儀は、酔い痴れていた。
そして満州に帰った溥儀を思いも掛けぬ事件が待ち受ける。妻の婉容が欺瞞に満ちた生活に飽き足らず自暴自棄となり一層阿片に蝕まれ、その上、親の知れない子供を宿していたことが発覚したのである。家臣との密通であった。既に臨月は近ずき、婉容は自分を離婚してくれるよう、子供は産みたいと、溥儀に哀願した。しかし、溥儀はおろおろするばかり、溥儀にとっても、関東軍にとっても体面が何よりも優先されなくてはならず、離婚など認めるわけには行かなかった。そして産まれたのは婉容に似た愛らしい女の子であったが、赤ん坊が母親に抱かれたのはほんの瞬間であり、溥儀の命令でその子は暖炉の炎の中に投じられ、たった 30 分しか、この世に居ることを赦され無かった。以後、婉容は最後の抵抗を示すように最早、髪を梳かすことも入浴することもなくなってしまった。彼女を訪ねた関係者は、彼女が既に阿片中毒で話す事もできず、指で空中に『宮中暗黒』の四文字を書くのを見たと言う。
そして妻を生き地獄に追いやりながら、尚も幻想にしがみつく溥儀に冷水を浴びせるような事態が起きた。関東軍による溥儀の側近の粛清である。日本への批判勢力に対する銃と刀による弾圧であった。
1937年、日中が全面戦争に突入した年の一月、ただ一人心を許して来た日本留学中の弟・溥傑が、日本の皇族と血縁関係にある嵯峨侯爵の娘・浩と結婚したことを知らされる。 (彼女のことは、『流転の王妃』として著名になる)これは勿論、軍部による政略結婚である。しかも軍部は皇帝に万一のことがあれば弟に、弟に万一のことがあればその子に、皇位継承権が移る事を通告して来た。彼は軍部が必要としているのは溥儀ではなく、日本の血を引いた皇帝なのだと気付く。溥儀 31 歳のときであり、否応なく突き付けられた現実に、為す術もなく身を震わせていた。尚、嵯峨家は孝明天皇に繋がる家柄である。
関東軍に抹殺されるかも知れないと言う恐怖感が、溥儀の神経を針のように尖らせた。食物を前にしても、栄養剤を注射するときも、何時毒が盛られるか?と怯える。折りしも弟の溥傑が日本人の妻を連れて帰ってきたときも、溥傑の前では思った事も口に出さない、その妻・浩が勧める食物は一口も食べないと決めていた。
この年、1937年(昭和 12 年)、溥儀は自分を裏切った婉容を懲らしめるためと称して、同じ満州貴族の17歳の少女『譚玉齢』と結婚、尚も皇帝の装いを凝らす事に必死となった。譚玉齢はそのための飾りにすぎない。
時は少し流れて1940年、溥儀を露骨に見下し始めた関東軍は、満州国の宗教を日本の『神道』にすることを通告する。溥儀は『清朝復活どころか、自分は、先祖の霊を崇めて来た清朝代々の売国奴になってしまう』と、自分の愚かさを呪わずにはいられなかった。
そして1941年、日本は米・英に対して戦火を開くと、満州の統治にも一層あからさまになり、溥儀にしきりと日本女性との結婚を持ち掛けるようになった。
翌年、追い討ちをかけるように、溥儀に恐ろしい事が起る。体調を崩していた妻の譚玉齢が、関東軍が日本人医師に彼女の治療を命じた直後に、22歳で謎の死を遂げた。 それが謀殺である事は溥儀の目にも明かであった。そして関東軍が溥儀に日本女性との結婚を迫ると溥儀は最後の抵抗を示すようにこれを拒否、1943年に、皮肉を込めて貧しい家の少女『李玉琴』15歳と再婚するが、実体は溥儀の召使同然であった。











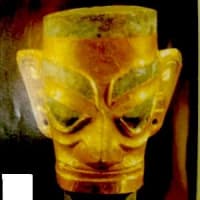








嘘を書くのはやめたまえ!