[2]中国革命
①歴史再評価…
『中華民族は1900年、義和団による北清事変のため八か国連合軍に北京を占領され、大きな屈辱を被り国家は滅亡の危機に瀕した……』と第十五回党大会の冒頭、政治報告に立った江沢民総書記(国家主席)は切り出し、二十世紀を回顧しながら来世紀に向けた指導方針を示した。江報告は『社会主義』と言う文言を使いながらも、この百年の革命の目標が『民族の解放』や『中華の振興』『国の繁栄・富強』にあったことを強調した。その上で『この一世紀、前進途上で三回の歴史的な大変化を体験し、時代の先頭に立つ三人の偉大な人物、孫文・毛沢東・登小平が現れた』と指摘し、その実現に貢献した共産党体制の堅持を宣言したのである。党史研究室でこの報告を受けて『中国共産党歴史上巻』の書き直しに入ったという。党史研究室の幹部『石仲泉』は『上巻は1911年の辛亥革命の後から書き出しているが、これは江報告も辛亥革命を二十世紀の三つの重要な歴史的変化の一つとしているし、多くの専門家も辛亥革命から書く方が党の真の歴史の発展状況を反映できると言う意見である為である』と説明している。従来中国では党史の起点を1919年の5.4 運動に置いて書くのが主流であったから、民族解放をキーワードに辛亥革命を中国革命の起点とする意味は大きい。何故ならロシアの十月革命に触発され、知識人、学生が立ち上がってマルクス主義が革命理論として導入された5.4 運動に起点を置けば、社会主義革命色が強まってしまう。一方、辛亥革命を起点とすれば中華を振興する民族民主主義革命色が強まる。1981年の歴史決議では未だ辛亥革命は清王朝を覆して二千年余りの封建帝政を終了させたが、中国社会の半植民地、半封建的体質は変わらなかったと言う評価しか与えられていない。しかし江報告では『孫文は先ず中華を振興しようと言うスローガンを打ち出し、完全な意味での近代民族民主主義革命の道を切り開いた』と毛による建国、登による経済建設と同格に論じている。
事情通によると、『ロシア革命と違って中国革命は確かに民族解放の面がある。社会主義が事実上失敗とされる今、この面を強調したほうが、現政権の正当化ができるのである。そこ迄溯れば香港返還後の最大課題である台湾統一にも環境作りができると言う読みがある』と言うことらしい。
民族解放の強調は毛の異常とも言える自力更生路線や大躍進運動への執着も説明しやすくなる。問題なのは孫文の始めた民族民主主義革命を結局は共産党が担ったことである。
石仲泉は『中国は半植民地、半封建の状態に置かれ、帝国主義列強は資本主義の道を許さなかった。従って結局は共産党を中心とする新民主主義革命と言う形を取る事になった』と分析する。この道は本来のマルクス主義の道からははみ出しており、毛沢東は経済を十分に発展させる新民主主義段階、その上に労働者階級が担うべき社会主義革命と言う二段階論を考えていた。しかし毛沢東は五年と待てず、経済基礎のないままに社会主義への道を突っ走ってしまったのである。その誤りが大躍進や文革の悲劇を生んだと言うのが、現在の公式見解である。毛の後を受けた登は二段階論に戻り『社会主義初級論』と言う理論を編み出した。これによると現在は社会主義であるが、未だその実現のための条件を整える経済建設中心の初級段階と言う事である。その期間は百年で来世紀の半ばに中国は真の社会主義の段階に入るとのことである。登は安定を重視して、事実上革命を棚上げする
『未完の革命』と言う形で党の支配体制に息を吹き込んだのである。毛の革命は何故に反転したのか?何故登の改革は党の支配を延命させる事ができたのか?中国革命は多様な側面を持ちその歴史は中国の風土の中で考えていかなくてはならない。
②辛亥革命・その栄光と挫折…
日清戦争の敗北で清王朝の落日が鮮明になった1895年10月当時28歳であった若き革命家孫文は広東省広州で最初の武装蜂起を企てたが、密告によって計画は決行寸前に露見してしまう。懸賞金まで掛けられた探索の目を逃れた孫文は同志二人と日本に逃れる。そして上陸した神戸で彼が手にしたのは『支那革命党の首領、孫文日本到着』と言う現地の新聞であった。清朝時代には王朝交代(易性革命)と同義語であった『革命』の文字は日本ではREVOLUTIONの訳語であった。彼はこの革命家と言う呼ばれ方を大いに気に入り、この言葉との出会いを機に清朝圧制の象徴である弁髪を切り落とすと共に『革命家』『革命党』を名乗るようになる。そしてその16年後に結実したのが、
二千百年余の専制王朝体制に終止符を打った『辛亥革命』である。
この間、孫文は広州蜂起を手始めに十回の武装蜂起を試み、ことごとく敗退しているのである。しかし孫文の指揮不在のまま1911年10月10日、湖北省武昌(現武漢市)での11回目の蜂起が成功し、翌年 1月に南京での孫文を臨時大統領とする『中華民国臨時政府』樹立へと進展している。
列強による半植民地化と腐敗の蔓延で命脈の尽きていた清朝に最後の一撃を加えたのが、この武昌での蜂起であった。関係者は革命勢力の主力となった『新軍』と革命支援基地としての日本の存在が蜂起成功の要因と見ている。
革命と言う二文字との邂逅逸話が示すように孫文と日本の縁は極めて深い。孫文の日本での亡命生活は実に九年に及び、後にアジアの革命運動の支援者として知られる宮崎滔天、国家社会主義の理論的指導者になる北一輝らと同志の絆を結んでいる。1905年には革命勢力を大同団結し、辛亥革命の母体となる『中国同盟会』を東京で結成する。
当時の日本には、孫文の他に湖南省長沙の革命結社『華興会』のリーダー黄興や、守旧派の西太后に追われた立憲君主派の梁啓超らも亡命していた。しかも清朝から派遣されていた留学生は15.000人にも達し、彼等の多くは革命派の巨頭やアジア唯一の列強国日本の実情に刺激され、次々に革命にその身を投じていったのである。まさに当時の日本は、中国革命勢力の集積地であった。
実際に武昌蜂起では清朝が西欧式に編成した新軍の兵士は帰国留学生たちが体勢を内側から崩すトロイの木馬の役割を果たしたので、三分の一が革命同盟会の傘下にはいってしまっている。勿論、日清、日露の戦勝でナショナリズムの燃え盛る日本も官民挙げて革命支援に動いている。孫文は『東洋は西洋に勝てないと言う神話を打ち砕いた日露戦争は全アジア民族を狂喜させ、大きな希望を抱かせた』と絶賛している。 この時期の日中連携は、東洋が西欧列強に蚕食されていく危機感を背景に、アジアナショナリズムが共鳴し合った一瞬であった。孫文は軍閥混戦を収束するため死去の前年1924年に広東から北京へ行く途中にわざわざ神戸に立ち寄り『大アジア主義』と題して生涯最後の講演を行っている。『日本民族は欧米の覇道の文化を取り入れると同時に、アジアの王道文化の本質も有している。日本が西欧覇道の番犬となるか、東洋の守りの兵士となるのかは、日本国民の慎重な選択に掛かっている』と言い残しているが、日本の革命支援の動機の大半は帝国主義に依存しており、孫文の警告とは逆の中国侵略と言う覇道を更に強めて行くのである。
辛亥革命は中華民国成立による清帝溥儀の退位を経て清朝末の新軍創設者袁世凱による権力簒奪、そして袁政権打倒に決起した『第二革命』が精強を誇る袁の北洋新軍の前に敗れ去った1913年 9月を以て終熄する。溥儀を退位させる詰めの駆け引のなか、在職僅か四十余日で大統領職を袁世凱に譲った孫文は袁の病没後の軍閥割拠に対抗して広東軍政府を組織し、真の共和国建設を目指して再起する。しかし1925年、『革命いまだ成らず』の遺訓を残して北京で病没する。中国革命の先陣を切った辛亥革命の栄光がかくも短く、挫折が深かったのは何故だろうか?
辛亥革命研究家は『この革命が成功だったのか?失敗だったのか?に付いてさえ、一致した見解はない。満州族王朝を覆したことは勝利と言えるが、独立、民主、富強の新中国建設が目的なら完全な失敗である』と言う。辛亥革命の背景には清朝の自壊、西欧列強の圧迫、国内の民族対立、資本主義の萌芽などの複雑な要素が絡み合っている。中国の史学会では革命勢力の内部矛盾に外圧が重なって短命となったと言う事では一致している。
1912年に発足した中華民国臨時政府の構成を見ても、大臣九人のうち革命派はたったの三人にすぎなく、残りは立憲君主派と旧官僚が占めている。北洋軍閥を握る袁世凱の担ぎ出しはこうした守旧派の他、革命派に警戒を募らせていた英国等の列強が早くから裏で荷担していたのである。つまり三民主義が象徴する共和制とはほど遠かったのが実態であり、理想国家を目指す孫文の卓越した先見性だけが、栄光に値する物であった。
その先見性を示すものが『中華民族論』である。民族の危機に直面した孫文は最初の革命団体を『興中会』と命名している。以来、中華振興は今世紀を通じて中華民族を奮い立たせ、励まし、凝集する中心的スローガンとなってきたのである。1894年に結成されたこの興中会の入会宣誓は『満州族を駆除し中華を恢復し合州政府を創立する』と言うものであり、更に臨時大統領就任演説では『漢、満、蒙古、回、チベットの諸民族を合わせて一人とし、これを民族統一とする』と唱えた。しかしこの『五族共和論』は清朝の採った満州族中心の異民族支配に通ずるものがあると言うことから、孫文は1920頃、五族と言う名称は不適切であり、中国の全ての民族を一つの中華民族に融合しなくてはならないと軌道修正をしている。これが現在中国で用いられている『中華民族』という観念語の起源であるという。ただ、列強の圧迫の元で中華民族の革命実現には強力な党と軍の出現を待たなくてはならなかったのである。
③国共合作・ソ連に学んだ双子…
1924年6 月16日、中国広東省広州の郊外、ソ連式軍服に身を包んだ五百人余の若者が整列していた。壇上に並ぶ軍閥の領袖たちの目は高い士気と規律の備わった新式軍隊の偉容に釘付けになっていた。国民党の孫文がソ連のコミンテルンと生まれたばかりの中国共産党との協力で設立した『黄埔軍官学校』の開校式である。それは孫文が夢にまで見た政治教育で理論武装した革命軍『党軍』誕生の記念すべき第一歩であり、中国革命を仕切り直す転換期でもあった。孫文は興奮した面持ちで『辛亥革命以来、今日迄の十三年間は失敗の連続であった。原因は我々革命党の奮闘はあったが革命軍の奮闘がなかったからである。本校の学生を基礎に革命軍を創設し中国の危機存亡を救う』と演説する。悲願の革命軍創設と軍官学校開設に当たって何故に孫文はコミンテルンと共産党の力を必要としたのか?これは各地に群雄割拠する軍閥混戦の中で苦戦を強いられた彼は局面の打開を図ろうとするが、日本などの西側への失望は徐々に広がる反面、ロシア革命の一連の経験を取り込みたいと思ったからである。勿論コミンテルン側は孫文の危機的状況を前にして精力的に働きかけ、派遣されていた軍師が国共合作を進言したのである。1923年孫文は党内右派の反対を押し切りソ連との協力を発表し、国共合作を打出す。これは共産党員がその党籍を保持した儘、個人資格で国民党に入党する方式であり対等な協力とは言い難いが、孫文は革命結社である国民党をソ連共産党型政党への改組作業に着手した。これらの事が国共両党が『双生児』と言われる理由である。
軍官学校開設に先だって孫文の指示でソ連に派遣され、赤軍の装備、訓練、組織を吸収して来たのが後に同校校長となる『蒋介石』である。彼は直ぐにソ連が中国固有の領土である外モンゴルを侵略する野心を持つ赤色帝国主義であることを見破りソ連が中国の永遠の友人でない事は良く分かったが、ソ連の援助なしには学校も作れない事も理解していたので、極めて注意深くソ連との友好関係を維持した。それにポスト孫文の争いも熾烈であったから、ここで反共を打出せば直ちに失脚する危険もあったので、この時点では容共政策が彼の取り得る唯一の方策であった。
この軍官学校は国民革命軍の基礎となり、北伐を成功させたばかりでなく、新中国建国の指導者を次々と輩出した。しかしこれは国共蜜月時代の象徴であると同時に、後に両党を引き裂く矛盾の温床となる一面もあった。
④国共合作・血まみれの分裂劇…
共産党は汪精衛の国民党左派と共に蒋介石の脅威となってきた。そして遂に『清党』の事態となる。これは国共合作により国民党の中に個人の資格で入った共産党分子の影響力を一掃することであった。そして1927年 4月12日、蒋介石は上海で反共クーデターを起こす。その少し前の1926年 7月、北伐を開始した国民革命軍は各地で民衆運動を刺激し、上海では労働者が武装糾察隊を組織し、1927年 3月には周恩来に指導された労働者がゼネストを決行し、更には武装蜂起して軍閥軍を駆逐した。労農運動の高揚と共産勢力拡張に危機感を強めた蒋介石は1927年 4月11日、上海に戒厳令を引いて、12日に青幇(チンパン)紅幇(ホンパン)と呼ばれるギャング団に糾察隊を襲わせた上に、国民党による糾察隊の武装解除をした。このとき抗議した糾察隊の幹部は射殺され、これに怒る十万人のデモ隊に機銃掃射を浴びせて数千人の犠牲者を出す。
この事件の後、蒋介石の党籍を剥奪、逮捕状まで出した武漢の国民政府は結局蒋介石に追従し 7月には容共政策を破棄する。この事によって1924年に成立した国民党と共産党の合作は 3年 7か月で終焉したのである。
こうした容共から反共へと戦略転換をせざるを得なかった背景には、予想以上の速度で勢力を拡大する共産党に対して最終的に国民党全体が食い尽くされると言う危機感がある。国共合作の当時、千人に満たない共産党は清党の直前には六万人に膨れ上がっていた。
確かに共産党員の参入が労働者や農民の大衆運動を可能にして地方軍閥を打倒し、中国統一を目指す蒋介石の北伐を成功させたのは事実ではあるが、一方で国民党は『蒋対反蒋』という派閥闘争の激化と言う深刻な後遺症に苦しむことになってしまったのである。
共産党の基本政策は、蒋介石の独裁を阻止し、国民党を分裂させて武漢の国民党左派 (汪精衛側)と連合して南京の国民党右派(蒋介石側)に対抗する事であった。
清党は共産党幹部の大量虐殺を引き起こし、これ以降、黄埔軍官学校は蒋介石に奉仕するだけの反革命拠点に変質し、怨念の対立は双生児である国共両党の骨肉の内戦を引き起こすことになる。
1936年12月、日本軍の侵略と言う国難を前にして西安事件を契機にして漸く第二次国共合作が成立する。しかしこれはかつての様に組織原理が似通った双生児党の協奏曲ではなく両党が夫々の支配地域で日本に抗戦する限定的な共闘でしかなかった。
それにしても孫文の信徒であり三民主義の実現に一生を捧げた筈の蒋介石が抗日戦も勝利し、圧倒的に有利な軍事力を持ちながら、何故共産党に敗れ大陸放棄に追いやられたのであろうか?蒋介石と共に戦い国民党の要職にあったある人物は『蒋介石は中国統一や不平等条約の撤廃等の功績は大きく、軍事の天才でもあるが、欠点は経済の才能に欠けていたことである』と証言している。確かに当時は抗日戦争による軍事費の負担で経済は疲弊し切っていたことは事実である。
1924年以来、25年に及ぶ両党の合作と相克の歴史が、21世紀を目前にした現在も両党を大陸と台湾に分かれて存在させ続けている。
因みに汪精衛(兆銘)の名は私どもの世代では懐かしい。彼は1938年、国民党の副総裁に就任したが、日中戦争の激化の中で日本軍の画策に乗せられ重慶から脱出し、ハノイで和平建議を発表して日本の近衛首相に接近し、1940年日本の傀儡政権である南京政府を樹立して首席に就任したが、1944年に不遇の内に名古屋で病没した。当時子供の私でも憎き蒋介石に相対する親日派として記憶に残っている。
①歴史再評価…
『中華民族は1900年、義和団による北清事変のため八か国連合軍に北京を占領され、大きな屈辱を被り国家は滅亡の危機に瀕した……』と第十五回党大会の冒頭、政治報告に立った江沢民総書記(国家主席)は切り出し、二十世紀を回顧しながら来世紀に向けた指導方針を示した。江報告は『社会主義』と言う文言を使いながらも、この百年の革命の目標が『民族の解放』や『中華の振興』『国の繁栄・富強』にあったことを強調した。その上で『この一世紀、前進途上で三回の歴史的な大変化を体験し、時代の先頭に立つ三人の偉大な人物、孫文・毛沢東・登小平が現れた』と指摘し、その実現に貢献した共産党体制の堅持を宣言したのである。党史研究室でこの報告を受けて『中国共産党歴史上巻』の書き直しに入ったという。党史研究室の幹部『石仲泉』は『上巻は1911年の辛亥革命の後から書き出しているが、これは江報告も辛亥革命を二十世紀の三つの重要な歴史的変化の一つとしているし、多くの専門家も辛亥革命から書く方が党の真の歴史の発展状況を反映できると言う意見である為である』と説明している。従来中国では党史の起点を1919年の5.4 運動に置いて書くのが主流であったから、民族解放をキーワードに辛亥革命を中国革命の起点とする意味は大きい。何故ならロシアの十月革命に触発され、知識人、学生が立ち上がってマルクス主義が革命理論として導入された5.4 運動に起点を置けば、社会主義革命色が強まってしまう。一方、辛亥革命を起点とすれば中華を振興する民族民主主義革命色が強まる。1981年の歴史決議では未だ辛亥革命は清王朝を覆して二千年余りの封建帝政を終了させたが、中国社会の半植民地、半封建的体質は変わらなかったと言う評価しか与えられていない。しかし江報告では『孫文は先ず中華を振興しようと言うスローガンを打ち出し、完全な意味での近代民族民主主義革命の道を切り開いた』と毛による建国、登による経済建設と同格に論じている。
事情通によると、『ロシア革命と違って中国革命は確かに民族解放の面がある。社会主義が事実上失敗とされる今、この面を強調したほうが、現政権の正当化ができるのである。そこ迄溯れば香港返還後の最大課題である台湾統一にも環境作りができると言う読みがある』と言うことらしい。
民族解放の強調は毛の異常とも言える自力更生路線や大躍進運動への執着も説明しやすくなる。問題なのは孫文の始めた民族民主主義革命を結局は共産党が担ったことである。
石仲泉は『中国は半植民地、半封建の状態に置かれ、帝国主義列強は資本主義の道を許さなかった。従って結局は共産党を中心とする新民主主義革命と言う形を取る事になった』と分析する。この道は本来のマルクス主義の道からははみ出しており、毛沢東は経済を十分に発展させる新民主主義段階、その上に労働者階級が担うべき社会主義革命と言う二段階論を考えていた。しかし毛沢東は五年と待てず、経済基礎のないままに社会主義への道を突っ走ってしまったのである。その誤りが大躍進や文革の悲劇を生んだと言うのが、現在の公式見解である。毛の後を受けた登は二段階論に戻り『社会主義初級論』と言う理論を編み出した。これによると現在は社会主義であるが、未だその実現のための条件を整える経済建設中心の初級段階と言う事である。その期間は百年で来世紀の半ばに中国は真の社会主義の段階に入るとのことである。登は安定を重視して、事実上革命を棚上げする
『未完の革命』と言う形で党の支配体制に息を吹き込んだのである。毛の革命は何故に反転したのか?何故登の改革は党の支配を延命させる事ができたのか?中国革命は多様な側面を持ちその歴史は中国の風土の中で考えていかなくてはならない。
②辛亥革命・その栄光と挫折…
日清戦争の敗北で清王朝の落日が鮮明になった1895年10月当時28歳であった若き革命家孫文は広東省広州で最初の武装蜂起を企てたが、密告によって計画は決行寸前に露見してしまう。懸賞金まで掛けられた探索の目を逃れた孫文は同志二人と日本に逃れる。そして上陸した神戸で彼が手にしたのは『支那革命党の首領、孫文日本到着』と言う現地の新聞であった。清朝時代には王朝交代(易性革命)と同義語であった『革命』の文字は日本ではREVOLUTIONの訳語であった。彼はこの革命家と言う呼ばれ方を大いに気に入り、この言葉との出会いを機に清朝圧制の象徴である弁髪を切り落とすと共に『革命家』『革命党』を名乗るようになる。そしてその16年後に結実したのが、
二千百年余の専制王朝体制に終止符を打った『辛亥革命』である。
この間、孫文は広州蜂起を手始めに十回の武装蜂起を試み、ことごとく敗退しているのである。しかし孫文の指揮不在のまま1911年10月10日、湖北省武昌(現武漢市)での11回目の蜂起が成功し、翌年 1月に南京での孫文を臨時大統領とする『中華民国臨時政府』樹立へと進展している。
列強による半植民地化と腐敗の蔓延で命脈の尽きていた清朝に最後の一撃を加えたのが、この武昌での蜂起であった。関係者は革命勢力の主力となった『新軍』と革命支援基地としての日本の存在が蜂起成功の要因と見ている。
革命と言う二文字との邂逅逸話が示すように孫文と日本の縁は極めて深い。孫文の日本での亡命生活は実に九年に及び、後にアジアの革命運動の支援者として知られる宮崎滔天、国家社会主義の理論的指導者になる北一輝らと同志の絆を結んでいる。1905年には革命勢力を大同団結し、辛亥革命の母体となる『中国同盟会』を東京で結成する。
当時の日本には、孫文の他に湖南省長沙の革命結社『華興会』のリーダー黄興や、守旧派の西太后に追われた立憲君主派の梁啓超らも亡命していた。しかも清朝から派遣されていた留学生は15.000人にも達し、彼等の多くは革命派の巨頭やアジア唯一の列強国日本の実情に刺激され、次々に革命にその身を投じていったのである。まさに当時の日本は、中国革命勢力の集積地であった。
実際に武昌蜂起では清朝が西欧式に編成した新軍の兵士は帰国留学生たちが体勢を内側から崩すトロイの木馬の役割を果たしたので、三分の一が革命同盟会の傘下にはいってしまっている。勿論、日清、日露の戦勝でナショナリズムの燃え盛る日本も官民挙げて革命支援に動いている。孫文は『東洋は西洋に勝てないと言う神話を打ち砕いた日露戦争は全アジア民族を狂喜させ、大きな希望を抱かせた』と絶賛している。 この時期の日中連携は、東洋が西欧列強に蚕食されていく危機感を背景に、アジアナショナリズムが共鳴し合った一瞬であった。孫文は軍閥混戦を収束するため死去の前年1924年に広東から北京へ行く途中にわざわざ神戸に立ち寄り『大アジア主義』と題して生涯最後の講演を行っている。『日本民族は欧米の覇道の文化を取り入れると同時に、アジアの王道文化の本質も有している。日本が西欧覇道の番犬となるか、東洋の守りの兵士となるのかは、日本国民の慎重な選択に掛かっている』と言い残しているが、日本の革命支援の動機の大半は帝国主義に依存しており、孫文の警告とは逆の中国侵略と言う覇道を更に強めて行くのである。
辛亥革命は中華民国成立による清帝溥儀の退位を経て清朝末の新軍創設者袁世凱による権力簒奪、そして袁政権打倒に決起した『第二革命』が精強を誇る袁の北洋新軍の前に敗れ去った1913年 9月を以て終熄する。溥儀を退位させる詰めの駆け引のなか、在職僅か四十余日で大統領職を袁世凱に譲った孫文は袁の病没後の軍閥割拠に対抗して広東軍政府を組織し、真の共和国建設を目指して再起する。しかし1925年、『革命いまだ成らず』の遺訓を残して北京で病没する。中国革命の先陣を切った辛亥革命の栄光がかくも短く、挫折が深かったのは何故だろうか?
辛亥革命研究家は『この革命が成功だったのか?失敗だったのか?に付いてさえ、一致した見解はない。満州族王朝を覆したことは勝利と言えるが、独立、民主、富強の新中国建設が目的なら完全な失敗である』と言う。辛亥革命の背景には清朝の自壊、西欧列強の圧迫、国内の民族対立、資本主義の萌芽などの複雑な要素が絡み合っている。中国の史学会では革命勢力の内部矛盾に外圧が重なって短命となったと言う事では一致している。
1912年に発足した中華民国臨時政府の構成を見ても、大臣九人のうち革命派はたったの三人にすぎなく、残りは立憲君主派と旧官僚が占めている。北洋軍閥を握る袁世凱の担ぎ出しはこうした守旧派の他、革命派に警戒を募らせていた英国等の列強が早くから裏で荷担していたのである。つまり三民主義が象徴する共和制とはほど遠かったのが実態であり、理想国家を目指す孫文の卓越した先見性だけが、栄光に値する物であった。
その先見性を示すものが『中華民族論』である。民族の危機に直面した孫文は最初の革命団体を『興中会』と命名している。以来、中華振興は今世紀を通じて中華民族を奮い立たせ、励まし、凝集する中心的スローガンとなってきたのである。1894年に結成されたこの興中会の入会宣誓は『満州族を駆除し中華を恢復し合州政府を創立する』と言うものであり、更に臨時大統領就任演説では『漢、満、蒙古、回、チベットの諸民族を合わせて一人とし、これを民族統一とする』と唱えた。しかしこの『五族共和論』は清朝の採った満州族中心の異民族支配に通ずるものがあると言うことから、孫文は1920頃、五族と言う名称は不適切であり、中国の全ての民族を一つの中華民族に融合しなくてはならないと軌道修正をしている。これが現在中国で用いられている『中華民族』という観念語の起源であるという。ただ、列強の圧迫の元で中華民族の革命実現には強力な党と軍の出現を待たなくてはならなかったのである。
③国共合作・ソ連に学んだ双子…
1924年6 月16日、中国広東省広州の郊外、ソ連式軍服に身を包んだ五百人余の若者が整列していた。壇上に並ぶ軍閥の領袖たちの目は高い士気と規律の備わった新式軍隊の偉容に釘付けになっていた。国民党の孫文がソ連のコミンテルンと生まれたばかりの中国共産党との協力で設立した『黄埔軍官学校』の開校式である。それは孫文が夢にまで見た政治教育で理論武装した革命軍『党軍』誕生の記念すべき第一歩であり、中国革命を仕切り直す転換期でもあった。孫文は興奮した面持ちで『辛亥革命以来、今日迄の十三年間は失敗の連続であった。原因は我々革命党の奮闘はあったが革命軍の奮闘がなかったからである。本校の学生を基礎に革命軍を創設し中国の危機存亡を救う』と演説する。悲願の革命軍創設と軍官学校開設に当たって何故に孫文はコミンテルンと共産党の力を必要としたのか?これは各地に群雄割拠する軍閥混戦の中で苦戦を強いられた彼は局面の打開を図ろうとするが、日本などの西側への失望は徐々に広がる反面、ロシア革命の一連の経験を取り込みたいと思ったからである。勿論コミンテルン側は孫文の危機的状況を前にして精力的に働きかけ、派遣されていた軍師が国共合作を進言したのである。1923年孫文は党内右派の反対を押し切りソ連との協力を発表し、国共合作を打出す。これは共産党員がその党籍を保持した儘、個人資格で国民党に入党する方式であり対等な協力とは言い難いが、孫文は革命結社である国民党をソ連共産党型政党への改組作業に着手した。これらの事が国共両党が『双生児』と言われる理由である。
軍官学校開設に先だって孫文の指示でソ連に派遣され、赤軍の装備、訓練、組織を吸収して来たのが後に同校校長となる『蒋介石』である。彼は直ぐにソ連が中国固有の領土である外モンゴルを侵略する野心を持つ赤色帝国主義であることを見破りソ連が中国の永遠の友人でない事は良く分かったが、ソ連の援助なしには学校も作れない事も理解していたので、極めて注意深くソ連との友好関係を維持した。それにポスト孫文の争いも熾烈であったから、ここで反共を打出せば直ちに失脚する危険もあったので、この時点では容共政策が彼の取り得る唯一の方策であった。
この軍官学校は国民革命軍の基礎となり、北伐を成功させたばかりでなく、新中国建国の指導者を次々と輩出した。しかしこれは国共蜜月時代の象徴であると同時に、後に両党を引き裂く矛盾の温床となる一面もあった。
④国共合作・血まみれの分裂劇…
共産党は汪精衛の国民党左派と共に蒋介石の脅威となってきた。そして遂に『清党』の事態となる。これは国共合作により国民党の中に個人の資格で入った共産党分子の影響力を一掃することであった。そして1927年 4月12日、蒋介石は上海で反共クーデターを起こす。その少し前の1926年 7月、北伐を開始した国民革命軍は各地で民衆運動を刺激し、上海では労働者が武装糾察隊を組織し、1927年 3月には周恩来に指導された労働者がゼネストを決行し、更には武装蜂起して軍閥軍を駆逐した。労農運動の高揚と共産勢力拡張に危機感を強めた蒋介石は1927年 4月11日、上海に戒厳令を引いて、12日に青幇(チンパン)紅幇(ホンパン)と呼ばれるギャング団に糾察隊を襲わせた上に、国民党による糾察隊の武装解除をした。このとき抗議した糾察隊の幹部は射殺され、これに怒る十万人のデモ隊に機銃掃射を浴びせて数千人の犠牲者を出す。
この事件の後、蒋介石の党籍を剥奪、逮捕状まで出した武漢の国民政府は結局蒋介石に追従し 7月には容共政策を破棄する。この事によって1924年に成立した国民党と共産党の合作は 3年 7か月で終焉したのである。
こうした容共から反共へと戦略転換をせざるを得なかった背景には、予想以上の速度で勢力を拡大する共産党に対して最終的に国民党全体が食い尽くされると言う危機感がある。国共合作の当時、千人に満たない共産党は清党の直前には六万人に膨れ上がっていた。
確かに共産党員の参入が労働者や農民の大衆運動を可能にして地方軍閥を打倒し、中国統一を目指す蒋介石の北伐を成功させたのは事実ではあるが、一方で国民党は『蒋対反蒋』という派閥闘争の激化と言う深刻な後遺症に苦しむことになってしまったのである。
共産党の基本政策は、蒋介石の独裁を阻止し、国民党を分裂させて武漢の国民党左派 (汪精衛側)と連合して南京の国民党右派(蒋介石側)に対抗する事であった。
清党は共産党幹部の大量虐殺を引き起こし、これ以降、黄埔軍官学校は蒋介石に奉仕するだけの反革命拠点に変質し、怨念の対立は双生児である国共両党の骨肉の内戦を引き起こすことになる。
1936年12月、日本軍の侵略と言う国難を前にして西安事件を契機にして漸く第二次国共合作が成立する。しかしこれはかつての様に組織原理が似通った双生児党の協奏曲ではなく両党が夫々の支配地域で日本に抗戦する限定的な共闘でしかなかった。
それにしても孫文の信徒であり三民主義の実現に一生を捧げた筈の蒋介石が抗日戦も勝利し、圧倒的に有利な軍事力を持ちながら、何故共産党に敗れ大陸放棄に追いやられたのであろうか?蒋介石と共に戦い国民党の要職にあったある人物は『蒋介石は中国統一や不平等条約の撤廃等の功績は大きく、軍事の天才でもあるが、欠点は経済の才能に欠けていたことである』と証言している。確かに当時は抗日戦争による軍事費の負担で経済は疲弊し切っていたことは事実である。
1924年以来、25年に及ぶ両党の合作と相克の歴史が、21世紀を目前にした現在も両党を大陸と台湾に分かれて存在させ続けている。
因みに汪精衛(兆銘)の名は私どもの世代では懐かしい。彼は1938年、国民党の副総裁に就任したが、日中戦争の激化の中で日本軍の画策に乗せられ重慶から脱出し、ハノイで和平建議を発表して日本の近衛首相に接近し、1940年日本の傀儡政権である南京政府を樹立して首席に就任したが、1944年に不遇の内に名古屋で病没した。当時子供の私でも憎き蒋介石に相対する親日派として記憶に残っている。











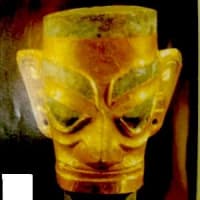








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます