こんばんは 、まろです。
、まろです。
今日は、昨日に続いて化学賞についてお話しをします 。
。
良い話は早く取り上げたいな、と考えたのです 。
。
ノーベル化学賞受賞者は下村脩先生 。
。
受賞理由は「緑色蛍光タンパク質(GFP

 )の発見と開発」です。
)の発見と開発」です。
蛍って夜 、綺麗に光りますよね
、綺麗に光りますよね 。
。
あの光 はルシフェリン
はルシフェリン という物質で、蛍や深海生物、微生物に含まれる発光物質です。
という物質で、蛍や深海生物、微生物に含まれる発光物質です。
下村先生が、発光するオワンクラゲの謎を突き止めるため研究していたころ、生物の発光現象 はこのルシフェリン
はこのルシフェリン が原因だと考えられていました。
が原因だと考えられていました。
無数のクラゲで実験したもののルシフェリン は見つからず
は見つからず 、「ルシフェリン
、「ルシフェリン にこだわらず何でもいいから光る物質
にこだわらず何でもいいから光る物質 を抽出しよう!」と教授の理解を得ないまま、自分で勝手に(!)実験を始めたそうです
を抽出しよう!」と教授の理解を得ないまま、自分で勝手に(!)実験を始めたそうです

 。
。
発光 物質を取り出すには光らない状態で取り出す必要があり(光ると分解しちゃうのです)、失敗を繰り返した後、ある日「生物発光
物質を取り出すには光らない状態で取り出す必要があり(光ると分解しちゃうのです)、失敗を繰り返した後、ある日「生物発光 にはpHが関係しているのでは?」と考え、溶液をpH4(酸性)にすると光らなくなることが判明しました。
にはpHが関係しているのでは?」と考え、溶液をpH4(酸性)にすると光らなくなることが判明しました。
気をよくして溶液を流しに捨てた途端「流しの中がパーッと緑色に光った







 」。
」。
流しには海水があり、そのカルシウム成分と反応して光った のです。
のです。
この発光 成分は「イクオリン
成分は「イクオリン 」と名付けられ、17年かけて発光メカニズムが解明されました。
」と名付けられ、17年かけて発光メカニズムが解明されました。
しかし、イクオリンは青色 なのに、オワンクラゲは緑色
なのに、オワンクラゲは緑色

 。
。
実はイクオリン を精製した際に緑色に輝く
を精製した際に緑色に輝く

 副産物を見つけ、捨てずに研究を重ねていたそうです。
副産物を見つけ、捨てずに研究を重ねていたそうです。
その正体が緑色蛍光タンパク質(GFP

 、ノーベル賞受賞の理由となった物質)。
、ノーベル賞受賞の理由となった物質)。
この物質がイクオリンの青い光 を受けて緑
を受けて緑

 に発光していたことを突き止めましたが、当時は「美しいだけが取り柄で、何の価値もない物質だった
に発光していたことを突き止めましたが、当時は「美しいだけが取り柄で、何の価値もない物質だった 」そうです。
」そうです。
ですが、蛍光タンパク質のなかでは自ら発光 する変わり種で、このため生体内で作り出せる特徴があり、90年代に入って一躍
する変わり種で、このため生体内で作り出せる特徴があり、90年代に入って一躍 脚光
脚光 を浴び始めました。
を浴び始めました。
調べたいタンパク質の遺伝子に、GFP遺伝子

 をくっつけてその蛍光を目印とし、目的のタンパク質がどこにあり、どう運ばれるのかわかるようになりました。
をくっつけてその蛍光を目印とし、目的のタンパク質がどこにあり、どう運ばれるのかわかるようになりました。
たとえばガン細胞であれば、転移や増殖がわかるようになったのです。
生体内で利用する手法を確立したチャルフィ博士、チエン博士と同時受賞で、病気の原因究明や治療薬の開発に大きく貢献しています

 。
。
今日も長くなってしまいましたが、ここまで読んでいただけて嬉しいです 。
。
今回は産経新聞を参考にさせていただきました 。
。
下村先生は今でも研究を続けられているそうで、飽くなき探求心を是非とも見習いたいです 。
。
何でも趣味は美術鑑賞 で、いわば対極にあるものが好きな理由は、「科学者として正しいゆがみのない思考力を持つためには、科学とまったく違う趣味を持つのがよい」からだそうです。
で、いわば対極にあるものが好きな理由は、「科学者として正しいゆがみのない思考力を持つためには、科学とまったく違う趣味を持つのがよい」からだそうです。
素敵な言葉です 。
。
ワタクシもそう思います

 !
!
ゆがみのない思考力を持つために、ワタクシはお菓子作り や映画鑑賞や読書
や映画鑑賞や読書 や温泉巡り
や温泉巡り しつつ、ボランティアにいそしみます。遊びすぎに注意?
しつつ、ボランティアにいそしみます。遊びすぎに注意?
来月は11月13日 19:30から 松山ベンチャークラブの11月定例会があります。

場所は 松山市民会館
ボランティアに興味のある方
私たちと一緒にボランティアに参加してみませんか。


お気軽にどうぞ。来られる方 コメントなどで お知らせください♪


人気blogランキング参加中です!
 ボランティアブログも登録しました!
ボランティアブログも登録しました!
 励みになります。
励みになります。
1クイックよろしくお願いいたしまぁす!
 、まろです。
、まろです。今日は、昨日に続いて化学賞についてお話しをします
 。
。良い話は早く取り上げたいな、と考えたのです
 。
。ノーベル化学賞受賞者は下村脩先生
 。
。受賞理由は「緑色蛍光タンパク質(GFP


 )の発見と開発」です。
)の発見と開発」です。蛍って夜
 、綺麗に光りますよね
、綺麗に光りますよね 。
。あの光
 はルシフェリン
はルシフェリン という物質で、蛍や深海生物、微生物に含まれる発光物質です。
という物質で、蛍や深海生物、微生物に含まれる発光物質です。下村先生が、発光するオワンクラゲの謎を突き止めるため研究していたころ、生物の発光現象
 はこのルシフェリン
はこのルシフェリン が原因だと考えられていました。
が原因だと考えられていました。無数のクラゲで実験したもののルシフェリン
 は見つからず
は見つからず 、「ルシフェリン
、「ルシフェリン にこだわらず何でもいいから光る物質
にこだわらず何でもいいから光る物質 を抽出しよう!」と教授の理解を得ないまま、自分で勝手に(!)実験を始めたそうです
を抽出しよう!」と教授の理解を得ないまま、自分で勝手に(!)実験を始めたそうです

 。
。発光
 物質を取り出すには光らない状態で取り出す必要があり(光ると分解しちゃうのです)、失敗を繰り返した後、ある日「生物発光
物質を取り出すには光らない状態で取り出す必要があり(光ると分解しちゃうのです)、失敗を繰り返した後、ある日「生物発光 にはpHが関係しているのでは?」と考え、溶液をpH4(酸性)にすると光らなくなることが判明しました。
にはpHが関係しているのでは?」と考え、溶液をpH4(酸性)にすると光らなくなることが判明しました。気をよくして溶液を流しに捨てた途端「流しの中がパーッと緑色に光った








 」。
」。流しには海水があり、そのカルシウム成分と反応して光った
 のです。
のです。この発光
 成分は「イクオリン
成分は「イクオリン 」と名付けられ、17年かけて発光メカニズムが解明されました。
」と名付けられ、17年かけて発光メカニズムが解明されました。しかし、イクオリンは青色
 なのに、オワンクラゲは緑色
なのに、オワンクラゲは緑色

 。
。実はイクオリン
 を精製した際に緑色に輝く
を精製した際に緑色に輝く

 副産物を見つけ、捨てずに研究を重ねていたそうです。
副産物を見つけ、捨てずに研究を重ねていたそうです。その正体が緑色蛍光タンパク質(GFP


 、ノーベル賞受賞の理由となった物質)。
、ノーベル賞受賞の理由となった物質)。この物質がイクオリンの青い光
 を受けて緑
を受けて緑

 に発光していたことを突き止めましたが、当時は「美しいだけが取り柄で、何の価値もない物質だった
に発光していたことを突き止めましたが、当時は「美しいだけが取り柄で、何の価値もない物質だった 」そうです。
」そうです。ですが、蛍光タンパク質のなかでは自ら発光
 する変わり種で、このため生体内で作り出せる特徴があり、90年代に入って一躍
する変わり種で、このため生体内で作り出せる特徴があり、90年代に入って一躍 脚光
脚光 を浴び始めました。
を浴び始めました。調べたいタンパク質の遺伝子に、GFP遺伝子


 をくっつけてその蛍光を目印とし、目的のタンパク質がどこにあり、どう運ばれるのかわかるようになりました。
をくっつけてその蛍光を目印とし、目的のタンパク質がどこにあり、どう運ばれるのかわかるようになりました。たとえばガン細胞であれば、転移や増殖がわかるようになったのです。
生体内で利用する手法を確立したチャルフィ博士、チエン博士と同時受賞で、病気の原因究明や治療薬の開発に大きく貢献しています


 。
。今日も長くなってしまいましたが、ここまで読んでいただけて嬉しいです
 。
。今回は産経新聞を参考にさせていただきました
 。
。下村先生は今でも研究を続けられているそうで、飽くなき探求心を是非とも見習いたいです
 。
。何でも趣味は美術鑑賞
 で、いわば対極にあるものが好きな理由は、「科学者として正しいゆがみのない思考力を持つためには、科学とまったく違う趣味を持つのがよい」からだそうです。
で、いわば対極にあるものが好きな理由は、「科学者として正しいゆがみのない思考力を持つためには、科学とまったく違う趣味を持つのがよい」からだそうです。素敵な言葉です
 。
。ワタクシもそう思います


 !
!ゆがみのない思考力を持つために、ワタクシはお菓子作り
 や映画鑑賞や読書
や映画鑑賞や読書 や温泉巡り
や温泉巡り しつつ、ボランティアにいそしみます。遊びすぎに注意?
しつつ、ボランティアにいそしみます。遊びすぎに注意?来月は11月13日 19:30から 松山ベンチャークラブの11月定例会があります。


場所は 松山市民会館
ボランティアに興味のある方
私たちと一緒にボランティアに参加してみませんか。



お気軽にどうぞ。来られる方 コメントなどで お知らせください♪



人気blogランキング参加中です!
 ボランティアブログも登録しました!
ボランティアブログも登録しました! 励みになります。
励みになります。1クイックよろしくお願いいたしまぁす!










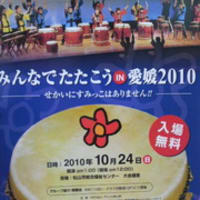









おお~失敗は 成功のもと 、、、
かなり はまりますね~ ノーベル賞シリーズ
柔軟な考え方で 研究されていたからこそ
発見でき その発見を 実用化された人たちがいる
自分と 違う分野のかたたちとの交流って大事ですね~
今回も 興味深く 読んじゃいました
あと、奇跡的な幸運を自分のものに出来る事が出来たのは、それまでの努力があってこそなんでしょう。
興味深く読んでもらえて嬉しいです♪