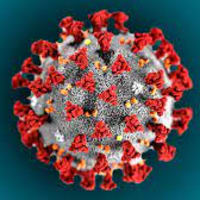山が新緑に萌える五月の日曜日、大菩薩嶺に登る。上日川峠への道中には、武田勝頼の終焉の地に建つ景徳院(天正10年・1582年3月没)、栖雲寺、竜門峡、温泉宿、釣り堀、ダム湖などがある。駐車場はほぼ満車で、遅れると下に迂回させられるようだ。
1000:長兵衛小屋発。福ちゃん荘までは緩斜面で、ここから唐松尾根にとりつく。名前の通り辺りは唐松の植林帯だ。森林限界を越えると眺望は一気に開ける。左手には甲斐駒から光岳まで南アの全山を望む。振り返ると、絵に描いたような富士山だ。確かにここから眺める富士は一級品だ。

1130:雷岩に着く。名の通り雷が落ちそうな岩だ。展望は更に開け、その主役はやはり富士山。三つ峠と黒岳の間の弓状に下がる山波の上に、均整のとれた山裾を優雅に広げて聳える。黒っぽい山肌には、白い筋を引くように残雪が5合目付近まで延びている。すぐ手前の湖も景色に一興を添える。

大菩薩嶺頂上(2057m)には展望がないので、雷岩まで戻り、岩屑が広がる平坦地で食事とする。贅沢な展望と涼風の心地よさに時の経つのを忘れた。長居して、1320に出発。尾根を南下し大菩薩峠(1897m)へ。峠からの下山道は歩きやすく、1430には出発点に帰着となった。

この山塊は主に四万十帯の砂岩から成り、そのためか全体になだらかな山容を呈する。峠からの道には所々に泥岩も混じていた。なぜか雷岩の付近にだけ深成岩が陥入していて、花崗岩やトーナル岩が転がる。これらの固い岩が浸食に耐えて残ったということだろう。
大菩薩という大仰な名前は、源義光(新羅三郎)の伝説によるらしい。奥州で戦う兄の八幡太郎義家の援軍に向かう途中、この山中で迷い、八幡大菩薩に導かれたことが由来という。義光はこの地で子孫を残し甲斐源氏の祖となった。笛吹市にある石橋八幡神社は義光の創建だ。
中里介山の小説「大菩薩峠」とも関連がある。もっとも、物語は幕末の剣士(机竜之介)がこの峠で巡礼の老人を無為に切り殺す所から始まる。その後も延々と殺伐とした因業話が続き、旧士族の憤懣と虚無感が満ちる。山容が真逆にも明るいのが、実は命名の妙なのかもしれない。