こんなことを言うのも気が引けるのだが、先週は恵子の介護を始めて以来初めて自分自身がダウンしてしまった。
おそらく、目の前で苦しんでいる私の様子を見て恵子の方があわてたのかもしれない。
彼女は麻痺でまだ思う通りに身体を動かせないのだから、いくら私が倒れたといっても彼女に私の身体を運んだりする芸当などできるわけがない。
それでも、「火事場のなんとか」ではないが、彼女も必死だったのだろう。
携帯電話を駆使して何とか私の急場を救ってくれた。
幸い、こんな「限界集落」のような別荘地でもすぐ近所にとても親しくしている元高校の養護の先生Yさんがいる。
彼女は八丈島の学校で養護教員を長い間やった後私たちの近所に家を買い、以来近所づきあいをずっと続けているが、恵子は咄嗟にこの彼女に救いを求めたのだ。
しかし、電話をしてすぐに駆けつけて来てもらったのは良いが、鍵のかかっている玄関のドアを開けないことにはYさんを家に招き入れることができない。
発症以来これまで恵子が一人で玄関の鍵を開けたことは一度もない。
きっと恵子にしてみれば「清水の舞台から飛び降りる」ような気持ちでその作業(廊下から20センチはある「あがりかまち」を降り、玄関ドアまで行き鍵をおろすまでの一連の動作にどれぐらいの時間を要したのだろう)をやったに違いない。
何度も「待っててください。今開けますから」と外に向って叫ぶ声が朦朧とした私の耳にも届いていた。
外からはそれに応えるように「いいよ、いいよ。ゆっくりで」とYさんの声がする。
ようやく家に入ってきたYさんがベッドの私に尋ねる」「どうしたの?」
立ちあがるとフラフラして真っすぐ立っていられない。身体が右に右に傾いてしまうし、気持ちが悪くて身体が動かせない。
何とか自分の症状を説明する。
彼女は私の血圧を計りながら「左手上げられる?」と私に聞く。
私が左手を上にあげると「ああ、大丈夫だ」と私をなだめる。
この日の昼間、私は暑いさなか恵子の入浴の介助をしたり忙しくたち働いたおかげで熱中症にかかったのかもしれなかった。
あるいは、長い間の介護疲れが出たのかもしれない。
しかし、この近所のYさんの適確な処置のおかげで、救急車を呼ばずに済んだ。
救急車を呼ぶことに抵抗があるわけではないが、その後に一人で家に残されてしまう恵子のことを考えるとそう簡単に「救急車を呼んで」とは言えない。
恵子にしてみれば、ちょうど二年前の自分自身が体験した「悪夢」が蘇り気が気ではなかったはずだ。
恵子が二年前脳溢血で倒れた時ちょうど一緒にいた叔母の話によれば、恵子は、食事をしていて急に「身体の右側が変だよ。気持ちが悪い」と言い、畳の上に倒れ込み吐いたのだという。
きっと私の症状に過去の自分の姿を見たことだろう。
彼女の頭の中はパニックになっていたのかもしれないが、しっかりと私を助けてくれた。
介護の現実というのはこんなところにも如実に現れる。
子供が親を介護するのは、子供にとってすごい「負担」であることは間違いないが、まだ子供は親より若い分「楽」なのかもしれない。
しかし、世の中には、老人が老人を介護する、認知症が認知症を介護する「現実」がそこかしこにあるし、その数はきっと増えこそすれ減ることはないだろう。
政治や行政は「予防医学」ということを盛んに言っていて「病気にならない」「介護の必要のない」健康を国民に求めるが、そのためにしなければならないことは一つや二つではないはずだ。
一人一人が自分自身の健康をもっと「義務」として考えるべきだし、もっと地域差や個人差など多様化した「生活」の中で多様化した「健康ライフ」を考えるべきなのではないのかなとも思う。
私の講演会でもそこにいた介護士、看護士、施設関係の人たちから浴びせられる質問は、私の語った「介護現場への音楽の必要性」などという「総論」などではなかった。
そんなことはわかっているから具体的にどうすれば良いのか教えてくれという叫びが私の耳の奥に聞こえるようだった。
「介護する疲れた人」にこそ音楽が必要と言って立ち上げた「MUSIC-HOPEプロジェクト」だが、ひょっとしたら一番音楽が必要なのは私自身なのかもしれない。
「医者の不養生」「紺屋の白袴」と言われないよう、自分自身の健康は今以上に気をつけなければと思う。
おそらく、目の前で苦しんでいる私の様子を見て恵子の方があわてたのかもしれない。
彼女は麻痺でまだ思う通りに身体を動かせないのだから、いくら私が倒れたといっても彼女に私の身体を運んだりする芸当などできるわけがない。
それでも、「火事場のなんとか」ではないが、彼女も必死だったのだろう。
携帯電話を駆使して何とか私の急場を救ってくれた。
幸い、こんな「限界集落」のような別荘地でもすぐ近所にとても親しくしている元高校の養護の先生Yさんがいる。
彼女は八丈島の学校で養護教員を長い間やった後私たちの近所に家を買い、以来近所づきあいをずっと続けているが、恵子は咄嗟にこの彼女に救いを求めたのだ。
しかし、電話をしてすぐに駆けつけて来てもらったのは良いが、鍵のかかっている玄関のドアを開けないことにはYさんを家に招き入れることができない。
発症以来これまで恵子が一人で玄関の鍵を開けたことは一度もない。
きっと恵子にしてみれば「清水の舞台から飛び降りる」ような気持ちでその作業(廊下から20センチはある「あがりかまち」を降り、玄関ドアまで行き鍵をおろすまでの一連の動作にどれぐらいの時間を要したのだろう)をやったに違いない。
何度も「待っててください。今開けますから」と外に向って叫ぶ声が朦朧とした私の耳にも届いていた。
外からはそれに応えるように「いいよ、いいよ。ゆっくりで」とYさんの声がする。
ようやく家に入ってきたYさんがベッドの私に尋ねる」「どうしたの?」
立ちあがるとフラフラして真っすぐ立っていられない。身体が右に右に傾いてしまうし、気持ちが悪くて身体が動かせない。
何とか自分の症状を説明する。
彼女は私の血圧を計りながら「左手上げられる?」と私に聞く。
私が左手を上にあげると「ああ、大丈夫だ」と私をなだめる。
この日の昼間、私は暑いさなか恵子の入浴の介助をしたり忙しくたち働いたおかげで熱中症にかかったのかもしれなかった。
あるいは、長い間の介護疲れが出たのかもしれない。
しかし、この近所のYさんの適確な処置のおかげで、救急車を呼ばずに済んだ。
救急車を呼ぶことに抵抗があるわけではないが、その後に一人で家に残されてしまう恵子のことを考えるとそう簡単に「救急車を呼んで」とは言えない。
恵子にしてみれば、ちょうど二年前の自分自身が体験した「悪夢」が蘇り気が気ではなかったはずだ。
恵子が二年前脳溢血で倒れた時ちょうど一緒にいた叔母の話によれば、恵子は、食事をしていて急に「身体の右側が変だよ。気持ちが悪い」と言い、畳の上に倒れ込み吐いたのだという。
きっと私の症状に過去の自分の姿を見たことだろう。
彼女の頭の中はパニックになっていたのかもしれないが、しっかりと私を助けてくれた。
介護の現実というのはこんなところにも如実に現れる。
子供が親を介護するのは、子供にとってすごい「負担」であることは間違いないが、まだ子供は親より若い分「楽」なのかもしれない。
しかし、世の中には、老人が老人を介護する、認知症が認知症を介護する「現実」がそこかしこにあるし、その数はきっと増えこそすれ減ることはないだろう。
政治や行政は「予防医学」ということを盛んに言っていて「病気にならない」「介護の必要のない」健康を国民に求めるが、そのためにしなければならないことは一つや二つではないはずだ。
一人一人が自分自身の健康をもっと「義務」として考えるべきだし、もっと地域差や個人差など多様化した「生活」の中で多様化した「健康ライフ」を考えるべきなのではないのかなとも思う。
私の講演会でもそこにいた介護士、看護士、施設関係の人たちから浴びせられる質問は、私の語った「介護現場への音楽の必要性」などという「総論」などではなかった。
そんなことはわかっているから具体的にどうすれば良いのか教えてくれという叫びが私の耳の奥に聞こえるようだった。
「介護する疲れた人」にこそ音楽が必要と言って立ち上げた「MUSIC-HOPEプロジェクト」だが、ひょっとしたら一番音楽が必要なのは私自身なのかもしれない。
「医者の不養生」「紺屋の白袴」と言われないよう、自分自身の健康は今以上に気をつけなければと思う。















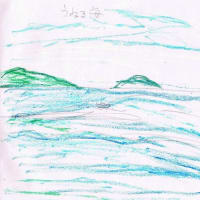


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます