…お久しぶりです。最近は一週間に一回の更新になってきていますね…まずいわ…(汗)。反省はいったんおいて、久しぶりに真面目な史実系長宗我部氏について語ります。はい、当ブログへの検索で時々見かける『長宗我部家の読みについて』と『長宗我部家は”曾”が正しい?』といったものなので、その辺りを解説します(笑)。
読み方に関しては私も確証がなかったのですが、先々週の歴史家の先生が教えてくれまして、ゆえに”ソ”の字も含めまして何とか解説できるレベルになったと思いますので、ちょっと書いていきます。なお、今回の内容は今までに出席した長宗我部氏に関する歴史研究家や学芸員の講義・講座や、御子孫の方が書いた本や、お話を元にしています。
Q1.長宗我部家の”ソ”は”宗”or”曾”のどっち?
A1.”宗”が正しいです。”曾”は厳密に言えば間違い。
いきなり断言みたいな言い回しですが、”宗”が正しいという根拠はあるのです。以下がその根拠。
1.元親の異母弟になりますが、島弥九郎親房系の御子孫が『長宗我部』が正しいとはっきりおっしゃっている(とはいえ、「”曽”でも”曾”でも長宗我部を大事にしてくれるなら問題はない」と言われています)
2.昔は地名が先に在り、名字はそれに付随するもの。元親の先祖の入った土地は「宗我部」という地名だった(なお、高知は「宗我部」という名字が多い)。
3.元親自身が、署名として書状に「長宗」と書いている史料が残っている
以上の三つが、長宗我部家の”宗”が正しいという根拠です。
1…については御子孫の方が書籍を発行していますし、長宗我部氏の勉強になりますので、長宗我部家が好きな方は読むことをお勧めします♪ただ、( )書きにもありますように、”長曽我部”や”長曾我部”として小説やゲームで知った方も多く、御子孫の方も「長宗我部を好きであるなら、大事にしてくれるなら”宗”でも”曾”でも”曽”でも構わない。」と話されていましたが、やはり本来の”宗”に対する思い入れはあると思います。
2…について、これは次のQ2で具体的に説明しますが、昔の名字と言うのは先に土地がありき、です。その土地に入っていく、という意味で名字が生まれた経緯があるという話もあります。よって、県外ではどうか知りませんが、高知では”宗我部”という地名が多くありました。どうして”宗”が使われているかは…わかりません(滝汗)。その辺りは大学教授とか研究者の分野だと思うので、ここでは追求しません、はい(汗)。
3…については…この史料は確かにありますが、一般的にあまり書籍に載るようなものではありません。私も長宗我部氏についての講議に参加し、そこで配られた資料で知ったくらいです。元親も四文字の名字は長いと思ったのか、名前だけとか、「長宮(長宗我部宮内少輔の略)」という風に署名していますが、まだ官職名を名乗っていなかったと思われる初期の書状は「長宗」と書いていたようです。この「長宗」と書かれた書状は国親が亡くなった後、本山氏を攻めている最中、現在の高知市内にいた本山方の有力者に対して書かれています。
ちょっと詳しくなりますが、今の高知市内にいた本山方の有力武家の多くは…じつは長宗我部家から分かれた分家筋が多かったのです(二代・三代・七代の兄弟達で分家が増えている。特に七代の兄弟達は高知市内に土地を得た模様)。ですから、元親も分家筋の攻略として力攻めではなく、「元は同じ秦氏であり、共通の先祖を持つから長宗我部家に帰属しませんか?今なら土地や既得権益も保証します」といった内容の書状を多く送りました。その中で書状の最後に「長宗元親」といった署名をしています。ちなみに…全く関係ない地元武家に対しては署名が花押だけ、といった結構「え?」なものもあり、分家筋とそうでない本山方の武家の対応差に思わず苦笑しました(笑)。
元親の直筆サインもあるので、”長宗我部”というのは間違いないのですが、県外…つか土佐国外に残された史料では全部”長曽我部”or”長曾我部”となっているのです。土佐と言う土地には独特の読みや名字(これらは土佐に限りませんがね)がありますが、恐らく当時の日本の中枢であった上方や中部・近畿地方の方では「ちょうそがべ」という音を聞く時、”宗”が”ソ”と読むのに気が付かなかったのではないかと……書状でも普通はあまり自分の家の家名は書きませんしね。ですから、土佐国外の武将達は自分たちの知っている範囲の音と同じ漢字として”曾”や”曽”を当てて書き記したのではないかと想像しています。
まあ…これは愚痴になりますけどね……どうしても気になることがありましてね…さらっと流してください……
2012年秋頃に出された若者向けの歴史雑誌『戦国魂』という本には「長曾我部」が正しくて、「長宗我部」は間違いだと断言している記事がありました……この記事を書いたライターの勉強不足に記事読んだ途端、手が震えるくらい激怒しましたが、雑誌自体がカプ〇ン系だと気が付いたので、むしろ飽きれました…。「知識不足のくせに、なにそのコー〇ーさんに対する対抗意識…」と(滝汗)。
正直申しますと、私はこの雑誌は最初買うつもり(神谷さんVoiceによるCDドラマも付いていましたしね)でいましたが、この記事を読んで一気に興醒め。買う気力も失せ、そのまま置きました。まだ「こういう説もありますよ」くらいで留めておけばいいのに、断言したところで「もうダメだ」と…(涙)。全国誌で、更に若者を対象にした雑誌で間違いを教えてどうする…と悲しくもなりました…。
ああ、もう愚痴は終わり!!そんなこんなで次の疑問に行きます。
Q2.長宗我部の読み方は、”ちょうそがべ”or”ちょうそかべ”のどっち?
A2.「ちょうそかべ」が正しいです。濁らない方が正解
これはA1の解説でもありました「名字は土地由来」が関係しています。長宗我部家が好きな方が良く聞くエピソードとして、元親の弟・親泰が養子に入った香宗我部家との関係についてですが、元々は違った家(秦氏と甲斐源氏)で親戚関係は無くただ、お互いに土地の名前を取って「宗我部」を名字を使っていました…が、領地が近い事と名字が一緒なことで混合されるかもしれないから、長岡郡にいた秦氏系宗我部さんは「長宗我部」、香美郡にいた甲斐源氏系宗我部さんは「香宗我部」となりました(結局、最終的には親泰が養子に入って親戚になりましたがね)。
しかし、この間聞いたお話ではその二つの家の読みについても言及があり、初めて読みの違いも知りました!!以下に解説!!!
1.秦氏が入った土地は元々「宗部」と書いて「そかべ」と呼んでいた。
2.甲斐源氏である中原家が入った土地は「宗我部」と書いて「そがべ」と呼んでいた。
3.いつ頃か時代がはっきりしないが、「宗部」の土地名は「宗我部」となっていった??
4.字は共通であるが、読みは元の土地の読みに従った。
と、いう事で……土地の呼び方を考慮して、
長宗我部家の読みは「ちょうそかべ」、
香宗我部家の読みは「こうそがべ」
が正しいのだそうです。濁点一つについても奥が深いですね…いや~勉強になりました!!
ちなみに…本当に高知の名字は「宗我部」と書いて「そがべ」さんと読む方が多いのです。逆に「曽我」という名字で”宗”の字を使っているのは見たことないです…。また、今では曽我部という地名や名字は見受けられますが、”曽”を使う家の中には長宗我部家の分家筋だが、山内家が入ってきたため、表立って”宗”を使うのがはばかられて”曽”を意図的に使っている…という家もあるようです。また主家にあやかって曽我部と名乗る家もあったようです…。この辺りは各家の伝承になるので、もう真偽のほどは確かめようがありませんけれどね…(汗)。
と、まあ私が仕入れた範囲の知識で長宗我部家の”ソ”の字がどちらなのか?という事と読みについて語らせていただきました。…そういえば、元親が行った検地もちゃんと「長宗我部検地帳」として表書きされているわ……今更ながら気が付いた(爆)
最新の画像[もっと見る]
-
 須崎で美味しい店発見!!
11年前
須崎で美味しい店発見!!
11年前
-
 前の記事に続き、しばらく溜めていた記事をアップ。進撃の巨人が楽し過ぎる!!
12年前
前の記事に続き、しばらく溜めていた記事をアップ。進撃の巨人が楽し過ぎる!!
12年前
-
 日曜日になんと、10年以上ぶりにあった友達と遊びました!!
12年前
日曜日になんと、10年以上ぶりにあった友達と遊びました!!
12年前
-
 一週間放置したので…そろそろ削除しようかと思うボウリング話。
12年前
一週間放置したので…そろそろ削除しようかと思うボウリング話。
12年前
-
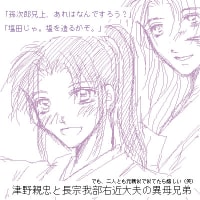 卵が先か、ヒヨコが先か…な気持ちになった、長宗我部右近大夫の話(笑)
12年前
卵が先か、ヒヨコが先か…な気持ちになった、長宗我部右近大夫の話(笑)
12年前
-
 ちょいとネタバレ!!(5/19のまつりについて)
12年前
ちょいとネタバレ!!(5/19のまつりについて)
12年前
-
 ちょいとネタバレ!!(5/19のまつりについて)
12年前
ちょいとネタバレ!!(5/19のまつりについて)
12年前
-
 長宗我部フェス&長宗我部まつりのチラシアップ!!
12年前
長宗我部フェス&長宗我部まつりのチラシアップ!!
12年前
-
 長宗我部フェス&長宗我部まつりのチラシアップ!!
12年前
長宗我部フェス&長宗我部まつりのチラシアップ!!
12年前
-
 長宗我部ファンクラブのホームページ、アップしたぞ~!!
12年前
長宗我部ファンクラブのホームページ、アップしたぞ~!!
12年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます