小学生の頃の愛読書は、『女工哀史』でした! 作家の三浦しをんさんは、友人からこう言われて度肝を抜かれたそうです。自身も読んでみて「おもしろい。たしかにこれはおもしろい!」と書いています。
「私がなによりも胸打たれたのは、著者の細井和喜蔵(わきぞう)の徹底した男女平等の視線だ……この本に書かれた社会のひずみと女性を取り巻く問題点は、もちろん改善されてはいるが、いまも完全な解決には至っていないと言っていいはずだ」(『本屋さんで待ちあわせ』)。
『女工哀史』は、紡績工場の過酷な実態を告発した100年前のルポルタージュです。人身売買同然の女工集め、監獄のような寮生活、一般女性の3倍もの死亡率といった多数の実例を挙げて描いています。
細井和喜蔵は機械修理工でした。工場の女性たちの荒れた手を見て「(人々は)衣服を纏(まと)うために幾万の若い女性が犠牲になって行くかを果(はた)して考えたことがあるだろうか」と胸を痛めます。仕事をやめ、病気を押して同書を書き上げました。
和喜蔵は『女工哀史』刊行の1カ月後に28歳の若さで病死。8月18日は没後100年にあたります。執筆を助けた妻の高井としをは、戦後、地域で労働組合を結成し、和喜蔵没後50年にはこう書いています。
「その心を そのがんばりを/私が みんなもらってる/そして 若い人にうけついでもらう」。今年6月、としをの評伝『不屈のひと 物語「女工哀史」』(石田陽子著)が出ました。今につながる和喜蔵からのバトンです。















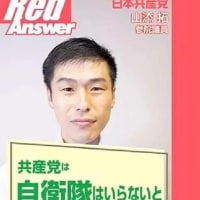




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます