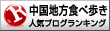松本清張原作「砂の器」のロケ地

「亀嵩駅」

その亀高駅舎内にあるお蕎麦屋さん

「扇屋」
なんと
店主は亀嵩駅長も兼務しているという

「割子そば」

蕎麦猪口の蕎麦湯が一緒に出されるのが
出雲そば流

割子そばの一般的なトッピングは
刻み海苔・ネギ・鰹節・もみじおろしだと思うが
こちらでは
もみじおろしなし

挽きぐるみ
太くてエッジがピンと立った蕎麦

つゆを回しかけ手繰る
強いコシ
ワシワシと噛み締めれば
蕎麦の香りが広がる
嘉味!

もみじおろしの代わりに一味唐辛子
間違いない
ところで
そばが出された際に
蕎麦つゆの徳利に書かれた「かっぱ天国」の意味について
尾根遺産に尋ねたが
ただ戸惑うだけだったことをこのエントリーを書きながら思い出し
ChatGPTに訊いてみた
「かっぱ天国」と書かれた徳利(とっくり)を見かけるのは、出雲地方の割子そば(わりごそば)を出すそば店でよくある光景ですね。これは実は、**島根県出雲市にある温泉旅館「かっぱ天国」**が使っていた、または販促品として出していた徳利が、そば店などに流通したことによるものと考えられています。つまり、「かっぱ天国」と書かれているのは製品名や店舗名の名残であり、現在のそば屋とは直接関係がない場合が多いです。
詳しく説明すると:
- 「かっぱ天国」はもともと玉造温泉(またはその周辺)にあった温泉施設・旅館の名前です。
- その施設が自家用に作ったり配布した徳利が、のちに飲食店に流通(あるいは譲渡)され、割子そばのつゆを入れる器として再利用されたと考えられます。
- 出雲地方では、そばのつゆを徳利で提供する文化があるため、その器に何かしらのロゴや文字が入っているのは珍しくありません。
- この徳利は、ある種の「業務用食器」としてそば店に広く使われているだけで、「かっぱ天国」というそば店が存在しているわけではないケースが大半です。
まとめ
- 「かっぱ天国」とは、過去に存在した温泉施設や旅館の名前。
- そば屋で使われている徳利は、その施設の名入り徳利が転用されているだけ。
- 出雲地方のそば文化や器の再利用文化が反映された、ちょっと不思議で面白い光景。

なるほど!
そういうことですか

ごちそうさまです

かっぱも昇天するくらいの美味しさでした

☆☆☆(☆☆☆また行きたい ☆☆美味しかった ☆まずまず ×価値なし)
営業時間 10:00〜15:00
定休日 火曜日(祝日の場合は営業)
駐車場 あり
仁多郡奥出雲町郡340JR木次線亀嵩駅構内 ℡0854-57-0034