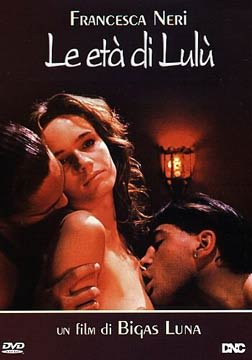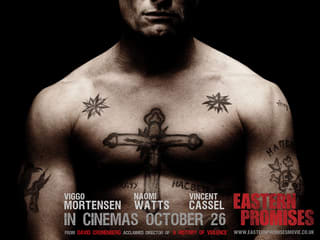映画「こねこ」
監督:イワン・ポポフ
出演:アンドレイ・クズネツォフ、リュドミラ・アリニナ、アレクセイ・ヴォイチューク、タチヤナ・グラウス、マーシャ・ポポワ、サーシャ・ポポフ
1996年
<あらすじ>
モスクワに住む音楽家一家の子供たちが、ペット市場で1匹の子猫を貰ってくる。子猫は、「チグラーシャ」(トラ猫の愛称で「トラちゃん」といった意味)と名づけられるが、一家に様々な波瀾を巻き起す。
ある日、チグラーシャは、窓辺で遊んでいるうちにトラックの荷台に落ちてしまい、見知らぬ通りに運ばれてしまう。
一家の懸命の捜索も空しく、何日たってもチグラーシャは見つからない。チグラーシャも我が家を探して街を歩き回り、ワーシカという猫に助けられる。ワーシカは、チグラーシャを雑役夫のフェージンのところへ連れて行く。そこには、たくさんの猫たちがいた。
チグラーシャが、やっと平静を得たと思ったのもつかの間、フェージンは屋根裏部屋の明渡しを要求する追い立て屋との争いで大怪我をし、病院に入れられてしまう。猫たちは街へ出て、様々な知恵を働かせて食べ物を探し、お互いを支えあって生き延びる。
大晦日、仲間たちと通りに出たチグラーシャは、懐かしい響きを耳にする。子供たちと一緒に過ごしていたころ聞いたパパのフルートのメロディーだった。チグラーシャは、演奏中のステージに駆け登る。
一方、病院から帰ってきたフェージンは、ひとり寂しく、新年を祝おうとしていた。そこに、猫たちが次々と帰ってくる。
家にいるかわいいやつらだけでは飽き足らないのか。
過剰な猫愛はとどまることを知りません。
前にもどこかで書きましたが、これって「種としての女」を愛している「女好きな男」の心理と似ていると思います。
とにかく「女=猫」であるだけでみんな愛しい、みたいな。
似てるようで、本質的に異なるのは「男好きな女」で、前者(女好きの男)が、「愛情を与えたがる」のに対して、後者は「愛情を欲しがる」。たまにその逆もあるけど、ほとんどこの形だと思うな。
さて、この映画、大変良く出来ています。
持ち主から「内容はそんなにないですよ」と言われていたのですが、これがなかなかちゃんとしたエンターテイメントな物語に出来上がっている。
人間や人慣れした犬なら演技が出来るけど、猫は基本的に人の言うことを聞かない動物なので、一体どうやって動かしたのか本当に不思議です。
(ロシアには有名な「猫サーカス」があり、そこで猫調教師の第一人者として活躍してる方が出演されていますが、猫にどうやって芸を仕込むんだろう)
それに私も奴らの動きを動画で撮ろうと日々追ってますが、いつもいい絵が撮れないうちにバッテリー、容量切れになってしまうんだよね。
画像的に(時代的にも)明らかにフィルムで撮ってるはずなのに、どれだけ回したんだろうこの映画…
猫に振り回される音楽家の家族とか、その生活とか、ロシアって結構精神的に豊かなんだなあ…とびっくりしました。
私の知ってる限り、まだ中国には動物映画はないような気がします(70年代~80年代の国営アニメラボの秀逸なアニメならある)。
ま、人民が動物に近い感じだから敢えてつくらなくてもいいような気がするけど(毒)。
印象に残ったのは猫数匹に囲まれて生活する中年男性(この人が本職では猫調教師)。
日雇いのような仕事を適当にやって、その日暮らしの生活を送っている感じなんだけど、猫に芸を仕込んだりして、かなり満足度の高い生活の様子。
臨時収入があるとちょっと豪華な餌を一緒に食べたりね。
私も去年は自分の誕生日のカウントダウンに、高級猫缶をあけて一緒にお祝いしたので、ほとんど同じだなと苦笑してしまいました。
今も2匹に囲まれて、非常に満ち足りた毎日を送れていて、なにはなくとも猫と自分の食い扶持が確保できればそれでいい…って思えてきた最近。
猫欠乏症の方には必見です(が重篤になる恐れがあります)。