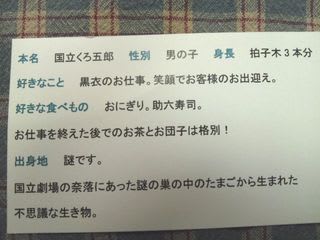このたびやっと、「山中常盤 牛若丸と常盤御前 母と子の物語」(監督:羽田澄子/カラー/35ミリ 16ミリ/1時間40分/製作:自由工房/2004年)を拝見することができました。


これは、江戸時代初期に活躍した絵師、岩佐又兵衛の作とされる「山中常盤物語絵巻」(MOA美術館所蔵)の各場面を撮影した映像に、古浄瑠璃をもとに復曲した義太夫節をつけて構成した映画で、義太夫を聴きながら美しい絵巻の映像を楽しむことができるという、私のような人間には極楽浄土のような作品です。
「山中常盤物語」は牛若丸とその母、常盤御前を題材にした古浄瑠璃で、現在では上演されませんが、当時は操浄瑠璃で大変人気があった演目だといいます。
(「山中常盤物語」のあらすじは、後日アップしたいと思っています)
同じ岩佐又兵衛の作とされる「洛中洛外図 舟木本」(東京国立博物館所蔵)にも、京の都で「山中常盤」が人形浄瑠璃で上演されている様子が描かれています(「洛中洛外図 舟木本」は10月8日より東京国立博物館の「京都―洛中洛外図と障壁画の美」展で大々的に公開されますので、お楽しみに!)
この映画では、伝えられている詞書をもとに鶴澤清治さんが作曲し、豊竹呂勢大夫さんが義太夫を語っています。
もともと、岩佐又兵衛という絵師に非常に関心があり、辻惟雄先生のご著書『岩佐又兵衛-浮世絵をつくった男の謎』(文藝春秋、2008年)を読んで「山中常盤物語絵巻」が好きだったということに加え、清治さんが作曲されたという義太夫をどうしても聞きたくて、ぜひ拝見したいとずっと思っていました。
このたび、機会をえて拝見することができたのですが、期待にたがわずすばらしい作品でした。
なかなか見ることができない又兵衛の絵巻の細部にいたるまで、実に美しい色で撮影された画面のすばらしさ。
かなり拡大して撮影している場面もあり、着物の柄や調度品、通行人など細部にいたるまで実に細やかに入念に描写された絵巻のクオリティの高さに、あらためてため息がでます。
そして、義太夫のすばらしいこと。
清治さんの作曲、かっこよすぎます。
しょっぱなから、清治さんとツレの清二郎さん(現・藤蔵さん)の三味線が実に歯切れがよく、かっこよさ全開です。
絵巻と同時に義太夫が進んでいくということで、紙芝居的な要素もあり、清治さんの曲も、盛り上がるところの盛り上げ方がはんぱでなく、よりエンターテイメント性を追及しているようにも思われ、義太夫に慣れていない方でも違和感なく楽しめそうです。
でももちろん、義太夫ファン、とくに義太夫三味線をすきな方でこの映画をまだご覧になっていない方はぜひ、ご覧いただきたい……。太棹の三味線に惚れ直します。
そして、又兵衛ファンは又兵衛に惚れ直します。絶対に。
このすばらしい作品をあまり上映の機会のないままにしておくのは、岩佐又兵衛のファンとしても、義太夫三味線のファンとしてもいたたまれません。
なんとか、上映の機会をつくれないものか、と真剣に思案している次第です。
なにかよい案がありましたら、ぜひご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。
おまけ:そして、岩佐又兵衛ファンには朗報があります!お話しできる段階になりましたらアップしますので、いましばらくお待ちください。


これは、江戸時代初期に活躍した絵師、岩佐又兵衛の作とされる「山中常盤物語絵巻」(MOA美術館所蔵)の各場面を撮影した映像に、古浄瑠璃をもとに復曲した義太夫節をつけて構成した映画で、義太夫を聴きながら美しい絵巻の映像を楽しむことができるという、私のような人間には極楽浄土のような作品です。
「山中常盤物語」は牛若丸とその母、常盤御前を題材にした古浄瑠璃で、現在では上演されませんが、当時は操浄瑠璃で大変人気があった演目だといいます。
(「山中常盤物語」のあらすじは、後日アップしたいと思っています)
同じ岩佐又兵衛の作とされる「洛中洛外図 舟木本」(東京国立博物館所蔵)にも、京の都で「山中常盤」が人形浄瑠璃で上演されている様子が描かれています(「洛中洛外図 舟木本」は10月8日より東京国立博物館の「京都―洛中洛外図と障壁画の美」展で大々的に公開されますので、お楽しみに!)
この映画では、伝えられている詞書をもとに鶴澤清治さんが作曲し、豊竹呂勢大夫さんが義太夫を語っています。
もともと、岩佐又兵衛という絵師に非常に関心があり、辻惟雄先生のご著書『岩佐又兵衛-浮世絵をつくった男の謎』(文藝春秋、2008年)を読んで「山中常盤物語絵巻」が好きだったということに加え、清治さんが作曲されたという義太夫をどうしても聞きたくて、ぜひ拝見したいとずっと思っていました。
このたび、機会をえて拝見することができたのですが、期待にたがわずすばらしい作品でした。
なかなか見ることができない又兵衛の絵巻の細部にいたるまで、実に美しい色で撮影された画面のすばらしさ。
かなり拡大して撮影している場面もあり、着物の柄や調度品、通行人など細部にいたるまで実に細やかに入念に描写された絵巻のクオリティの高さに、あらためてため息がでます。
そして、義太夫のすばらしいこと。
清治さんの作曲、かっこよすぎます。
しょっぱなから、清治さんとツレの清二郎さん(現・藤蔵さん)の三味線が実に歯切れがよく、かっこよさ全開です。
絵巻と同時に義太夫が進んでいくということで、紙芝居的な要素もあり、清治さんの曲も、盛り上がるところの盛り上げ方がはんぱでなく、よりエンターテイメント性を追及しているようにも思われ、義太夫に慣れていない方でも違和感なく楽しめそうです。
でももちろん、義太夫ファン、とくに義太夫三味線をすきな方でこの映画をまだご覧になっていない方はぜひ、ご覧いただきたい……。太棹の三味線に惚れ直します。
そして、又兵衛ファンは又兵衛に惚れ直します。絶対に。
このすばらしい作品をあまり上映の機会のないままにしておくのは、岩佐又兵衛のファンとしても、義太夫三味線のファンとしてもいたたまれません。
なんとか、上映の機会をつくれないものか、と真剣に思案している次第です。
なにかよい案がありましたら、ぜひご教示くださいませ。
よろしくお願いいたします。
おまけ:そして、岩佐又兵衛ファンには朗報があります!お話しできる段階になりましたらアップしますので、いましばらくお待ちください。