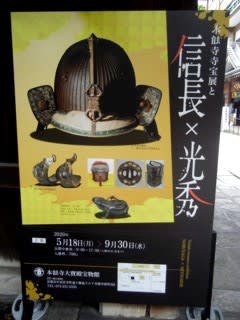今回は彦根

彦根城博物館

拵-井伊家伝来刀装選-
期間:7月17日(金)~8月18日(火)

井伊直政所用 黒蝋色塗鞘大小拵

井伊直孝所用 黒いぢいぢ塗鞘大小拵
井伊直孝所用 朱漆塗蛭巻鞘大小拵

井伊直弼所用 黒蝋色塗鞘大小拵

金梨子地菊紋蒔絵鞘糸巻太刀拵
12代・直亮が光格上皇より拝領した。
ここからは常設展示

古瀬戸肩衝茶入 銘 夏山

共筒茶杓 銘 ゆふ月 井伊直弼作

七宝唐草文小釜
平戸藩主・松浦鎮信好み

彦根城博物館

拵-井伊家伝来刀装選-
期間:7月17日(金)~8月18日(火)

井伊直政所用 黒蝋色塗鞘大小拵

井伊直孝所用 黒いぢいぢ塗鞘大小拵
井伊直孝所用 朱漆塗蛭巻鞘大小拵

井伊直弼所用 黒蝋色塗鞘大小拵

金梨子地菊紋蒔絵鞘糸巻太刀拵
12代・直亮が光格上皇より拝領した。
ここからは常設展示

古瀬戸肩衝茶入 銘 夏山

共筒茶杓 銘 ゆふ月 井伊直弼作

七宝唐草文小釜
平戸藩主・松浦鎮信好み