受験生のための『世界史B』 もくじ
↑ここから各項目に入れます。
こんにちは、セプテンバーです。
最近パソコンをWindowsからMacbookに変えました。もし、文字化けとか、「今までとちがう! 読みづらい!」ということがあれば言ってください。
さて、今日は引き続き中国史ですね。
僕の苦手な分野が続きます←
どうか、教科書レベルの記述にとどまってしまうことをお許しください。
[ 中央集権国家を取り戻す ]
中国を含む東アジア地域というのは、常に「中央集権」をめざして努力してきました。
秦の時代(前3世紀)に、地方の豪族に左右されない中華帝国という考え方が現実のものになり、続く漢では武帝の活躍によって中央集権国家は成功を収めていました(後1世紀)。
しかし、武帝亡き後の時代はどうだったかというと、南北朝時代という大いなる分裂の時代。
そして一度分裂の方に振られた中国はまもなく、逆の方向である統一へと向かうことになります。
その中心となったのが、北朝の北周という国の出身である楊堅(ようけん)という人物。
彼は隋という国を建て、文帝と名乗りました。
首都は、長安です。
時代は、581年のこと。
長安大事だよ!
文帝の功績といえばなんといっても、科挙の開始でしょう。
前回紹介したように、中国では長らく、お金持ちで地元で発言力をもつ豪族たちによって中央の政治が支配されることを許してしまうような制度が実施されてきました。
たとえば、郷挙里選とか九品中世とか。
これを、なんと、試験にしちゃったんですね!!
わかりやすく言えば、能力主義です。個人の、努力次第なんです(※一応は)。
もちろん、中国の柱を支える官僚を採用するための試験ですから、すさまじく大変です。
受験生のみなさんには申し訳ないですが、センター試験の比ではないでしょう←
といっても、このころの科挙はまだ発展途上というか、実は依然として地方の貴族の受験者が多く、本来文帝が期待したほどの効果は得られなかったようです。
試験も2次までで、後世に残るような厳しい試験となったのはもうちょっと後のこと。
しかしいずれにしろ、科挙を開始したという功績は評価されてしかるべきでしょう。
また、律令を制定したのも文帝です。
多分小学生とか中学生のころの日本史の授業では、飛鳥時代から始まる日本の政治は唐の律令を参考にした、というふうに習うと思うのですが、実際には隋のころに律令はできているみたいです。
一応説明しておくと、
「律」……刑法(他人に危害を加えた場合に裁くための法律)
「令」……行政法および民法(政治のやり方と個人同士のトラブルにかかわる法律)
ですね。
また、日本の奈良時代にもその例がある租庸調制も文帝がつくったものです。
これは、税のシステム。
このようにして、科挙で優秀な人材を集めて中央権力の周囲を固め、律令と租庸調制で農民たちをまとめ、税をもらうという形で文帝は中央集権国家を復活させたわけです。
[ しかし、2代で終わる ]
はい。
終わってしまうんですね、隋。
文帝を継いだのは、煬帝(ようだい)という人物(読み方に注意)。
彼は、中国の南部と北部を結ぶ大運河の建設に心血を注ぎます。
運河が完成すれば、船を用いて大量の物資を運べるからですね。
あ、運河ってこんな感じ。

……しかしもちろん、実際に「心血を注ぐ」のは煬帝ではなく民衆ですよね。
さらに、3度に渡る高句麗遠征も財政的に大きな負担となり、しかも失敗しました。
※ 高句麗と朝鮮半島についてちょっと解説 ※
当時、朝鮮半島は三国時代と呼ばれる時代にありました(中国の「三国時代」とは別)。
すなわち、高句麗(コグリョ)と新羅(シラギ)と百済(ペクチェ)のことです。
中でも高句麗が最強で、当時、武帝がその昔設置した楽浪郡をぶっ壊したりして煬帝の怒りを買っていたみたいです。
後の展開はもうおわかりだと思うのですが、まもなく大規模な反乱が起き、618年、隋は滅びます。
ちなみにこれは有名な話ですが、「煬帝」という名前は彼の死後、後の人が付けたニックネームみたいなもので、彼を罵倒するような意味があります。
最近では彼の功績を見直す動きもあるそうですが、まあ、ちょっとかわいそうですよね←
こうして2代で終わってしまった隋ですが、その中央集権化の志は次の王朝に引き継がれ、そしてそこで大きな花を開かせることになります。
◎ 今日のポイント ◎
・ 隋の首都はどこか。
・ 文帝が始めた官僚任用制度の名称を答えよ。
・ 煬帝は朝鮮半島のどの国に遠征し、失敗したか。
↑ここから各項目に入れます。
こんにちは、セプテンバーです。
最近パソコンをWindowsからMacbookに変えました。もし、文字化けとか、「今までとちがう! 読みづらい!」ということがあれば言ってください。
さて、今日は引き続き中国史ですね。
僕の苦手な分野が続きます←
どうか、教科書レベルの記述にとどまってしまうことをお許しください。
[ 中央集権国家を取り戻す ]
中国を含む東アジア地域というのは、常に「中央集権」をめざして努力してきました。
秦の時代(前3世紀)に、地方の豪族に左右されない中華帝国という考え方が現実のものになり、続く漢では武帝の活躍によって中央集権国家は成功を収めていました(後1世紀)。
しかし、武帝亡き後の時代はどうだったかというと、南北朝時代という大いなる分裂の時代。
そして一度分裂の方に振られた中国はまもなく、逆の方向である統一へと向かうことになります。
その中心となったのが、北朝の北周という国の出身である楊堅(ようけん)という人物。
彼は隋という国を建て、文帝と名乗りました。
首都は、長安です。
時代は、581年のこと。
長安大事だよ!
文帝の功績といえばなんといっても、科挙の開始でしょう。
前回紹介したように、中国では長らく、お金持ちで地元で発言力をもつ豪族たちによって中央の政治が支配されることを許してしまうような制度が実施されてきました。
たとえば、郷挙里選とか九品中世とか。
これを、なんと、試験にしちゃったんですね!!
わかりやすく言えば、能力主義です。個人の、努力次第なんです(※一応は)。
もちろん、中国の柱を支える官僚を採用するための試験ですから、すさまじく大変です。
受験生のみなさんには申し訳ないですが、センター試験の比ではないでしょう←
といっても、このころの科挙はまだ発展途上というか、実は依然として地方の貴族の受験者が多く、本来文帝が期待したほどの効果は得られなかったようです。
試験も2次までで、後世に残るような厳しい試験となったのはもうちょっと後のこと。
しかしいずれにしろ、科挙を開始したという功績は評価されてしかるべきでしょう。
また、律令を制定したのも文帝です。
多分小学生とか中学生のころの日本史の授業では、飛鳥時代から始まる日本の政治は唐の律令を参考にした、というふうに習うと思うのですが、実際には隋のころに律令はできているみたいです。
一応説明しておくと、
「律」……刑法(他人に危害を加えた場合に裁くための法律)
「令」……行政法および民法(政治のやり方と個人同士のトラブルにかかわる法律)
ですね。
また、日本の奈良時代にもその例がある租庸調制も文帝がつくったものです。
これは、税のシステム。
このようにして、科挙で優秀な人材を集めて中央権力の周囲を固め、律令と租庸調制で農民たちをまとめ、税をもらうという形で文帝は中央集権国家を復活させたわけです。
[ しかし、2代で終わる ]
はい。
終わってしまうんですね、隋。
文帝を継いだのは、煬帝(ようだい)という人物(読み方に注意)。
彼は、中国の南部と北部を結ぶ大運河の建設に心血を注ぎます。
運河が完成すれば、船を用いて大量の物資を運べるからですね。
あ、運河ってこんな感じ。

……しかしもちろん、実際に「心血を注ぐ」のは煬帝ではなく民衆ですよね。
さらに、3度に渡る高句麗遠征も財政的に大きな負担となり、しかも失敗しました。
※ 高句麗と朝鮮半島についてちょっと解説 ※
当時、朝鮮半島は三国時代と呼ばれる時代にありました(中国の「三国時代」とは別)。
すなわち、高句麗(コグリョ)と新羅(シラギ)と百済(ペクチェ)のことです。
中でも高句麗が最強で、当時、武帝がその昔設置した楽浪郡をぶっ壊したりして煬帝の怒りを買っていたみたいです。
後の展開はもうおわかりだと思うのですが、まもなく大規模な反乱が起き、618年、隋は滅びます。
ちなみにこれは有名な話ですが、「煬帝」という名前は彼の死後、後の人が付けたニックネームみたいなもので、彼を罵倒するような意味があります。
最近では彼の功績を見直す動きもあるそうですが、まあ、ちょっとかわいそうですよね←
こうして2代で終わってしまった隋ですが、その中央集権化の志は次の王朝に引き継がれ、そしてそこで大きな花を開かせることになります。
◎ 今日のポイント ◎
・ 隋の首都はどこか。
・ 文帝が始めた官僚任用制度の名称を答えよ。
・ 煬帝は朝鮮半島のどの国に遠征し、失敗したか。










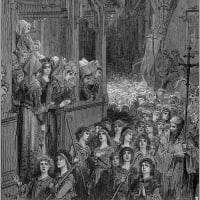


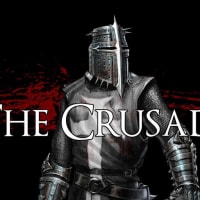

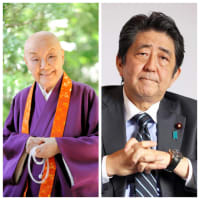
![受験生のための『世界史B』―東アジア世界[(8)前漢の文化と崩壊]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/13/88/e6ff55c7a4d5157036f0bf5482be41b3.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(3)大帝は焼き肉がお好き]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5a/60/34ff4463e0f35516b385e3c0579be51f.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(2)あなたは朝シャン派? それとも夜シャン派?]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/9c/5fb553a8ca637bc77dae8ab10e798673.jpg)
![受験生のための『世界史B』―中世ヨーロッパ[(1)ヤァ! ヤァ! ヤァ! ゲルマン人がやってきた!]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0c/77/06e8d5c1a63490a28fc419c8cc13b104.jpg)
自分は学校の先生の説明ではよくわからない所があってそれを補っている感じです。なので本当によく助かっております。今後ともよろしくお願いします