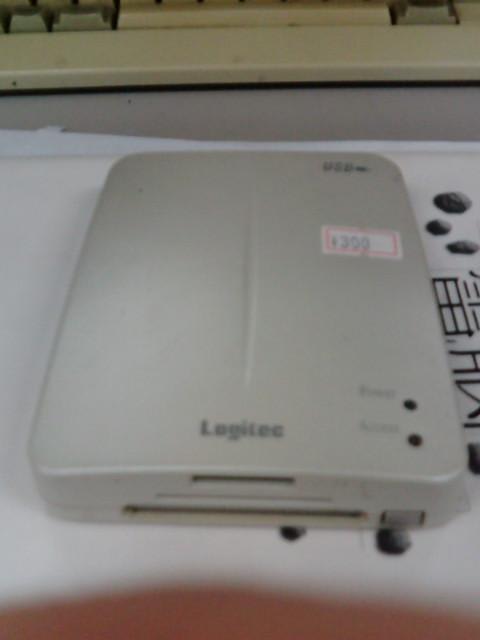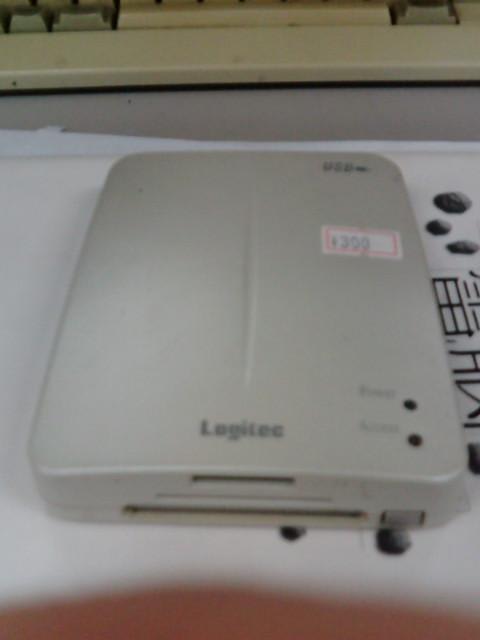カノープスezdv ntsc改造のacex 1k評価基板の進捗。
いままで満足にシミュレータをつかえてなかったのだけど、
シミュレートで動きを確認しなければこの先進歩はなさそうなので
がんばってquartus2のシミュレータで波形を確認して、ブロックramが
まともに動作するようにできた。特に何も用意せず、メガファンクションの
ウィザード内でhexファイルを指定しただけで、シミュレータで
ブロックramの内容が読み書きできて非常に助かりました。
もっと早くシミュレータに取り組めばよかった。
シミュレータにはまだよくわからないところがあって、
表示したい信号を指定しても、合成?の過程で信号が消えてしまうので、
見たい信号を全てtopで外部に出力するようにしているのだけど、
本当はどうするのが正しいのだろう?
この評価基板であとやりたいのは以下の
・シリアル入力がたまに化けるのを改善する。
自作部分なので何か間違っているのだろうからシミュレータも
なんとなく使えるようになったのでデバッグしなおしする。
オシロのみでデバッグして、だいたい動くのでなげだしてたけど、
sramを接続したあとはhexファイルをシリアルから流し込める
ようにしたいのでこれは必ずやらないといけない。
・古典電脳物語のtiny basicを移植する。
cp/mの数個のシステムコールを古典電脳物語使用のマイコンボード用に
用意してある部分を書き直すだけなので非常に簡単なはずだけど、
昨日は環境整えたりして時間切れで完了できなかった。
最初の初期化の後がよくわからなかった。割り込み許可したあとは
どうなってるんだろう? 本に解説書いてあるような気もするので
読み直すか。あと、z80用のソースがアークピット様がフリーで
公開していたxz80アセンブラ用になってるけど、いつのまにか
アークピット(http://www.arcpit.co.jp)につながらなくなってる。
今後似たようなことをする人はちょっとめんどくさいかも。
・外部にsramを接続する。
もともとリフレッシュ無しで使用できるらしい28ピンのfifo dramが
ついていたのだけど、接続を確認したところ、多少のパターンカットと
信号線の追加で通常の非同期sramを接続できそうなので必ず実現したい。
・モノクロビデオ出力かアナログrgb出力で画像表示する。
これは以前マイコン(avr等)やfpga(デザインウェーブ2007/7付録基板)で
やってみたことがあるので外部sramが用意できれば問題なさそう。
・画像出力のテキストvram化
やってみればそんなに難しくなさそうだけど、これができればfz80からの
ハンドリングが非常に楽になるので是非実現したい。
ブロックramがちゃんと動くようになったので簡単なモニタを作ってみた。

config後の起動画面。

ダンプとかしてみたり。

どこに書き込もうかな。

LD A,$55
OUT ($80),A
JP $0000

たしかにメモリに書き込まれている。

ポート$80への出力はLEDにわりつけてて、今は全点灯。
ちょっとみにくいね。

実行!

ひとつおきの点灯に変わった。

まだまだ入る。