「我らが女王陛下のお通りだ」昂然と工場内を睥睨して回るミセス・ソーントン。お喋りをしている従業員に「お前たちの代わりはいくらでもいる」と恫喝し、病んで泣いている子供を役に立たないと帰す。「1時間以内に別の子供をつれてくれば、職を与えてやろう」と告げる。
そこに、徐々に衰えていく母のために主治医を教えてもらいにくるマーガレット。ミセス・ヘイルの"Low Spirits"をせせら笑い、ミルトンについて知らないマーガレットを非難するミセス・ソーントン。帰り際に労働者の娘たちに声をかけられ、ストライキについて聞くが、娘たちは黙り込む。背後にミスタ・ソーントンが立っていたのだ。従業員の生活について配慮していないミスタ・ソーントンを責めるマーガレットに、彼は私は彼女らの父でも兄でもなくマスターであり、気にかけるのは効率的な工場の運営だと告げる。ふと虚空を見つめるマーガレットに、ミスタ・ソーントンも振り向くと、工場の窓から彼の母が見おろしていた。
ベッシーに「いつでもそこにいるのよ!まるで私が彼の求婚者のように!」とミセス・ソーントンのことを訴えるマーガレット。もっといい身なりをするように言うベッシー。「彼の背後には女の子が山のように追いかけているのよ。」(やっぱりもてるのか?ミスタ・ソーントン)
「私は息子ができても彼女のように縛り付けたりはしない」というマーガレットに、私はどんな息子も持つことはない、と重病であることを示唆するベッシー。子供のころに肺に綿毛が詰まったのが原因らしい。(工場から出る塵煙ではなく綿毛?そうなのか、そうヒギンズ親子が思い込んでいるのか不明)気付くとすぐにヒギンズはミスタ・ソーントンの工場に移った。(他にも労働者たちは、マールバラミルのほうが他の工場よりはいいと告げている)
父と娘、母と息子は愛し合うものだから、あの古斧(ミセス・ソーントン)にも寛容にならないとね、という話から、マーガレットにフレデリックという兄がいたことが判明。海軍に入隊したが、船長が精神異常者で子供を虐待していたため反抗し、反逆者とされて今はスペインにいるという。イングランドに戻れば絞首刑が待っている。「でも貴女は、誇れるはずだわ。他の弱虫たちと違って彼は勇敢で、人を救ったのだということを」「ええ。でも正直なところ、臆病者であって欲しかったとも思うの。もしそれが母が二度と兄に会えないということを意味するなら」
パーティーの準備をしているミセス・ソーントンと傍らで刺繍をしているミス・ファニー・ソーントン。二人がヘイル一家、とりわけマーガレットの教養のなさ、などを扱き下ろすのに苛立つミスタ・ソーントン。二人にマーガレットの友人になるように指示するミスタ・ソーントン。「まさか彼女に愛情を抱いているわけじゃないね?だとしても、彼女はお前を選びませんよ。その話をしたら面前で笑ったのよ。自己評価がずいぶんといいようね!」という母に、うっすらと笑んで見せる彼。(というか、マーガレットはその考えに対してじゃなくて、貴女が可笑しかったのでは?初対面でいきなりウチの息子に気があるんでしょ!と言わんばかりの母親はいかがなものか。)
組合と工場主との交渉が決裂しつつある。金曜日にストライキを始めると扇動するヒギンズ。…乗せられそうな迫力。「いいか!暴力はだめだ!けだもののように振舞うな!俺たちは思考ある人間だということを見せるんだ!ストライキの敵は俺たち自身しかいない!」5年前に半数が脱落し、ストライキは失敗に終わった。
アイルランド人を雇うことを考えるソーントン親子。紡織業界の不況はアメリカの台頭にあるようだ。ミスタ・ソーントンの銀行の借り入れは£400近く。そして、ストライキが始まった。
奇妙に静まっている街のこと、飢える心配のないことに罪悪感を抱いていることを、赤ん坊の服の色について悩むイーディスに手紙で記すマーガレット。子供たちが飢えているとバウチャーがヒギンズに泣きついてきた。マーガレットも彼に食べ物などを差し入れている。ヒギンズ宅も訪れるマーガレットだが、マスターズを擁護するような発言をしたら、「あんたはよそ者だ。何もわかっていない!」と言い捨てられる。
「ミスタ・ソーントンは本当に他の人たちと同じくらい悪いの?」「彼は戦士だ。獰猛なこと、ブルドッグに同じだ」「あら、彼はブルドッグよりは見栄えはいいわよ、確かに。」(あの鋭角的な鼻と端正な顔立ちはむしろ真逆だろう)と場を和ませようとするが「戦う相手として不足はない」と返されてしまう。
テーブルの上に並ぶクリスタルのグラス、銀のカトラリー、ソーントン家の晩餐の宵。ミセス&ミス・ソーントンと明らかな社交辞令を交わしていると、ミスタ・ソーントンが入室、思わず眼で追うマーガレットに訳知り顔をするミス・ソーントン。ミス・ラティマーという令嬢を紹介された彼は、紳士らしく握手ではなくその白い手袋をした手をとって挨拶をする。マーガレットは裸手でミスタ・ソーントンと握手をして、「ミルトンの流儀を覚えたでしょう?」と告げる。(このシーンはよくわからない。普通のレイディなら、他の淑女には手をとって挨拶をして自分には握手を求められたら侮辱と考えると思う。ミスタ・ソーントンはミルトンの、自分の流儀を理解して欲しかった?それとも単に経済的に困窮した-レイディが手袋をしないで社交の場に出るのはありえない-マーガレットを淑女とみなしてなかった?)
晩餐の合間も、不穏な現状の話になる。出資者?でマーガレットの名付け親のミスタ・ベル(ダンディで瀟洒な素敵なおじさん)の問いをウィットでかわすミスタ・ソーントン。よく召使のゴシップに耳を傾けているらしいファニーが、マーガレットが下町の家に差し入れに行っていることを暴露する。ベッシーもヒギンズも友人だというマーガレット。差し入れをすることでストライキを長引かせ結果的に彼らを苦しめるのは、親切な行いとは言えないというミスタ・ソーントンに、飢えている赤ん坊が泣いているのに手を差し伸べるのに理屈は関係ないと切り返す。
家に帰ると医師が帰るところで、思っていたよりずっと母が重病だったと気付くマーガレット。メイドのディクソンが知っていたのに自分が知らされていないことにも遣る瀬無い憤りを覚える。だが結局、耐えられないだろうと父には告げないことにする。ディクソンは自分ほど彼女を愛しているものはないと主張する。美しく社交界の花だったミセス・ヘイルがこんなところにこさせられるのは、痛ましいと。
夜中、ミスタ・ソーントンがアイリッシュの人足を入れているのをバウチャーが目撃する。翌日人気のない通りを訝りながら、母のためにウォーターベッドを借りにマールバラミルを訪れるマーガレット。(こんな昔からあったんだ、ウォーターベッド)ミセス&ミスソーントンと話している最中、暴徒が押し寄せてくる。ストライキをする従業員の要求に応える代わりに、アイルランド人を雇うことを決めたからだ。
兵士たちが彼らに"道理"を教えるまで勇気を保ってくれ、というミスタ・ソーントンに、マーガレットは憤って「道理ってなんですの?今すぐに下に降りていって男として彼らに向き合ってください。彼らが人として扱って、語りかけてください」という。扉を開けて暴徒と対峙するミスタ・ソーントンを見送ったマーガレットだが、バウチャーを含む暴徒が石を握るのを見て自身も駆け下りて、解散するように訴える。結局暴発した暴徒、バウチャが投げた石からミスタ・ソーントンを庇いマーガレットは気を失ってしまう。
兵士が来て暴徒を駆逐した後、ソーントン邸で横たわるマーガレット。その傍らで彼女がご主人様に抱きついたと行って騒ぐメイドとミス・ソーントン。母を案じてすぐに帰宅するマーガレット。後処理を終えて帰宅したミスタ・ソーントンは、マーガレットがいないことに気付き、彼女に会いに行こうとするが母に止められる。「私はお前にお願いしているのよ、ジョン」彼女の懇願に驚いた顔を見せるミスタ・ソーントン。
その夜、メアリ・ヒギンズがマーガレットを迎えに来る。ベッシーの病状が悪化したためだ。咳き込みながら泣き咽ぶベッシーの背を撫でながら一夜を過ごすマーガレット。
夜遅くに帰宅したミスタ・ソーントンに、母は名誉に縛られていないかと問いただす。「彼女は自分の感情を世界中に表した。怒り狂う暴徒たちの前に駆けつけて、お前を危機から救った。」ミルトン中の噂になるだろうという母。「彼女は私を救った・・・。だが、彼女のような女性が私を気に掛けるとはとても信じられない。」「愚かなことを!」彼女はお前の求婚を受けるだろうから、今日は行かせたくなかったと語る母。今日が自分がお前の愛情の一番の対象である最後の日になるのだからと。「私は、彼女が私を気に掛けていないことを知っている。だが、沈黙して入られない。彼女に尋ねてみなければ。」
イーディスからの手紙を読んでいるところにミスタ・ソーントンが訪れる。昨日のことは誰もがしたことをしただけ、と告げるマーガレット。「そんなことはない。」「私には貴男を危地に送り込んだ責任がありました。どんな男性が相手であっても同じことをしたでしょう。」「どんな男でも?」
(この"Any man?"っていう言い方がとても好き)続けて労働者たちを擁護するマーガレットといつものように言い争いになるミスタ・ソーントンは、ふとわれに返り、自分の心持を述べようとするが、マーガレットに押しとどめられ、それは紳士的なやり方ではないと指摘される。(どの辺が紳士的でないのか、私にはわからないけど。ヘンリー・レノックスの求婚だって充分唐突だったし)
「私が貴女の眼から見て紳士でないことは承知している。だけど、そんなにも責められる謂れを知る権利位はあると思うが。」というミスタ・ソーントンに、「貴男が私の評判を救う義務があるとでもいう様に話すからです!」(それは紳士的なのでは?)貴男はお金持ちで私の父は落ちぶれていっているから私を所有できると思ったのか?と問うマーガレット(口が過ぎる・・・と思うけどこの二人の身分差については後に考察)「貴女を所有したいと思ったことはない!妻に娶りたいと望んだけだ。貴女を愛しているから!」
貴男に好意も抱いていないというマーガレット。ベッシーのことで彼を責めたかった事に気付いたマーガレットは、自分の無礼を詫びるが、ミスタ・ソーントンはそれを拒絶する。
「お願い、わかってください、ミスタ・ソーントン・・・」
「理解している。私は、完全に貴女を理解した。」
な、長い・・・。そのうち台詞を全部書き出しそう・・・。

そこに、徐々に衰えていく母のために主治医を教えてもらいにくるマーガレット。ミセス・ヘイルの"Low Spirits"をせせら笑い、ミルトンについて知らないマーガレットを非難するミセス・ソーントン。帰り際に労働者の娘たちに声をかけられ、ストライキについて聞くが、娘たちは黙り込む。背後にミスタ・ソーントンが立っていたのだ。従業員の生活について配慮していないミスタ・ソーントンを責めるマーガレットに、彼は私は彼女らの父でも兄でもなくマスターであり、気にかけるのは効率的な工場の運営だと告げる。ふと虚空を見つめるマーガレットに、ミスタ・ソーントンも振り向くと、工場の窓から彼の母が見おろしていた。
ベッシーに「いつでもそこにいるのよ!まるで私が彼の求婚者のように!」とミセス・ソーントンのことを訴えるマーガレット。もっといい身なりをするように言うベッシー。「彼の背後には女の子が山のように追いかけているのよ。」(やっぱりもてるのか?ミスタ・ソーントン)
「私は息子ができても彼女のように縛り付けたりはしない」というマーガレットに、私はどんな息子も持つことはない、と重病であることを示唆するベッシー。子供のころに肺に綿毛が詰まったのが原因らしい。(工場から出る塵煙ではなく綿毛?そうなのか、そうヒギンズ親子が思い込んでいるのか不明)気付くとすぐにヒギンズはミスタ・ソーントンの工場に移った。(他にも労働者たちは、マールバラミルのほうが他の工場よりはいいと告げている)
父と娘、母と息子は愛し合うものだから、あの古斧(ミセス・ソーントン)にも寛容にならないとね、という話から、マーガレットにフレデリックという兄がいたことが判明。海軍に入隊したが、船長が精神異常者で子供を虐待していたため反抗し、反逆者とされて今はスペインにいるという。イングランドに戻れば絞首刑が待っている。「でも貴女は、誇れるはずだわ。他の弱虫たちと違って彼は勇敢で、人を救ったのだということを」「ええ。でも正直なところ、臆病者であって欲しかったとも思うの。もしそれが母が二度と兄に会えないということを意味するなら」
パーティーの準備をしているミセス・ソーントンと傍らで刺繍をしているミス・ファニー・ソーントン。二人がヘイル一家、とりわけマーガレットの教養のなさ、などを扱き下ろすのに苛立つミスタ・ソーントン。二人にマーガレットの友人になるように指示するミスタ・ソーントン。「まさか彼女に愛情を抱いているわけじゃないね?だとしても、彼女はお前を選びませんよ。その話をしたら面前で笑ったのよ。自己評価がずいぶんといいようね!」という母に、うっすらと笑んで見せる彼。(というか、マーガレットはその考えに対してじゃなくて、貴女が可笑しかったのでは?初対面でいきなりウチの息子に気があるんでしょ!と言わんばかりの母親はいかがなものか。)
組合と工場主との交渉が決裂しつつある。金曜日にストライキを始めると扇動するヒギンズ。…乗せられそうな迫力。「いいか!暴力はだめだ!けだもののように振舞うな!俺たちは思考ある人間だということを見せるんだ!ストライキの敵は俺たち自身しかいない!」5年前に半数が脱落し、ストライキは失敗に終わった。
アイルランド人を雇うことを考えるソーントン親子。紡織業界の不況はアメリカの台頭にあるようだ。ミスタ・ソーントンの銀行の借り入れは£400近く。そして、ストライキが始まった。
奇妙に静まっている街のこと、飢える心配のないことに罪悪感を抱いていることを、赤ん坊の服の色について悩むイーディスに手紙で記すマーガレット。子供たちが飢えているとバウチャーがヒギンズに泣きついてきた。マーガレットも彼に食べ物などを差し入れている。ヒギンズ宅も訪れるマーガレットだが、マスターズを擁護するような発言をしたら、「あんたはよそ者だ。何もわかっていない!」と言い捨てられる。
「ミスタ・ソーントンは本当に他の人たちと同じくらい悪いの?」「彼は戦士だ。獰猛なこと、ブルドッグに同じだ」「あら、彼はブルドッグよりは見栄えはいいわよ、確かに。」(あの鋭角的な鼻と端正な顔立ちはむしろ真逆だろう)と場を和ませようとするが「戦う相手として不足はない」と返されてしまう。
テーブルの上に並ぶクリスタルのグラス、銀のカトラリー、ソーントン家の晩餐の宵。ミセス&ミス・ソーントンと明らかな社交辞令を交わしていると、ミスタ・ソーントンが入室、思わず眼で追うマーガレットに訳知り顔をするミス・ソーントン。ミス・ラティマーという令嬢を紹介された彼は、紳士らしく握手ではなくその白い手袋をした手をとって挨拶をする。マーガレットは裸手でミスタ・ソーントンと握手をして、「ミルトンの流儀を覚えたでしょう?」と告げる。(このシーンはよくわからない。普通のレイディなら、他の淑女には手をとって挨拶をして自分には握手を求められたら侮辱と考えると思う。ミスタ・ソーントンはミルトンの、自分の流儀を理解して欲しかった?それとも単に経済的に困窮した-レイディが手袋をしないで社交の場に出るのはありえない-マーガレットを淑女とみなしてなかった?)
晩餐の合間も、不穏な現状の話になる。出資者?でマーガレットの名付け親のミスタ・ベル(ダンディで瀟洒な素敵なおじさん)の問いをウィットでかわすミスタ・ソーントン。よく召使のゴシップに耳を傾けているらしいファニーが、マーガレットが下町の家に差し入れに行っていることを暴露する。ベッシーもヒギンズも友人だというマーガレット。差し入れをすることでストライキを長引かせ結果的に彼らを苦しめるのは、親切な行いとは言えないというミスタ・ソーントンに、飢えている赤ん坊が泣いているのに手を差し伸べるのに理屈は関係ないと切り返す。
家に帰ると医師が帰るところで、思っていたよりずっと母が重病だったと気付くマーガレット。メイドのディクソンが知っていたのに自分が知らされていないことにも遣る瀬無い憤りを覚える。だが結局、耐えられないだろうと父には告げないことにする。ディクソンは自分ほど彼女を愛しているものはないと主張する。美しく社交界の花だったミセス・ヘイルがこんなところにこさせられるのは、痛ましいと。
夜中、ミスタ・ソーントンがアイリッシュの人足を入れているのをバウチャーが目撃する。翌日人気のない通りを訝りながら、母のためにウォーターベッドを借りにマールバラミルを訪れるマーガレット。(こんな昔からあったんだ、ウォーターベッド)ミセス&ミスソーントンと話している最中、暴徒が押し寄せてくる。ストライキをする従業員の要求に応える代わりに、アイルランド人を雇うことを決めたからだ。
兵士たちが彼らに"道理"を教えるまで勇気を保ってくれ、というミスタ・ソーントンに、マーガレットは憤って「道理ってなんですの?今すぐに下に降りていって男として彼らに向き合ってください。彼らが人として扱って、語りかけてください」という。扉を開けて暴徒と対峙するミスタ・ソーントンを見送ったマーガレットだが、バウチャーを含む暴徒が石を握るのを見て自身も駆け下りて、解散するように訴える。結局暴発した暴徒、バウチャが投げた石からミスタ・ソーントンを庇いマーガレットは気を失ってしまう。
兵士が来て暴徒を駆逐した後、ソーントン邸で横たわるマーガレット。その傍らで彼女がご主人様に抱きついたと行って騒ぐメイドとミス・ソーントン。母を案じてすぐに帰宅するマーガレット。後処理を終えて帰宅したミスタ・ソーントンは、マーガレットがいないことに気付き、彼女に会いに行こうとするが母に止められる。「私はお前にお願いしているのよ、ジョン」彼女の懇願に驚いた顔を見せるミスタ・ソーントン。
その夜、メアリ・ヒギンズがマーガレットを迎えに来る。ベッシーの病状が悪化したためだ。咳き込みながら泣き咽ぶベッシーの背を撫でながら一夜を過ごすマーガレット。
夜遅くに帰宅したミスタ・ソーントンに、母は名誉に縛られていないかと問いただす。「彼女は自分の感情を世界中に表した。怒り狂う暴徒たちの前に駆けつけて、お前を危機から救った。」ミルトン中の噂になるだろうという母。「彼女は私を救った・・・。だが、彼女のような女性が私を気に掛けるとはとても信じられない。」「愚かなことを!」彼女はお前の求婚を受けるだろうから、今日は行かせたくなかったと語る母。今日が自分がお前の愛情の一番の対象である最後の日になるのだからと。「私は、彼女が私を気に掛けていないことを知っている。だが、沈黙して入られない。彼女に尋ねてみなければ。」
イーディスからの手紙を読んでいるところにミスタ・ソーントンが訪れる。昨日のことは誰もがしたことをしただけ、と告げるマーガレット。「そんなことはない。」「私には貴男を危地に送り込んだ責任がありました。どんな男性が相手であっても同じことをしたでしょう。」「どんな男でも?」
(この"Any man?"っていう言い方がとても好き)続けて労働者たちを擁護するマーガレットといつものように言い争いになるミスタ・ソーントンは、ふとわれに返り、自分の心持を述べようとするが、マーガレットに押しとどめられ、それは紳士的なやり方ではないと指摘される。(どの辺が紳士的でないのか、私にはわからないけど。ヘンリー・レノックスの求婚だって充分唐突だったし)
「私が貴女の眼から見て紳士でないことは承知している。だけど、そんなにも責められる謂れを知る権利位はあると思うが。」というミスタ・ソーントンに、「貴男が私の評判を救う義務があるとでもいう様に話すからです!」(それは紳士的なのでは?)貴男はお金持ちで私の父は落ちぶれていっているから私を所有できると思ったのか?と問うマーガレット(口が過ぎる・・・と思うけどこの二人の身分差については後に考察)「貴女を所有したいと思ったことはない!妻に娶りたいと望んだけだ。貴女を愛しているから!」
貴男に好意も抱いていないというマーガレット。ベッシーのことで彼を責めたかった事に気付いたマーガレットは、自分の無礼を詫びるが、ミスタ・ソーントンはそれを拒絶する。
「お願い、わかってください、ミスタ・ソーントン・・・」
「理解している。私は、完全に貴女を理解した。」
な、長い・・・。そのうち台詞を全部書き出しそう・・・。











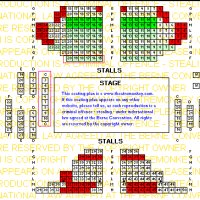














晩餐会で、ミスター・ソーントンがミス・ラティマーの手を取るところはその次のマーガレットとの握手のシーンと関係してたんですね。この二人の素手で握手するシーンは、マーガレットから手を差し出したように見えます。一話でソーントンからの握手を突っ撥ねた時、お父さんに怒られたのもあって、マーガレットなりに北部(ソーントン)に対する偏見を取り除いていこうとする努力の表れ---かと自分は勝手に解釈してました…。
North & South、ご覧になっているんですね。本国ではリージェンシー・ロマンスの王道、ジェーン・オースティンものと並び称されるほどのドラマですけど、日本ではあまり知られていないようで、残念ですねー。
そのうち、NHK BSかLala TVで字幕で放送してくれることを願っています。
仰るとおり、晩餐会での握手はマーガレットなりに北部=ミスタ・ソーントンへの歩み寄りなんだろうと思います。
ただ、最初にヘイル宅でマーガレットに握手を求めたミスタ・ソーントンが、ミス・ラティマーには最初から握手を求めずに、紳士の礼だったのは何故かな?と気になってしまいまして。
またN&S話をしにお立ち寄りくださいませ。
ミスタ・ベルに落ちました。←こんなんばっか
えーと、英語不自由な身としましては、
最後のマーガレットの拒みっぷりが意味不明・・・。
ただの意地っ張りにしか見えておりませんで(汗)。
ええ、この時既に95%ミスタ・ソーントン目線。
>ベッシーのことで彼を責めたかった事に気付いたマーガレット
こういう事だったのですね。
義務>愛なんでしょ!てなメロドラマかと思っておりましたわ(おい)。
>最後のマーガレットの拒みっぷりが意味不明・・・。
ここは、私もちょっと腑に落ちていないのです。紳士的ではない、と責める辺りが。当時の常識としては、男性と親密な関係にあるのでは?と疑われてしまった女性は、不名誉な立場に追い込まれる恐れがあり(ふしだらだとか)、それを救う手段としては正式な結婚しかないので、義務感から(ではなかった訳ですが、彼的には)結婚を申し込んだミスタ・ソーントンは紳士として名誉ある行動をとったことになる筈なのですがねー・・・。
ベスのような弱い立場の人間を慮ることのない貴男は、紳士なんかじゃない!みたいな反発かなーと。
それと、本来ならミスタ・ソーントンより上の立場な筈の自分の凋落にも苛立っていたのかもしれませんけど。
>義務>愛なんでしょ!
これは思いつきませんでした。