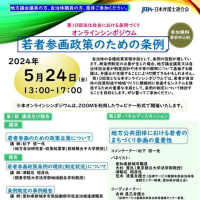『実践自治』(イマジン出版)の9月号は、「自治体職員の社会貢献型地域参画」を取り上げる。だいたいこんな感じで考えている。
1.地域に住む自治体職員が、地域に対する愛着や関係性等をよりどころに、地域のまちづくり活動等に参画(社会貢献型地域参画)するのは自由であり、むしろ好ましいことである。
ただ、それが私的行為であっても、公務員全体の信頼を損なうなどの場合には、その範囲で、地方公務員法は公務員の私的な活動にも関与するが、一般的には、社会貢献型地域参画が、この例外的なケースに該当することはきわめて稀だろう。
2.ただ、注意すべき点もある。最大のものは、この地域参画が有償で行われる場合をどう評価するかである。
地方公務員法第38条では、自治体職員は任命権者の許可を得なければ、①営利企業の役員を兼ね、②営利企業を営み、③報酬を得て事業事務に従事することができない。
任命権者が許可すべき事例として総務省が例示しているケースのひとつが、「補助金に頼らない商店街活性化に取り組もうと、職員が地元NPO法人の理事長として商店街活性化の活動に、週休日、年次有給休暇等を使って年50回程度、報酬月間3万円程度で参画する」ような場合である。
月額3万円といえども、「報酬を得て事業事務に従事すること」に当たるが、この場合は、許可すべき事例というのが総務省の考え方である。
民間企業では、兼業や副業が促進される傾向があるなかで、地方公務員についても、地域社会のコーディネーター等として、公務以外でも活躍することが期待されるようになっている。そうしたなかで、有償の社会貢献型地域参画をあいまいに処理するのではなく、許可基準を明確にすることで、これを積極的に推進しようというのが国に考え方である。
この総務省の考え方が、通知という方法で明確にされたことを受けて、自治体のなかには、社会貢献型地域参画について積極的に推進する要綱が制定され始めている。本稿では、こうした要綱が制定される背景と現行の水準を地方公務員制度の基本から考えてみたい。
3.あわせて、どんなに優れた制度も、それを活用できる環境になければ、社会貢献型地域参画は広がらない。上司や同僚の理解が乏しかったり、日常業務に追われ休日は寝るだけの暮らしぶりでは、社会貢献型地域参画をやりたくてもできないだろう。ライフワークバランスや働き方改革につながる問題で、一片の通知や要綱の制定では解決できない大きな課題である。
4.自治体の業務が変化し、自治体側の事情として、地域参画を経験する職員が必要になってくるが、その結果、本来ならば、自治体職員の自由で自主的な社会貢献型地域参画が、義務的・強制的な参画になっていく懸念である。この点にも目配せした制度設計が求められる。
このように自治体職員の社会貢献型地域参画をめぐる課題は、多面的であり、また日本社会の深層にふれる問題でもあり、一筋縄ではいかないテーマである。
8000字くらいの紙面なので、全部は書ききれないが、考えてみたい。