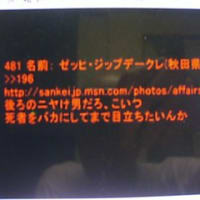産経新聞が母体と見ていますが、『MEPHIST』の豊富な裁判資料を活用したいと思いまして、できるかぎりプリントし、そして、目を通してみることにしました(情報収集において非力である私にとっては、まことにありがたいのです)。
印刷は、ドライアイを患い、目が痛い関係で、液晶画面を見る時間を減らすためです。
一方で、夏ですから、室内温度の上昇とともに、パソコンの本体が熱くなって、部品の溶熱の可能性があり、しばしの中断を余儀なくされています。
このパソコンは立ち上げのとき、応援団風の三三七七拍子が聞こえてきます。ピッピッピッ、チャチャってな音が10回ぐらい繰り返して、立ち上がってきます。
本体ではなくデイスクドライブのCDの回転する音のようですので、パンク寸前の音ではないと半ば安心し、且つ、パソコンのくれる応援歌と思って妙に癒されています。
資料に目を通して、アンビバレンスに関係する箇所に注目しました。
ネジレを記号として読み解くといいますか、これを利用して、一気に彩香ちゃん殺害時の被告の異常心理に迫りたいと考えています。
たとえば、公判で「(検察官が)怖かったから信頼していたというか・・・逆らえなかった」(裁判8・A・11/18)と鈴香被告は答えていますが、これは「怖い男だから安心して甘えることが出来る」という被告の幼児的なアンビバレンスな態度(一般的な女性心理?)と見ることが出来ます。
父親が家庭内では暴力を振るっていたから、被告を保護してくれる父親を外に求める結果になったと思っています。
次に、弁護側と鑑定人の間のやり取りで、彩香ちゃん事件の起きる4、5日前の出来事として、「彩香ちゃんが『学校へ行きたくない』と予想外のことが起き」(裁判13・A・7/17)たことを話題にして、「怖い」とか意味不明のやり取りがあるのですが、私の読みは「学校にいる間に、母親が自分を置いてどこかに行くかもしれないと不安に思っての甘え行動」というものです。
母親の鈴香被告は子捨て願望を取り付かれており、一方の子どもは空気を察知(以心伝心?)して「遺棄の恐怖」に取り付かれているわけです。
これに対して、「自分の子に対して何をするか分からず怖い」と被告が思うのは、「子殺し願望」の可能性を示唆するも、「子捨て願望」を満たそうとする自己への恐怖心を語るものいえないでしょうか。
(■続いて弁護側は、大沢橋の上で、鈴香被告が彩香ちゃんを「怖い」と感じていた理由を問う。鑑定人は当時の彩香ちゃんの行動から、「推測」を語る。
弁護側 「鈴香被告は彩香ちゃんを怖いと。『自分の自由や希望を奪うので怖かった』と供述している。そう思うか?」
鑑定人 「思わない。『怖い』には深い意味があると思う」
弁護側 「彩香ちゃんの『普通の母親になってほしい』という自己変革への(恐れという)見解か?」
鑑定人 「(彩香ちゃん)事件の4、5日前、彩香ちゃんが『学校に行きたくない』と予想外のことが起きる。そのころ、彩香ちゃんが友達の家に行っている。自分の母と友達の母の違いが分かり、彩香ちゃんの心に矛盾、葛藤が生まれる」
弁護側 「彩香ちゃんが鈴香被告に自己変革を要求したと?」
鑑定人 「推測です」
弁護側 「『怖い』に関連して。(鈴香被告の)『自分の子に対して何をするか分からず怖い』という調書をどう思うか?」
鑑定人 「強く感じない。彩香ちゃんへそういう気持ちが生じても、それは一般的なこと」
『MEPHIST』「裁判12・A =7/17P
http://shadow99.blog116.fc2.com/blog-entry-311.html)
註:子捨て願望について●それまでに自殺未遂事件を起こしていれば、鈴香被告の心の中に秘めた「自殺願望」の存在を裏付けますが、仮に、それが「母子心中未遂事件」という場合は、同じような理由で「未遂事件」を起こしているはずで、「母子心中願望」の存在が裏付けられるはずです。しかし、それがない以上、「母子心中未遂事件」という見方は成立しないと思います。
では、「子捨て願望」とどうか、となると、私の調べた範囲では、「子捨て未遂事件」を被告はそれまでに一度も引き起こしてはいません。
しかし、ネグレクトの母親というのは、一般的に「子捨て願望」をもつといえるのではないんでしょうか。
三番目のアンビバレンスな態度は、入院した父親を看護する被告の態度にあります。
公判の証人台には父親は立たなかったんですかねえ、裁判資料に目を通してみても、見当たりません。
私は鈴香被告が父親に対して、甘えと恐怖という幼児的なアンビバレンスの感情を持っていたと見ています。
下のasahicomの記事(所収は、『DANGER』(←『MEPHIST』の前身?)にありますように、被告はホームヘルパーの資格を取り、父親が脳梗塞で倒れて入院すると介護の手伝いをやります。
■畠山被告 介護疲れも要因か
父入院し生活も困窮 秋田(2006/10/01)
秋田県藤里町の連続児童殺害事件で、畠山鈴香被告(33)=殺人罪などで起訴=が長女彩香さん(当時9)を殺害したとされる4月9日の直前、入院中だった畠山被告の父親が、他の患者との間でトラブルとなり、ハサミを持ち出す騒ぎを起こしていたことがわかった。
捜査当局は、子育てや経済的な困窮などでストレスを抱えていた畠山被告が、父親のトラブルでフラストレーションを一気に高めたとみている。
彩香さん殺害の直接の動機について、畠山被告は捜査段階で、彩香さんに求められて近くの川に魚を見に行ったが、見えないことに彩香さんが「だだをこねた」ことから衝動的に殺害したと供述。しかし、殺害理由としては弱く、捜査当局は何らかの背景事情があったとみて調べていた。
畠山被告の父親は、脳梗塞(こうそく)のために05年に倒れて県北部の病院でリハビリを続けていた。
関係者によると、父親は4月7日、病院内で、ほかの患者との間でトラブルとなり、相手に向けてハサミを振り回そうとしたという。
翌8日、畠山被告が病院を訪れた際、病院側から「(畠山被告の父親の)面倒を見切れない」という趣旨のことを言われたという。
畠山被告は03年に自己破産し、生活保護の受給に加え、実家からも金銭的な支援を受けていた。しかし、父親が倒れたため、援助を受けられなくなり、経済的に追いつめられていた。また、地元住民の話では、畠山被告は、父親の介護の手伝いもしていて、介護疲れも見られたという。
捜査当局は、畠山被告が彩香さんをネグレクト(育児放棄)するなど、もともと子どもに対して激しい嫌悪感を抱いていた点も重視している。畠山被告は母親らの手助けを受けて子育てをしていたが、父親の入院のために、彩香さんの子育ての負担が被告1人にかかるようになったという。
(asahi.com 一部抜粋)
DANGER http://shadow9.blog54.fc2.com/blog-entry-149.html
上の引用にありますように、被告の「介護手伝い」は、二つの意味が隠されていると思います。
一つは、育ててくれた親への「恩返し」という意味です。
もう一つは、父親に対して被告は甘えと怖いという、幼児さながらのアンビバレンスな態度を持していることです。この意味は、「危険」と読めるわけです。
最初の意味については、被告が自己確立者であるならば、さしたる問題は起きないと思われるわけですが、非英雄の基本路線を生ききらざるをえなかった被告の場合は、その意味が屈折するのが当たり前です。
つまり、鈴香被告の「恩返し」は「親越え→恐怖越え」と連絡(ジャンプ)する可能性を秘めているわけです。
次の意味については、父親が恐怖の対象であるならば、娘被告は彼から逃れて他の男に父親代わりを求め、娘時代に満たされなかった甘えを満たすことが出来ます。
ですから、被告の介護手伝いは、怖い父親に対して甘えるという、一種危険な賭けに打って出たとしか考えられないわけです。
註1:父親は「すずゆう興業」なる会社を経営しているとか。この名の由来は、二人の子どもの名前から取ったから子煩悩な父親のごとき人物像として描かれていますが、下の「興業」は、ヤバイ系という認識で私たち建設作業員の間では一致しています。
註2:暴力とは、国際紛争にしろ、夫婦喧嘩にしろ、それまでの古い関係を解体して、新しい上下関係を構築する狙いが隠されています。一言で言えば、関係のリセットです。連日連夜、暴力が振るわれるとすれば、もはやリセットの意味が失われ、ただ人間(あるいは、国)が壊されていきます。
註3:仮に闘犬の血筋を引き継いだ子犬が幼少期に「咬ませ犬」のごとき処遇を受けていたならば、彼は「闘犬の死」に等しい、負け犬根性を身につけるはずです。
ウウウと闘う前から唸るようでは、闘犬を廃業する必要があります。人間だって、同じでしょう。
父親の入院に伴う生活援助金の打ち切りは、細々と生活保護を受けて暮らす母子家庭の生活不安につながりますが、それ以上に、それの持つ象徴的な意味は、甘えたいという願望の挫折でしょう。
そこに突然、父親が院内暴力を働くことは、それまで忘れていたトラウマを思い出させた可能性があります。
私はそれを「遺棄の恐怖」と読みました
願望を満たす道はとざされ、突如として「遺棄の恐怖」に襲われた可能性は否定できません。
ですが、この場合は、被告には3つの選択肢があったはずです。
pは、父親から逃れて、県外へ脱出する方法。
qは、愛人との性生活におぼれて、嫌なことを忘れる方法。
rは、親越えを意味する、象徴的な恐怖越えを行って、自己回復を遂げる方法。
pとqは、いずれも一時しのぎに過ぎず、原点回帰が目に見えています。
というのは、父親の「壁」が立ちはだかるからです。何をやってもこの壁にぶち当たり、挫折感に打ちひしがれてしまうのです。
ですから、鈴香被告にとっては「もう逃げないぞ」と覚悟を決めて臨んだ「介護手伝い」ではなかったかと見ています。
参考資料■
弁護側 「父親の暴力はどのように影響しているのか?」
鑑定人 「父親に対しては、愛情を感じる要素、感じたくない要素という矛盾した気持ちを持っていた。お父さんの介護をイヤイヤながらして血のつながりを感じていたが、父親がイヤであるという葛藤(かっとう)は大きかった」 『MEPHIST』の裁判資料(12・A ・4/17P)
http://shadow99.blog116.fc2.com/blog-entry-311.html