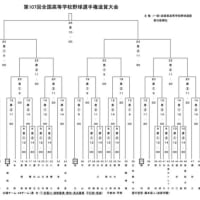長浜市木之本町の山間部にかつてあり、1965年(昭和40年)の閉山まで銅鉱山で栄えた「土倉集落」で、写真が残っているものの場所が不明だった民家や学校の跡38カ所の位置が分かった。

↑中日新聞より
集落跡は草木に覆われ痕跡がわかりにくくなっているが、長浜市のながはま森林マッチングセンターや元住民がフィールドワークで明らかにした。インターネット上の地図「グーグルマップ」で閲覧できる。
土倉集落は、明治末期から土倉鉱山の銅採掘で栄えた。
最大で鉱山労働者やその家族ら1000人以上が居住。鉱山施設のほか、ブロック住宅や学校、映画館などが立ち並んだが、閉山で無人に。現在は一部施設のコンクリート土台などが木々の間から見えるのみとなっている。
集落の痕跡を読み取るのは難しいが、集落出身の白川陽子さん(米原市坂口)の父で鉱山職員だった雅一さんが閉山前の集落を白黒写真に収めていた。集落の日常を捉えた2000枚以上が現存する。

↑中日新聞より
センターは集落周辺の活性化に向け、昨年から一帯の歴史や自然について学ぶフィールドワークを展開。今回は5月28日、白川さんの案内で、写真に写った主な施設の場所を調べた。
木が少ない平たん部などで、建物の基礎や水道管、ガイシが残る変電所跡、坑道の入り口などを確認。写真や記憶、以前に見つかっていた手書き地図と照らし合わせ、民家や寮、学校、映画館などの位置を推定した。
白川さんによると、集落では共同浴場を使ったり、限られた食べ物を融通しあったりと、住民同士の連帯が強かったが、元住民は高齢化が進み、鉱山で働いた世代の多くは他界。記憶は失われつつある。白川さんは中学卒業まで集落で暮らし、卒業とほぼ同時に閉山となった。「友人や近所の人の顔が思い出されてしんみりした」と振り返る。
今後は他施設の位置も特定を進め、地図にまとめるという。一帯を巡るツアー企画の計画もある。
白川さんは「閉山後に埋め立てられた場所もあった。集落が社会に知られ、残っていくとうれしい」と話した。
<中日新聞より>