
ECM系の音楽が好きな人は是非観るべき映画だと思う。バップ一辺倒の人には、もしかしたらある種の拒絶反応が起こるかも知れない。
ジャズの進化、現在、そして未来を描いたドキュメンタリーだ。出演しているミュージシャンは、リー・コニッツを始め、いずれも現代のレジェンドと呼ばれるオリジナリティ溢れる素晴らしい巨匠達。一音聞けば、すぐさま彼等だと分かる。
しかし、映画が進行する中で、僕の中に「これは果たして『ジャズ』なのか?」という考えが頭をもたげた。若い頃なら「それは凝り固まった年寄りの考えだ!ジャズは常に進化して形を変えて行くもんだ!」と非難した事だろう。しかし、劇中に流れる音楽はどれも、ジャズと言うより「improvised music」にしか聴こえないのだ。
勿論、それは「否定」ではなく、そういう音楽が有っても良いと僕は思ってるし、僕自身、今まで散々色んなジャンルを演って来たり聴いて来たわけで、否定に至る筈も無く、寧ろリスナーとしての自分の許容量はそんじょそこらの人よりかは遥かに広いと思ってる。
しかし、ここで聞かれる音楽のリズムはGrooveというよりは寧ろPulseに感じるし、コード進行は簡素化され個々のミュージシャン達の集団的即興に重点を置かれている。ジャズのジャズたる所以は何だろう?と考え始めた。つい先日、Facebookでバリー・ハリス(p)の教えについて語ってみたら、様々なミュージシャンとのやり取りに発展したので、興味が有ればコメント欄まで読んで頂きたい。https://www.facebook.com/share/16MWMEnMnm/?mibextid=wwXIfr
(コピペが必要みたいです。)
こういった音楽は、オーネット・コールマンなどフリージャズのムーブメントの時代から有るし(トリスターノが’49年にやった集団即興は取り敢えずは置いておこう)、僕は'94年頃、実際にNYのヴィレッジ・ヴァンガードで、この映画にも出演している、ジョー・ロバーノ(ts)、ビル・フリーゼル(g)、ポール・モチアン(ds)のトリオで同様のコンセプトの演奏を聴いた。全く理解出来なかったし、楽しいとは思えなかった。
楽しいかどうかは置いておいて、劇中でもコニッツが、自分が演奏したこういった音楽を「理解出来ない。」と言うシーンが有る。それがいずれ、この映画のタイトルにも結び付くのだが、それは映画を観て確認して欲しい。
そのシーンは思わず僕の笑いを誘ったんだけど、所々でコニッツの無邪気さや奔放さが飛び出して笑ってしまう。ボケてんじゃないの?って思う事もあるけど、単に何でも衝動的にやっちゃって、後で困るタイプなんだなぁと思った(終盤のタクシーのシーン)。まさにインプロバイザー(笑)
マーク・ターナーの演奏なんかは、クラシック系現代音楽の美しさを感じるし、劇中でもあらゆる所で彼の神経質な所が伺える。たとえ即興と言えども、彼の様に全てに完璧を求める人も居れば、ヴァイブの方を重要視する人も居る。
寧ろ多くは、子供や原始人の様なプリミティブな方向性を模索してる様な気がする。テクニックや理論などの知識を一旦忘れて、個々の人間が持つそれぞれの人間性を吐露してこそ初めてオリジナリティが生まれる…という所まで初期段階に原点回帰させてる様な。可愛らしい赤ちゃんの映像も数回流れるが、それを暗示している様な気がしてならない。(ついでに、我が子がまだ0歳の頃、涎垂らしながらキーボードをガンガン鳴らしてるビデオまで思い出した笑)
こういった原始への回帰は、60年代の黒人達によるアフリカ回帰のムーブメントにも見受けられるし、白人でもヨーロピアンなんかは結構好んでいる様な気がする。だから、本来のルーツであるアフリカ回帰ともヨーロピアンの原始回帰とも異なるマーク・ターナーの演奏は中でも異質に感じたのかも知れない。
さて、冒頭のジャズか否か…は、流石に不毛な議論であると思えるのだが、この音楽が楽しいか楽しくないかでいうと、僕にとってはかなり微妙だし、アルバムを買うか?と言われると、いや、過去のレジェンド達のレコード買うので精一杯なのでごめんなさい!と答えるしかない。でも、要所要所で「素晴らしい!美しい!」と思ったのも事実だ。
もう、僕は残りも減って来た人生で自分には嘘は付けない。聴きたいのは心底「楽しい!」と思える音楽だけだ。
施設に入ってる母は、面会に行くとずっと歌っている。彼女は昔、あれほどアメリカナイズドされて洋楽ばかり聴いていたってのに、今口ずさんでいるのは昭和歌謡や童謡ばかりだ。結局、原始回帰すると本当に好きだったものに戻るんだなぁ…と思った。彼女にとって洋楽なんてのは単に背伸びする為の道具で、無理して好きになって聴いてた様な気がする。
なんだか、今のジャズって演奏者もリスナーもスノッブになり過ぎて、本当に心底楽しんでるのかな…って思う。「テク、スゲ〜!」とか「最新!」とか「これぞ芸術的!」とかどうでもいいんだよね。心底楽しくないと…
他人が作るジャズの進化にはもう正直興味は無く、自分自身で言うと、兎に角、残りの人生で自分の音楽性をもっと高めて充実させて、文化的に豊かな人生を送りたいってだけだ。それが個人的なジャズの進化と言うならそうかも知れない。でも、この映画に出演した偉大なミュージシャン達もそれぞれ、結局は同じなんだと思う。
あとは、好きな人が心底楽しめる好きな音楽を聴けば良いだけの話。
冒頭、コニッツが自作の「Kary's Trance」(だっけかな??)を練習してて上手く行かず、イラついてるのがとても身近に感じた。










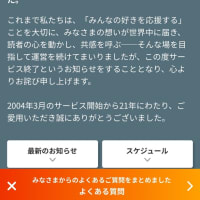







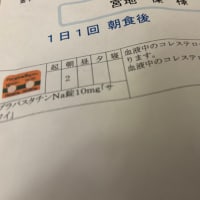

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます