寒川駅から徒歩5分のところに大神(応神)塚と呼ばれる古墳があります
私の住む倉見駅からわずか2駅
徒歩でも40分もかからない場所にあるのですが
東京の人が東京タワーに行かないように
近いところほどなぜか盲点になってしまうようです
意を決して?大神塚を目指し出発しました
現在は真言宗安楽寺の境内の一部になっている大神塚古墳は
2段になった前方後円墳で下壇周縁部は墓地や宅地になっていました

いちおう上壇部分は木や草が茂り かろうじて保存されています

寒川町教育委員会の説明看板には
「全長約50メートル後円部径役30メートル高さ約5メートルの
帆立貝形を呈する大きな前方後円墳である
明治41年4月寒川神社宮司の提唱で坪井博士により発掘調査が行われた
出土した和鏡2面 漢鏡1面 直刀3振 金銀環 勾玉 管玉らは寒川神社参集殿に展示されている
古墳の築造は5世紀と推定される」と書いてありました
当時のヤマトの東端のサガミのクニは貿易の拠点として重要だったはず
蘇我氏の支配地域だったサガミの信仰の中心として造った寒川神社
そのそばに葬られたのは誰だったのでしょうか?
今となっては何もわからなくなってしまいました
古墳を降りると安楽寺の境内にいたのはトラ猫

お寺を出たらまたトラ猫

角を曲がったらまたまたトラ猫

なぜか大陸から半島にかけて棲んでいた虎たちに見えてきました
私の住む倉見駅からわずか2駅
徒歩でも40分もかからない場所にあるのですが
東京の人が東京タワーに行かないように
近いところほどなぜか盲点になってしまうようです
意を決して?大神塚を目指し出発しました
現在は真言宗安楽寺の境内の一部になっている大神塚古墳は
2段になった前方後円墳で下壇周縁部は墓地や宅地になっていました

いちおう上壇部分は木や草が茂り かろうじて保存されています

寒川町教育委員会の説明看板には
「全長約50メートル後円部径役30メートル高さ約5メートルの
帆立貝形を呈する大きな前方後円墳である
明治41年4月寒川神社宮司の提唱で坪井博士により発掘調査が行われた
出土した和鏡2面 漢鏡1面 直刀3振 金銀環 勾玉 管玉らは寒川神社参集殿に展示されている
古墳の築造は5世紀と推定される」と書いてありました
当時のヤマトの東端のサガミのクニは貿易の拠点として重要だったはず
蘇我氏の支配地域だったサガミの信仰の中心として造った寒川神社
そのそばに葬られたのは誰だったのでしょうか?
今となっては何もわからなくなってしまいました
古墳を降りると安楽寺の境内にいたのはトラ猫

お寺を出たらまたトラ猫

角を曲がったらまたまたトラ猫

なぜか大陸から半島にかけて棲んでいた虎たちに見えてきました










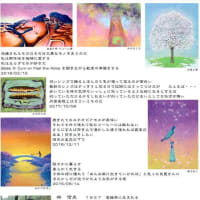
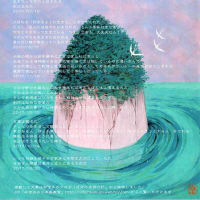
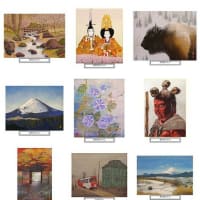












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます