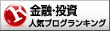先日の健康診断の結果が送られてきた。
胸部X線・心電図・貧血・肝機能・血中糖質・糖代謝・血圧・ヘマトクリット・・・、
すべて正常、判定A
これで、気をつけるのは相場の病気だけだな(笑)
「曲がりの病気 2」
先物相場に志を持つ人は、曲がりの病気は避けて通れない仕組みである。
であるから、相場に曲がるということは日常茶飯事。決して恥ずかしいことではない。
ただし、この病気だけは非常に苦しい。
苦しいのは病気を可愛がるからである。矛盾しているようだが、これがすべてである。
病人には医者、そして薬、周囲のあたたかい看護を必要とするが、曲がりの病気は
それらすべてが、逆に病気を酷くする。お金が続かず玉が切られる。これは死である。
死ぬ時は、再起不能なくらい無理してきている。それを思うから、なかなか死ねない。
もっと早く死んでいればよかったと思うのは、随分あとからだ。
この病気のタチの悪さは、なんの前触れもなくある時ふいと治ることである。
治ると見るや、今度は当たりの病気が始まる。
曲がりの病気も死に病であるが、当たりの病も死に病である。
当たって当たって、大当たり、大儲けした人は、必ずもっと大きな曲がりの病気が
来るものである。相場の方程式でいえば、大当たりに当たったあとは必ず
死ぬような曲がり方をする。
まあ、やられるまで止めれないから
遅かれ早かれこうなる運命なんだろう(苦笑)
Christina Milian ~ Someday One Day (with lyrics)
胸部X線・心電図・貧血・肝機能・血中糖質・糖代謝・血圧・ヘマトクリット・・・、
すべて正常、判定A
これで、気をつけるのは相場の病気だけだな(笑)
「曲がりの病気 2」
先物相場に志を持つ人は、曲がりの病気は避けて通れない仕組みである。
であるから、相場に曲がるということは日常茶飯事。決して恥ずかしいことではない。
ただし、この病気だけは非常に苦しい。
苦しいのは病気を可愛がるからである。矛盾しているようだが、これがすべてである。
病人には医者、そして薬、周囲のあたたかい看護を必要とするが、曲がりの病気は
それらすべてが、逆に病気を酷くする。お金が続かず玉が切られる。これは死である。
死ぬ時は、再起不能なくらい無理してきている。それを思うから、なかなか死ねない。
もっと早く死んでいればよかったと思うのは、随分あとからだ。
この病気のタチの悪さは、なんの前触れもなくある時ふいと治ることである。
治ると見るや、今度は当たりの病気が始まる。
曲がりの病気も死に病であるが、当たりの病も死に病である。
当たって当たって、大当たり、大儲けした人は、必ずもっと大きな曲がりの病気が
来るものである。相場の方程式でいえば、大当たりに当たったあとは必ず
死ぬような曲がり方をする。
まあ、やられるまで止めれないから
遅かれ早かれこうなる運命なんだろう(苦笑)
Christina Milian ~ Someday One Day (with lyrics)