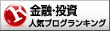豪商何某の話
相場が安くなってしまい売り叩かれ、仕入れた商品は元金を割って
投げ売るしかない。仕方ないと心を放しているうちに、相場は上昇しだし
何故あれほど心を痛めたか、など忘れてしまった。
その時に売ってしまえば一割ほどの利益になったのに、せめて二割くらいは
儲けたいという気になった。その時の仲間内の人気といったら、私の持っている
商品を売ってくれ、売ってくれとやかましい。
自分は欲に目がくらんで、もっと高く売ろうと思っているうちに相場は
下がり出して大損してしまったのです。
この時に悟ったのが損得にびくびくしていては商法にならないという事です。
そのような心配をしなくてよい方法はないものか。
自分の気持ちが冷静である時に確り思い極めておき、その時の相場動向や
人気に左右されず、当初に決めたところで欲を出さず売りさばく。
古人言う。
業は勤むるに精しく勤むれば必ず其極致に達すと。諸学人、請ふ、怠るなかれ。
相場の世界も、つきつめていえば「全てこれ心中の惑い」ということ。
理屈は判っていても・・・、(苦笑)
相場が安くなってしまい売り叩かれ、仕入れた商品は元金を割って
投げ売るしかない。仕方ないと心を放しているうちに、相場は上昇しだし
何故あれほど心を痛めたか、など忘れてしまった。
その時に売ってしまえば一割ほどの利益になったのに、せめて二割くらいは
儲けたいという気になった。その時の仲間内の人気といったら、私の持っている
商品を売ってくれ、売ってくれとやかましい。
自分は欲に目がくらんで、もっと高く売ろうと思っているうちに相場は
下がり出して大損してしまったのです。
この時に悟ったのが損得にびくびくしていては商法にならないという事です。
そのような心配をしなくてよい方法はないものか。
自分の気持ちが冷静である時に確り思い極めておき、その時の相場動向や
人気に左右されず、当初に決めたところで欲を出さず売りさばく。
古人言う。
業は勤むるに精しく勤むれば必ず其極致に達すと。諸学人、請ふ、怠るなかれ。
相場の世界も、つきつめていえば「全てこれ心中の惑い」ということ。
理屈は判っていても・・・、(苦笑)