三ノ輪の浄閑寺といえば、またの名を、投げ込み寺で知られる寺である。投げ込み寺の由来は、遊里吉原に身を沈め、そこで不幸にも命を落とした身寄りのない遊女たち二万五千人余りを投げ込み同然の状態でその寺に埋葬したことによる。
日比谷線三ノ輪駅を降り、商店街を東に少し入ると、下町には珍しく、そこだけ濃い緑に包まれた一角がある。
山門をくぐり、秋の日が長い影を落とす狭い境内に踏み込むと、ふいに、あたりの物音が絶え、不思議なくらいの静寂に包まれる。 投げ込み寺と知って訪れるせいか、寺に漂う雰囲気がなにやらいわくあり気である。
浄閑寺のある地は、かつて吉原への遊客が足繁く通った日本堤の入口にあたる場所でもあった。
日本堤と呼ばれたのは、当時、そこに音無川という小流があり、流れに沿って土堤が連なっていたためだ。吉原への遊客はその土堤を通い、あるいは、その流れに船を浮かべて吉原にやって来たのである。
音無川はその一部を山谷堀とも呼んだ。現在も暗渠となって残り、隅田川に注いでいる。
流れに沿って、地方橋だとか、今戸橋などの懐かしい名がそのまま残されている。
* * *
かつての遊里吉原と浄閑寺が日本堤で結ばれていた因縁から、浄閑寺が、いつの頃から吉原の遊女たちの投げ込み寺となったのかは定かではない。
が、この寺が浄土宗であったことが、ひとつの機縁であったともいえる。というのも、浄土宗は、念仏を唱えれば衆生みな救われるという教えで、当時庶民の間に大変広まった宗派であったからだ。
浄閑寺は文字通りそれを実践していた寺であった。この寺の門をひとたびくぐれば、有縁無縁の者すべて救われる、というのがこの寺の宗旨でもあった。落命した身寄りのない遊女たちの埋葬地として、この寺が選ばれたのもごく自然のなりゆきであったかも知れない。
その浄閑寺が創建されたのは明暦元年(1655)のこと。二年後の明暦三年正月一八日に、俗に振袖火事と呼ばれた江戸大火が起こる。そして、吉原遊郭が日本橋から浅草田圃の一角に移されたのが、その年の八月。
以来、名前も新吉原と呼ばれるようになって江戸名所のひとつとして繁栄する。が、その繁栄は薄幸の遊女たちの身を切る犠牲の上に咲いた徒花とも言えた。
一方、吉原の遊女たちにとって浄閑寺は、特別の意味をもつ寺となったのである。
そもそも、江戸という町に吉原のような幕府公認の遊郭がつくられたのは、江戸の男女の人口構成が極端にバランスを欠いていたところに理由がある。
江戸は開府以来、出稼ぎの町であった。地方から上京する働き手のほとんどは男であった。それに幕府の参勤交代制度が敷かれたこともあって、国許に妻女を残して単身赴任している武士が沢山いた。
幕府は、こうした江戸の町の実態を憂慮して、犯罪防止のために、一定の場所に公認の郭町を造り、治安、風紀を保つことを目論んだのである。
かくして、新吉原開業から昭和三十三年四月の廃業までの三百年もの間、吉原は公認の遊郭として栄え、さまざまな文化と風俗を提供することになった。
そして、そこに身を沈め、不幸にして命を落とした女たちが浄閑寺に葬られつづけたのである。
もちろん、遊女のすべてが、この寺に葬むられたわけではない。ほかにもこの種の寺が吉原近辺にはあったし、多くは楼主の菩提寺に埋葬された。
浄閑寺には、引き取り手がなかったり、身寄りのない者が埋葬されたのである。
そのありさまが今に伝えられている。
骸になった遊女は、大引け過ぎ、今の午前二時過ぎになると、青楼の裏口から、そっと担ぎ出された。骸は薦に包み、戸板に乗せられ、それを楼の若い衆が土手沿いに運んでいった。
浄閑寺には今もこれら遊女たちの顛末を伝える過去帳が残されているという。
そこに記載されているのは、法名と没年、どこの妓楼の者であったか、の文字だけである。もちろん、これでは本姓も、どこの生まれの者かも、年齢さえ分からないままだ。 江戸時代、遊女は身を売ると同時に戸籍簿からもその存在を抹消されていたわけだ。
* * *
永井荷風は人も知る遊里を徘徊し、遊里小説を著した作家である。荷風はその縁もあって、遊女に因んだ浄閑寺を幾度か訪れている。荷風が初めてここを訪れた時の様子が、『夜の女界』という小品の中に記されている。明治三十一、二年頃の記録だ。
「哀れな娼婦が白骨の行衛を知らうと思ふ人あらば、哀れな娼婦が悲しき運命の最後を弔はんと欲する人あらば、乞ふ、吉原の花散る大門を出て、五十軒を過ぎ、衣紋坂を上り、土手八丁、其の堤を左へと辿り辿って行き給へよ」と、まず浄閑寺に誘っている。
そして、浄閑寺に至る土堤八丁からの眺めを、「堤の両側すこぶる美しき田園の光景を、行く人の眼の前に広げるであらう。右手は見渡す限りの水田を隔てて、小塚原や千住の青楼が、高く低く屋根を並べて居る。此の一団の人家を越えては、所々に樹や竹藪の茂りが青々と望まれ、そして其の又、彼方には、隅田の上流を行く白い帆影が、幽かに其れとなく認められる。若し天気が通る様であったなら、無論紫の筑波山さへもが雲から見出されるのである。目を転ずる堤の左側、其処には、大分畠を埋めた新開の町に立てられた借家が居並んで居る。樹の茂りの間には高い屋根のお寺なども折々見られるであらう。上野から日暮里、道灌山へ及ぶ一帯の丘を蔽ふ森の茂り、如何にも心地よく眺められる。此の美しい景色の間を行く中に、軈屠獣場の門前に掛って血腥き風に鼻を蔽う事があるけれど、小時の中に行き過ぎれば、堤の上は、古風な並木街道になって了ふ」と描写している。
現在と比較すると、土堤の左右の景観は隔世の感がある。土堤の右手、日本堤から千住の方向は、いまだ一面の水田風景が開けていた。墨田川の流れがゆったりと望まれた様子も知れる。一方、左手、竜泉、根岸の方面は、畑地の中に貸家らしき建物が点在する郊外地の風情であったことが分かる。
やがて歩くほどに、前方右手に高く築き上げられた汽車道が見えてくる。それは現在の常磐線の線路で、浄閑寺はその汽車道の下にあった。
「堤の右側の裾に沿うて、流れて居る溝の様な小流れ、其の上に、一ツの古雅な形をなした石橋が架けられてある。流れは寺の小笹の茂り多き垣を取巻いて、後ろの汽車道の方へと見えなくなって居る。如何にも寂びた有様を愛でながら、橋を渡り、黒い寺門に達して、仰ぎ見ると、浄閑寺と云ふ寺である事を知る」
もちろん、現在はその小流はない。周囲は人家が密集し、寺の敷地だけが大谷石の石塀に守られ、かろうじて緑に包まれている。ただ古びた寺門は荷風が訪れた時のまま今も健在である。
「門を這入ると、例の花売る小屋がある。余り広からぬ本堂の左手から、其の裏手へ掛けて、此処が墓地、石塔や、卒塔婆が累々として並んで居る。叢の様になって居る垣の近く、又は石塔の間の其処此処には、かなりに年経た、瘤多き榎木が、幾株も立ち茂って、ふる風の来る度に物悲しい声をして、其の枝を顫はして居る。先、見当たり次第の石碑の前に屈んで、すでに能くは見分からぬ、其の彫付けた文字を見ると、柳生院花容童女之墓と云ふ様な仏名が読まれる、又は、□□楼代々の墓とか、或は男と女の名が二ツ並べて彫ってあるのも身当てられる。然し、何の石塔も二尺、三尺と計る程、高いものは無い、何れも、小さな汚いものばかりで、久しく香花を手向けられた事もないと思はれる。・・・何たる、淋しい、物恐ろしい有様なるよ。来る人は忽ち陰惨の気に打たれて、已に冷たい穴の中には這入った様な心持がする。昨日まで、緑の黒髪を黄金に飾り、雪なす肌を錦の襠裲にまとはせた、花とも蝶とも見るべき遊女の骨は、実に、此の陰気な淋しい処に横たはって居るのであった。見よ。二本ほど、大きな榎木を後にして、此処に、巍然と高く石垣を築き上げた、その上に、一個の石柱がある。新吉原無縁墓此の六字が彫り付けられてあるばかり。其の周囲には幾何の雑草の生へて居るのも見た。安政大地震の時に大供養をした太い卒塔婆が猶、腐れずに立って居るのも見た」
荷風が訪れた当時は、寺は大改修の直前であったらしい。そのためもあって、荷風も記しているように、寺の荒廃がかなり進んでいたことがうかがえる。
また、その頃はまだ土葬であったために、墓地内は凸凹が激しく、それが一層陰惨の風を高めていたともいえる。
そして、その墓群の中に、ひときわ高くそそり立つ遊女たちの無縁墓があった。現在は新吉原總霊塔という文字が刻まれているが、これは昭和四年に改修されたものだ。
石塔は、蓮の形をした台座の上に乗り、それを支えるように昔のままに石垣が築かれている。
その石垣には「生まれては苦界 死しては浄閑寺」の花又花酔の句が刻まれている。
石垣の横に小さな窓のついた扉があった。その窓から墓の内部を覗くと、氷室のような墓室に骨壷が累々と並べられている。
思わず見てはならないものを見てしまった思いと同時に、卒然と哀れさが胸に迫ってきたのである。
荷風はそれから四十年後、再びここを訪れている。その頃吉原を題材にした小説を書こうとしていたからである。
「掛茶屋の老婆に浄閑寺の所在を問ひ鉄道線路下の道路に出るに、大谷石の塀を囲らしたる寺即これなり。門を見るに庇の下雨風に洗はれざるあたりに朱塗の色の残りたるに、三十余年むかしの記憶は忽ち呼返されたり。土手を下り小流に沿ひて歩みしむかしこの寺の門は赤く塗られたるなり。・・・今日の朝三十年ぶりにて浄閑寺を訪ひし時ほど心嬉しき事はなかりき。近隣のさまは変りたれど寺の門と堂宇との震災に焼けざりしはかさねがさね嬉しきかぎりなり。余死するの時、後人もし余が墓など建てむと思はば、この浄閑寺の塋域娼妓の墓乱れ倒れたる間を選びて一片の石を建てよ。石の高さ五尺を超ゆべからず、名は荷風散人墓の五字を以て足れりとすべし」(『断腸亭日乗』昭和12/6/12日より)
荷風も記しているように、本堂と庫裡は震災にも遭わず、その後の戦災にも無事で、ついこの間まで寛保二年(1742)以来の建物(本堂は昭和五十九年に残念ながら一部焼失する)の姿かたちを保っていた。
が、それもさすがの老朽化には勝てなかったと見え、現在は取り壊され、新しいコンクリート造りの堂宇が建てられている。
* * *
ところで、『断腸亭日乗』に著し、そう願った荷風の墓は、結局この浄閑寺には建てられなかった(墓は雑司ケ谷の永井家代々の墓地にある)。代わりに、浄閑寺の娼妓たちの霊を祀った総霊塔の前に、荷風散人の文学碑が立っている。
その碑面には、「今の世のわかき人々われにな問ひそ今の世と、また来る時代の芸術を」で始まる『偏奇館吟草』の一部「震災」から抜粋した詩文が刻まれている。
そして、その碑の左隅に、赤御影石でできた荷風の筆塚がひっそりとそえられている。それは荷風氏のせめてもの願いにそった事蹟であるかも知れない。
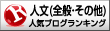
日比谷線三ノ輪駅を降り、商店街を東に少し入ると、下町には珍しく、そこだけ濃い緑に包まれた一角がある。
山門をくぐり、秋の日が長い影を落とす狭い境内に踏み込むと、ふいに、あたりの物音が絶え、不思議なくらいの静寂に包まれる。 投げ込み寺と知って訪れるせいか、寺に漂う雰囲気がなにやらいわくあり気である。
浄閑寺のある地は、かつて吉原への遊客が足繁く通った日本堤の入口にあたる場所でもあった。
日本堤と呼ばれたのは、当時、そこに音無川という小流があり、流れに沿って土堤が連なっていたためだ。吉原への遊客はその土堤を通い、あるいは、その流れに船を浮かべて吉原にやって来たのである。
音無川はその一部を山谷堀とも呼んだ。現在も暗渠となって残り、隅田川に注いでいる。
流れに沿って、地方橋だとか、今戸橋などの懐かしい名がそのまま残されている。
* * *
かつての遊里吉原と浄閑寺が日本堤で結ばれていた因縁から、浄閑寺が、いつの頃から吉原の遊女たちの投げ込み寺となったのかは定かではない。
が、この寺が浄土宗であったことが、ひとつの機縁であったともいえる。というのも、浄土宗は、念仏を唱えれば衆生みな救われるという教えで、当時庶民の間に大変広まった宗派であったからだ。
浄閑寺は文字通りそれを実践していた寺であった。この寺の門をひとたびくぐれば、有縁無縁の者すべて救われる、というのがこの寺の宗旨でもあった。落命した身寄りのない遊女たちの埋葬地として、この寺が選ばれたのもごく自然のなりゆきであったかも知れない。
その浄閑寺が創建されたのは明暦元年(1655)のこと。二年後の明暦三年正月一八日に、俗に振袖火事と呼ばれた江戸大火が起こる。そして、吉原遊郭が日本橋から浅草田圃の一角に移されたのが、その年の八月。
以来、名前も新吉原と呼ばれるようになって江戸名所のひとつとして繁栄する。が、その繁栄は薄幸の遊女たちの身を切る犠牲の上に咲いた徒花とも言えた。
一方、吉原の遊女たちにとって浄閑寺は、特別の意味をもつ寺となったのである。
そもそも、江戸という町に吉原のような幕府公認の遊郭がつくられたのは、江戸の男女の人口構成が極端にバランスを欠いていたところに理由がある。
江戸は開府以来、出稼ぎの町であった。地方から上京する働き手のほとんどは男であった。それに幕府の参勤交代制度が敷かれたこともあって、国許に妻女を残して単身赴任している武士が沢山いた。
幕府は、こうした江戸の町の実態を憂慮して、犯罪防止のために、一定の場所に公認の郭町を造り、治安、風紀を保つことを目論んだのである。
かくして、新吉原開業から昭和三十三年四月の廃業までの三百年もの間、吉原は公認の遊郭として栄え、さまざまな文化と風俗を提供することになった。
そして、そこに身を沈め、不幸にして命を落とした女たちが浄閑寺に葬られつづけたのである。
もちろん、遊女のすべてが、この寺に葬むられたわけではない。ほかにもこの種の寺が吉原近辺にはあったし、多くは楼主の菩提寺に埋葬された。
浄閑寺には、引き取り手がなかったり、身寄りのない者が埋葬されたのである。
そのありさまが今に伝えられている。
骸になった遊女は、大引け過ぎ、今の午前二時過ぎになると、青楼の裏口から、そっと担ぎ出された。骸は薦に包み、戸板に乗せられ、それを楼の若い衆が土手沿いに運んでいった。
浄閑寺には今もこれら遊女たちの顛末を伝える過去帳が残されているという。
そこに記載されているのは、法名と没年、どこの妓楼の者であったか、の文字だけである。もちろん、これでは本姓も、どこの生まれの者かも、年齢さえ分からないままだ。 江戸時代、遊女は身を売ると同時に戸籍簿からもその存在を抹消されていたわけだ。
* * *
永井荷風は人も知る遊里を徘徊し、遊里小説を著した作家である。荷風はその縁もあって、遊女に因んだ浄閑寺を幾度か訪れている。荷風が初めてここを訪れた時の様子が、『夜の女界』という小品の中に記されている。明治三十一、二年頃の記録だ。
「哀れな娼婦が白骨の行衛を知らうと思ふ人あらば、哀れな娼婦が悲しき運命の最後を弔はんと欲する人あらば、乞ふ、吉原の花散る大門を出て、五十軒を過ぎ、衣紋坂を上り、土手八丁、其の堤を左へと辿り辿って行き給へよ」と、まず浄閑寺に誘っている。
そして、浄閑寺に至る土堤八丁からの眺めを、「堤の両側すこぶる美しき田園の光景を、行く人の眼の前に広げるであらう。右手は見渡す限りの水田を隔てて、小塚原や千住の青楼が、高く低く屋根を並べて居る。此の一団の人家を越えては、所々に樹や竹藪の茂りが青々と望まれ、そして其の又、彼方には、隅田の上流を行く白い帆影が、幽かに其れとなく認められる。若し天気が通る様であったなら、無論紫の筑波山さへもが雲から見出されるのである。目を転ずる堤の左側、其処には、大分畠を埋めた新開の町に立てられた借家が居並んで居る。樹の茂りの間には高い屋根のお寺なども折々見られるであらう。上野から日暮里、道灌山へ及ぶ一帯の丘を蔽ふ森の茂り、如何にも心地よく眺められる。此の美しい景色の間を行く中に、軈屠獣場の門前に掛って血腥き風に鼻を蔽う事があるけれど、小時の中に行き過ぎれば、堤の上は、古風な並木街道になって了ふ」と描写している。
現在と比較すると、土堤の左右の景観は隔世の感がある。土堤の右手、日本堤から千住の方向は、いまだ一面の水田風景が開けていた。墨田川の流れがゆったりと望まれた様子も知れる。一方、左手、竜泉、根岸の方面は、畑地の中に貸家らしき建物が点在する郊外地の風情であったことが分かる。
やがて歩くほどに、前方右手に高く築き上げられた汽車道が見えてくる。それは現在の常磐線の線路で、浄閑寺はその汽車道の下にあった。
「堤の右側の裾に沿うて、流れて居る溝の様な小流れ、其の上に、一ツの古雅な形をなした石橋が架けられてある。流れは寺の小笹の茂り多き垣を取巻いて、後ろの汽車道の方へと見えなくなって居る。如何にも寂びた有様を愛でながら、橋を渡り、黒い寺門に達して、仰ぎ見ると、浄閑寺と云ふ寺である事を知る」
もちろん、現在はその小流はない。周囲は人家が密集し、寺の敷地だけが大谷石の石塀に守られ、かろうじて緑に包まれている。ただ古びた寺門は荷風が訪れた時のまま今も健在である。
「門を這入ると、例の花売る小屋がある。余り広からぬ本堂の左手から、其の裏手へ掛けて、此処が墓地、石塔や、卒塔婆が累々として並んで居る。叢の様になって居る垣の近く、又は石塔の間の其処此処には、かなりに年経た、瘤多き榎木が、幾株も立ち茂って、ふる風の来る度に物悲しい声をして、其の枝を顫はして居る。先、見当たり次第の石碑の前に屈んで、すでに能くは見分からぬ、其の彫付けた文字を見ると、柳生院花容童女之墓と云ふ様な仏名が読まれる、又は、□□楼代々の墓とか、或は男と女の名が二ツ並べて彫ってあるのも身当てられる。然し、何の石塔も二尺、三尺と計る程、高いものは無い、何れも、小さな汚いものばかりで、久しく香花を手向けられた事もないと思はれる。・・・何たる、淋しい、物恐ろしい有様なるよ。来る人は忽ち陰惨の気に打たれて、已に冷たい穴の中には這入った様な心持がする。昨日まで、緑の黒髪を黄金に飾り、雪なす肌を錦の襠裲にまとはせた、花とも蝶とも見るべき遊女の骨は、実に、此の陰気な淋しい処に横たはって居るのであった。見よ。二本ほど、大きな榎木を後にして、此処に、巍然と高く石垣を築き上げた、その上に、一個の石柱がある。新吉原無縁墓此の六字が彫り付けられてあるばかり。其の周囲には幾何の雑草の生へて居るのも見た。安政大地震の時に大供養をした太い卒塔婆が猶、腐れずに立って居るのも見た」
荷風が訪れた当時は、寺は大改修の直前であったらしい。そのためもあって、荷風も記しているように、寺の荒廃がかなり進んでいたことがうかがえる。
また、その頃はまだ土葬であったために、墓地内は凸凹が激しく、それが一層陰惨の風を高めていたともいえる。
そして、その墓群の中に、ひときわ高くそそり立つ遊女たちの無縁墓があった。現在は新吉原總霊塔という文字が刻まれているが、これは昭和四年に改修されたものだ。
石塔は、蓮の形をした台座の上に乗り、それを支えるように昔のままに石垣が築かれている。
その石垣には「生まれては苦界 死しては浄閑寺」の花又花酔の句が刻まれている。
石垣の横に小さな窓のついた扉があった。その窓から墓の内部を覗くと、氷室のような墓室に骨壷が累々と並べられている。
思わず見てはならないものを見てしまった思いと同時に、卒然と哀れさが胸に迫ってきたのである。
荷風はそれから四十年後、再びここを訪れている。その頃吉原を題材にした小説を書こうとしていたからである。
「掛茶屋の老婆に浄閑寺の所在を問ひ鉄道線路下の道路に出るに、大谷石の塀を囲らしたる寺即これなり。門を見るに庇の下雨風に洗はれざるあたりに朱塗の色の残りたるに、三十余年むかしの記憶は忽ち呼返されたり。土手を下り小流に沿ひて歩みしむかしこの寺の門は赤く塗られたるなり。・・・今日の朝三十年ぶりにて浄閑寺を訪ひし時ほど心嬉しき事はなかりき。近隣のさまは変りたれど寺の門と堂宇との震災に焼けざりしはかさねがさね嬉しきかぎりなり。余死するの時、後人もし余が墓など建てむと思はば、この浄閑寺の塋域娼妓の墓乱れ倒れたる間を選びて一片の石を建てよ。石の高さ五尺を超ゆべからず、名は荷風散人墓の五字を以て足れりとすべし」(『断腸亭日乗』昭和12/6/12日より)
荷風も記しているように、本堂と庫裡は震災にも遭わず、その後の戦災にも無事で、ついこの間まで寛保二年(1742)以来の建物(本堂は昭和五十九年に残念ながら一部焼失する)の姿かたちを保っていた。
が、それもさすがの老朽化には勝てなかったと見え、現在は取り壊され、新しいコンクリート造りの堂宇が建てられている。
* * *
ところで、『断腸亭日乗』に著し、そう願った荷風の墓は、結局この浄閑寺には建てられなかった(墓は雑司ケ谷の永井家代々の墓地にある)。代わりに、浄閑寺の娼妓たちの霊を祀った総霊塔の前に、荷風散人の文学碑が立っている。
その碑面には、「今の世のわかき人々われにな問ひそ今の世と、また来る時代の芸術を」で始まる『偏奇館吟草』の一部「震災」から抜粋した詩文が刻まれている。
そして、その碑の左隅に、赤御影石でできた荷風の筆塚がひっそりとそえられている。それは荷風氏のせめてもの願いにそった事蹟であるかも知れない。










名づけなれたようです。