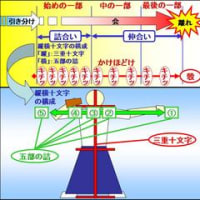平成18年9月3日(日)、宇都宮市弓道場で行われた市弓道連盟の定例射会に参加してきました。これはほぼ毎月1回行われているのですが、自分は仕事の都合などでなかなか参加できず、1月の初射会以来の参加ということになりました。
この日は自分が所属している宇都宮中央支部が当番の担当だったのですが、商品の準備などは既に支部長と何人かの方が済ませて下さっていたため、自分は特に何もせずに済んでしまいました。なので当日は早めに会場に入って準備をしようかと思い、8:30に到着するように家を出たのですが、到着した頃にはシャッターなども開けられており、結局安土の幕張りくらいしか作業はしませんでした。。。
開会式では昇段者の紹介と言うことで、前週の審査で四段に合格したため挨拶をする機会を頂きました。最近はたまに離れが出なくなってしまうようなこともあり、四段だと胸を張って言えるような弓は引けていなかったのですが、「四段を頂きました」と挨拶をしてしまった以上、とりあえず恥ずかしくない程度には一生懸命引こうと思いました。
定例射会は坐射一手、四つ矢の立射が4回の計18射の成績を付けます。矢振りによって立ち位置を決め、立ち順から3人毎にチームになって団体の順位も競います。ただしこの日は県民スポーツ大会前最後の定例射会であったため、宇都宮代表の選手は同じ立ちに集めることになりました。自分は市民体育祭への参加の件でとりまとめをして頂いている方とお話をしていたため、矢振りの矢を渡すことができずに一番最後の立ち順になりました。この日の参加者が34人、1チーム3人だと割り切れないことから、坐者は4人1立ち、立射は2人づつに別れてのチームと言うことになり、自分の前が中央支部の支部長であったためこの方と2人チームになりました。
この日の行射については、この週に購入した弓道関連の書籍「霊箭~阿波研造物語」「弓の道 正法流入門―武道としての弓道技術教本」に書いてあったことがずっと頭にありました。技術的な注意点というよりは弓界の英雄譚のイメージが頭にあって「よ~しやるぜ~!!!」みたいなかんじでした。ただ前日に土曜日講習を受けており、ここでご指導を頂いていた「大三では握り込まず、目通りを過ぎた辺りから徐々に角見を効かせていく」ということは意識をするようにしました。
初めの坐射では甲矢はなんとか7時頃に的中しましたが、乙矢は3時頃に大きく抜けました。この乙矢の時は引き分けの途中で弓手手の内の拇指が中指と離れてしまい、まったく角見を効かせることができませんでした。
この反省点を踏まえ、次の立射に臨みました。意識をしたのはあくまで弓手先行で角見を効かせることでした。この立ちだけは順番の関係で自分の後にも一人入ったのですが、大前の方が1本目、2本目、3本目まで的中されたのと、落の方も1本目、2本目を的中されて流れに乗ることができました。結果久しぶりに自分も四射皆中することができました。練習ではたまには皆中することもありましたが、記録を付けての四射皆中となると昨年11月の秀郷大会以来でしたので、やはり嬉しかったですね。
しかしこれでかなり的中の意識が強くなりました。そうでなくとも元々中て気にとらわれがちなのですが、ここで皆中したことで通常以上に意識が強まったこと、またこの日は四段合格と言うことで挨拶したこともあって実力以上によく見せようとする射り気も普段以上に大きかったような気がします。このようなこともあり、その後の四つ矢3立ちは力んでしまってまともに離れが出なくなってしまい、それぞれ1中しかできませんでした。結果この日は18射8中で、終わってみれば5割も的中できませんでした。(|○×|○○○○|×××○|×○××|×○××|8)
以前も書いたことがありますが、弓道はメンタル面に大きく左右されるスポーツだと思います。いかに自分自身をコントロールできるかに関わっています。自分は基本的に力みがちで、ちょっと良かったり悪かったりするとすぐに力んでしまう部分がありますので、良かったり悪かったりということを自分で感じたときにどれだけ力まずに力を抜けるかということが課題になるなと改めて痛感しました。
この日は自分が所属している宇都宮中央支部が当番の担当だったのですが、商品の準備などは既に支部長と何人かの方が済ませて下さっていたため、自分は特に何もせずに済んでしまいました。なので当日は早めに会場に入って準備をしようかと思い、8:30に到着するように家を出たのですが、到着した頃にはシャッターなども開けられており、結局安土の幕張りくらいしか作業はしませんでした。。。
開会式では昇段者の紹介と言うことで、前週の審査で四段に合格したため挨拶をする機会を頂きました。最近はたまに離れが出なくなってしまうようなこともあり、四段だと胸を張って言えるような弓は引けていなかったのですが、「四段を頂きました」と挨拶をしてしまった以上、とりあえず恥ずかしくない程度には一生懸命引こうと思いました。
定例射会は坐射一手、四つ矢の立射が4回の計18射の成績を付けます。矢振りによって立ち位置を決め、立ち順から3人毎にチームになって団体の順位も競います。ただしこの日は県民スポーツ大会前最後の定例射会であったため、宇都宮代表の選手は同じ立ちに集めることになりました。自分は市民体育祭への参加の件でとりまとめをして頂いている方とお話をしていたため、矢振りの矢を渡すことができずに一番最後の立ち順になりました。この日の参加者が34人、1チーム3人だと割り切れないことから、坐者は4人1立ち、立射は2人づつに別れてのチームと言うことになり、自分の前が中央支部の支部長であったためこの方と2人チームになりました。
この日の行射については、この週に購入した弓道関連の書籍「霊箭~阿波研造物語」「弓の道 正法流入門―武道としての弓道技術教本」に書いてあったことがずっと頭にありました。技術的な注意点というよりは弓界の英雄譚のイメージが頭にあって「よ~しやるぜ~!!!」みたいなかんじでした。ただ前日に土曜日講習を受けており、ここでご指導を頂いていた「大三では握り込まず、目通りを過ぎた辺りから徐々に角見を効かせていく」ということは意識をするようにしました。
初めの坐射では甲矢はなんとか7時頃に的中しましたが、乙矢は3時頃に大きく抜けました。この乙矢の時は引き分けの途中で弓手手の内の拇指が中指と離れてしまい、まったく角見を効かせることができませんでした。
この反省点を踏まえ、次の立射に臨みました。意識をしたのはあくまで弓手先行で角見を効かせることでした。この立ちだけは順番の関係で自分の後にも一人入ったのですが、大前の方が1本目、2本目、3本目まで的中されたのと、落の方も1本目、2本目を的中されて流れに乗ることができました。結果久しぶりに自分も四射皆中することができました。練習ではたまには皆中することもありましたが、記録を付けての四射皆中となると昨年11月の秀郷大会以来でしたので、やはり嬉しかったですね。
しかしこれでかなり的中の意識が強くなりました。そうでなくとも元々中て気にとらわれがちなのですが、ここで皆中したことで通常以上に意識が強まったこと、またこの日は四段合格と言うことで挨拶したこともあって実力以上によく見せようとする射り気も普段以上に大きかったような気がします。このようなこともあり、その後の四つ矢3立ちは力んでしまってまともに離れが出なくなってしまい、それぞれ1中しかできませんでした。結果この日は18射8中で、終わってみれば5割も的中できませんでした。(|○×|○○○○|×××○|×○××|×○××|8)
以前も書いたことがありますが、弓道はメンタル面に大きく左右されるスポーツだと思います。いかに自分自身をコントロールできるかに関わっています。自分は基本的に力みがちで、ちょっと良かったり悪かったりするとすぐに力んでしまう部分がありますので、良かったり悪かったりということを自分で感じたときにどれだけ力まずに力を抜けるかということが課題になるなと改めて痛感しました。