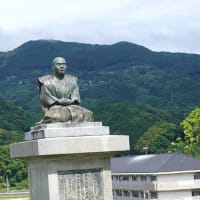「昭和6年5月、われはじめて土佐の国に遊びぬ。海は荒かりしかども空あかるく、風光の美そぞろにわが心を惹くものありき。かへりてのち興のおもむくままに土佐百首をつくりしが、ここにはその半ばを選びつ」(「人間経」)
その土佐百首だが、室戸岬の歌だけで10首を越える。
他の歌集や、後年室戸岬を懐かしくふり返って詠んだ歌を合わせると実に40首を越える。
そんな勇にとっても特別の地、室戸岬を旅した。
歌に詠まれた情景を我が目で見たかったのだ。
はるばると室戸岬にわれは来ていきどほろしく荒海を見つ
(以下、文中の青色文字は吉井勇の短歌)
激しく波が打ちつける「荒海」を期待していたのだが、この日の海は穏やかだった。

とどろとどろ潮高鳴れどうら安し室戸岬はまこと浄土か
ここが浄土と言われればそんな気もしないでもなかった。

波の浸食を受けた岩はユニークで、その様を勇は「印相」に例えた。
岩も木もことごとく印を結びぬ空海いまも世にいますごと
さて、この室戸岬の海岸には空海伝説にまつわるものが多く残っている。
灌頂が浜



たたなはる岩の間をゆくほどに灌頂が浜に出でにけるかも
ここで目にしたお遍路さんの姿はいつまでも勇の記憶にのこっていたようだ。
吉井勇最後の歌集「形影抄」(昭和31年出版)の中に
灌頂が濱邊に会ひし年おいし遍路の顔やいまもうかび来
目洗いの池

行水の池


いまもなほ大師修法のすがた見ゆ行水の池目洗ひの池
空海修行の地

若き日の空海が修行をした洞窟

今は落石防止のための屋根が入り口に設置されている。
(雰囲気が損なわれるが仕方ない)

説明板

左の洞窟(御厨人窟) 生活のための洞窟

右の洞窟(神明窟) 修行のための洞窟

空海の窟(いわや)かしこし沖辺より吹き来る風もここに来て凪ぐ
空海が修法の洞の窟守古蝙蝠にものな問ひそね
海岸沿いの道

いろいろな植物


亜熱帯の植物 リュウゼツラン

アコウの木

荒海のあら潮風のなかに生ふる室戸榕樹(あこう)はいとほしきかも
どでかいアコウの木


岩を掴んでいる根もでかい

水掛地蔵

潮曇る室戸の浜に夕さむく水掛地蔵立ちてまします

毘沙姑巖(びしゃごいわ)

絶え間なく海とたたかふ若行者の毘沙姑巖はたふとかりけり
毘沙姑巖のほとりまで来て足悩める遍路の老をあはれみにけり
龍宮巖



室戸なる龍宮巌のうへに立ちて旅びとわれはものをこそ思へ
烏帽子巌

天狗巌

海岸の流木

室戸岬の海岸で勇たちは流木を燃やし、焼いたトコブシを肴に酒盛りをしている。
そのときの情景を詠んだ4首
流れ木を掻き集めては燃やすなり室戸の浜に酒を煮るべく
ゆふぐれの室戸の浜の流れ木をあつめて燃せば焚火かなしも
室戸岬の景色うれしみ酒酌むと浜の焚火に流れ鮑(こ)を焼く
注:「流れ鮑」は高知の方言で「トコブシ」のこと。
流れ鮑を焼きて浜辺に酒酌めばわが世小さきことは思はず
私も若い頃、屋久島の海岸で似たようなことをした。
トコブシ(他にウニやカメノテ)

海岸での焚き火と酒盛り

(1980年 春 屋久島にて)
勇の海岸での酒盛りの歌を目にしたとき、自分自身の遠い昔のことが思い出された。
若い頃だったらこの海岸で野宿をしたかも知れない。
そしたら勇が詠んだ日の出の光景にも出合えたかも知れない。
大土佐の室戸岬に見し日の出いまもおもほゆ胸も鳴るがに
わがこころあらたにすべく土佐に来てのぼる日を見る