この文章は阿修羅と言う掲示板に昨日(11月8日)投稿したものです。手直しして再度ブログの書き込みます。本文の方もよろしかったら開いて流れを汲み取ってください。
http://www.asyura2.com/08/dispute28/msg/452.html
投稿者 縄文ビト 日時 2008 年 11 月 08 日 21:30:15: egUyw5BLxswRI
(回答先: 操作される金相場 投稿者 あ+ 日時 2008 年 11 月 08 日 12:11:15)
あ+さん読ませていただきました。
ただ私なりに疑問がありますので書かさせてもらいます。。
>総量3万トンの金地金のうち、半分以上が貸し出しされた状態になっている。
>金融分析者の中には、何らかの引き金によって金相場が上昇し始めると、すぐに相場は2倍に(今の750ドルから1500ドルへ)はね上がると予測する人もいる。
縄文ビト=米国には3万トンの金地金があるということ。これが現在の750ドルから1500ドルになったとしたら金地金で裏打ちされたドルは強くなるのではないでしょうか。
ここからウィキペディアより引用。
ブレトン・ウッズ体制という。 この協定は1929年の世界大恐慌により、1930年代に各国がブロック経済圏をつくって世界大戦をまねいた反省によっているだけでなく、第二次世界大戦で疲弊・混乱した世界経済を安定化させる目的があった。そのため具体的には、国際的協力による通貨価値の安定、貿易振興、開発途上国の開発を行い、自由で多角的な世界貿易体制をつくるため為替相場の安定が計られた。
そのため、金1オンスを35USドルとさだめ、そのドルに対し各国通貨の交換比率をさだめた。(金本位制)
1971年にニクソン・ショックによりアメリカはドルと金の交換を停止した。
引用終わり
J=ブレトン・ウッズ体制で金1オンス35ドルでドルとの交換をしていた1930年代から考えると、現在の金価格はすざましい暴騰といえます。この時期以後アメリカはドル札を刷りまくり金を蓄蔵していたとしたら、まさに通貨発行益を得ていたということになります。
私も前にIMFが金を売りに出すという新聞記事から金が暴落するという書き込みを入れ、売り時だということを書きましたが、それは少しずつ放出するということです。一気に大量の金を放出すれば完全なる暴落になりますが少しずつなら値下がりになりますが暴落にはつながりません。
逆に考えればIMFが銀行救済に金(キン)を使っているのではないでしょうか。IMFという公的機関が直接市場でキンを売ることができないため銀行に金利をつけて貸していると言う形をとっていると考えられます。
またドルとユーロの刷りすぎ(いったん刷った貨幣は減ることはない)は解消されていませんから投資家の手元に現金として残っています。投機の対象になる物が現れればそれが穀物であれ原油であれ利潤を求めて動き出します。
現在の段階ではドルに替わる貿易決済に使われる通貨がないことから、ドルの暴落はありえないとみています。ただ世界的な金余り(偏った所持)からこれからも頻繁にミニバブルが発生するのではないでしょうか。現在の株式相場がそのいい例かと考えます。景気後退局面でも株が下がれば買いを入れていく。そして上がった段階で売り抜けていく。刷った貨幣は減ることはないことから 素人投資家が騙され玄人が儲けていく場面だと考えています。そしてより偏った貨幣所持がこれからの状況になっていくと考えます。
最終的にはあまりにも偏った貨幣所持は、人が生きていくために必要な食物を得るために百姓一揆的な暴動に繋がっていくことになります。それも世界的な規模といえます。
現在の段階で、世界が不況を克服するために市中にカネを投入しても偏った所持に繋がっていくだけで、労働の価値が上がらない(失業が増える)ため資源インフレがあっても本来のインフレにはならないし、むしろ消費が進まないことから世界的なデフレになっていくといえます。それは新しい形のスタグフレーション、不況の中の物価高なのかもしれません。
ここから私のホームページより移します。
『 無心論者』
私は以前キリスト教に興味を持ったことがある。だがひとつの疑問を持った現在全ての宗教から遠ざかってしまった。それは人間は死後魂となって存在できるのかという疑問だった。
魂―それは現在生きている人間の肉体の内部にあり、死後肉体から離れ永遠の生命を得るというものである。私が思考する範囲内においてだが、唯一いえることは、私の魂というものが死後の世界においても私というものでなければならないという条件がいる。
私が私に、私とは何かと問いかけたとき、私とは1メートル60数センチの身長を保持する肉体ではなく、私が存在するという思念そのものであるといえる。
例えば科学がいつの時代かに人間の脳だけを生かしておける時代が来たとする。その脳はガラスの容器の中で機械的な神経を通し肉体として生きていけるときと同じように、見、聞き、話すことができるとする。そのとき必要としなくなった彼の肉体が焼かれて一片の灰になったとしても、彼の脳がなおも思考し続けるとき彼は彼自身存在しているということを自覚できるはずだ。たとえ彼の目の前で、つまり機械的な視聴覚を通し自己の肉体が葬儀の名において知人等の別れの涙を受けながら焼かれていく自己の姿を見たとしてでもあるが、彼は自分が死んだという自覚はさらさら無いはずである。
そのことから私というものが緻密な脳細胞の結合体より生じる思考を束ねている基礎にあるものであり、現在私が思考するのは口から食物を摂り栄養を脳に与えることができるからでしかない。だが死後エネルギー源を持たない魂なるものがどうして思考できるかというのが問題だ。しかもそれが永遠であるというおまけまでついている。永遠とは地球が滅び、太陽もすべての星もこの宇宙から消え、幾多のゼロを何世紀という下につけてもまだそれは永遠ではない。
他にもあるが、そんなこんなで私は魂なるものは無いと私なりの断定を下し、魂が無ければ宗教等も必要で無いという結論にまで至ってしまった。
そして私は人間は物として考えたほうが、人生は死に対する諦めという気持ちは残るが解りやすいような気がする。
私の生きている時代はつくづく不思議な時代だと考える、生者と死者との別れということであれば解るが、ありもしない魂なるものを祀るために良い戒名を得るために葬式に多額の金をかけ、宗教という名の下に我が身の自由を差し出していく、後世の人達が二十世紀という時代を歴史という書を通して考えたとき、おかしな時代だったんだなという気がする。
あたかもチョンマゲを付け刀を差し侍という名の下に平民とは違うのだという、時代が僅か前にあったときと同じように。
1964年5月
『幽霊について』
最近ある本で幽霊に関しての記事を読んだ。私自身はその存在を信じていないながらも関心があるので書いてみたい。
幽霊とは哲学的には形而上学に属するもので(広辞苑によれば、絶対存在を純粋思惟によりあるいは直感によって探求しようとする学問。神、霊魂、などがその主要問題となっている)
つまり人間に魂(霊魂)なるものがあり、死後この世に未練を残し迷っている者ということができる。生物の中で高等に進化した人間が、有る時宇宙的な感覚の中で生命体としての自己の存在の不思議を感じ、時間の流れの無限性(時計は時間を測る器具として人間が作ったものであり、時間には始まりも終わりも無い、時間は物質の変化を通して初めて理解できるものである)つまり永遠の時間の中での有限性に絶望し(人間には六十年ほどの寿命しかなく、死によって打ち切られてしまうことに耐えられない)救いを生命体の不可思議の中で捉えた神的な存在(万物を創造し、地上に生命を宿したものがあると考え、その者に結び付けることによって有限であるという絶望感から、死後の時間的無限、永遠の世界において魂となって存在するという逃げ道を考え出したのであるといえる。その宗教的な考察の中では、この世は(無)に近く、ただ永遠の世界であるところの死後に目的を置き、時間的無限に対する有限であるところのつかの間の人生などは問題でなくなってしまうという考え方に導かれていく。その考え方により(戦時中若者が特攻機で死んでいった)人生を短く終わらされてしまったなら、言う本人があの世を知っているわけが無いのに、もしあの世が無いなら最高の詐欺にかかったことになる、また詐欺云々というようなものではない、なぜならただ一度の人生を短くされてしまうからだ。
もし幽霊(迷っている霊魂)なるものが科学的に実在を証明されたとしたならばどうであろうか。
過去の歴史の中で哲学者、宗教家、科学者などが果たした役割がいかに大きかったかを考えると以後の歴史は大きく変わっていくだろう。そこでは宗教的倫理という枠の中で人間は現世的なものを拒否され、宗教的規格にあったものとして造られていく。いくら分別があるからどうのといったとしても、そのようなものは馬の耳に念仏のたぐいであり、階級性がどうのといったとしても、すべて無に近いことだ。ただひたすら死後の世界であるところの永遠の世界での幸福を願えばいいのである。
だが幸か不幸か(不幸とは有限であるということに絶望しても救いは無い)科学が神秘的なベールを剥がしていき、ここで言う科学とは生物学としての進化論であり、考古学を入れた歴史学というものであり、人間をこの世だけのものとして固定していく、現代の政教分離という考え方はここからきている。現代の社会にキリストや釈迦を生まれ変わらせたと仮定しても、世間が釈迦を釈迦としないだろうし、イエス・キリストはキリストとはなりえないだろう。
そして中途半端な悟りは別として、ベルグソン(フランスの哲学者)の言葉を借りれば
「より深きものはより多くのものを引き出してくる(哲学的直感より)という言葉もあるように科学の前に何等の疑惑も抱かずにイコール『死後』という回答を持ってくることの不可能を悟るだろうからだ。
そして科学の発達した現代の悟りとは、微生物からの成り上がりものであるところの己を悟ることだろう。
幽霊とは見たという人の妄想である。
1964年12月
『先取り』
今夜も眠れなかった。時計の音が闇の中で浮かび上がってくる。今日で五日、病の床に伏せている自分を思い返させた。「もしや熱が下がらないのも…」眠りを諦めた意識かが過去の記憶を再現させ、現在の病につながるものとして宗教的な事柄を浮かび上がらせてきた。
数年前までの私は宗教とは関係ないながらも聖書を読み、また宗教的な事柄に関しては厳粛な気持ちの中でそれ等を迎い入れた。だがある意識がそのような自分を破壊したときから私の生活は大きく変わった。
「 そんなものが宗教の持つ本当の意味ではないですよ」
私は家主の奥さんが話すことに次元の違う世界を感じ、どのように話していいのかを考えていた。
「でも貴方は信じないかもしれないけど、知っている人にこういう人がいたわ」
「いいえ多分どんな宗教にせよ万物、いや人間を存在させたもの、それが何かということではないですか、そこに神や仏を置いたとき私や奥さんを存在させた者として宗教は成り立ちますけど、そのことが自然の力であるという自然界をおいたとき宗教は成り立たなくなります」
私の話からは彼女はイメージをこしらえることができないようだった。だが私は、私の話すことが理解されなかったとしても、偽りを言っているのではないということのために、私自身に意識を注げばいいのだ。
現在という時間の中に私はいる。見渡せる視界の届く範囲から脳裏に浮かび上がってくる広大な宇宙の中に、現在存在しているのが私なのだ。その私を誰が存在させたのか、弁証法という螺旋を昇り生命の起源まで辿り着く、そして今いるという自分を…、私は神や仏をとらなかっただけだった。
話のやりとりの中で家主の奥さんはそんな私に業を煮やしたのか<けなしたりすると罰が当るから>と最終的な宣告を下してきた。
「いいですよ、僕は変わっているから罰が当ることを喜びますね、単なる短い存在として自分を考えるよりも、死後、地獄でもいいから永遠が保障されていると考える方が僕には救いになりますから。どうぞ、今ここで死という罰が下されることを僕のために祈ってください。存在しないことの永遠の無を考えるよりも、存在していることの永遠の有を考えることの方が人間には幸せではないですか。ただありもしないものを信じるなどということはやりたくないだけです。
私は自分の行きついた概念には少なくとも統一があるものと考えていた。だが一旦口から出た言葉は意識の底に残り、ふとした切っ掛けがもとで大きく広がってくるのだ。私はいま病気であった。それが過去の捨て鉢的な意識から来た不摂生が原因であることも分かっていたが、五日も床から離れることができないでいると、無意識からの統一で無い限り類似した過去の出来事を伴い私を悶々とさせるのだった。「人間は偉大なる自然界の力で地球上に存在するようになった一つの生物でしかない、科学の発達していなかった時代ならともかく、万物の創造を神仏に結び付け、しかも数千年経った現在でもまだ依然として続けている。これほどの詐欺行為がかつて人間の歴史の中にあっただろうか、あの世が無かったなら、あの世が在るということで貴重な人生を短く終わらされてしまった人達への責任、誰が取るというのだ、大きな詐欺行為だ」
私は弱気になる意識を追いやるために自己を正当化するため欺瞞だと意識しながらも心の中で叫んでいた。
時計がとうに午前四時を回っている、眠らなくてはならない、だが心の中の不安は消え去っていなかった。< <多分眠りに入れば私は夢を見るだろう>ただどのような形で意識化のものが夢に現れるかに興味があった、やがてそのような考えに行き着いたとき心が落ち着いてきた。静かに寄せてくる眠りの中で私は見るであろう夢のことを考えていた。
家に向う暗い道を歩いていた、辺りには武蔵野の丈高い木々が黒い輪郭を空に描いている。だがいつも通いなれ見慣れたはずの道だったが、私の心の中にあった道とはなぜか違った感じとして受け取れた。野菜畑のはずだった土地が黒い地肌を見せ遠くまで伸び、視界を遮るものも無かった平面が古びた一軒の家で終止符をうっている。好奇心と恐怖心の混ざり合った気持ちで惹かれるように近づいていった家の中から、囁きに似た声が耳に入ってくる。それがだんだんと大きくなり読経の声だとはっきりと聞き取れたとき、私の身体は重く、それ自体威厳があり逆らいを許さない声に抑えつけられてしまった。だが時が経つうちに冷静さが別の意識を浮き上がらせてきた。
「無い、在るわけが無い、人間が最高の存在なのだ」
私は自分の声に驚き夢からさめてしまった。
1966年6月
『恐山』
東北へ来てから三日目、無計画なたびの中にも恐山(青森県下北半島)に行くということは最初からの計画だった。
バスが狭い山道を登りきると左手に宇曽利湖、さざ波が金色に光をはね返し夕暮れの中に落ちていく。山門を入り宿坊に急ぐ道、薄暮の中での異様な光景に目を奪われる、それは現実とかけ離れた光景だった。
「君らは泊まるつもりだろう、早く来ないから部屋はもう無いよ」
宿坊の案内に立つ僧が見とれている私たちに近寄ってくるなり声をかけてきた。
「そんなことを言わずどんな所でも…」
「三人か、何とかしよう」
僧はからかいであったかのか笑いながらあっさりと引き受けてくれた。私たち二人に旅の途中知り合った医大生と同宿することになった。遅く来たせいか冷えかかった食事をがらんとした食事部屋で早々に済ませると、疲れを癒すために風呂に入りに行った。
硫黄の香が強い湯船は男女混浴であったが、目的とするものが宗教的なせいか老人が多く、たまに観光を目的とした若い人達が混じっている。湯から上がり裸電球が薄い影を作る部屋でほてった体を冷やしていたが寝るにはまだ早く外に出てみることにした。
星が空一面手に取れるようにここ東北の澄んだ空気の空で瞬いている。その下にある恐山という世界、夜陰の中に建物と灯篭が気味悪く浮かび上がっていた。
「写真を撮ってくれる」
一段高い所にある塔婆の林立した場所に上がり、塔婆を背景にして立った。ストロボが一瞬光を撒き散らす。写している方が気味悪くなるのか代わりにといったが友は応じてくれなかった。
翌朝食事前に起きるとカメラを片手にさして広くない地内を見て回った。無限地獄、賭博地獄、血の池地獄、賽の河原、薄黒く岩肌を見せ所々口を開けた穴から硫黄の湯気を噴出している金堀地獄。地獄の連続だった。
この山の祭典(7月21日~24日)が済んでまだ日も経ってなかったのか、供養の石が高く積み重ねてあったり、子供の喜びそうな飴や素朴な生活を思わせる袋がしの類が雨と日差しの中で白くなり穴の縁を取り巻いている。歩くうちにいつか宇曾利湖の水辺に出た、白い砂を敷き緩い傾斜を湖に走らせている岸辺、立て札に極楽浜と書かれてある。その周りを取り囲むように石で縁取りをし、空に向かった供養の文字が小石で並び書かれてあった。
<弘ちゃんー母より>見ているうちに母親の姿が瞼に浮かんできた、生きている者にとっての死、それはなおも生かそうとする思いが魂になって存在しているのだという架空を創り出した、そのことをしないと人間という生物は生きていけないのかもしれない。だが身体を走る虚無感、足でかき回してやりたい、それは他人に対する死ではなかった。いつか自分も死ぬ、それは早いか遅いかだけであり確実に自分も死ぬ。永遠という時間の中で「生」とはなんと短いことか。
いつか回りきっていた。朝の勤行にも参加した、朝食も済ませ写真も充分に写した、後はバスを待つまでの時間をつぶせばいいのだった。支払いを済ませるために寺務所に入って行った。支払いが終わった後、住職らしき僧がいろいろな話をしてきた、その中で宗教的な話が出た、たぶん昨夜塔婆を背景に写真を撮っているとき訝るように懐中電灯の光を向けてきたのはこのお坊さんだったのだろう話の途中で思い当たった。
「今の若い人達は宗教を嫌うけど教えは必要だよ」
私に宗教心?
「けれど教えは二義的なものではないですか、まず人間存在をどのように見るかが大事だと思いますけど、そして如何に生きるか…」
私ははじめ黙って話を聞いていたが、話の腰を折るようにいつか返答をしていた。私は全て唯物として見ている、そこに絶望があったとしても真理なら選ばねばならない。住職らしき僧は私が話しているだけで何も言わなくなってしまった。まだ時間はあったがお礼を言い立ち上がると、バスの乗り場まで歩き出した。
1966年8月
http://www.asyura2.com/08/dispute28/msg/452.html
投稿者 縄文ビト 日時 2008 年 11 月 08 日 21:30:15: egUyw5BLxswRI
(回答先: 操作される金相場 投稿者 あ+ 日時 2008 年 11 月 08 日 12:11:15)
あ+さん読ませていただきました。
ただ私なりに疑問がありますので書かさせてもらいます。。
>総量3万トンの金地金のうち、半分以上が貸し出しされた状態になっている。
>金融分析者の中には、何らかの引き金によって金相場が上昇し始めると、すぐに相場は2倍に(今の750ドルから1500ドルへ)はね上がると予測する人もいる。
縄文ビト=米国には3万トンの金地金があるということ。これが現在の750ドルから1500ドルになったとしたら金地金で裏打ちされたドルは強くなるのではないでしょうか。
ここからウィキペディアより引用。
ブレトン・ウッズ体制という。 この協定は1929年の世界大恐慌により、1930年代に各国がブロック経済圏をつくって世界大戦をまねいた反省によっているだけでなく、第二次世界大戦で疲弊・混乱した世界経済を安定化させる目的があった。そのため具体的には、国際的協力による通貨価値の安定、貿易振興、開発途上国の開発を行い、自由で多角的な世界貿易体制をつくるため為替相場の安定が計られた。
そのため、金1オンスを35USドルとさだめ、そのドルに対し各国通貨の交換比率をさだめた。(金本位制)
1971年にニクソン・ショックによりアメリカはドルと金の交換を停止した。
引用終わり
J=ブレトン・ウッズ体制で金1オンス35ドルでドルとの交換をしていた1930年代から考えると、現在の金価格はすざましい暴騰といえます。この時期以後アメリカはドル札を刷りまくり金を蓄蔵していたとしたら、まさに通貨発行益を得ていたということになります。
私も前にIMFが金を売りに出すという新聞記事から金が暴落するという書き込みを入れ、売り時だということを書きましたが、それは少しずつ放出するということです。一気に大量の金を放出すれば完全なる暴落になりますが少しずつなら値下がりになりますが暴落にはつながりません。
逆に考えればIMFが銀行救済に金(キン)を使っているのではないでしょうか。IMFという公的機関が直接市場でキンを売ることができないため銀行に金利をつけて貸していると言う形をとっていると考えられます。
またドルとユーロの刷りすぎ(いったん刷った貨幣は減ることはない)は解消されていませんから投資家の手元に現金として残っています。投機の対象になる物が現れればそれが穀物であれ原油であれ利潤を求めて動き出します。
現在の段階ではドルに替わる貿易決済に使われる通貨がないことから、ドルの暴落はありえないとみています。ただ世界的な金余り(偏った所持)からこれからも頻繁にミニバブルが発生するのではないでしょうか。現在の株式相場がそのいい例かと考えます。景気後退局面でも株が下がれば買いを入れていく。そして上がった段階で売り抜けていく。刷った貨幣は減ることはないことから 素人投資家が騙され玄人が儲けていく場面だと考えています。そしてより偏った貨幣所持がこれからの状況になっていくと考えます。
最終的にはあまりにも偏った貨幣所持は、人が生きていくために必要な食物を得るために百姓一揆的な暴動に繋がっていくことになります。それも世界的な規模といえます。
現在の段階で、世界が不況を克服するために市中にカネを投入しても偏った所持に繋がっていくだけで、労働の価値が上がらない(失業が増える)ため資源インフレがあっても本来のインフレにはならないし、むしろ消費が進まないことから世界的なデフレになっていくといえます。それは新しい形のスタグフレーション、不況の中の物価高なのかもしれません。
ここから私のホームページより移します。
『 無心論者』
私は以前キリスト教に興味を持ったことがある。だがひとつの疑問を持った現在全ての宗教から遠ざかってしまった。それは人間は死後魂となって存在できるのかという疑問だった。
魂―それは現在生きている人間の肉体の内部にあり、死後肉体から離れ永遠の生命を得るというものである。私が思考する範囲内においてだが、唯一いえることは、私の魂というものが死後の世界においても私というものでなければならないという条件がいる。
私が私に、私とは何かと問いかけたとき、私とは1メートル60数センチの身長を保持する肉体ではなく、私が存在するという思念そのものであるといえる。
例えば科学がいつの時代かに人間の脳だけを生かしておける時代が来たとする。その脳はガラスの容器の中で機械的な神経を通し肉体として生きていけるときと同じように、見、聞き、話すことができるとする。そのとき必要としなくなった彼の肉体が焼かれて一片の灰になったとしても、彼の脳がなおも思考し続けるとき彼は彼自身存在しているということを自覚できるはずだ。たとえ彼の目の前で、つまり機械的な視聴覚を通し自己の肉体が葬儀の名において知人等の別れの涙を受けながら焼かれていく自己の姿を見たとしてでもあるが、彼は自分が死んだという自覚はさらさら無いはずである。
そのことから私というものが緻密な脳細胞の結合体より生じる思考を束ねている基礎にあるものであり、現在私が思考するのは口から食物を摂り栄養を脳に与えることができるからでしかない。だが死後エネルギー源を持たない魂なるものがどうして思考できるかというのが問題だ。しかもそれが永遠であるというおまけまでついている。永遠とは地球が滅び、太陽もすべての星もこの宇宙から消え、幾多のゼロを何世紀という下につけてもまだそれは永遠ではない。
他にもあるが、そんなこんなで私は魂なるものは無いと私なりの断定を下し、魂が無ければ宗教等も必要で無いという結論にまで至ってしまった。
そして私は人間は物として考えたほうが、人生は死に対する諦めという気持ちは残るが解りやすいような気がする。
私の生きている時代はつくづく不思議な時代だと考える、生者と死者との別れということであれば解るが、ありもしない魂なるものを祀るために良い戒名を得るために葬式に多額の金をかけ、宗教という名の下に我が身の自由を差し出していく、後世の人達が二十世紀という時代を歴史という書を通して考えたとき、おかしな時代だったんだなという気がする。
あたかもチョンマゲを付け刀を差し侍という名の下に平民とは違うのだという、時代が僅か前にあったときと同じように。
1964年5月
『幽霊について』
最近ある本で幽霊に関しての記事を読んだ。私自身はその存在を信じていないながらも関心があるので書いてみたい。
幽霊とは哲学的には形而上学に属するもので(広辞苑によれば、絶対存在を純粋思惟によりあるいは直感によって探求しようとする学問。神、霊魂、などがその主要問題となっている)
つまり人間に魂(霊魂)なるものがあり、死後この世に未練を残し迷っている者ということができる。生物の中で高等に進化した人間が、有る時宇宙的な感覚の中で生命体としての自己の存在の不思議を感じ、時間の流れの無限性(時計は時間を測る器具として人間が作ったものであり、時間には始まりも終わりも無い、時間は物質の変化を通して初めて理解できるものである)つまり永遠の時間の中での有限性に絶望し(人間には六十年ほどの寿命しかなく、死によって打ち切られてしまうことに耐えられない)救いを生命体の不可思議の中で捉えた神的な存在(万物を創造し、地上に生命を宿したものがあると考え、その者に結び付けることによって有限であるという絶望感から、死後の時間的無限、永遠の世界において魂となって存在するという逃げ道を考え出したのであるといえる。その宗教的な考察の中では、この世は(無)に近く、ただ永遠の世界であるところの死後に目的を置き、時間的無限に対する有限であるところのつかの間の人生などは問題でなくなってしまうという考え方に導かれていく。その考え方により(戦時中若者が特攻機で死んでいった)人生を短く終わらされてしまったなら、言う本人があの世を知っているわけが無いのに、もしあの世が無いなら最高の詐欺にかかったことになる、また詐欺云々というようなものではない、なぜならただ一度の人生を短くされてしまうからだ。
もし幽霊(迷っている霊魂)なるものが科学的に実在を証明されたとしたならばどうであろうか。
過去の歴史の中で哲学者、宗教家、科学者などが果たした役割がいかに大きかったかを考えると以後の歴史は大きく変わっていくだろう。そこでは宗教的倫理という枠の中で人間は現世的なものを拒否され、宗教的規格にあったものとして造られていく。いくら分別があるからどうのといったとしても、そのようなものは馬の耳に念仏のたぐいであり、階級性がどうのといったとしても、すべて無に近いことだ。ただひたすら死後の世界であるところの永遠の世界での幸福を願えばいいのである。
だが幸か不幸か(不幸とは有限であるということに絶望しても救いは無い)科学が神秘的なベールを剥がしていき、ここで言う科学とは生物学としての進化論であり、考古学を入れた歴史学というものであり、人間をこの世だけのものとして固定していく、現代の政教分離という考え方はここからきている。現代の社会にキリストや釈迦を生まれ変わらせたと仮定しても、世間が釈迦を釈迦としないだろうし、イエス・キリストはキリストとはなりえないだろう。
そして中途半端な悟りは別として、ベルグソン(フランスの哲学者)の言葉を借りれば
「より深きものはより多くのものを引き出してくる(哲学的直感より)という言葉もあるように科学の前に何等の疑惑も抱かずにイコール『死後』という回答を持ってくることの不可能を悟るだろうからだ。
そして科学の発達した現代の悟りとは、微生物からの成り上がりものであるところの己を悟ることだろう。
幽霊とは見たという人の妄想である。
1964年12月
『先取り』
今夜も眠れなかった。時計の音が闇の中で浮かび上がってくる。今日で五日、病の床に伏せている自分を思い返させた。「もしや熱が下がらないのも…」眠りを諦めた意識かが過去の記憶を再現させ、現在の病につながるものとして宗教的な事柄を浮かび上がらせてきた。
数年前までの私は宗教とは関係ないながらも聖書を読み、また宗教的な事柄に関しては厳粛な気持ちの中でそれ等を迎い入れた。だがある意識がそのような自分を破壊したときから私の生活は大きく変わった。
「 そんなものが宗教の持つ本当の意味ではないですよ」
私は家主の奥さんが話すことに次元の違う世界を感じ、どのように話していいのかを考えていた。
「でも貴方は信じないかもしれないけど、知っている人にこういう人がいたわ」
「いいえ多分どんな宗教にせよ万物、いや人間を存在させたもの、それが何かということではないですか、そこに神や仏を置いたとき私や奥さんを存在させた者として宗教は成り立ちますけど、そのことが自然の力であるという自然界をおいたとき宗教は成り立たなくなります」
私の話からは彼女はイメージをこしらえることができないようだった。だが私は、私の話すことが理解されなかったとしても、偽りを言っているのではないということのために、私自身に意識を注げばいいのだ。
現在という時間の中に私はいる。見渡せる視界の届く範囲から脳裏に浮かび上がってくる広大な宇宙の中に、現在存在しているのが私なのだ。その私を誰が存在させたのか、弁証法という螺旋を昇り生命の起源まで辿り着く、そして今いるという自分を…、私は神や仏をとらなかっただけだった。
話のやりとりの中で家主の奥さんはそんな私に業を煮やしたのか<けなしたりすると罰が当るから>と最終的な宣告を下してきた。
「いいですよ、僕は変わっているから罰が当ることを喜びますね、単なる短い存在として自分を考えるよりも、死後、地獄でもいいから永遠が保障されていると考える方が僕には救いになりますから。どうぞ、今ここで死という罰が下されることを僕のために祈ってください。存在しないことの永遠の無を考えるよりも、存在していることの永遠の有を考えることの方が人間には幸せではないですか。ただありもしないものを信じるなどということはやりたくないだけです。
私は自分の行きついた概念には少なくとも統一があるものと考えていた。だが一旦口から出た言葉は意識の底に残り、ふとした切っ掛けがもとで大きく広がってくるのだ。私はいま病気であった。それが過去の捨て鉢的な意識から来た不摂生が原因であることも分かっていたが、五日も床から離れることができないでいると、無意識からの統一で無い限り類似した過去の出来事を伴い私を悶々とさせるのだった。「人間は偉大なる自然界の力で地球上に存在するようになった一つの生物でしかない、科学の発達していなかった時代ならともかく、万物の創造を神仏に結び付け、しかも数千年経った現在でもまだ依然として続けている。これほどの詐欺行為がかつて人間の歴史の中にあっただろうか、あの世が無かったなら、あの世が在るということで貴重な人生を短く終わらされてしまった人達への責任、誰が取るというのだ、大きな詐欺行為だ」
私は弱気になる意識を追いやるために自己を正当化するため欺瞞だと意識しながらも心の中で叫んでいた。
時計がとうに午前四時を回っている、眠らなくてはならない、だが心の中の不安は消え去っていなかった。< <多分眠りに入れば私は夢を見るだろう>ただどのような形で意識化のものが夢に現れるかに興味があった、やがてそのような考えに行き着いたとき心が落ち着いてきた。静かに寄せてくる眠りの中で私は見るであろう夢のことを考えていた。
家に向う暗い道を歩いていた、辺りには武蔵野の丈高い木々が黒い輪郭を空に描いている。だがいつも通いなれ見慣れたはずの道だったが、私の心の中にあった道とはなぜか違った感じとして受け取れた。野菜畑のはずだった土地が黒い地肌を見せ遠くまで伸び、視界を遮るものも無かった平面が古びた一軒の家で終止符をうっている。好奇心と恐怖心の混ざり合った気持ちで惹かれるように近づいていった家の中から、囁きに似た声が耳に入ってくる。それがだんだんと大きくなり読経の声だとはっきりと聞き取れたとき、私の身体は重く、それ自体威厳があり逆らいを許さない声に抑えつけられてしまった。だが時が経つうちに冷静さが別の意識を浮き上がらせてきた。
「無い、在るわけが無い、人間が最高の存在なのだ」
私は自分の声に驚き夢からさめてしまった。
1966年6月
『恐山』
東北へ来てから三日目、無計画なたびの中にも恐山(青森県下北半島)に行くということは最初からの計画だった。
バスが狭い山道を登りきると左手に宇曽利湖、さざ波が金色に光をはね返し夕暮れの中に落ちていく。山門を入り宿坊に急ぐ道、薄暮の中での異様な光景に目を奪われる、それは現実とかけ離れた光景だった。
「君らは泊まるつもりだろう、早く来ないから部屋はもう無いよ」
宿坊の案内に立つ僧が見とれている私たちに近寄ってくるなり声をかけてきた。
「そんなことを言わずどんな所でも…」
「三人か、何とかしよう」
僧はからかいであったかのか笑いながらあっさりと引き受けてくれた。私たち二人に旅の途中知り合った医大生と同宿することになった。遅く来たせいか冷えかかった食事をがらんとした食事部屋で早々に済ませると、疲れを癒すために風呂に入りに行った。
硫黄の香が強い湯船は男女混浴であったが、目的とするものが宗教的なせいか老人が多く、たまに観光を目的とした若い人達が混じっている。湯から上がり裸電球が薄い影を作る部屋でほてった体を冷やしていたが寝るにはまだ早く外に出てみることにした。
星が空一面手に取れるようにここ東北の澄んだ空気の空で瞬いている。その下にある恐山という世界、夜陰の中に建物と灯篭が気味悪く浮かび上がっていた。
「写真を撮ってくれる」
一段高い所にある塔婆の林立した場所に上がり、塔婆を背景にして立った。ストロボが一瞬光を撒き散らす。写している方が気味悪くなるのか代わりにといったが友は応じてくれなかった。
翌朝食事前に起きるとカメラを片手にさして広くない地内を見て回った。無限地獄、賭博地獄、血の池地獄、賽の河原、薄黒く岩肌を見せ所々口を開けた穴から硫黄の湯気を噴出している金堀地獄。地獄の連続だった。
この山の祭典(7月21日~24日)が済んでまだ日も経ってなかったのか、供養の石が高く積み重ねてあったり、子供の喜びそうな飴や素朴な生活を思わせる袋がしの類が雨と日差しの中で白くなり穴の縁を取り巻いている。歩くうちにいつか宇曾利湖の水辺に出た、白い砂を敷き緩い傾斜を湖に走らせている岸辺、立て札に極楽浜と書かれてある。その周りを取り囲むように石で縁取りをし、空に向かった供養の文字が小石で並び書かれてあった。
<弘ちゃんー母より>見ているうちに母親の姿が瞼に浮かんできた、生きている者にとっての死、それはなおも生かそうとする思いが魂になって存在しているのだという架空を創り出した、そのことをしないと人間という生物は生きていけないのかもしれない。だが身体を走る虚無感、足でかき回してやりたい、それは他人に対する死ではなかった。いつか自分も死ぬ、それは早いか遅いかだけであり確実に自分も死ぬ。永遠という時間の中で「生」とはなんと短いことか。
いつか回りきっていた。朝の勤行にも参加した、朝食も済ませ写真も充分に写した、後はバスを待つまでの時間をつぶせばいいのだった。支払いを済ませるために寺務所に入って行った。支払いが終わった後、住職らしき僧がいろいろな話をしてきた、その中で宗教的な話が出た、たぶん昨夜塔婆を背景に写真を撮っているとき訝るように懐中電灯の光を向けてきたのはこのお坊さんだったのだろう話の途中で思い当たった。
「今の若い人達は宗教を嫌うけど教えは必要だよ」
私に宗教心?
「けれど教えは二義的なものではないですか、まず人間存在をどのように見るかが大事だと思いますけど、そして如何に生きるか…」
私ははじめ黙って話を聞いていたが、話の腰を折るようにいつか返答をしていた。私は全て唯物として見ている、そこに絶望があったとしても真理なら選ばねばならない。住職らしき僧は私が話しているだけで何も言わなくなってしまった。まだ時間はあったがお礼を言い立ち上がると、バスの乗り場まで歩き出した。
1966年8月










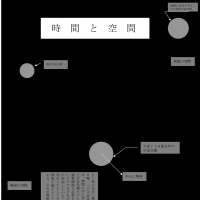
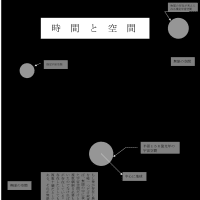



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます