
短編集『レキシントンの幽霊』を読んだ。この本には七編の短編が収録されている。
順番に並べると,
「レキシントンの幽霊」(初出 1996年10月)
「緑色の獣」(1991年4月)
「沈黙」(1991年1月)
「氷男」(1991年1月)
「トニー滝谷」(1990年6月)
「七番目の男」(1996年2月)
「めくらやなぎと,眠る女」(1995年11月
の七編だ。
全体的には,ひたひたとした孤独感,静かな恐怖感,死生観をテーマとして構成されているように思われる。特に生と死については村上春樹の作品に共通するテーマといえるものかもしれない。この中で一番好きな作品は「トニー滝谷」だが,この作品の感想はあとに譲ることにして,ここでは本のタイトルにもなっている「レキシントンの幽霊」について感想を述べてみたい。
「レキシントンの幽霊」にはロングバージョンとショートバージョンの二編が存在することを,筆者自身がこの短編集のあとがきで述べている。この短編集に収録されているものはロングバージョンで,ショートバージョンの方はおおよそ半分くらいの長さとのこと。高校教科書用の作品はショートバージョンの方になろうかと思われる。村上氏の短編には,同じタイトルの作品でもバージョンが異なるものが,その時その時の事情や村上氏の考えによりいくつか存在するとのことだ。
この作品は実話風に語られる。主人公の「僕」が村上氏本人であるように読者に思わせている。
おおまかなあらすじは以下のとおり。
---------------------------------------------
レキシントンの古い屋敷に住むケイシー(仮称となっている。建築設計の仕事をする50歳をすぎたばかりの健康的でハンサムな男)と僕は,ケイシーからの働きかけにより知り合う。ケイシーは父親から受け継いだ膨大な量の古いジャズコレクションを所蔵している。滅多に読者に会うことがない僕がケイシーの呼びかけにこたえたのもそれが大きな理由だ。
その屋敷にはピアノの調律師ジェレミー(30代半ばの男性でひどく無口で顔色があまりよくない)が一緒に暮らしている。また,大型のマスチフ犬が飼われている。
ケイシーと知り合ってから半年後のこと(その間,月に一度は屋敷を訪問するようになる),ケイシーがヨーロッパに所用で1週間留守にするあいだ,屋敷の留守を頼まれる。ジェレミーは母親の病気で田舎に行ったきりになっている。
留守番初日の深夜,二階の客用寝室で寝ていた僕は物音で目をさます。それは一階の居間からで,大勢でジャズを聴きながらパーティをしているように聞こえる。居間の外から聞き耳をたて,それが幽霊であると突然気づき主人公は愕然とする。そのとき犬は見当たらない。そのまま寝室に戻り朝まで一睡もできないでいた。しかし,その日以降,幽霊たちが出てくることはなく約束の1週間が過ぎる。帰宅したケイシーにはそのことは伝えなかった。
それからまた半年後,僕はケイシーとたまたま出会う。ジェレミーは母親の死後戻ってはこず,電話で話をしても以前と様子がすっかり変わっているという。ケイシー自身もすっかり老化しており,父親と自分の死に向き合う予備的な死のような「長い眠り」について語る。
僕はときどきレキシントンの幽霊のことを思い出すが,つい最近起こった出来事であるにもかかわらず,遠い過去のように思われ,また,その遠さの故に,僕にはそれがちっとも奇妙なことには思えないでいる。
---------------------------------------------
以上,けっこう長いあらすじとなってしまった。
最初にちょっと推理してみたい。おそらく村上氏のことだから,アメリカ在住の際レキシントンで古い屋敷をたまたま目にして,そこから想像を膨らませて短編小説に仕上げたのではないだろうか。というのも,主人公の僕が初めてその屋敷を訪問したときの情景描写がまるで映画のオープニングを観るように,目に鮮やかに飛び込んでくるからだ。これはあくまで推測なので実際はどうなのかわからない。
さて,そのレキシントンの古い屋敷で起こる不思議で怖い出来事には,背筋がすーっと冷めるような静かな恐怖を感じてしまう。そして,真夜中そこにいるのは幽霊以外では自分一人。恐怖の中での孤独感・・・。かなり怖い。昔観た映画「シャイニング」を連想させるところも多少あるのだが,この物語では,作者はその恐怖感を増幅させるようなことはせずに,どちらかというと,いつのまにかその恐怖に読者を馴染ませてしまうように持っていく。さらに突き詰めて考えると,幽霊(死後の世界)を現実的なものとして感じさせてしまうようにも思える。
幽霊の恐怖に馴染んだあとに読者が感じるのは死(死後)の世界だ。生の向こうにある死の世界が,レキシントンの屋敷をその入り口として語られているのだ。幽霊達が繰り広げる真夜中のパーティ。それはおそらくケイシーの死んだ父母とその一族や友人達が開いているものでろう。父親が大切にしていたジャズのレコードコレクションの音楽が夜会を楽しく盛り上げているのだ。
ケイシーの父は,ケイシーが子供の頃事故で亡くなった妻を弔うように昏々と長い眠りにつく(おおよそ2週間ほど)。そしてまたケイシーも10年前の父の死後,同様に長い眠りにつく。その話をケイシーから聞いた僕はそれを予備的な死のように感じるのだ。
ケイシーは自分の死を予見していたのではないかと思う。ケイシーには,同居人であるジェレミーが母親の死のために自分の元を去ったたため,自分の死を悼み「長い眠り」の儀式を執り行ってくれるものはいなくなっていた。そこで選んだのが「僕」だったのだと思われる。もちろん,「僕」はケイシーのためにそのような「長い眠り」などはしないのだが,今このようにして一編の小説にして,我々読者がそれを読む形となっている。ケイシーがそこまで期待していたかどうか,読者の判断のわかれるところだが,僕(作中の僕ではない)の場合はそこに作者の意図的なものを感じる。
レキシントンの屋敷から離れた僕は,死への誘いからはすっかり離れてしまい,死も幽霊たちのことも遠い出来事に感じられるだけに,客観的な目でケイシーが望む世界を描いてみせているといえるだろう。
この短編をよんで,村上氏の死と死後の世界についての考え方の一端を垣間見ることができる。村上氏が描く死は,生からぷっつり切れてしまったものではなく,生から連続して存在するもののように思われる。人々が経験する一つの世界なのだ。ただし,村上氏も他の誰も実際に経験したこととして,それを語ることは不可能なのだが。ふだんは,それは遠い世界のことであり,自分のことではないように思われる。だから,その世界がどのような世界であろうともけっして奇妙なことには思えないのだ。
村上氏の作品はそれが短編であれ長編であれ,それを理解するのは一筋縄ではいかない。しかし,心の中にすとーんと入り込んできて,いつまでも忘れられない感覚的記憶として頭に刻み込まれ深い余韻を残す。そしてそれと同時に,一つ一つの文章を味わい,比喩的表現の数々を読み解きながら,あれこれ頭を悩ませることがこのうえなく楽しいものとなる。
順番に並べると,
「レキシントンの幽霊」(初出 1996年10月)
「緑色の獣」(1991年4月)
「沈黙」(1991年1月)
「氷男」(1991年1月)
「トニー滝谷」(1990年6月)
「七番目の男」(1996年2月)
「めくらやなぎと,眠る女」(1995年11月
の七編だ。
全体的には,ひたひたとした孤独感,静かな恐怖感,死生観をテーマとして構成されているように思われる。特に生と死については村上春樹の作品に共通するテーマといえるものかもしれない。この中で一番好きな作品は「トニー滝谷」だが,この作品の感想はあとに譲ることにして,ここでは本のタイトルにもなっている「レキシントンの幽霊」について感想を述べてみたい。
「レキシントンの幽霊」にはロングバージョンとショートバージョンの二編が存在することを,筆者自身がこの短編集のあとがきで述べている。この短編集に収録されているものはロングバージョンで,ショートバージョンの方はおおよそ半分くらいの長さとのこと。高校教科書用の作品はショートバージョンの方になろうかと思われる。村上氏の短編には,同じタイトルの作品でもバージョンが異なるものが,その時その時の事情や村上氏の考えによりいくつか存在するとのことだ。
この作品は実話風に語られる。主人公の「僕」が村上氏本人であるように読者に思わせている。
おおまかなあらすじは以下のとおり。
---------------------------------------------
レキシントンの古い屋敷に住むケイシー(仮称となっている。建築設計の仕事をする50歳をすぎたばかりの健康的でハンサムな男)と僕は,ケイシーからの働きかけにより知り合う。ケイシーは父親から受け継いだ膨大な量の古いジャズコレクションを所蔵している。滅多に読者に会うことがない僕がケイシーの呼びかけにこたえたのもそれが大きな理由だ。
その屋敷にはピアノの調律師ジェレミー(30代半ばの男性でひどく無口で顔色があまりよくない)が一緒に暮らしている。また,大型のマスチフ犬が飼われている。
ケイシーと知り合ってから半年後のこと(その間,月に一度は屋敷を訪問するようになる),ケイシーがヨーロッパに所用で1週間留守にするあいだ,屋敷の留守を頼まれる。ジェレミーは母親の病気で田舎に行ったきりになっている。
留守番初日の深夜,二階の客用寝室で寝ていた僕は物音で目をさます。それは一階の居間からで,大勢でジャズを聴きながらパーティをしているように聞こえる。居間の外から聞き耳をたて,それが幽霊であると突然気づき主人公は愕然とする。そのとき犬は見当たらない。そのまま寝室に戻り朝まで一睡もできないでいた。しかし,その日以降,幽霊たちが出てくることはなく約束の1週間が過ぎる。帰宅したケイシーにはそのことは伝えなかった。
それからまた半年後,僕はケイシーとたまたま出会う。ジェレミーは母親の死後戻ってはこず,電話で話をしても以前と様子がすっかり変わっているという。ケイシー自身もすっかり老化しており,父親と自分の死に向き合う予備的な死のような「長い眠り」について語る。
僕はときどきレキシントンの幽霊のことを思い出すが,つい最近起こった出来事であるにもかかわらず,遠い過去のように思われ,また,その遠さの故に,僕にはそれがちっとも奇妙なことには思えないでいる。
---------------------------------------------
以上,けっこう長いあらすじとなってしまった。
最初にちょっと推理してみたい。おそらく村上氏のことだから,アメリカ在住の際レキシントンで古い屋敷をたまたま目にして,そこから想像を膨らませて短編小説に仕上げたのではないだろうか。というのも,主人公の僕が初めてその屋敷を訪問したときの情景描写がまるで映画のオープニングを観るように,目に鮮やかに飛び込んでくるからだ。これはあくまで推測なので実際はどうなのかわからない。
さて,そのレキシントンの古い屋敷で起こる不思議で怖い出来事には,背筋がすーっと冷めるような静かな恐怖を感じてしまう。そして,真夜中そこにいるのは幽霊以外では自分一人。恐怖の中での孤独感・・・。かなり怖い。昔観た映画「シャイニング」を連想させるところも多少あるのだが,この物語では,作者はその恐怖感を増幅させるようなことはせずに,どちらかというと,いつのまにかその恐怖に読者を馴染ませてしまうように持っていく。さらに突き詰めて考えると,幽霊(死後の世界)を現実的なものとして感じさせてしまうようにも思える。
幽霊の恐怖に馴染んだあとに読者が感じるのは死(死後)の世界だ。生の向こうにある死の世界が,レキシントンの屋敷をその入り口として語られているのだ。幽霊達が繰り広げる真夜中のパーティ。それはおそらくケイシーの死んだ父母とその一族や友人達が開いているものでろう。父親が大切にしていたジャズのレコードコレクションの音楽が夜会を楽しく盛り上げているのだ。
ケイシーの父は,ケイシーが子供の頃事故で亡くなった妻を弔うように昏々と長い眠りにつく(おおよそ2週間ほど)。そしてまたケイシーも10年前の父の死後,同様に長い眠りにつく。その話をケイシーから聞いた僕はそれを予備的な死のように感じるのだ。
ケイシーは自分の死を予見していたのではないかと思う。ケイシーには,同居人であるジェレミーが母親の死のために自分の元を去ったたため,自分の死を悼み「長い眠り」の儀式を執り行ってくれるものはいなくなっていた。そこで選んだのが「僕」だったのだと思われる。もちろん,「僕」はケイシーのためにそのような「長い眠り」などはしないのだが,今このようにして一編の小説にして,我々読者がそれを読む形となっている。ケイシーがそこまで期待していたかどうか,読者の判断のわかれるところだが,僕(作中の僕ではない)の場合はそこに作者の意図的なものを感じる。
レキシントンの屋敷から離れた僕は,死への誘いからはすっかり離れてしまい,死も幽霊たちのことも遠い出来事に感じられるだけに,客観的な目でケイシーが望む世界を描いてみせているといえるだろう。
この短編をよんで,村上氏の死と死後の世界についての考え方の一端を垣間見ることができる。村上氏が描く死は,生からぷっつり切れてしまったものではなく,生から連続して存在するもののように思われる。人々が経験する一つの世界なのだ。ただし,村上氏も他の誰も実際に経験したこととして,それを語ることは不可能なのだが。ふだんは,それは遠い世界のことであり,自分のことではないように思われる。だから,その世界がどのような世界であろうともけっして奇妙なことには思えないのだ。
村上氏の作品はそれが短編であれ長編であれ,それを理解するのは一筋縄ではいかない。しかし,心の中にすとーんと入り込んできて,いつまでも忘れられない感覚的記憶として頭に刻み込まれ深い余韻を残す。そしてそれと同時に,一つ一つの文章を味わい,比喩的表現の数々を読み解きながら,あれこれ頭を悩ませることがこのうえなく楽しいものとなる。










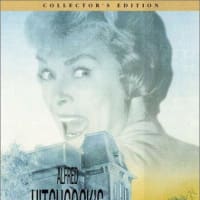








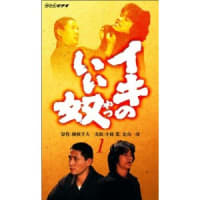
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます