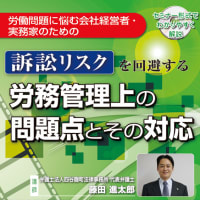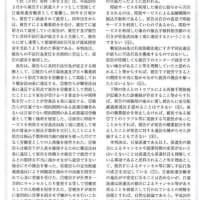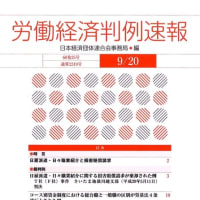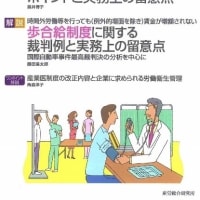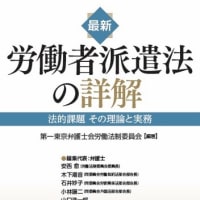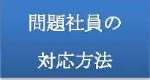
有期契約労働者が正社員と同じ待遇を要求する。
1 問題の所在
有期契約労働者の労働条件は個別労働契約又は就業規則等により決定されるものであり,正社員と同じ待遇を要求することは認められないのが原則です。しかし,有期契約労働者が正社員と同じ仕事に従事し,同じ責任を負担しているにもかかわらず,単に有期契約というだけの理由で労働条件が低くなっているような場合には,「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を定めた労契法20条に違反,正社員と同じ待遇を要求することができるのではないかが問題となります。
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
労契法20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が,期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては,当該労働条件の相違は,労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,不合理と認められるものであってはならない。
2 労契法20条の趣旨
労契法20条は,使用者に対し,有期契約労働者と無期契約労働者の間の均等待遇を義務づけるものではありません。また,条文の表題からも明らかなように,労契法20条は,有期契約労働者と無期契約労働者との間で「期間の定めがあることによる」不合理な労働条件の相違を設けることを禁止する趣旨の規定であり,期間の定めを理由としない労働条件の相違については射程の範囲外です。
基発0810第2号平成24年8月10日「労働契約法の施行について」でも,「法第20条は,有期契約労働者の労働条件が期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合,その相違は,職務の内容(労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度をいう。以下同じ。),当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して,有期契約労働者にとって不合理と認められるものであってはならないことを明らかにしたものであること。」「したがって,有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件の相違があれば直ちに不合理とされるものではなく,法第20条に列挙されている要素を考慮して『期間の定めがあること』を理由とした不合理な労働条件の相違と認められる場合を禁止するものであること。」とされています。
3 労契法20条の禁止内容
ア 期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては,
イ 有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違は,
① 労働者の業務の内容
② 当該業務に伴う責任の程度
③ 当該職務の内容(=①+②)及び配置の変更の範囲
④ その他の事情
を考慮して,不合理と認められるものであってはならないとされています。
有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違が期間の定めを理由としている場合に初めて労契法20条違反が問題となりますので,訴訟や労働審判においては,有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違が不合理と認められるものかどうかだけでなく,有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違が期間の定めを理由としたものかについても問題となります。
①労働者の業務の内容,②当該業務に伴う責任の程度,③当該職務の内容及び配置の変更の範囲,④その他の事情は,それぞれ独立した要件ではなく,不合理性を判断する上で考慮される要素です。
比較の対象となる「無期契約労働者」は正社員とは限らず,正社員以外に無期契約労働者がいる場合は,無期契約労働者が比較の対象となることも考えられます。また,労契法20条は,同一の使用者に雇用されている有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違に関する条文ですから,使用者が異なれば比較の対象にはなりません。
不合理性の解釈にあたっては,「本条の『不合理と認められるものであってはならない』とは,有期契約労働者の労働条件が無期契約労働者の労働条件に比して単に低いばかりではなく,法的に否認すべき程度に不公正に低いものであってはならないとの趣旨を表現したものと解される。」(『労働法(第十版)』235頁)との有力な見解があります。
4 労契法20条違反の効果
労契法20条は,違反の効果について「不合理と認められるものであってはならない。」と規定しており,使用者の行為規範としての性質を有することは明らかであり,使用者と労働組合との間の団体交渉等で活用されることが予想されますが,本条違反の効果について明確に規定されていないこともあり,裁判規範たり得るかについては検討を要します。
本条が使用者の行為規範として作用する以上,同条に違反した場合に使用者が不法行為法上の義務違反ないしは労働契約上の債務不履行が認められ,他の要件を充たせば損害賠償責任を負う可能性があるとまではいえるものと思われます。問題は,本条に違反した労働条件を無効と解すべきか否か,無効となるとすると,無効とされた労働条件はどのような内容となるのかです。
この点,平成24年8月10日付け基発0810第2号「労契法の施行について」は,「法第20条は,民事的効力のある規定であること。法第20条により不合理とされた労働条件の定めは無効となり,故意・過失による権利侵害,すなわち不法行為として損害賠償が認められ得ると解されるものであること。法第20条により,無効とされた労働条件については,基本的には,無期契約労働者と同じ労働条件が認められると解されるものであること。」としています。しかし,立法の際参考にされた特許法35条が,まずは3項において従業員等は一定の場合に「相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と定めた上で,同条4項において「契約,勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には,対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況,策定された当該基準の開示の状況,対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して,その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。」と定めているのとは異なり,労契法20条には,特許法35条3項に相当する条項(一定の労働条件を請求する権利を有する旨直接規定した条項)が存在しません。また,本条は,無効となった労働条件をどのように補充するのかについて具体的に規定しておらず,労働協約,就業規則,労働契約の解釈により,無効となった労働条件を補充する労働条件を導き出すことができる事案であれば,有期契約労働者は,当該労働条件の無効及びあるべき労働条件を主張立証していけばよいとも考えられますが,無効となった労働条件を補充する労働条件を導き出すことができない場合は,同条に違反した場合の労働条件を直ちに無効としてしまうと,不合理ながらも存在していた労働条件に関する合意すら効力がなくなってしまい,かえって有期契約労働者にとって不利益となりかねません。正社員等の無期契約労働者の労働条件が職務内容等に照らし高過ぎるような場合には,有期契約労働者の労働条件を引き上げたらかえって不合理に高い労働条件になってしまいますので,有期契約労働者の労働条件を引き上げるのではなく,不合理に高い労働条件となっている無期契約労働者の労働条件を引き下げた方が合理的な場合もあり得ます。
労契法20条違反の効果に関しては,「労働条件分科会での議論をみれば,本条は,訓示規定にとどまるものではなく,私法上の効力をもつことを想定して構想されたといえる。つまり,『不合理』と認められた労働条件の定め(労働協約,就業規則,労働契約)は無効とされよう。」としつつ,「不合理性の判断に際して比較対象となった無期契約労働者の労働条件を定める就業規則等の基準が存しており,その合理的な解釈によって同基準を有期契約労働者にも適用できるような場合でなければ,無効と損害賠償の法的救済にとどめ,関係労使間の新たな労働条件の設定を待つべきであると考える。」(『労働法(第十版)』238頁~239頁)との有力な見解が存するところですが,本条違反の効果について明確に規定されていない以上,本条は単なる訓示規定に過ぎず,本条違反の労働条件も無効とはならないという解釈も成り立ち得るところです。