
1 自分で仕事をこなす能力と部下を管理する能力は別
まずは,自分で仕事をこなす能力と,部下を管理する能力は,別の能力であることをよく理解した上で,人員の配置を行う必要があります。自分で仕事をこなす能力が高い社員であっても,部下を管理する能力は低いということは,珍しくありません。
2 部下を管理できない理由に応じた対応
部下に問題があるために上司が部下を管理できていない場合は,上司に任せきりにせず,組織として対応する必要があります。問題行動が多い部下がいることを役員等が知りながら,本腰で対策を練らずにそのまま放置した結果,問題をこじらせるケースが多い印象があります。問題から逃げずに正面から向き合い,組織として対応すれば,余程難易度の高い事案でない限り,問題は解決に向かうのが通常です。
部下を管理できない理由が,管理職の単なる経験不足によるものである場合は,部下の管理方法について指導しながら経験を積ませたり,研修を受けさせたりして教育することにより,管理職としての育成を図ることになります。
管理職としての適性がないことが原因で部下を管理できない場合は,当該社員の能力でも対応できるレベルの管理職に降格させるか,管理職から外して対応するのが原則です。
3 人事権の行使としての降格処分
人事権の行使としての降格処分は,就業規則等の根拠規定がなくても会社の裁量的判断により行うことができるのが原則です。ただし,その裁量も無限定のものではなく,相当な理由がないのに労働者に大きな不利益を課したような場合には,人事権の濫用により無効と判断されることがあります。
賃金減額を伴う降格処分も行うことができますが,賃金の減額を伴う場合は,降格の効力を争われるリスクが高まります。賃金減額の程度は,人事権の濫用の有無を判断する際に考慮され,賃金減額の程度が大きい場合は人事権の濫用と判断されやすくなります。降格を行う必要性と賃金減額の相当性について,説明できるようにしておく必要があります。可能であれば,賃金減額を伴う降格に同意する旨の書面を取ってから降格させることが望ましいところです。
地位を特定して管理職として中途採用した社員については降格が予定されていないため,本人の同意を得ずに降格処分を行うことはできません。
4 解雇
管理職としての適性がないことが原因で部下を管理できない場合であっても直ちに退職勧奨したり解雇したりせず,当該社員の能力でも対応できるレベルの管理職に降格させるか,管理職から外して対応するのが原則です。
ただし,地位を特定して高給で採用された社員に労働契約で予定された能力がなかった場合には,降格ではなく退職勧奨や解雇を検討することになります。
地位特定者を解雇するにあたっては,地位を特定して採用された事実を主張立証する必要がありますので,労働契約書等の書面に明示しておくべきです。
管理職として不適格であることを理由とした解雇が有効と判断されるようにするためには,何月何日に管理職として不適格であることを示す事実があったのかを,当該事実があった当時の証拠により説明できるようにしておく必要があります。抽象的に「管理職として不適格である。」と言ってみてもあまり意味はありませんし,「彼が管理職として不適格であることは,周りの社員も,取引先もみんな知っている。」というだけでは足りません。
会社関係者の陳述書や法廷での証言は,証拠価値があまり高くないため,紛争が表面化する前の書面等の客観的証拠がないと,何月何日にどのような管理職として不適格であることを示す事実があったのかを主張立証するのには困難を伴うことが多いというのが実情です。
------------------













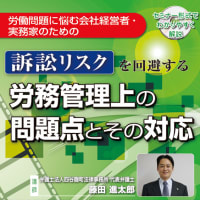


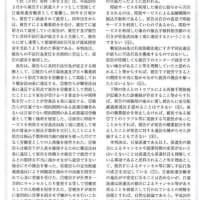
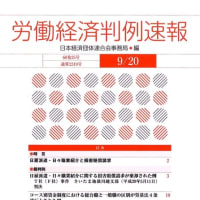

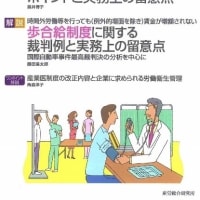














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます