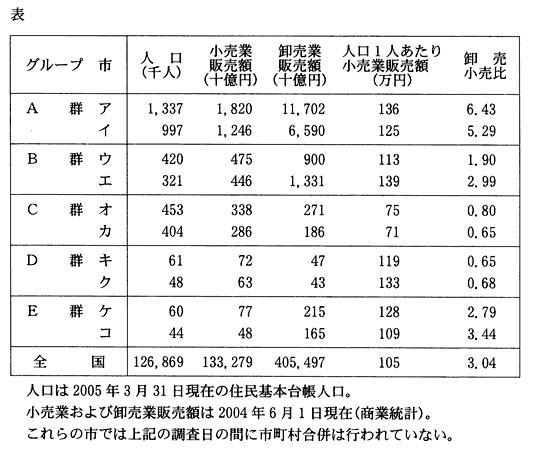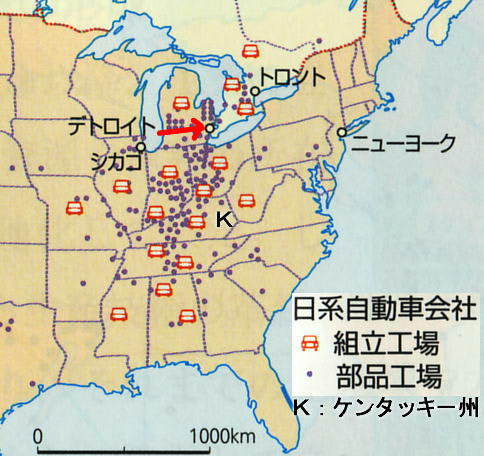2007年東大2次地理B
第1問 ヨーロッパの環境とエネルギーについて、設問Aと設問Bに答えなさい。
第1問設問A ヨーロッパの自然環境に関連し、各問いに答えなさい。
地球では過去200万年に氷河期と間氷期が、ほぼ10万年周期でくりかえされてきた。次の図1は、ヨーロッパにおける氷河期の分布と、
a)氷河期と現在の海岸線の位置を示したものである。
図2は北緯55度付近の3都市の現在の気温と降水量のグラフである。氷河の侵食作用でできた地形は【 ア 】と呼ばれる。スカンジナビア半島西岸では【 ア 】に海水が侵入してできた【 イ 】を
b)冬季も海水が凍結しない天然の良港として利用してきた。また、氷河期に氷河が覆った地域には、
c)湿地や湖がしばしば見られる。バルト海南部沿岸地域やイギリスでは土壌がやせているため、【 ウ 】中心の農業が行われている。そのうち、図1のP地域では、大きな標高差と気候の季節変化を生かした【 エ 】が行われている。
(1)ア~エに適切な語句を答えなさい。
(2)図2の気候XYZは、図1の都市ABCの都市のいずれか。
(3)説明文のa)について。氷河期の海岸線は、現在の海岸線と比較すると、どのような位置関係にあるか。60字以内で述べなさい。
(4)説明文のb)について。その理由を30字以内で述べなさい。
(5)説明文のc)について。近年の環境問題とはどのようなものか。30字以内で述べなさい。

--------------------------------------
第1問設問A解答
(1)ア-U字谷 イ-フィヨルド ウ-酪農 エ-移牧
(2)X-B Y-A Z-C
(3)氷河期には大陸に海面が低下したため、大陸棚や海峡部分などの浅海が陸地化した。大陸は現在よりも拡大していた。
(4)沖合を強い暖流北大西洋海流が北上するからである。
(5)化石燃料の消費による酸性雨のため、湖沼が酸性化した。
第1問設問A解説
(1)ア-U字谷
U字谷 最終氷河期の最盛期は2万年前、海面が150m低下した。3万年前から2万年までが氷河拡大期であり、海面が低下した。1年平均では1.5cmの低下になる。
最終氷河期後、2万年前から1万年前までは氷河縮小期であり、海面が上昇した。1万年前にほぼ現在の海面と同じ高さになった。
2万年前の氷河期には海面が低下したが、その海面めざして氷河が大陸をゆっくり流れた。1日1m程度のゆっくりした流速だが、岩石を巻き込んだ、1000mを越える厚さの氷河は、侵食力が強かった。その浸食断面がU字型なのでU字谷といわれる。氷河の運んだ岩石が氷河末端に堆積し、モレーンといわれる。

イ-フィヨルド
フィヨルド ノルウェー、グリーンランド、ニュージーランド、チリなどの海岸には、フィヨルドが見られる。氷河の侵食したU字谷に、後氷期海に面が上昇し、海水が侵入した谷である。水深が深く、距離が長い。ノルウェー、チリではフィヨルドの一部を仕切ってサケを養殖し、日本に輸出している。
ウ-酪農
酪農 酪農は乳牛を飼育し、乳製品を販売する農業である。酪農の発達した国・地域は冷涼な低地であり、他の作物の栽培が難しいという特徴がある。
デンマークは現在も冷涼な気候であり、さらに氷河跡の砂礫地モレーンが広がり、小麦栽培が難しい。牧草・ライ麦・じゃがいもなど、寒さに強い飼料作物を栽培できるので、酪農が盛んになった。農業協同組合が酪農農民の経済面を支援する、金融・商社システムである。
デンマークの農業地域が酪農ではなく、混合農業に区分される場合がある。これは、メス牛が生まれると酪農をいつまでも続けることができるが、オス牛が生まれると肉牛として飼育することになり、酪農には区分できない。混合農業になる。酪農は混合農業における乳牛飼育の経営形態とみなすことができる。
エ-移牧
移牧 スイスアルプスで古くから行われている酪農。冬は、低地の畜舎で乳牛を飼育し、夏には暑さを避け、アルプスの高地牧場(アルプあるいはエルム)で飼育する。なお、スペインでは羊の飼育地を季節的に変える移牧がある。
(2)西岸気候
西岸海洋性気候Cfb 地図Aはアイルランドのダブリンで気候は西岸海洋性気候Cfbである。暖流の影響が3都市のうちで一番強いから、グラフ(Y)が該当する。
Bはデンマークのコペンハーゲンで西岸海洋性気候Cfbであるが、暖流の影響が届きにくい位置にあるので、グラフ(X)が該当する。CはロシアのモスクワDfであり、冬の低温からグラフ(Z)になる。
西岸気候は、暖流と偏西風の影響が強く、高緯度でも温暖な気候である。
海洋性気候は、海の影響で、気温の年較差の小さい気候である。
西岸海洋性気候Cfbの記号のうち、bは最暖月平均気温が22℃未満である。夏に涼しいから、気温比較差が小さいことを示す。
日本は東岸気候Cfaである。aは最暖月平均気温が22℃以上である。夏に高温であるから、気温年較差が大きいことを示す。
(3)氷河性海面変動
氷河 図1には2万年前、北西ヨーロッパに大陸氷河が最も広がった氷河分布と、アルプスの山岳氷河の分布図が描かれている。
2万年前の最終氷河期には海面が150mも低下して、大陸棚部分は陸地になった。イギリスがヨーロッパ大陸の一部、北海も陸地になった。また、トルコのボスポラス海峡が陸地になって、黒海は湖の状態になった。氷河の中心となったバルト海・ボスニア湾では、氷河の重さで大陸が沈降し、本来は凸型の楯状地が、凹型になってしまった。バルト楯状地は、氷河が消えたあと、隆起が始まった。現在も隆起を続け、8000年後には、凸型の楯状地になる。
陸地、例えば河口に大量の砂礫が運搬されると、河口に堆積しても河口が沈んでしまい、河口に堆積地形としての三角州はできない。三角州のない河口はエスチュアリーといわれるが、河口が堆積物の重量に敏感に反応して沈降するエスチュアリー(ラプラタ川)と、砂礫が運ばれないエスチュアリー(テムズ川)とがある。
氷河の発達によって大陸の沈む例として、バルト楯状地以外に、カナダ楯状地がある。南極大陸は氷河の厚さが3000mもあり、氷河を取り除くと島の集合体になるが、氷河の重さが消えた分だけ隆起する。南極大陸ができるのである。このような、大陸の浮き沈みによる均衡維持はアイソスタシーといわれる。

(4)北大西洋海流
メキシコ湾流と北大西洋海流 北赤道海流として熱帯海域の熱エネルギーを集めて西に流れる。メキシコ湾岸ではメキシコ湾流として強い流れるになる。この部分は西岸強化流である。北大西洋では北大西洋海流と名称が変わる。メキシコ湾からヨーロッパ西岸にまで熱エネルギーを運搬する強い暖流である。ヨーロッパ西岸、特にノルウェーなどの高緯度西岸地域が、冬でも温暖な西岸海洋性気候Cfbになる。
北大西洋海流の一部は寒流のカナリア海流になる。カナリア海流、北赤道海流、メキシコ湾流、北大西洋海流、そしてカナリア海流というように、海流が大西洋の北半球部分で一回りする。これが環流である。

(5)酸性雨
酸性雨 もともと自然状態の雨でも、大気中の二酸化炭素が溶けてpH5.6の弱酸性になっている。そのため、酸性雨はpH5.6以下と定義される。
酸性雨は石炭・石油の化石燃料の大量消費によって起こる。大気中に硫黄酸化物SOx、窒素酸化物NOxが浮遊し、硫酸・硝酸の酸性雨が降る。酸性雨は産業革命以降、ヨーロッパから始まった。国境を越えて酸性雨が降る。

最初は酸性に弱い石像、石造建築、ブロンズ彫刻などに酸性雨の影響が見られたが、次第に酸性雨被害が拡大し、ドイツ・デンマーク・スウェーデン・フィンランドなどでは、広い面積にわたって森林が枯死した。最終的には酸性水が低地に流れて、湖沼・湿地に集まり、動植物の生態系を変えた。先進国では脱硫装置、脱硝装置によって、酸性雨の酸性濃度を減らすことができた。
20世紀末、旧東欧の工業地域では脱硫・脱硝装置を設置するだけの資本も技術もなく、ここを発生源とする酸性雨が北ドイツの森林・湖沼の動植物に大きな影響を与えた。
生態系を守るためにヘリコプターなどを使って、石灰が大量散布され、森林・湖沼の中和作業が進められた。
 酸性雨防止の国際協力
酸性雨防止の国際協力 酸性雨の被害拡大をおさえるため、次のような条約がある。国境を越えた汚染問題が深刻なヨーロッパが中心の条約である。
○長距離越境大気汚染条約 (1979)
○ヘルシンキ議定書(1985)
○ソフィア議定書(1988)
21世紀になると、中国・インドの工業の発展により、中国・インドが酸性雨の発生源となり、新たな国際的対策が必要になっている。
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
07年第1問設問A解答解説終了
07年第1問設問Bに進む
07年のはじめに戻る