
水上バスというのを皆さんはご存知だろうか。隅田川や東京のお台場などのウォーターフロント(ある種死語)をめぐる観光船である。
学生の頃、西岡の人文地理という名物授業があり、その中で教授が撮影した、船からの橋巡りのビデオを今でもしっかり覚えている。
実はこの水上バス、歴史はかなり古く、大正年間にさかのぼるという。これは一度乗ってみなくては・・・と思いつつ、三十年余、その西岡教授がこの八月にお亡くなりになり、だからというわけではないが、先日初めて乗ってみた。

船は日の出桟橋から出て、吾妻橋へ向うというオーソドックスなコース。平たい船は二階建てになっており、屋根がガラス張りになっているので、日当たりは抜群(苦笑)。
艦内限定という隅田川ヴァイツェンなるビールを飲みながら進む。気分はさながら、セーヌ川のクルーズ(爆) だが、さすがに建物の風情が・・・と思うまもなく、橋の下をくぐる。
最初の橋は「勝鬨橋」だ。中央が跳ね上げ式になっているのが特徴だが、もう何年開いていないのか・・・そして、また橋、またまた橋という感じで橋をくぐる。
普段見たことのないアングルから見る町並みは妙に新鮮だ。築地とか朝日新聞、読売新聞・・・いかに江戸が海っぱたにあるかを再認識する。
永代橋ときくと、落語の「たがや」で、たがやさんがつぶやく、「今から、永代に回るのもしゃくだしなあ・・・」が思い出された。
やがて、その花火の当日、たがやの事件のあった両国橋をくぐる。当時はこの右岸が下総の国だったんだよなあと・・・
もっとも当時は橋のなかったところにも何本も橋がかかっているのが現在、○○中央なんて橋の名前を見ると、もうちょっとネーミングなんとかならなかったのかと・・・
気が付けば、あっという間に吾妻橋が見えてきた。時間にして40分だが、けっして長いとは思わなかった。
この吾妻橋も「文七元結」を始め、いろんな落語の舞台になっている。考えてみると、落語の舞台そのものというコースかも。
船を下りながら、なんとなく「徳さん大丈夫かあ」と言いそうな気分になっている自分がいた。それにしても暑かったなあ・・・
学生の頃、西岡の人文地理という名物授業があり、その中で教授が撮影した、船からの橋巡りのビデオを今でもしっかり覚えている。
実はこの水上バス、歴史はかなり古く、大正年間にさかのぼるという。これは一度乗ってみなくては・・・と思いつつ、三十年余、その西岡教授がこの八月にお亡くなりになり、だからというわけではないが、先日初めて乗ってみた。

船は日の出桟橋から出て、吾妻橋へ向うというオーソドックスなコース。平たい船は二階建てになっており、屋根がガラス張りになっているので、日当たりは抜群(苦笑)。
艦内限定という隅田川ヴァイツェンなるビールを飲みながら進む。気分はさながら、セーヌ川のクルーズ(爆) だが、さすがに建物の風情が・・・と思うまもなく、橋の下をくぐる。
最初の橋は「勝鬨橋」だ。中央が跳ね上げ式になっているのが特徴だが、もう何年開いていないのか・・・そして、また橋、またまた橋という感じで橋をくぐる。
普段見たことのないアングルから見る町並みは妙に新鮮だ。築地とか朝日新聞、読売新聞・・・いかに江戸が海っぱたにあるかを再認識する。
永代橋ときくと、落語の「たがや」で、たがやさんがつぶやく、「今から、永代に回るのもしゃくだしなあ・・・」が思い出された。
やがて、その花火の当日、たがやの事件のあった両国橋をくぐる。当時はこの右岸が下総の国だったんだよなあと・・・
もっとも当時は橋のなかったところにも何本も橋がかかっているのが現在、○○中央なんて橋の名前を見ると、もうちょっとネーミングなんとかならなかったのかと・・・
気が付けば、あっという間に吾妻橋が見えてきた。時間にして40分だが、けっして長いとは思わなかった。
この吾妻橋も「文七元結」を始め、いろんな落語の舞台になっている。考えてみると、落語の舞台そのものというコースかも。
船を下りながら、なんとなく「徳さん大丈夫かあ」と言いそうな気分になっている自分がいた。それにしても暑かったなあ・・・

























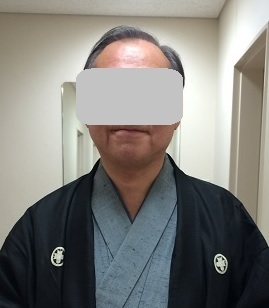

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます