東京国立博物館の特別展。
入場者数トップ10を確認する。
(私の確認できた範囲)
1位:1,505,239人
モナ・リザ展
1974(昭和49)年4月20日~6月10日
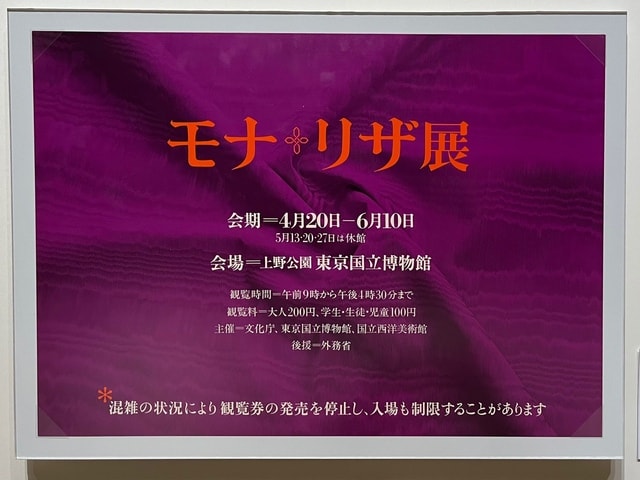
日本における美術展入場者数(1会場)の歴代1位を記録した歴史的な展覧会。
「モナ・リザ」がルーヴルから貸し出されたのは、1963年のワシントン・ナショナル・ギャラリーとメトロポリタン美術館、1974年の東京国立博物館とプーシキン美術館だけである。
2位:1,297,718人
ツタンカーメン展
1965(昭和40)年8月21日〜10月10日

ツタンカーメン王墓の埋葬品から「黄金のマスク」をはじめとする45点の古代エジプト美術が出品されたらしい。
3会場を巡回し、合計で295万人を記録。
東京国立博物館:1,297,718人
1965.8.21〜10.10
京都市美術館 :1,074,495人
1965.10.15〜11.28
福岡県文化会館: 586,413人
1965.12.3〜12.26
3位:946,172人
国宝 阿修羅展
2009(平成21)年3月31日~ 6月7日
旧西金堂の国宝「八部衆立像(阿修羅など8体)」、国宝「十大弟子立像(現存6体)」が初めて寺外でそろって公開された展覧会。
福岡に巡回し、合計で165万人を記録。
九州国立博物館:710,138人
2009.7.14〜9.27
4位:796,004人
レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像
2007(平成19)年3月20日~6月17日
レオナルド・ダ・ヴィンチ《受胎告知》ウフィツィ美術館蔵 が来日するという、日伊で社会的事件?となった展覧会。
1974年の《モナ・リザ》、1993年の《聖ヒエロニムス》、2002年の《白貂を抱く貴婦人》に続くレオナルド油彩画4作品目の来日であった。
5位:794,909人
国宝 薬師寺展
2008(平成20)年3月25日~6月8日
国宝8点・重文5点を含む47点の展示。
金堂の国宝《日光・月光菩薩立像》が、そろって寺外ではじめて公開された。
6位:774,572人
日本国宝展
1990(平成2)年4月10日~5月27日
「日本国宝展」と題する展覧会は、確認した範囲では、過去7回開催されている。
入場者数は、1990年の日本国宝展がトップ。
近年では、2017年の京博「国宝」展の加熱ぶりが印象的。
1960年:298,634人 東京国立博物館
1969年:京都国立博物館
1976年:京都国立博物館
1990年:774,572人 東京国立博物館
2000年:439,039人 東京国立博物館
2014年:386,708人 東京国立博物館
2017年:624,493人 京都国立博物館「国宝」展
7位:722,082人
ルーブルを中心とするフランス美術展
1961(昭和36)年11月3日〜1962年1月15日
1954年に東博「ルーヴル・国立美術館所蔵-フランス美術展」は、中世から19世紀までのフランス美術約360点を紹介し、入場者数は約52万人であったらしい。
本展は、それに続く時代、アングル、ドラクロワに始まり、ミレーや印象派を経て、ピカソ、マティス、抽象絵画に至るまで、1840年〜1940年までの1世紀間のフランス美術の展開を、絵画260点、彫刻60点、素描119点、版画39点の計478点で紹介する。
次の巡回地・京都では、東京を上回る入場者数を記録する。
京都市美術館:746,314人
1962年1月25日〜3月15日
8位:632,543人
エジプト美術五千年展
1963(昭和38)年3月3日〜5月5日
ユネスコは、「アスワン・ハイ・ダム建築計画」の実行によりダム湖に沈没してしまう「ヌビアの遺跡群」を高台に移転させる救済キャンペーンを開始。本展や「ツタンカーメン展」の収益金は、このキャンペーンに寄付されたという。
京都市美術館:586,114人
1963年5月26日〜7月21日
9位:620,390人
世界四大文明展 エジプト文明展
2000(平成12)年8月2日~10月1日
「世界四大文明展」として、エジプト、メソポタミア、インダス、中国の各文明を紹介する展覧会を開催するという大規模企画。
首都圏では、4展が4館で同時開催される。入場者数では、東博のエジプトがトップとなるが、東京都美術館のインダス、世田谷美術館のメソポタミア、横浜美術館の中国も、40万人超と大人気。
4展は、首都圏のあと、それぞれ1〜4都市を巡回している。
【エジプト文明】
東京国立博物館:620,390人
2000年8月2日~10月1日
愛媛県美術館
2000年10月21日〜12月17日
国立国際美術館:404,825人
2001年1月13日〜4月8日
北海道立近代美術館
2001年4月21日〜7月1日
【メソポタミア文明】
世田谷美術館:408,831人
2000年8月5日〜12月3日
福岡アジア美術館
2000年12月16日〜2001年3月4日
【インダス文明】
東京都美術館:428,263人
2000年8月5日〜12月3日
名古屋市博物館
2001年1月20日〜3月11日
【中国文明】
横浜美術館:421,899人
2000年8月5日〜11月5日
仙台市博物館
2000年11月14日〜12月24日
石川県立美術館
2001年1月13日〜2月12日
香川県歴史博物館
2001年2月24日〜4月1日
広島県立美術館
2001年4月12日〜6月17日
10位:600,439人
運慶展
2017(平成29)年9月26日~ 11月26日
「運慶作あるいはその可能性が高いと考えられているのは、異論はあるものの、31体という見方が一般的」(当時)であるなか、そのうち22体が出品された「史上最大の運慶展」。
ちなみに、同年4-6月には「快慶展」が奈良国立博物館で開催、入場者数123,842人であった。
次点(11位):596,137人
古代エジプト展
1978年4月1日~5月28日
トップ11のうち、
4展が「古代エジプト」。
4展が「日本美術」。
3展が「西洋美術」(うち2展がレオナルド・ダ・ヴィンチ作品展)。
トップ11を、開催順に、通常一般(大人)料金を添えて並べる。
1961(昭和36)年
ルーブルを中心とするフランス美術展 未確認
1963(昭和38)年
エジプト美術五千年展 未確認
1965(昭和40)年
ツタンカーメン展 300円
1974(昭和49)年
モナ・リザ展 200円
1978(昭和53)年
古代エジプト展 800円
1990(平成2)年
日本国宝展 1100円
2000(平成12)年
世界四大文明展 エジプト文明展 1300円
2007(平成19)年
レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像
1500円
2008(平成20)年
国宝薬師寺展 1500円
2009(平成21)年
国宝阿修羅展 1500円
2017年(平成29)年
運慶展 1600円
さて、現在開催中の「国宝 東京国立博物館のすべて」は、第3期および第4期の事前日時指定券が予約開始すぐに完売になるなど、大人気の模様。
このご時世でなく、事前予約制による入場者数制限がなければ、トップ10入りを狙えただろうか。
なお、一般料金は、2000円。
ちなみに、東博の特別展入場料金の過去最高額は、2020年10-11月の「桃山-天下人の100年」展で、一般料金2400円。
同展以降の平成館の特別展の一般料金は、以下のような推移。
鳥獣戯画のすべて 2000円
聖徳太子と法隆寺 2200円
最澄と天台宗のすべて 2200円
ポンペイ 2100円
琉球 2100円
国宝 東京国立博物館のすべて 2000円
総合文化展一般料金+1000円少しの水準である。
〈追加〉
資料館にも行きたいな。
資料館では所蔵図書類の中から特別展関連図書コーナーを設けています。今回は、戦後開催された特別展の中から来場者数ベスト100の図録等を紹介しています。お手に取ってご覧ください。
— 東京国立博物館(トーハク) 広報室 (@TNM_PR) November 18, 2022
*12/23まで
*資料館は12/9まで月~金曜日 10時半~16時に開館。11/30は月末休館日。資料館専用の予約優先、当日枠有 pic.twitter.com/SIeKXzRsxU













