目次
1.はじめに
2.調査方法
3.日本と世界の迷信
3.1.文化による迷信の共通点
3.2.恐れによる迷信の共通点
4.考察
5.終わりに
6.参考文献
1.はじめに
人間の生活の中には、祖先から伝わっていたものをそのまま信じている迷信も多い。Wikipediaには「迷信(めいしん、英語:superstition)とは、人々に信じられていることのうちで、合理的な根拠を欠いているもの。 一般的には社会生活をいとなむのに実害があり、道徳に反するような知識や俗信などをこう呼ぶ。 様々な俗信のうち、社会生活に実害を及ぼすものである。迷信ということは人間の信じられることのうちで合理的な根拠を欠いているものである。」と述べられている。また、『日本語大辞典』では「誤って信じること。誤信。現在の科学的見地から見て不合理であると考えられる言い伝えや対象物を信じ、時代の人心に有害になる信仰。」と述べている。このような迷信は、日本だけでなく世界の色々な国にもある。このレポートでは世界のいろいろな国にもある日本の迷信について調べた。
2.調査方法
インターネットウエーページの情報、グーグルプラスのハングアウトで質問をすること、クラスメートに自分の国にもある日本の迷信についてのことにアンケートを作って情報を集めた。
3.日本と世界の迷信
今のような科学が発展された時代でも迷信ということがどうして残っているのだろうか。それには、二つの理由があると思われる。一つは歴史的、伝統的、文化的なものを信じる気持ちがあること。もう一つは人間の恐れから生まれたことである。例えば、「してはいけない」という迷信をすると何か悪い縁ができてしまったのではないかと恐れる。日本だけではなく世界でもそのような考えで迷信が続いてきたのである。では、日本にある迷信が他の国にあるのだろうか。
3.1.文化による迷信の共通点
「何でも調査団」と言うインターネットウェプページの2013年の調査によると「信じている迷信、第一位は「茶柱が立つと縁起が良い」で46%」と書かれていた。茶柱が立つことで本当に縁がよくなるのだろうか。ブー・フォン・ザン(2015)によると、昔あるお茶の店で、一番のお茶だけが売られて、二番のお茶がたくさん残っていた。二番のお茶は茎が多く混ざってしまったからである。それで、「茶柱が立つと縁起が良い」と二番目のお茶の弱点を良いこととして言い広めたということから始まったという伝説もあると述べている。お茶というのは日本人にとって長い歴史を持ち、現在の日本の文化にも関わっているから、この迷信は一番人気があるのだろう。確かに、その迷信は私の国ミャンマーにもある。グーグルプラスで質問した結果によると韓国やお茶を飲む文化があるほかの国にもあるということが分かった。また、ヨーロッパの国にも日本と同じ迷信があるがこの迷信は知らないと言う人も多い。それは、その国ではお茶についての習慣がないからと言うことが分かった。
また、TABIZINE というウエブページに「塩をつまみ肩にかけて、厄を払う」と言う迷信がアメリカ、アイルランド、ロシア、日本などの多くの国にもあると述べていた。この、塩は悪運を除くものとして共通していること、そして身を清めるために使うことは日本と同じ考えだと思う。つまり、迷信というのは宗教、歴史、文化や考え方の様相によって迷信も同じということが分かった。
3.2.恐れによる迷信の共通点
次に、日本でよく知られているもう一つの迷信である「夜爪を切ると親の死に目に会えない」と言う迷信について調査した。これは、昔の日本では近しい人が死んだときに自分の髪や爪を一緒に埋める風習があったことで、爪を切るということは縁起の悪いことだと考えられてできた迷信である。もう一つ、昔は今のような電気もないから夜に爪を切るとよく見えなくて傷つける恐れから、そして、それを踏むと痛いからということ由来もあるそうだ。クラスメートのアンケートやグーグルプラスの結果によるとその迷信は上の3.1のことと違って文化が同じ国だけじゃなく、文化が違う国にもあるということが分かった。これと似た迷信はアラブ、セルビア、ヨーロッパのバルカン諸国、フィリピン、トルコ、ミャンマー などの世界の色々な国にもある。国や文化が違っても同じなのは「恐れ」と言う共通の感覚である。他にも同じ迷信がたくさんあるが、由来の意味がわかっていても、何かやってはいけないことをやるとその影響が自分にふりかかるのを恐れてその迷信は多くの国で引き継がれてきたのだろう。
4.考察
上の調査で分かったことは国が違っても色々な原因で同じ迷信が存在することである。人から人へ伝えてそれが他の国にも伝わって同じ迷信になることもあるかも知れないが、文化や宗教が似ていて迷信も同じになる場合もあると言うことが分かった。そして、迷信ということは本来の意味が分かっても、たとえば人にとって「死」と言うことはとても恐くて、「もし、これをすると自分や自分の家族が悪い縁になる」ということは、その恐れの感覚で今まで伝わってきたということが分かった。だから、国が違っても迷信が同じになると考えられる。
5.終わりに
世界には色々なたくさんの迷信がある。悪い迷信もあれば、いい迷信もあると思う。迷信を信じるというより守っていると自分にも損がないという考えで受け入れて、それが知らないうちに人間の生活の習慣になっているかもしれないと思う。どんなに科学が発展しても人の恐れがある限り迷信というものは続いていくだろう。
6.参考文献
・迷信 –Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E4%BF%A1
・「意外と深い日本の迷信」
http://japanese-superstitions.biz/action/ (2016年11月10日参照)
・「一度は聞いたことがある日本の迷信・びっくりな世界の迷信」
http://matome.naver.jp/odai/2140953647351889601 (2016年11月10日参照)
・「【海外の反応】「夜爪を切ると…」日本の信じられない<迷信>7選~」
autobahn.blog.jp/archives/1049237577.html (2016年11月11日参照)
・「何でも調査団 レポート05 信じている迷信、第1位は「茶柱が立つと縁起がいい」で46%」
http://chosa.nifty.com/season/chosa_report_A20130111/5/ (2016年11月12日参照)
・ブー・フォン・ザン(2015)「日本人の迷信についての研究」『日本語・日本文化研修プログラム研修レポート集』30期巻 広島大学国際センター
ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/38679/.../ReportJTP_30_107.pd...
・「迷信一覧」いくつ知ってる?世界の迷信と言い伝え12選 http://tabizine.jp/2015/03/18/32089/ (2016年11月10日参照)










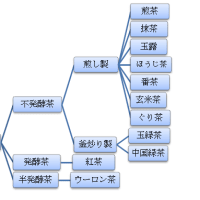
数の迷信もありますよね。日本だと、「4」とか「9」とかを使わないことがよくあるし、結婚式やお葬式で「2」を避けたり、逆に、「8(八)」は喜ばれたり…。そんなことも、時間があったら調べてみてね。そして、ミャンマーの迷信も、また教えてください!