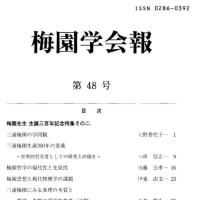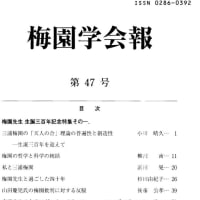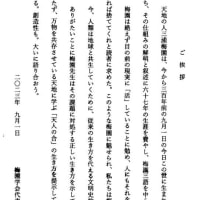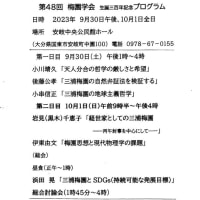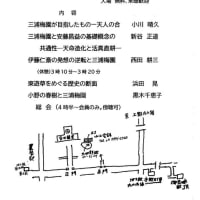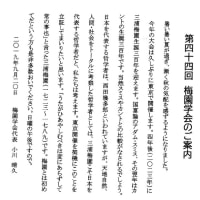「知足解」(戊辰稿)の書き下し文と大意
☆
原文の漢文は
国会図書館デジタルコレクション『梅園全集・下巻』『梅園文集』に781頁と782頁
で、翻刻を読むことができます。(781頁下段6行目11字目 「依」は「倚」が正)
☆
馬を指して之を問ふに孩堤(がいてい)の童と雖も其の馬なるを知る。
剣を指して之を問ふに庸愚(ようぐ)の人と雖も其の剣なるを知る。
伯楽之を観て後其の千里の技あることを知る。張華之に遇ひて後に其の天下の宝なるを知る。
馬を指してこれは何かと問うと二三歳の幼児でさえもそれが馬だと知っている。
剣を指してこれは何かと問うとおろか者でもそれが剣だと知っている。
伯楽は馬を観てその馬が千里を駆ける能力があることを知る。張華はこの剣が後世天下の宝であること知る(見抜いた)。
之を知る者は必ず之を用ゆ 故に嶮しきを逾(こ)え 遐(か)なるを度り 其の労を知らず。蛟(みずち)を斬り金を断て其の鈍きことを覚えず。
名馬の能力を知るものは必ずその馬を使いこなせる。それ故その馬はどんなに険しい場所でも越えてゆき、どんなに遠くまでも走り、疲労知らずなのである。名剣であれば蛟(みずち)を斬っても、金を断ち切っても、鈍くはならない。
知は則ち知るなり。而して愚者の知 猶(なお)知らざるがごとし。
「知」とはすなわち「知る(能力を見抜く・見極める)」ことであろう。そうであるから愚者の「知る」はちょうど知ってるとはいえないのと同じである。
昔者(むかし)師曠(しこう)堂に座り瑟(しつ)を鼓す。
客有り、門に倚て立つ。従者出て曰く、客何をか為(な)す、と。曰く瑟(しつ)を聴く、と。吾聞く夫子の瑟(しつ)に玄鶴降舞 鬼神来たりて聴く、と。曰く何の操(曲)ぞ。曰く文王の操也。間(しばらく)あって之又客有り。亦門に倚て立つ。従者曰く、客何をか為(な)す、と。曰く瑟(しつ)を聴く、と。吾聞く 夫子の瑟(しつ)に玄鶴降舞し鬼神来たりて聴く、と。曰く何の操ぞ。曰く操(そう)は即ち我未だ知らずや。二客皆師曠(しこう)の瑟に妙なることを知る。然れども之を要するに一客は瑟を知り一客は瑟を知らずなり。
昔、師曠〈しこう(前609〜前527)中国春秋時代の晋の平公に仕えた楽人。字は子野。盲であったが琴の名手〉が部屋に座り瑟(おおごと)を演奏していると、一人の客が門の傍に立っていた。従者が出て「何をしているのですか」と尋ねた。客は「瑟(おおごと)の演奏を聴いているのです。私が先生の瑟を聞いていると黒い鶴が舞い降り、鬼神が来て聞いてします」と言った。「何の曲ですか」と従者が問うと、「文王の操 (琴の曲名)です」と答えた。
しばらくして又客があった。また門のそばに立っている。従者が「なにをしているのですか」と聞くと客は「私が先生の瑟を聞いていると黒い鶴が舞い降り、鬼神が来て聞いています」と言った。「何の曲ですか」と従者が問うと、「曲名はまだ知りません」と答えた。客は二人とも師曠の演奏する瑟が絶妙なのを知っている(理解している)。しかしこの例を要約すると、一人の客は瑟を知り(が分かり)、もう一人は瑟を知っていないと言える。
財津子壁に知足二字を壁榜(へきぼう)し、自ら箴とす。賢坦(けんたん)小串子之が解を為す。噫(ああ)、財津子蓋し此に見る所有りや。将に此に思ふこと有るべしか。
戝津氏は壁に「知足」の二字を掲げて、自らの箴言としている。女(むすめ)婿の小串子(小串政俊の妻は財津永昌=政幸・新兵衛・和左衛門の娘・也津)がその解釈をした。ああ、財津氏はこの言葉に思うところがあるのだろうか。まさしくこの言葉に思うことがあったのだろう。
人の陋巷(ろうこう)に在る 蔬食菜羹(そしょくさいこう)と雖も未だ嘗て飽かざるはなし。布衣韋帯(ふいいたい)と雖も之に居り悪(にく)まず。而て傲然と自ずから以て足れりと為す。
是所謂(いわゆる)孩堤(がいてい)の童馬を知り、庸愚(ようぐ)の人剣を知り、倚門の客瑟(しつ)を知るなり。
人が狭くむさくるしい町に住み、粗食であっても飽くことがない。粗末な着物しか着れない身分であっても恨まない。誇り高くこういうあり方に満足する。これはいわばに二、三才の子どもが馬を識別し、愚か者が剣を識別し、門のそばで瑟を聞いていた客が師曠(しこう)の瑟の音色素晴らしいと知っているレベルと同じだ。
一旦金紫(きんし)を前に引き、声色富貴 後を推さば澹然(たんぜん)と心を動さざることを安(いずくん)ぞ得んか。
千賞は左に在れども盲の如く、美褒は右に在れども聾の如し。
能(よく)幾人有るか。是に於いて従容(しょうよう)として富貴の岐に於いて趨らず、
義にこれ与(とも)に比(した)しむ【『論語』里仁第四】。謂ふべし 足れることを知れる者なりと。
ひとたび富貴をちらつかされ、甘い言葉で富と地位を後押しされたら平然として心を動かされないようになることがどうしてなかろうか。
右に多くの恩賞あっても目もくれず、左に美しいものや栄誉があっても耳に入らないような人は何人いるだろうか。
そういう場でゆったりとして岐路で富貴ほうには走らない。義に適っているか否かをみて、義に叶っていることにだけ従う。このような人を「足れることを知る者」というべきである。
天下大なりと雖ども足れることを知れるより富めるは莫し。
秦楚の富も猶饜(あか)ざること有り。
故に日夜黽勉(びんべん)として合従連衡 之を力(つと)む。
苟も足れることを知る(は)則ち之を観て 将に何物と為(す)るや。
故に知れるに於いて真に知ること有らば 則ち将に秦楚の富を介視せんとす。
苟(いやしく)も 能(よく)秦楚の富を介視せば一大丈夫と謂うべし。
天下は大きいといっても足ることを知るより豊かなことはない。
富んだ秦楚の国にも飽き足らないことがある。
そうであるから日夜せっせと合従連衡に励み努め、領土を増やそうとする。
かりにも足るとことを知ることからみればこの様子を何とみなすだろうか。
従って知るということにおいて本当に知っているのであれば、そこで秦楚の富を度外視する。
まことに秦楚の富を度外視できるようであれば立派な人物だといえる。
財津子蓋し此において見る所有るか。将に此に思い有るべし。
予其の意を美なりとして以て云(ここに)贅とすと。
戝津氏はもしやこの点に見るところがあったのか。まさにこの点に思うところがあったのだろう。
私はそのこころを立派に思い、ここに記すことにした。