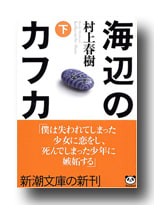フェルマーの最終定理―ピュタゴラスに始まり、ワイルズが証明するまで
サイモン シン (著)
価格: ¥2,415 (税込)
単行本: 397 p ; サイズ(cm): 19 x 13
出版社: 新潮社 ; ISBN: 4105393014 ; (2000/01)
3以上の自然数nに対してX^n+Y^n=Z^nを満たすような自然数X、Y、Zはない。
「私はこの命題の真に驚くべき証明をもっているが、余白が狭すぎるのでここに記すことはできない」。
というある意味、非常に意地悪な書置きを残した17世紀の数学者「ピエール・ド・フェルマー」
この一見ピュタゴラスの定理のような「単純」な定理がその後300年もの間、日本人を含む世界中の数学者を巻き込む「最大の謎」になろうとは!
という話ですが、とてつもなく面白い。数学が苦手な方でも、この困難と栄光の物語に感動を覚えることでしょう。
アンドリュー・ワイルズがどういうふうにこの「超難問」を証明できたかというと、誤解を恐れずに単純化すれば(できっこないのですが)・・・
ワイルズは「楕円方程式」の研究者になった。
「楕円方程式」は「モジュラー形式」に関係するという予想があった・・・「谷山=志村予想」
ゲルハルト・フライは「谷山=志村予想」を証明することは、フェルマーの最終定理の証明になると主張した。
(1)もしも谷山=志村予想が証明されれば、すべての楕円方程式はモジュラーでなければならない。
(2)もしもすべての楕円方程式がモジュラーなら、フライの楕円方程式は存在し得ない。
(3)フライの楕円方程式は存在しなければ、フェルマーの方程式は解をもたない。
(4)ゆえに、フェルマーの最終定理は成り立つ!
しかし、世界の数学者の絶対多数は「谷山=志村予想」は証明できないと考えていた。
アンドリュー・ワイルズはこの予想を証明できると考えた(無謀な)ひとりだった。
ワイルズはそのために、19世紀に決闘で命を落した仏のガロアの生み出した「ガロア群」を利用した。
そして(まだ新しい)「コリヴァギン=フラッハ法」を適用して、ついに「谷山=志村予想」を証明した。
「これで終わりにしたいと思います」といって世紀の証明「フェルマーの最終定理」を証明したワイルズであったが、数ヵ月後、欠陥が発見された。ワイルズのすごいところは(これまでも十分凄い)この欠陥の修正に不屈の闘志を見せたこと。
それだけでは不十分だった「岩澤理論」と、またそれだけでは不十分だった「コリヴァギン=フラッハ法」を相互に補完しあうことで完璧にしたワイルズは、真に「フェルマーの最終定理」を証明した。(ホント強引)
17世紀の天才数学者フェルマーのだした超難問を証明するには、文字通り古今東西の数学者たちの「先駆」があったからです。そしてそれを不断の努力で「優雅に」結びつけたのがアンドリュー・ワイルズだったのです。
「大事なのは、どれだけ考え抜けるかです。(略)長時間とてつもない集中力で問題に向わなければならない。(略)ただそれだけを考えるのです。それから集中を解く。すると、ふっとリラックスした瞬間が訪れます。そのとき潜在意識が働いて、新しい洞察が得られるのです」
これはもう仏教でいう「他力」のことですよね。
数学という縁遠い分野ですが、小川洋子さんの「博士の愛した数式」を読めばこの「数」という神に愛を感じるのも、あながち理解できないことではないと思います。
素人の我々には一見無益だと思えることでも、その舞台裏にはすばらしいドラマが隠されているという好例です。

















 デザインは日常の未知化だ、というのである。
デザインは日常の未知化だ、というのである。