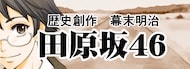占星術では、ようやく土星が天秤座から抜けたようで、急激にテンション上がってまいりました。
やー2年間長かったね。まったくもう、土星と共にウチに来たのが、大塚美容の連載の話で
本当に土星の支配下よ。精神修業になったわ。
得た答は1つ。「人生、たとえカスだと言われようが楽しんだが勝ち!」
もともとエピキュリアンの天秤座だもんよ。お誕生月ですよね。
さー本領発揮しようぜぇ!
ブラシの問題。
しかし、ここで「やはりダメだ」と負けてしまっては、システムやソフトに投資した意味がありません。
ガンガレ、デジタル。
というわけで、
ブラシを自作してみる事にします。
かなり、細かい調整も可能になっていますので、「筆作り」に凝り出したら、
それはそれで一生の道ができてしまいそうです。
カスタムブラシ道という、奥の細道。
でもここでは、大目的であるのは、ブラシを完璧に作る事ではなくて、
「そこそこのブラシでも、アナログ水彩表現ができたら良し」なんで、忘れずに。
とりあえず、初心者の私でも細道に入らずすむように、
最初から用意されている素材で作ってみました。手順は以下です。
別窓用サムネ↓

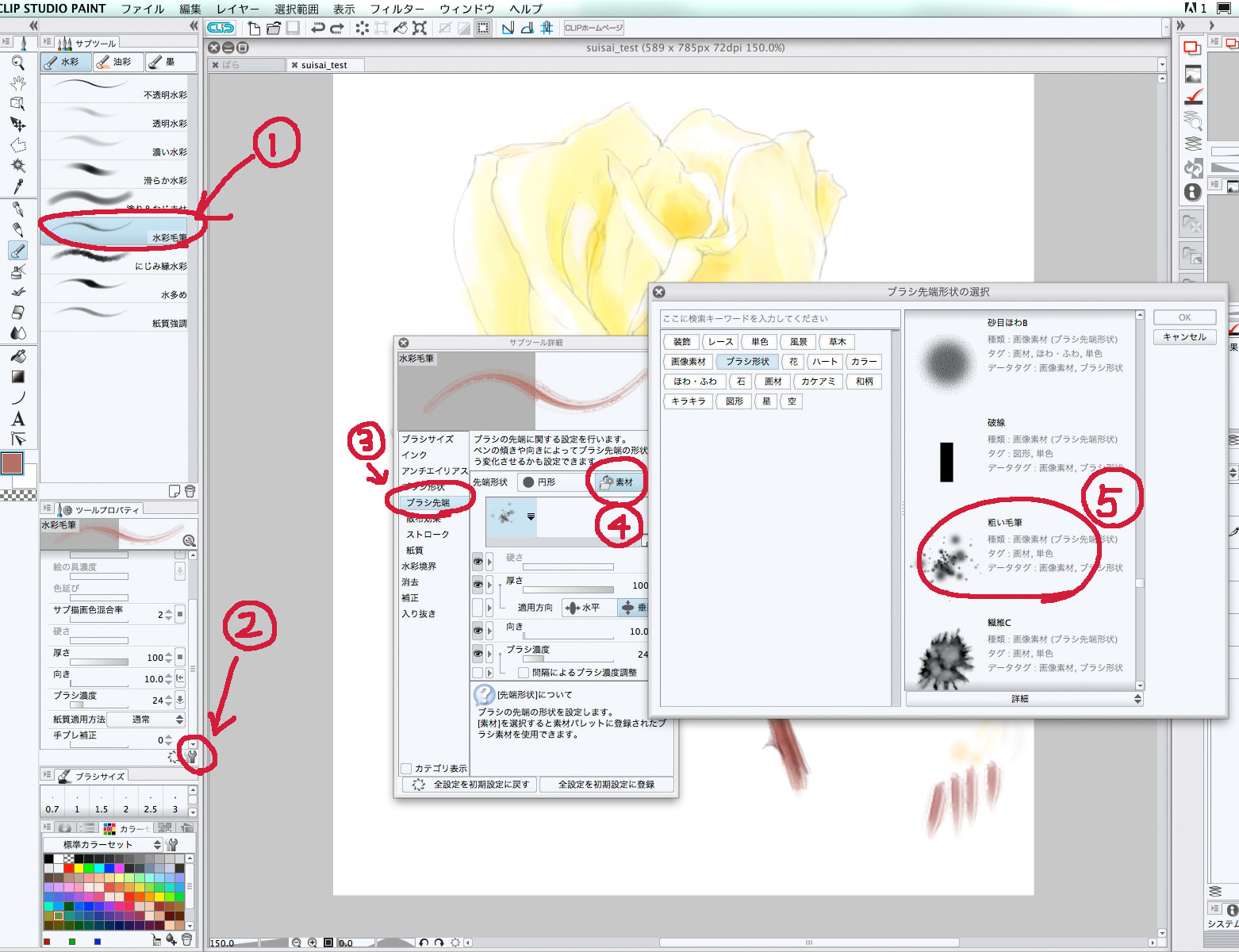
1. 筆のツールボックスにある「水彩毛筆」を選択します。
2. 「ツールプロパティ」の右下にある、詳細設定アイコンをクリック
3.「サブツール詳細」のウィンドウが開きますので
4.「先端形状」の方を選択して、「ブラシ先端形状」を選びます。
5.「ブラシ形状」から、「粗い毛筆」を選択。OKをクリックしておわり。
まあ、あとはこれで微調整をしつつやるしか…

右下に試しております。まあこんなもんか、今はというかんじ。
陰影もちょっと塗り重ねてみました。
CGでは、重ねぬリで立体を出す時、
「同じ色をスポイドで取って濃く」とか…レイヤー乗算で同じ色を重ねたりしますが
私はアナログ水彩では、「紫色」の薄いものを影として使うのが好きです。
影を出す方法には3通りあります。
1つは同一色の濃淡。
1つは色相を変えて、黄>赤>青 ←黄色が淡い方 補色を混ぜたり重ねたりとか
カンでやるんでなかなか表現しにくいです。すみません。
もう一つ、グレーや黒を乗せる、混ぜるというのがありますけど
これ、汚くなりがちなんですよね…
19世紀の画家さんはどうも、黒でなくて紫を使っていたようなので
真似してたり。
まあこのへんは好き勝手に感覚的に選んでいいと思います。
それから、「全体色」「色の分散」
今回、赤茶色で茎を塗ってますが
これのごくごくごく、薄い色を、花の部分にもちょっとだけ乗せるんです。
いや、別にそんな…光の当たる部分に乗せんでもいいので…
赤茶の薄い色=オレンジ色と思って下さい。
こうすると、全体的な統一感が生まれ、いーかんじ味が出る
と、思います。
今回はここまでね。
やー2年間長かったね。まったくもう、土星と共にウチに来たのが、大塚美容の連載の話で
本当に土星の支配下よ。精神修業になったわ。
得た答は1つ。「人生、たとえカスだと言われようが楽しんだが勝ち!」
もともとエピキュリアンの天秤座だもんよ。お誕生月ですよね。
さー本領発揮しようぜぇ!
ブラシの問題。
しかし、ここで「やはりダメだ」と負けてしまっては、システムやソフトに投資した意味がありません。
ガンガレ、デジタル。
というわけで、
ブラシを自作してみる事にします。
かなり、細かい調整も可能になっていますので、「筆作り」に凝り出したら、
それはそれで一生の道ができてしまいそうです。
カスタムブラシ道という、奥の細道。
でもここでは、大目的であるのは、ブラシを完璧に作る事ではなくて、
「そこそこのブラシでも、アナログ水彩表現ができたら良し」なんで、忘れずに。
とりあえず、初心者の私でも細道に入らずすむように、
最初から用意されている素材で作ってみました。手順は以下です。
別窓用サムネ↓

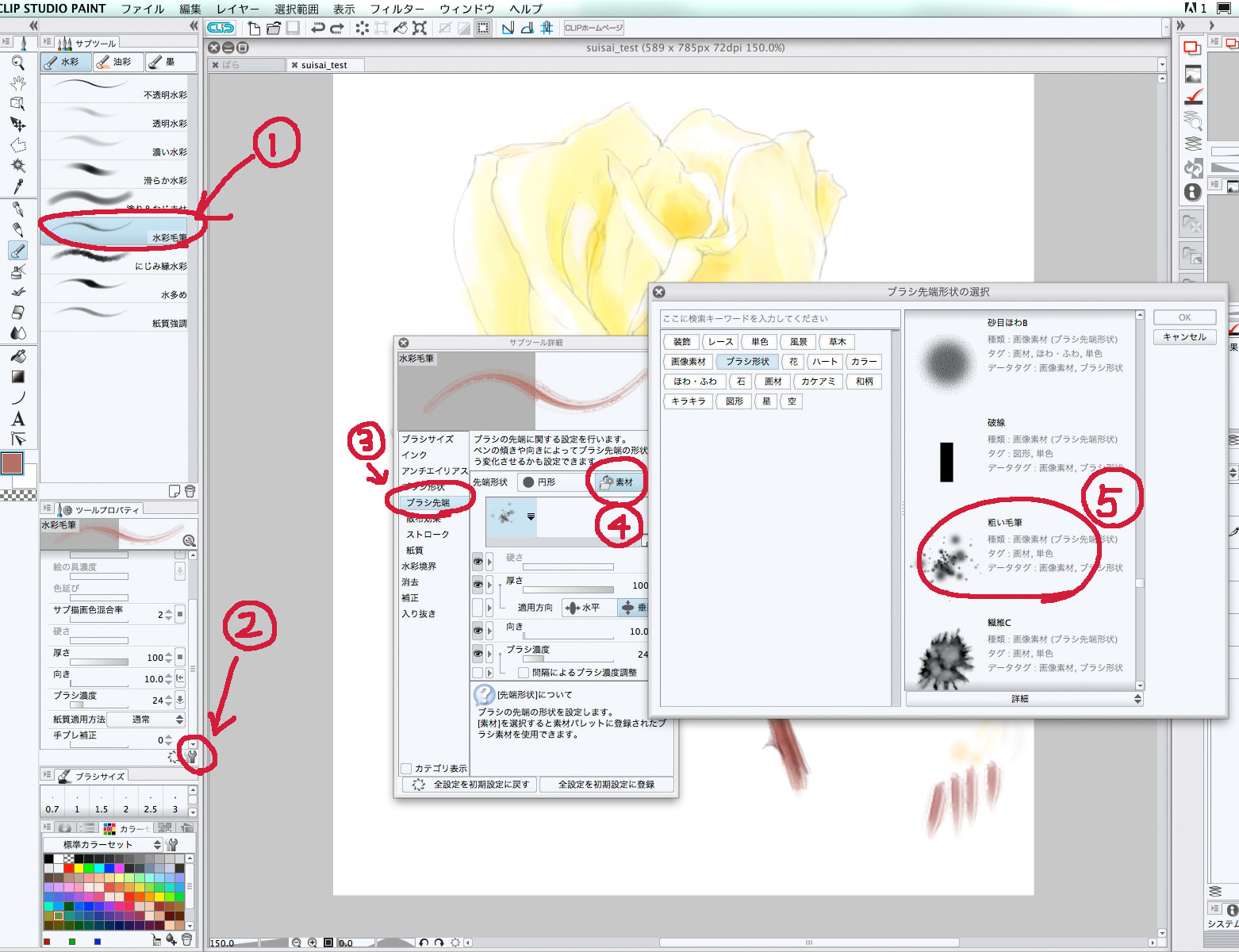
1. 筆のツールボックスにある「水彩毛筆」を選択します。
2. 「ツールプロパティ」の右下にある、詳細設定アイコンをクリック
3.「サブツール詳細」のウィンドウが開きますので
4.「先端形状」の方を選択して、「ブラシ先端形状」を選びます。
5.「ブラシ形状」から、「粗い毛筆」を選択。OKをクリックしておわり。
まあ、あとはこれで微調整をしつつやるしか…

右下に試しております。まあこんなもんか、今はというかんじ。
陰影もちょっと塗り重ねてみました。
CGでは、重ねぬリで立体を出す時、
「同じ色をスポイドで取って濃く」とか…レイヤー乗算で同じ色を重ねたりしますが
私はアナログ水彩では、「紫色」の薄いものを影として使うのが好きです。
影を出す方法には3通りあります。
1つは同一色の濃淡。
1つは色相を変えて、黄>赤>青 ←黄色が淡い方 補色を混ぜたり重ねたりとか
カンでやるんでなかなか表現しにくいです。すみません。
もう一つ、グレーや黒を乗せる、混ぜるというのがありますけど
これ、汚くなりがちなんですよね…
19世紀の画家さんはどうも、黒でなくて紫を使っていたようなので
真似してたり。
まあこのへんは好き勝手に感覚的に選んでいいと思います。
それから、「全体色」「色の分散」
今回、赤茶色で茎を塗ってますが
これのごくごくごく、薄い色を、花の部分にもちょっとだけ乗せるんです。
いや、別にそんな…光の当たる部分に乗せんでもいいので…
赤茶の薄い色=オレンジ色と思って下さい。
こうすると、全体的な統一感が生まれ、いーかんじ味が出る
と、思います。
今回はここまでね。