スマホで小説を読まれるなら If you read a novel in the smartphone
吾十有五而志于学(孔子・論語)に適い、中学卒業を期に香取飛行場から蒸気機関車で上京。
「私とは何か」という述語探しのオブセッションの果てに、八月の京都駅頭で覚醒する物語。
著者30代はこの作品にかかりっきり、10年かかった渾身の一作。 228,500文字・四百字詰め原稿用紙換算571枚・PDF261枚。


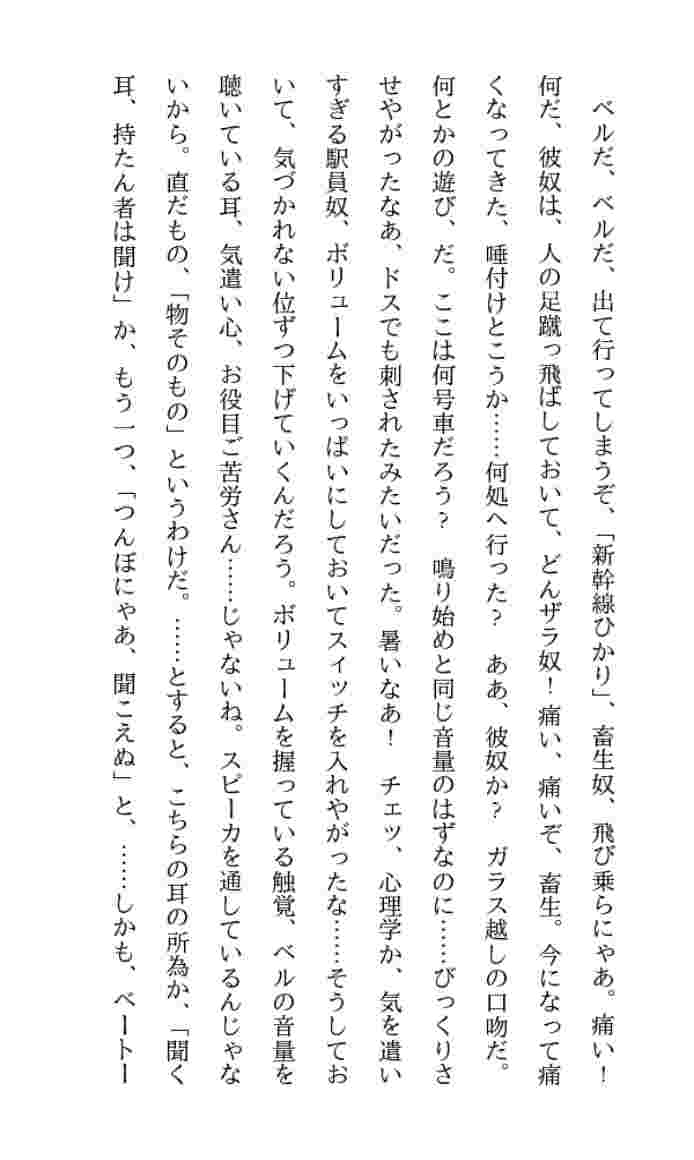
ベルだ、ベルだ、出て行ってしまうぞ、「新幹線ひかり」、畜生奴、飛び乗らにゃあ。痛い! 何だ、彼奴は、人の足蹴っ飛ばしておいて、どんザラ奴! 痛い、痛いぞ、畜生。今になって痛くなってきた、唾付けとこうか……何処へ行った? ああ、彼奴か? ガラス越しの口吻だ。何とかの遊び、だ。ここは何号車だろう? 鳴り始めと同じ音量のはずなのに……びっくりさせやがったなあ、ドスでも刺されたみたいだった。暑いなあ! チェッ、心理学か、気を遣いすぎる駅員奴、ボリュームをいっぱいにしておいてスィッチを入れやがったな……そうしておいて、気づかれない位ずつ下げていくんだろう。ボリュームを握っている触覚、ベルの音量を聴いている耳、気遣い心、お役目ご苦労さん……じゃないね。スピーカを通しているんじゃないから。直だもの、「物そのもの」というわけだ。……とすると、こちらの耳の所為か、「聞く耳、持たん者は聞け」か、もう一つ、「つんぼにゃあ、聞こえぬ」と、……しかも、ベートーベェンは聴いた、と……。混んでいるなぁ、ここは……ううん、いい匂い! コーヒーも欲しいけど腹も……。何時だろうなあ……昼飯だなあ。先に食っとくか……でも、いっぱいだろうなあ……後にしようか。四号車なのか。皆座って……る、ああ、あそこ二つとも。ちょうどいいや、後ろ向きだ、おっ、危ない。揺れる、揺れる、こん畜生! うん? 今、何て言った? ……「畜生!」運転手に言ったつもりなのか、この列車に言ったのか。おっと又々。十返舎一九は狂歌を吟じながらの二人連れを東海道に泳がせ、もちろん二本足だったが……私はここに座って……最後の列の……Dか、じゃないE席だ、ああ、いい席だ、お誂えだ、一人になれる……
肉が痙攣したのを機に、針を刺されたような激痛が走り、ガバッと跳ね起きようとしたが……身動きも出来ない重さで押さえつけられ、潰されそうになっている自分に、まるで過去を一巡りしてきたかのように気がついた。ウンウン唸ってその重いものを跳ね除けようとするのだが、手も足も硬直したみたいに意のままにならない。うなされてでもいたのだろうか。切れ切れの呻き声のような谺が記憶の網に引っ掛かって震えていた。それは有るとも無いともはっきりしないほんの幽かな想い出のよう……しかし、その更に奥まったところには、自分が気のつく前の、夢の記憶のような暗黒の大陸が黒々と横たわっているのが感じられたし、意識の轍を見失う遙か彼方に燎原の火の、残り火のようなものがチョロチョロと燃えているのがはっきり望めた。しかし、大腿部の破けるような痛みと胸から肩にかけての引きつるような痛みに加えて軀の何処か、場所のはっきりしない遠方の地、これと名指せない多義的な地点、心の内科的辺境に、何か尋常とは異なった特殊な痛み、というか……感覚、いや、自我の放棄され尽くした後の、為されるがままの、決壊中の堤防の心地。形式から内容の抜け出してしまった後の、蝉の抜け殻のような半透明な白々しさがあって、死に行く者が手の届かない所へ行ってしまったりこの世へと再び上がって来たりしているかのように、ある境界を彷徨っていた。
蜥蜴の緑や紫に入り交じる切り離された尻尾が時々引きつりを起こしてピクピクッと生き返るように、痛みが暗黒の大陸と燎原の火の方へのめり込みそうな私を目の前の現実へと引き戻していた。相手を抱き込む仕儀になっていた私の両手は痩せ猫の背を、濡れたその背を撫でたときの感覚……そのゾオッとする気味悪さを離すに離せぬままであった。痛みは鉄の爪でも立てられたよう……少しでも軀を動かせば、動かしただけ食い込み……そこから血がゾロゾロと垂れ流れ……既に、私は血の海に横たわっていた。ベットリした血の流れがゆっくりと暖かい臭気を発して鼻を抜けていった。そうして、ついに、私が目にしたのは……ピューマのような……あるいは豹のような、いや、虎のようにしなやかな、そう、ゆったりと構えていて虎かもしれない。何かそういう猫の縁者、猫科の動物。……その虎とおぼしきものがしっかと私の上に覆い被さり、鋼の爪を胸の上に突き立て、そのしっとりとした三叉の口は胃の辺りの臭いを嗅ぎながら鼻をピクピク……させて……狙っていた、が……? ……風がふっと切れたかのように、ふと、私はある疑問に取り付かれてしまった。……そんなはずはないと、よく見れば見るほど疑問であったものは徐々に確信に変わらざるを得なかった。そ、そんなはずはないのだが、……その虎とおぼしきものの仕草や視線の置き具合が……どことなく……この私自身に似ているのを驚き呆れながら発見したのだ。な、なんということだ……。
枕辺にいた女達はどうしたのだろうと思って、引き攣るような痛みを引き出さないように、そろりそろりと眼球だけずらして室内を見回すと……散乱した家具があるだけで、女達の姿は見当たらず、気配もありゃあしない……、ただ、彼女達のお喋りの二言三言が心を絞るように思い出された。……どうしたんだろう、助けを求めに行ってくれたのだろうか、この私の陥った奇妙な窮地のために。……それとも、何処か安全なところに逃げ延びてほっと深いため息と共に恐怖に震えているのだろうか……、あるいは全然事を知らずに……あるいは知ろうともしないで、あるいは故意に忘却して……、すでに熟睡しているのか、他の部屋で! というのも、私を呼ぶ声は何処にもないのだ。まるでみんな眠り込んでいるみたいだ。私の他は。それはまるで真夜中に、突然目を覚ましてしまった子供のようだ。その子はおそるおそる夜の帳の中に目を凝らすけど母親の姿は見当たらない。闇が物に侵入し、物はその個物性を奪われている。羊羹のような闇が辺りを固めている。そのねっとり固まった物を、懸命に手足をばたつかせてほぐしにかかる、泣きもせずに。しかし、この見離され絞り出されている孤独の場は馴染みの病室みたいだ。そお、孤独は、私には馴染みの領域だ。相対の場に晒されることこそ危険地帯なのだ。そこは物から物へ、ただ、彷徨っているだけの、修羅の妄執の堕地獄だし、存在の保全のために虚構に継ぐ虚構を仕掛ける世界だ。その危険地帯から逃れてもその危険を削ぐことにはならない。その危険を見据えて、それとは別に私の孤独を創るのだ。そぉ、懐かしさが込み上げる……おお、抽象の暗室よ!
……ムッとするような暑気の中、海へ行く道は砂利の道、真夏の太陽が照り付け、低い防砂林の中をくねくねと白い道がまるで過去を訪ねるときの道筋のように、あるときは濃い松の林に消え、突然直線となって視界に現れたりしていた。一〇分も自転車で走ると、やがて防砂林の向こうから太平洋の海の音が幽かに聞こえてくる。走るにつれてその海の音は汗ばんだ皮膚を通して体中に響き合う。砂利の軋みや草藪のキリギリスの鳴き声と共に。防砂林の松は音もなく立ち居並び……太陽が照り付ける。その中をくねくねと白い道が続く。防砂林が切れると、茫々と飛び込んでくる海。砂丘の向こうに打ち寄せる波の白い波頭、きらめく波頭。潮を含んだ強い風。すると、軀の中から発散される生の息吹。茫々たる九十九里の浜に、見渡す限りの海。そして積乱雲と蒼空の丸い海。描線の定かでない水平線。打ち寄せるあまたの波。潮含みの強い風。盛夏の太陽がレンズと化した中空を切り裂いて照り付ける。中空を爆破しそうな生の息吹。海、そして生、生。……ああ、これも過去の生だ……。
その間にも、五感は死につつあり知覚器官は囚われの恍惚のような痺れを引き起こしていたが……その中から一つの懸念が浮上し、見ている間にそれは恐怖に様変わりしていった。それは視界を遮る入道雲のように、これ見よがしに起き上がってきた。その雲に立ち向かうには余りにも自分の力の微弱なのを痛感せざるを得なかった。
(以下はAmazonでご覧ください)
参考

Book Review 情緒の力業 高野 義博著
東洋大学文学部教授、校友会副会長 針生 清人
世の識者は、屡々「哲学が今こそ必要だ」という。それは現代社会に「哲学」が欠如しているからだという。しかし他方で、『ソフィーの世界』の爆発的な売れ行きを見て、「哲学が流行している」ともいわれている。しかし哲学は他者に要求されて始めるものでも、流行となるようなものでもあるまい。
「生きるに値する人生とは何か」、「世界とは何か」、「かく生き、かく問う私とは何か」を問うことから始まるのが哲学の元来だとすれば、各自が内発的に「哲学する」ことにこそ意義があるのであって、本書はその好個の例だといえる。前述の問いは、概念が先か個物が先かの如き抽象的な形式で問いを立て、それに対して客観的な答を用意して教説する講壇哲学者とは異なって、問わずにおれぬが故に問うところのものであり、真に「哲学する」ことを示す重味が本書にはある。そうであれば、本書の内容を要約して紹介するよりは、本書が成立した所以のことを紹介した方がより意義があると思われる。
高野義博氏は、ヤスパースの「暗号について」を卒業論文(百枚)として提出した(主査故飯島宗享教授)。すでにロマン派の文学は自然と歴史を神の暗号とみなしていたが、ヤスパースも哲学と宗教の歴史、超越者との出会いという人類の最も重要な経験がいわば暗号で書かれていると主唱し、自己の哲学的な経験こそがこの暗号を解読し得るのであって、そうでない者にとっては暗号で書かれている深部はないかのようである。いうならば科学的、合理的な目には歴史の表層しか見えぬということである。この問題を取り上げていた著者には、理性を万能とする知的な、科学的な客観主義への懐疑が既にあり、「私とは何か」の問いの暗号解読を試みていた。このことに関わって、校庭に遊ぶ友人達に突如、意識が集中して、「存在の事実として、客観的対象として、そこに彼等が居る事実を認めさせられた」という中学生時代の経験を卒論に記述していた。これが著者の哲学することの原点であったが、硬直した客観主義に批判的な実存主義者であった指導教授の故飯島教授は、後に、『気分の哲学―失われた想像力を求めて―』という著書に於いて著者のこの「経験」を引用されたのである。このことは、著者にとって卒論に記述された私的な問題であったものが、公刊、公開されたことによって社会的営為となったため、更に深くこの問題を問いつめることを不可避としたのである。その追求は30代を貫いて六百三十枚の『述語は永遠に…
』となったのであるが、そこでの結論は、「私とは何か」を問うには知的な、科学的な客観主義に基づく探求では限界があるということであり、概念ならざるものによる探求が更に進められ、本書となったのである。著者は社会人として生きながら、思索と読書と執筆に明け暮れ、「人生から三十代が抜け落ちていた」といわしめるほど、「哲学する」ものが格闘してきた軌跡を示すのが本書である。
本書の成立を支えたのは膨大なる読書量である。それは巻末に「文献一覧」として示されている。著者によると「三百冊ほどの本全てが一冊一冊有機的な繋がりを持ち、読み進む度に新たな可能性が現れ細部が強固になる異常な精神の興奮の渦中で、意図せずに、自然に、幾多の啓示を受けたかのように、帰納的に或るヴィジョンが塊となった」というものである。しかも、読了した一冊一冊について、著者の心を深く捉えたと思われる箇所を引用し、列挙している。一読書人の読書記録としても壮観である。
著者が「哲学する」ことは更に続くであろうから、本書は尚「途上にあるもの」であるが、その論述されているところは的確であり、説得的である。著者が身辺を見回し、人生の意味を問い始めたのは、中学生時代の体験を問い直すことによってである。このことについて、著者は孔子の「吾十有五而志干学」における「志学」を考える。それまで与えられた環境、習慣、伝統等にただ順応して生き、全てを「見て見ず」であった事象を初めて意識的にそれを「それ」として「そこ」に見るということによって、即有的な状態に外部世界=現実が出現し、主客分離が始まるという。このことが、「志学」の意味だという。我々は本書を読むことで、「哲学する」志学一年を始め得るといえよう。
*著者による転載(東洋大学:校友会報・第188号・P.8Book Review 平成8年7月31日発行)










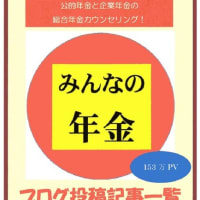






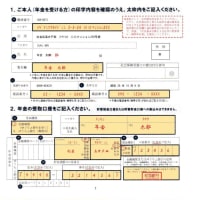

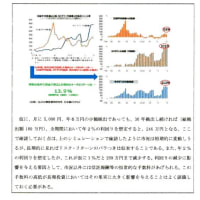
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます