アサヒカメラ1951年12月号の表紙はヴァイオリニストの巌本真理さん(1926-1979)です。

めっちゃ魅力的!女優さんみたいですね。吉岡専造(1916-2005)撮影。
1959年の松竹映画『乙女の祈り』にも出演されたそうです。
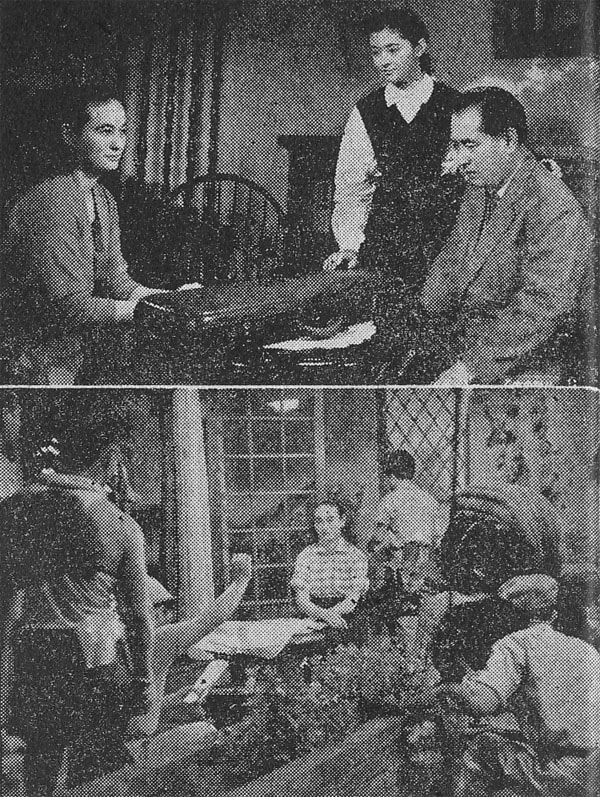
↑上の画像の真ん中は主役の鰐淵晴子さん。
そんな巌本真理さんですが、ヴァイオリニストを目指した当初はけっこう屈折していたようです。『藝術新潮』1959年8月号より。
-----------------
「真理は世間でいわれるような天才とは思っていない。しかし、異常な才能をもっているということは親馬鹿でなくともいえる」。これは今から十年ほど前、彼女の父親が語ったことばである。その異常な才能というのはどんなあらわれ方をしたのだろうか。やはり父親の言葉だが、四歳ごろから、ラジオのヴァイオリン音楽に興味をもち、メロディをすぐ覚えてしまう。そしてやや長じてからは指づかいの批判をした。
両親は天才....はともかくとして娘の才能を認め、これをなんとか伸ばしてみようとしたことはたしかだ。それは父親自身が、ヴァイオリンを志し、家庭の反対にあって断念したからだともいわれているが、父親のその方針は彼女の記憶のなかに生きている。数え年六歳で小野アンナ(1879-1979)のもとへ入門させられた時、父親からの「諏訪根自子みたいになるんだよ」という一句を今日でも印象深く覚えている。それは諏訪が小野門下の先輩として、すでに"天才少女"という形容詞で紹介され、今日でいえばマスコミの世界で華やかに活動していたからだろう。エルマンやジンバリストの演奏会にも連れてゆかれた。
このような両親の教育を彼女自身は相反する心理で受けとめていた。一つは「諏訪根自子みたいになるのは大変だぞ」「なるためには、今でさえいやでたまらない練習をこれ以上やらなければならない」という嫌悪感であり、もう一つは「諏訪根自子みたいになってみたいな」といういわば少女的なあこがれである。このあこがれは一般的な少女のスター崇拝熱の一種にはちがいない。だが彼女の場合にはもう一つ別な感情がからみつく。それは混血児の悲しみと、それに対する猛烈な反発心である。今にみろ、という感情だ。
後年、バスのなかで女性が彼女に挨拶をした。「ざまあみろ」と思ったそうである。その女性は小学校で彼女をもっとも苦しめた同級生だったからだという。ともかく小学校は三年で中退した。病気もあってか、ちょっと想像に難いような激しい圧迫(同級生からの)に耐えられなくなったためでもある。学校へ行かれなくなった時、ヴァイオリンを選ぶ決心をした。「ヴァイオリンは好きではない。しかし学校へ行くよりはよい」という消極的な意味であったらしい。
昭和十二年、第六回毎日音楽コンクールに第一位入賞。決心はここから積極的になる。当然うれしい。それと、友だちをみかえすことができたという高揚した感情が方向を決めさせたのだといえる。"絶対負けられない"というその反発心は今日まで支えになっている。
-----------------
。。。どこまでが真実なのかは不明ですが、とにかく巌本さんはすごく負けず嫌いだったんですね!自分はどっちかというと負けず好きなので嫌いになるべく、さっそく巌本真理弦楽四重奏団のCD「日本の弦楽四重奏曲」を購入しました。興味深い曲ばかり。

一回通して聴いてみただけで、かなり根性入っている演奏であることがわかりました。さらに繰り返しきいていきたいです!

↑ 藝術新潮1959年2月号より









