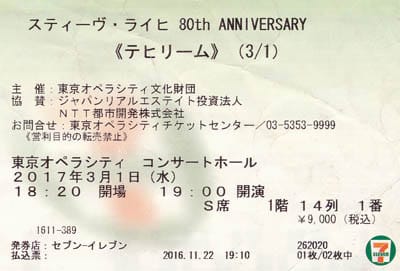ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第8番は15曲ある四重奏曲のド真ん中でしかも最高傑作との評判ですよね。
でも一方、交響曲第5番と一緒で、肩の力入りすぎ、作り込まれすぎって感じで、いつもの直感的モーツァルトライクな天才インスピレーション炸裂しまくりの音楽とは言えないのでは?って勝手に一段ランク下の曲と思っていました。
ところが何度も何気に聴いているうち、むしろ、いつもは巧みに隠していた作曲者の本心が一番表面化しちゃた音楽に聞こえ始めました。最終楽章ラルゴの88小節のあいだなんて、タコ弱音を吐いてしくしく泣きっぱなし。かわいそう。
こんなふうに作曲者個人の思いを暴露した作品であるとの評価がある一方、「ファシズムと戦争の犠牲者の思い出」に捧げられているんですが、今まで別に不思議に思っていませんでした。
全音楽譜出版社のスコアの解説には「四重奏曲の仕事は映画『五日五夜』の音楽(のちに作品111として発表)と平衡してドレスデンで(?)すすめられた。作品の主題は作曲者の証言によると、映画を撮影した印象や、町の人たちがファシズムと戦争の時代について語っていた話をもとに生まれたものである」とあるし、音楽之友社作曲家別名曲解説ライブラリーにもやはり「映画のなかの戦争の物語に感動してこの曲を着想し、3日間で作曲を完成した」とあります。
この『五日五夜』という映画、第二次世界大戦中のドレスデン爆撃の最中に、苦労して美術品を救い出す様を描いたもの(音楽之友社作曲家・人と作品シリーズ223ページ)らしいのですが、この四重奏曲はそんな安っぽいものと関係あるって感じが全くしないし、なにしろDSCH音型ドバドバ出まくりなのに変な話ですよね?
『わが父ショスタコーヴィチ』に重要なことが書いてありました。
娘ガリーナの言葉:「あれは1960年、ジューコフスカの別荘のことでした。父が二階から降りてくると、椅子に腰をおろして言ったのです。『僕自身を記念する作品を、たった今書き上げたよ。』..(中略)..《第8番》は演奏されるとすぐ、たいへんな評判を呼びました。するとたちまち、献辞を変更しろといういつもの圧力が始まったのです。父は譲歩せざるを得ませんでした。」
ショスタコーヴィチ、ウソ言わされてるんやん。本人も「ファシズムの犠牲者」なら結局は矛盾してないのかもしれないけど、ほんま、おそロシア!