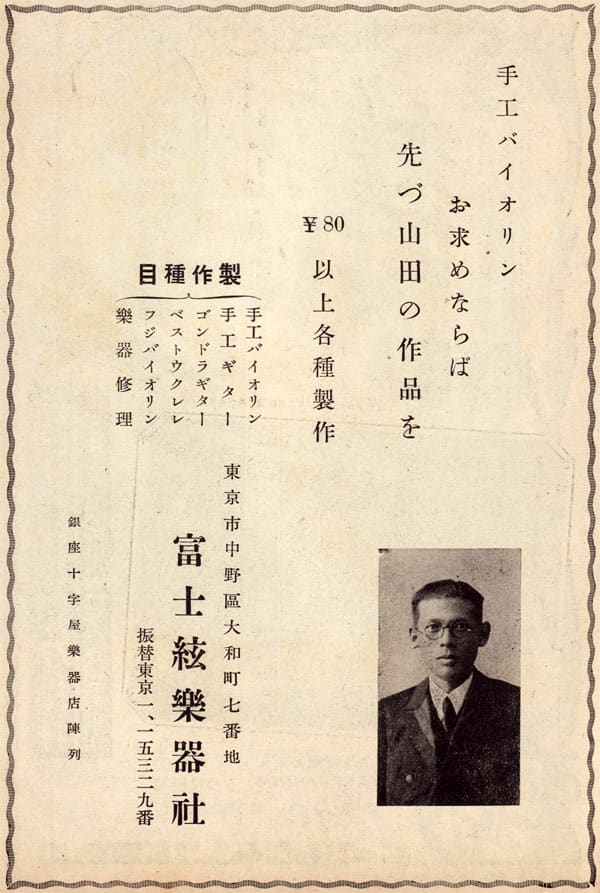アサヒグラフ昭和9年11月21日号から日本楽器浜松工場におけるピアノ製造工程です。

↑ ピアノの鋼線の張力は、約75キログラムの目方を支えるに足る。それが約220本張ってあるのだから、その全体の張力は大変なものだ。だからその絃を支えるためにこんな厳めしい機械によってまず鉄骨を作らなければならない。


↑ ピアノの製造で、一番手数のかかるのは鍵盤から絃を打つ間の機械つまりアクションの製作である。小指の先の細かいものを一々削ったり、磨いたり、いやもう見ているだけでウンザリするような細かい仕事である。

↑ そして今一つピアノの製作で重要なことは木材の処理である。一台のピアノに使用してある木材の種類だけでも20種類に余るが、その木材を天然乾燥、人工乾燥等によって均一な乾燥度を保たせるほか、ベニア板として使用される部分がまた非常にたくさんある。写真はそのベニア板製造用の圧搾機だが水圧120ポンドの強力なものである。

↑ ここまで来るとだいぶピアノらしくなってくるが、絃を張る仕事は見ていてもなかなか気持ちがいいものだ。
鍵盤をたたいてから内部に張ってある絃がポーンと鳴るだけの仕掛けに、金属品が20種、木片が23種、布革片が14種、合計57種の細かい部分から出来上がっている。しかも、それが人間の指先のように自由自在に、滑らかに動くことが必要な上、標準型88の鍵盤が全部均等に揃っていなければならないのだから、その細かい各部分の仕事は実際大変なものだ。。
。。。昭和9年というと今から80年も前ですが、日本人って元来手先が器用なんですね!その頃年産5000台。
オマケですが、同じ雑誌からキッコーマン醤油の広告です。「味の交響楽」。どこのオーケストラ? ↓