お正月から始まった日経新聞の連載「私の履歴書」は伊藤忠商事会長CEOの藤岡正広さん。
毎日、令和版ドラマ「あかんたれ」のような展開を見せている。明日はどうなる?!と続きが楽しみ。
だいたいお偉い人々の出世譚は、環境の良い家族に生まれ、優秀で、人脈が派手、順風満帆!なお話も多いなか!
藤岡さんは、元旦の誌面からホームレスをうらやむほどのどん底を経験する。生い立ち編では、両親の夫婦喧嘩に耳を塞ぎ、病気を克服して伊藤忠入社後すぐに、なぜかお偉方に一発カマしたれと、大先輩の過去を穿り出して、総スカンをくらってし、人が一年で終わる事務仕事を3年も4年もすることになる。はやく営業に行きたいのに。
今日の誌面では、会社の暗黙のルールになじめず、頑固に正しい主張をしまくり周りから浮まくり、正しいことが罷り通らないことが受け入れられず、お先真っ暗と落ち込んだところ。
とにかく、わかりやすく悲惨な道(我が道!)を突き進んでいく藤岡さんに、感情移入させられる。
これ、ドラマになると思う。ドラマで観てみたい。













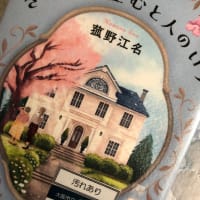






まあ簡単に言うとシナジーということで
1+1=2 だけではなく
1+1=3 という世界を
数理的に表現しようとしたもののように受け止められる。マネジメント体制にも応用可能なのはこういうことか。
重要となる焼入れ性評価に用いるTTT曲線の均一核生成モデルでの方程式の解析をPTCのMathCADで行い、熱力学と速度論の関数接合論による結果と理論式と比べn=2~3あたりが精度的にもよいとしたところなんかがとても参考になりましたね。