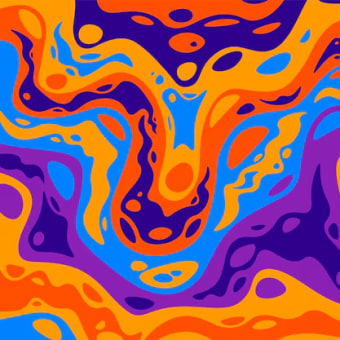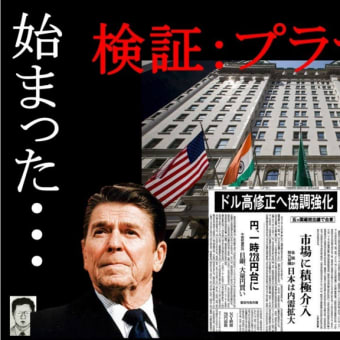台湾にきてから、殆どハードカバー本を手にしていません
記憶にあるのは
持参した、項羽と劉邦(司馬遼太郎)三巻、三国志(吉川英治)二巻or三巻?
一年前に、Amazonで手配した「日本国紀」くらいです。。
図書館に行っても、日本の書籍はありませんせんし、紀伊国屋といった日系の書店でも入手できるのは月刊誌くらいで、文藝春秋と正論、Willくらいです。
日常的に、week-dayの朝は、日本時間の朝6時から10時までは、
文化放送→ニッポン放送→虎ノ門ニュースを視聴し、夕食後は、討論やトークあるいは解説系のメジャーな動画コンテンツを視聴します。
すべてがネット媒体による発信コンテンツで、ポッドキャストであったり、ネットユーザーによる、地上波ラジオの動画配信であったり、オリジナルなネット配信動画として発信されています。
こんなことから、結果的に、文藝春秋のかなりの寄稿者や正論、Willならその殆どの寄稿者が日常的に視聴しているコンテンツでおなじみの面々であることから、この数年はほとんど月刊誌の購入はスルーしています。
+ + +
12年前に逝ったマダムkazanの実家にあった、義父(故人)の書棚にその全集が並んでいた記憶があります。
マダムも父親同様に松本清張のファンでしたので、生前は愛読していたのを記憶しており、最後の病床である虎ノ門の病棟に入院中持ち込んでいた一冊が遺品の中に入っていいたのを想像できます。
+ + +
なにはともあれ、久方ぶりのハードカバーの感触が懐かしく、かって文庫版で読んだことのある「草の陰刻」を二日掛かりで、一気に読み終えました。
不思議なことに、見田宗介(社会学者)による巻末にあるあとがきまで精読したのですから、おそらく Cover to cover の読書経験は、長い人生でこれがはじめての経験のはずです。
+ + +
四十代以降、小説系は殆どが文庫か新書判であったのは、通勤途中での読書や、自宅では横になり、あるいはベッドで臥せながらの読書が状態でしたので、ハードカバーとなるとその重量からして、ベッドでの臥せながら読みは、五分か十分が限界になります。
今回は、そのような理由から、珍しくデスクやソファーでの読みスタイルにプラス水割りの「ながら読み」で読破出来たことから、この集中エネルギーの根源のひつに、やはりアルコール燃料パワーであったことを再認識しました。
アルコールパワーにより、1972発刊の全集本(今回は一巻443ページ)ながら、清張が発信する強力なパワーを十分に堪能することを実感しました。
+ + +
以下、偶然、荷物から出てきたマダムの遺品のハードカバー本の読後感でブログ更新を考えています。