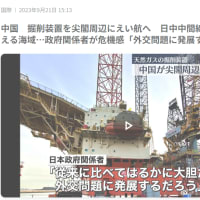▼▼▼
「バイデンが「親方日の丸」をマネし始めた…?
自由の国アメリカが、ここにきて「昭和ニッポン」そっくりになっていた!」
という記事が、現代ビジネスに掲載されています。 原文元記事リンクは本稿末のリンクカードで参照可
昭和の日本が先行してたのか? あるいは、混迷を決まる米国社会と米国政治が、自由主義経済・自由市場原理から国家主導の統制経済のような手法を選択するのかということに興味が行く話ながら、米国の二大政党には大きな政府、小さな政府という概念があることはよく知られている構図です。
つまり民主党は大きな政府、共和党は小さな政府です。
このククリで見るなら、民主党のバイデン・アメリカが、大きな政府への舵取りをしたとしても、先祖帰りか、特筆するべき内容でもないような気がします。
▼▼▼
以下は本記事の要約です。
記事は、バイデン政権が、半導体、電気自動車(EV)、バッテリー、人工知能(AI)など、戦略的な先端技術に関するすべてが、法によって予算が裏付けられる「国家主導の政策」を打ち出したことを報じています。
この政策は、かって通商産業省が主導した「昭和日本」を彷彿とさせると指摘されています。
記事は、米ブルームバーグや英フィナンシャル・タイムズ紙も同様の見出しで報じていることを紹介。
▼▼▼
昭和の通商産業省といえば、米国には"Notorious MITI" とまで罵られるほどの存在であったことは有名で、また通産官僚と通産省を題材にした、「官僚たちの夏・城山三郎」1975年新潮社の淡赤地系の表紙が目に浮かびます。
いうなればイケイケドンドン、護送船団方式式でトランジスタラジオから家電品、オートバイ、乗用車、建設機械、船舶、衣料雑貨で、米国の対日貿易赤字を膨らませ、コテウヨ、ガチ保守には、まさに、ヒロシマ・長崎の報復家のようにも見えるような側面があるほど、日本経済が気合が入った時期であったのを記憶します。
▼▼▼
今にして冷静に考えるなら、中国が2008年頃からの対米貿易を拡大させたのは、その基本モデルが昭和の日本の通産行政であったと言えます。
ですから、伊藤忠の例を取るなら、「ソウゴウショウシャ」としての経験をそのまま中国で執り行うというビジネスモデルを展開した結果、中国を太らせ、駐中国大使に伊藤忠の元社長が任命されたのも、極めて普通の展開であったといえます。
この周辺の物語は、山崎豊子著「不毛地帯」が参考になるはずです。
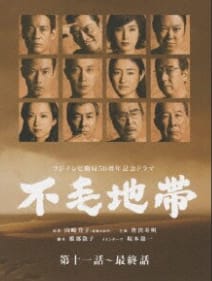
▼▼▼
ソース元リンク