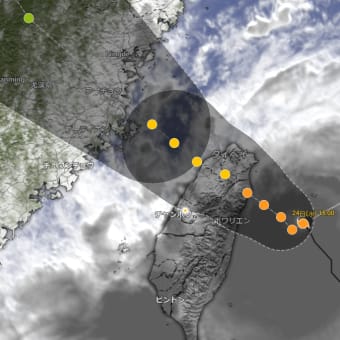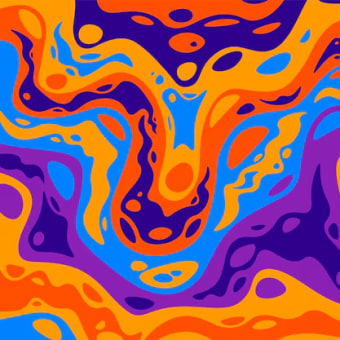▼▼▼
「失われた30年」のキーワードが、「失われた20年」から独り歩きして、この「30年」が定着し、思考にインプットされてすでに20年が経過したことを、つい印象の中で見逃している現実に気が付きます。
つまり、「失われた時間」の長さは、気が遠くなるなるほど長い時間であり、こうした社会が生まれた背景を考えざるを得ないようなシリアス感に襲われます。
▼▼▼
手っ取り早いのが、反省と、犯人探しで、その結果が、政治と税制に集約されて、現在の財務省解体デモ、4.29霞が関デモ、令和の農民一揆・首都圏デモに繋がったとみれば、大きな感慨であり、思うことが数多く浮かびます。
そんな印象で、自分的に最も気になったのが、昨日投稿した記事で紹介した、米国・NYタイムズが、一連の東京でのデモの様子を、米国で一面扱いで報道されたという内容に注目します。
▼▼▼
一連のデモは「N共朝毎」で代表される日本のオールドメディアのほとんどが、財務省に忖度して、報道をスルーしてきた現実があります。
日本には、「黒船効果」という認識が、存在していて、江戸期末期、徳川300年の安泰を壊した最初のカルチャーショックが「ぺりー(ぺルリ)の浦賀来航」で、それまでの「鎖国」が「開国」に変わり、幕末の動乱につながり、「明治」を迎えた歴史があります。
▼▼▼
今回のNYタイムズの報道の事実は、これまで財務省への忖度で、スルーを決め込んできた日本のメディアの報道スタンスを変える可能性を期待させてくれます。
政府は、1955年来「改憲ヤルヤル詐欺」を平然と行い、選挙民を騙し、愚弄してきました。
「失われた20年」だって、その起点が、1986年の中曽根首相、竹下蔵相の渡米で始まった9月のニューヨーク・プラザホテルでのG5国によるプラザ合意が起点です。
そうなると、今年9月で、事態は「失われた40年」ということになります。
40年の時間の重さを考えた時、これは、制度、政治の欠陥以外に、原因は考えられません。
このことを発信したい。