マルクス剰余価値論批判序説 その36
(1)「労働がどのようにして使用価値を増加させることができるか、ということを理解するのは、容易である。むずかしいのは、労働がどのようにして前提されたもの以上の諸交換価値をつくりだすことができるか、という点である。」(『資本論草稿集』第一巻、三八七頁)。
(2) MEW二三、九〇頁。
(3)同、六一三頁。
(4)同、六一二頁。
(5)岩井克人氏(『ヴェニスの商人の資本論』ちくま学芸文庫、七九、一〇三頁)が主張している剰余価値論は、その内実としては平田清明氏の言う「増加価値」(『社会形成の経験と概念』岩波書店、九八頁)の説明でしかない。日常的概念としての企業利潤をマルクスの剰余価値だとしてしまうのでは、マルクスの問題意識を無視することになる。マルクスは、個々の資本家の価値が増加するのは・どのようにしてなされるのかという、常識的問題を設定したのではない。新たな価値が、どのようにして産み出されるのかを、問うたのである。差異がどのようにして産み出されるのかという問いに対して、岩井氏はそこに差異があるからだと答える。差異は産み出されるのではなく、別の差異が転化するのだと言うのである。たしかに、個別資本家の価値増加の一部分の説明にはなっているが、マルクスは価値の移動を問題にしたのではない。価値が、ある所から別の所に移動するには、すでに価値の存在が前提される。交換でも盗みでも、価値の移動を行なうには、価値が存在していなければならないのである。その価値は、どのようにして産み出されたのか。価値が新たな価値を産み出す(自己増殖)とは、どのようなことなのかが問われているのである。しかし、労働力商品(労働力と貨幤との交換)を自明の前提にしておいて労働価値説を否定しようとする非論理への無自覚さは、論理的すぎるマルクスの剰余価値論の問題設定の高みにすら、届かないのである。
(6)「その純粋な形態では、商品交換は等価どうしの交換であり、したがって、価値を増やす手段ではない。」( MEW二三、一七三頁)。
(7)「剰余価値の形成、したがってまた貨帑の資本への転化は、売り手が商品をその価値よりも高く売るということによっても、また、買い手が商品をその価値よりも安く買うということによっても、説明することはできない。」(同、一七五頁)。
(8)「等価どうしが交換されるとすれば剰余価値は生まれないし、非等価どうしが交換されるとしてもやはり剰余価値は生まれない。流通または商品交換は価値を創造しない。」(同、一七七~一七八頁)。
(9)同、一七九~一八〇頁。
(10) 同、一八〇~一八一頁。
(11)「売るために買うこと、または、もっと完全に言えば、より高く売るために買うこと、G―W―‘Gは、たしかに、ただ資本の一つの種類だけに、商人資本だけに、特有な形式のように見える。しかし、産業的資本もまた、商品に転化し商品の販売によってより多くの貨幤に再転化する貨幤である。買いと売りとの中間で、すなわち流通部面の外部で、行なわれるかもしれない行為は、この運動の形式を少しも変えるものではない。」(同、一七〇頁)。
(12)「労働過程は、資本家が買った物と物とのあいだの、彼に属する物と物とのあいだの、一過程である。それゆえ、この過程の生産物が彼のものであるのは、ちょうど、彼のぶどう酒ぐらのなかの発酵過程の産物が彼のものであるようなものである。」(同、二〇〇頁)。
(13)同、二〇九頁。
(14) 「古典派経済学は、日常的生活からこれという批判もなしに『労働の価格』という範疇を借りてきて、それからあとで、どのようにこの価格が規定されるか? を問題にした。……他の諸商品の場合と同じに、この価値も次にはさらに生産費によって規定された。だが、生産費ーー労働者の生産費。すなわち、労働者そのものを生産または再生産するための費用とはなにか? ……経済学が労働の価値と呼ぶものは、じつは労働力の価値なのであり、……」(同、五六〇ー五六一頁)。このようにマルクスは、プルジョア経済学が「自分自身の分析の成果を意識していなかった」のに対して、プルジョア経済学に代わって自分がその成果を意識しただけだと、言っている。労働の価値とは、じつは労働力の価値なのだというマルクスの発見は、労働とは労働する行為という労働者の流動的存在状態なのだから、それを労働者とは別の対象として提えるには、労働者が持っている労働能力(可能性)として把握するしかない、というものである。これは、観点の切り替えであって、労働を価値(商品)と見なすプルジョア経済学の立場を離れるものではない。たしかに、労働の価値規定は科学的になった。が、同時に、労働力価値規定は、賃金を労働力の価格として、労働を商品とみなして、労働の取得が商品交換という合理的なものであるとするプルジョア経済学の地平に、マルクスを縛り付けることになるのである。したがって、労働から労働力という言葉の切り替えを分析しているアルチュセール(『資本論を読む』合同出版、二二 ー三二頁)が見出している「地盤の変更」とは、「科学的」なーープルジョア的なーー認識の進展にすぎないのである。
(15)同、一八四ー一八五頁。
(16)同、一八五~一八七頁。「こうしてこの独特な商品所持者の種族が商品市場で永久化される。」のであり、そのための費用が賃金である。労働者階級の維持の最低限が賃金額の原則であり、それを不変数(ラサールの賃金鉄則)とするか、それとも変数(マルクスの階級闘争論)とするかの違いがあるが、両者とも、賃金が労働の対価ではないとするところでは一致している。しかしマルクスは、ラサール批判の行き過ぎか、あるいは自分の商品交換法則にもとづく賃金論の整合性に酔っていたためか、賃金を労働力の(必然的に不払の部分を含む)対価であるとする。これは、資本制生産を奴隷制であるとする一方で、近代合理的なものとして捉えようとするプルジョア啓蒙家としてのマルクスの現われである。










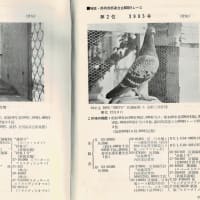

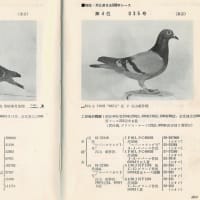







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます