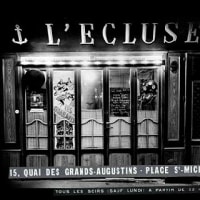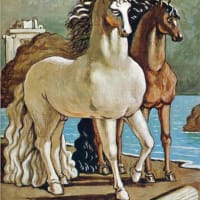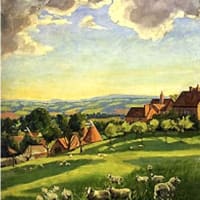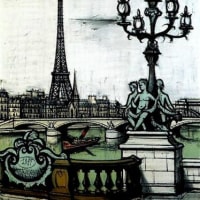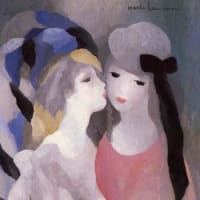うろ覚えなのだけれど、あるヨーロッパ映画で仮装パーティーをして、その人物を当てると言うシーンでのこと。「あっ、ネブカドネザル王!」
日本人なら世界史をしっかり学んでいなければ、ネブカドネザル王の名前も、ましてや顔や姿も思い浮かばないだろう。
こういうシーンもあった。
ケロッグのコーンフレイクを食べながら、話がケロッグ・ブリアン条約に及ぶのだ。
日常会話に、ケロッグ・ブリアン条約が出てくるとは、日本人の水準から見れば、ヨーロッパ映画のセリフはなんと、high-browなことだろう。
私は生涯に一度だけこの水準に勝るとも劣らない日本人同士の会話を聞いた貴重な?体験がある。だからこれを日本映画のセリフに使ってほしい。
エジプトを団体旅行中のホテルでの食事中の会話。一人は世界を何度も飛び回っている60代の日本人男性A。もう一人は元M新聞の編集長70歳くらいのB。
A: ロシアに革命はあっても、常に外からの反乱で内部からの覚醒した改革的反乱はあの国には皆無だ。
B: そんなことはない。デカブリストの乱があるでしょう。
正直、さすが元M新聞編集長は違うなと感じた。私ならせいぜいデカブリストの乱、1825年程度で「ナポレオン戦争に出征して自由の空気に触れて帰国した士官たちがツァーの専制政治に反対して、知識層と結んで起こしたニコライ1世即位の日の暴動」等というその性質まで知らなかったし、またそれまで知ろうともしなかった。
デカブリストの乱は、なるほど、その特異性にこそ、記憶されるべきものかも知れない。
そう言えばケロッグ・ブリアン条約も、国策遂行手段としての戦争の排除を約束した多分世界初の条約という性格を持つ筈だ。
また新バビロニアのネブカドネザル王は、イスラエルを征服破壊してユダヤ人をその首都バビロンに強制移住させた王。モーゼの苦労を水泡と化し、以後度重なるユダヤ人の悲劇的運命の開幕を決定付けた人物。
普通に世界史をやっておれば当然、身近に感じるべき人物なのかもしれない。
しかしこれは日本人がlow-browと言うより、世界史自体が西欧と日本では本質的に異なるためだと思える。地域によって、国によって歴史認識が違うのは、たとえば建築様式、音楽形式、宗教、民族などがそれぞれ異なるのに、おそらく比例しているに違いない。
単語や文法、発音等、言語が異なるのはその結果なのかもしれない。あるいは、その原因なのだろうか。
新しく言語を学ぶことは、もうひとつの新しい発想をマスターすることだと以前書いたが、それだけではない。別の国の国民になってゼロから人生を生き直すことだ。すべてを血の次元から生き直さなければ、母国語人と同じ距離でその言語を修得することは不可能かも知れない。
せめて形而上的にでもそういうアプローチを覚悟しなければ、外国人とスリリングな知的会話を楽しむことは永遠に不可能だろう。