朝日記170927 「あうふへーべん」と今日の絵(権兵衛が種まきゃ)
おはようございます。きょうは弁証法のおはなしです。
絵は(権兵衛が種まきゃ)です。
いま、メディアがさかんに煽っている(私の偏見でそうみています)さる女性政治家に注目します。このひとが突如として ドイツ語の「あうふへーべん」という語を持ち出して、周りを煙に巻いています。そして、意味は説明せず、自分で調べろと突き放していますね。 多分、緻密なことを説明することは嫌いなのでしょう。
ここでは、ご本人は多分、理解しているとしまして いかのふたつのドイツ語を中心にこの「あうふへーべん」をあぶりだします。おつきあいください。
徒然こと 1 Aufheben
徒然こと 2 Dialectic
徒然こと 3 小池百合子さんのいうAufhebenとはつぎの三つのどれでしょうか?
~~~~
徒然こと 1 Aufheben
(1. Aufheben 止揚)
From Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Aufheben
Aufheben or Aufhebung[1]という語はドイツ語である。この言葉は一見 いくつかの矛盾する意味をもっている。 拾う、 捨てる、解約する または 中止する、または止揚するである[2]。この「止揚」という語につては、さらにつぎのように定義される、棄却する、保持する、そして超越するである。 哲学では、aufheben(アウフヘーベン)は、Hegelによって使われ、課題と反課題antithesisが関与するときに何がおこるかを説明し、この意味で、止揚という用語で翻訳している。
ドイツの哲学者Walter Kaufmann カウフマンは、Aufhebungという語を pick upと翻訳している。これは通常のドイツ語とまったく共通している: いま、或るものが床に落ちているときに君はどうするか? この「或るもの」は拾われよう。それは、「或るもの」がそこにもはや存在していないことを命ずるものである;そして、君はそれを大切に保持するのである[3]。Kaufmannもまた、言う、ヘーゲルは、あるものが拾われる、そのことは、そのものがそこにあったが、すでにそこにはなくてよいという指示のもとで拾われる。それにも拘わらず、そのものは、どちらにあるとも棄却されない、しかし、それは異なる水準の上にあるというものである[3]。
英国のマルクス派の雑誌Aufhebenはこの概念からの名前である。
英語ではsublationという語を当てている。 sublationは、弁証法上の機能であるmotor駆動力であり、ヘーゲルの論理的システムのもっとも根底レベルで働くと見られている。
歴史的progress進展についての彼の概念は、らせん状的なdialectic弁証法に従う。ここでは課題は反課題によって反対されるが、これ自身が、synthesis合成によってsuglate止揚されるのである。
ヘーゲルは言う;Aufhebeは、その歴史的進展からのくるユニークな事例になる、そこでは、すべての時間に亘って真であると想定され、das absolute Wissen ("absolute knowledge")絶対知として、さらなる進展による変化はないとしている。
徒然こと 2 Dialectic
(2. Dialectic 弁証法)
From Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic
Dialectic or dialectics (Greek: διαλεκτική, dialektikḗ 弁証法は、ひとつの課題についてpoints of viewことなる見方をもち、reasoned理性的な議論を通してtruth真理を確立したいとする二人以上の人たちとの間でのdiscourse言説である。
哲学において、弁証法はmethodology方法論を含んでいる。これは哲学的対象の吟味と認知のために使われる。
弁証法は、その使用者に命ずる;他の対象との関係においてその対象を吟味せよ、そして、全体のシステムへの関係を吟味せよ、さらに動的進化の環境のなかでその対象を吟味することを命ずる。
弁証法は、通常、metaphysical method形而上学的方法と対比される。形而上学では、その対象が、分離され、孤立されそして静的環境のなかで吟味している。
弁証法は 英語のdebateという言葉でいわれている論議とは同義語ではない。Debate論議では、彼らの視点には感情が伴っていることを必要としない。Debate論議は、反対者への説得をともなって勝利する。そこにはこちら側が正しく、反対側が正しくないことを証明することを経て、判定者が判定する。判定は、判定者、裁判官、group consensusグループ合意によってしばしば決定するのである。
弁証法という語はまた、華麗な言語表現であるレトリックrhetoric という語とも同義ではない。この語は言説の手法や技である。これは聴衆を説得し、案内し、動機付けることを模索するものである[1]。 "logos"のような概念や、"pathos"のような合理的なアッピール、そして"ethos"のような倫理的なアッピールは、聴衆を説得するrhetoriciansによって意図的に使われる[2]。
徒然こと 3 小池百合子さんのいう Aufhebenとはつぎの三つのどれでしょうか?
答え1.弁証法での「止揚」を採る
弁証法dialecticsは、ギリシャにさかのぼる古典時代の歴史のある真理を見出す手法です。 この方法の前提は、考える対象について 正と反のふたつの論理で戦わせるもので、その結果 あたらしい課題へと昇華つまり止揚していく方法です。 そして限りなく絶対的な真理のレベルまで到達するという思考手段です。 ものごとの動的な変化を通じてものを知るというものです。
答え2.論議法debateでの判定として「止揚」と呼ぶ。
欧米で、いまの主流の論議法debateは、ひとつの提案に対して、それに対する提案をする場合に、あくまでも対象そのものに対する理解の仕方が、どちらが正しいかをのみ問う。ここに感情は入り込まないように配慮することが前提です。 勝ち負けは判定者の判定によるというものです。 こでは正反のふたつの論議から合成されるいわゆる’真理への階段’を考えていません。
答え3. レトリックとして、他人、聴衆に対して説得をして、自分の意に同意させる表現の技の行使を意味する。意見の異なるひとたちも、これから違いを論議して、あるいは話し合いで互いを理解し、仲良くしましょうという説得術を「止揚」とする。 レトリックというのは、対象について 論理の追及ではなく、言辞の中での論理の一致にのみ意をはらい、聴衆にアッピールして説得するものです。
さて、小池さんのいうAufhebenは、うえの「答え」のどれでしょうか。
読者のみなさま、当ててみてください。
以上。


(権兵衛が種まきゃ)



















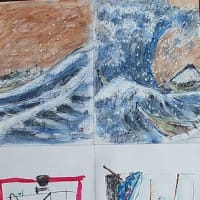





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます