朝日記191113 これからポーランドへの旅、つれづれ思うこと
まさに徒然ことを書きます。 (ペルシャの陶器から)
(ペルシャの陶器から)
 (ペルシャの陶器から)
(ペルシャの陶器から)徒然こと1 畏友AB氏のメモから
徒然こと2 ポーランドへの旅 私のメモ
徒然こと3 ポーランドの旅 アウシュヴィッツを訪ねようか。
徒然こと4「広島、長崎の原爆投下」に行きつくやすい」
徒然こと5 映画『肯定と否定』ホロコーストがほんとうにあったかという映画
YouTube The PAGEから
~~~~~
「G20サミット1日目が終了 狂言師の野村萬斎さんらが歓迎行事(2019年6月28日)
28日に大阪市で開幕したG20大阪サミットは1日目のセッションが終了した。夜には、大阪城公園の大阪迎賓館で各国首脳らを歓迎する文化行事と夕食会が開かれた。文化行事では、狂言師の野村萬斎さんによる狂言、ピアニス...」
~~~~~
徒然こと1 畏友AB氏のメモから
日本流の美と西欧流の美を極めて高いレベルで示すことが出来たと思います。
明治維新とは独自の美学を持つ国が西欧列強の取り仕切る世界に一人前に参加した世界史上の一大イベントだったのではないかと思います。
そして、有色人種の野蛮な国家と思われていた日本が実は西欧諸国の範となるべき高い倫理観を保持する世界最長の国家であることに一種の畏れを抱いたのが20世紀前半であったように思います。
将来だれかが地球史を書くなら、帝国主義に汚染されてアジアを蚕食していた欧米列強がなぜ日本を侵略しなかった(できなかった)のか、その日本がなぜ植民地化されたアジアの解放のために大東亜戦争を行ったのかが語られると思います。
帝国たちに簒奪されるだけの植民地だらけの世界では日本が日本らしく生きていくことはできなかったのでしょう。
日本はWW2では敗戦しましたが、負けても植民地を開放できればいずれ日本が活躍できるという「読み」はあったと思います。
原子力爆弾という「反人類的兵器」を使われるという想定外の事件がありましたし東京大空襲のような大殺戮もありましたがそれでも復活する日本は凄い国だなぁと思いました。
徒然こと2 ポーランドへの旅 私のメモ
ABさん、よくぞそこまで言明されました。同感します。WWIIは、世界秩序の覇権戦争であったとおもいます。
フランスの哲学者のコジェーヴが指摘したように権威の根源は父性、腕力、賢者、裁判といったものがあり、実際はその組み合わせですが根源は、腕力です。
腕力の所有者に理を期待するのが根底としますと、WWIIは、その腕力の所有者の優勝戦だったのでした。
その結果、優勝したのは端的にアメリカであります。そして彼らアングロ流の政治価値観が規範になります。これが現在の世界秩序となりその価値文脈のなかで歴史が現在の正統な歴史観となっているといえます。この場合、仮にドイツが戦勝した場合での価値をもって歴史をみることは暗黙裡に禁止されます。ドイツの哲学者ヤスパースあたりは、その「責罪論」のなかで、したがって、爾後の世界秩序の形成維持の責任はひとえに戦勝側にあるからしっかりしてくれと言い切ります。
思うに、戦後体制の特徴として、ドイツと日本が戦勝アメリカにひたすら忠誠を尽くすという図になります。アメリカは、米州全体をみずからの利権の元に納めていたとはいえ、英国やフランスなどの主流の植民国家とは別の新興国家であったので、その意味で植民の支配の負の遺産が軽かったとおもいます。少なくとも大戦終了時点のことですが。 世界は自由市場主義経済のもとでの機会均等主義、そして徹底的に競争原理を前に出しました。当時の世界の富の7割を掌握していたこともあり、これによる世界支配でした。ソ連との冷戦経過で、結果的に独や日に対して、戦争賠償は要求せず、むしろ、白頭のワシの翼の元での経済復興を援けます。そして、現在は、独と日にアングロ支配体制の幹事メンバーとしての地位を与えた構造です。 個人の尊厳と自由、平等原理の規範の大義名分があって、その基盤を根拠にする。したがってその根底を覆えす価値理念は徹底的に押しつぶすレジーム原理です。戦後のドイツや日本の経済復興はかれらのレジームの成功ショールームでもあったともいえます。
徒然こと3 ポーランドの旅 アウシュヴィッツを訪ねようか。
話は違いますが、ありがたいハップニングで、今週末ポーランドに旅行します。社会人になった孫娘の一人旅へのまことに頼りがいのない付き添いという機会がめぐってきました。 この娘が、なかよしの学友がすむこの国で久闊を叙すという休日ものです。ワルシャワ空港からの陸上交通で3時間ほどクラクフというこの国の古都に2日ほど滞在します。王族の城や古都の街並み、Salt Mineという塩の鉱山もあります。しかしここでの最大の観光スポットは、此処からバスで1時間余のところにあるアウシュヴィッツ収容所跡です。わずかな日数でここに1日を割くことは、如何かとは思いますが、一人で行ってみようと思っています。
私の朝日記などでも、映画「ハンナアレント」からはじまり、彼女の「全体主義の起源」に触れましたが、ユダヤ人へのホロコーストが全く合法のもとに公開のもとに行われたこと、それがなぜ可能になったのかという問いであったと思います。戦後にアルジェンチンでイスラエルの官憲によって逮捕されたあのひと、そう、にアイヒマンも、ごく普通にはたらく官吏で、かれは淡々として自分の業務を実行していく。また、ナチスが残したドキュメントは想像を絶するほどの正確精緻なものであったと記します。合法であれば正しいとするドイツ人の価値観にたいして、この事態に対して、人間としてなにもなし得なかった罪は、いったい何処に帰するのかという問題への解は、いまだに見いだされていないとアーレントは書いていたと思います。ヤスパースにもどれば、合法であるが本質的なところで良心に反するという状況には、理性原理が、働かないとみます。それを人類の神に対する「原罪」として置き、哲学的には、「形而上学的罪」とおきます。非キリスト教文化の我々には、非常に分かり難い帰着意識です。敢えていえば、個人個人がもつ人類共通の罪への倫理問題として位置付けようとするものであろうと解します。(日本人としてならどうとらえるでしょうか)
しかしながら、それからの展開はどうなったか。国連憲章はカントの道徳律を基盤としてまとめられたとききます。個別の宗教を越えた形而上学的規範をして人類は共有すべきと呼びかけます。しかし、それからの内省は、その後どうあったかは 御存じのとおりです。(哲学の死か)
ドイツ人自身は、ドイツ基本法をその前文に、西側の平和勢力に同意して立法化する根拠としました。戦後体制の価値規範に恭順の意を示した形になっています。日本の現憲法の前文も、その意味では価値規範の恭順となります。ここでは当然ながら自らの哲学による発意ではなく、勝者に恭順の姿勢を示すことが、大前提となっています。
その意味では、敗者としての「価値理念」のくびきにつながれているとみることもできるとおもいます。あの旧約(聖書)でのユダヤ人のバビロン捕囚を思い起こすまでもなく、なお、戦後世界体制の中の「捕囚」の状態にあると思います。
勝者側の理念からの規範、つまり現実の「規範理念」では、現体制の中の価値規範に位置づけられた国家であることになります。その元で、主権国家の形態をとみることができるとおもいます。思うに、ここでの本当の勝者は、アメリカで、本当の敗者は、日本とドイツであるとみます。現レジームは端的には、この敗者二者を取り込んだ「ローマ」つまりアメリカ合衆帝国の形成とみます。
敢えて勝者を加えるとすれば英国とイスラエルくらいかましれません。日本やのドイツは基本的「規範理念」に則り、この大「帝国」を根底にて支えるところ(属州)であるとみます。 この根底認識がぶれるとその報復は過酷であり、大悲劇を招来することになります。
つまり帝国なのです。
徒然こと4 「広島、長崎の原爆投下」に行きつくやすい」
さて、その上で、このお話しの最初の「形而上学的罪」を考えることから免れるかという課題がのこります。ホロコーストについての考える問題と類比の先は、「広島、長崎の原爆投下」に行きつくやすい。
昔、もう半世紀前のことですが、私の留学先のアメリカの大学の学生寮の生活を思い出します。同室のルームメートが生粋の東部ボストン出のアメリカ人でした。かれとはおおむね仲がよかったとおもいます。そのなかで、ひとつだけ、深い落胆をしたのは、以下です。たしかトルーマン(アイゼンハウアーであったか)の死去のニュースに接して、彼との会話が必然的に原爆投下の話に至った時、彼は決然として、真珠湾奇襲への報復であり、戦争終結を早めるためにとられた国際戦時法上、合法的なものであると主張しました。
これは、アメリカ人は総じて、彼と同じ見解であることをそのあとで知ります。しかし、ここには、上でいう「形而上学」問題を彼らの内面に曳いていくと感じました。合法であっても、一般市民を殺戮したそれをなすべきではないというの意識は、その国民に重くのしかかるのではないかとみます。 日本人も、それについて一貫して口を閉ざしています。 その意識が、人類の平和という次元を高めた形で、直接には、彼らに責罪を迫らない状況とおもいます。 これは意識にも歴史観の次元に立ち返ることを避けているともいえます。隣の国が日本が歴史を顧みないということを喧伝しますが、我々は、意識的にこれを避けているともいえます。決着のついたものは、深い眠りにつかせるともいえましょうか。
徒然こと5 映画『肯定と否定』、ホロコーストがほんとうにあったのかという映画
名前をわすれましたが、英国の孤独な評論家で、アウシュヴィッツでは、ホロコーストがほんとうにあったのかと投げかけたひとがいます。思い出しました、D.アーヴィングとうひとです。 これに対して、アメリカのユダヤ人女性学者が敢然と立ち、大弁護団を形成して、ロンドンで裁判になる。結局、この孤独な評論家の論証記述の痂疲を突いた形で、裁判は結審し、彼は負けます。これは昨年確か『肯定と否定』という題名の映画でした。 この評論家は、幼少の時からヒットラー贔屓であったこと、英国のドイツの一都市(あの美声のピーターシュライヤーがいる都市)への絨毯爆撃の執拗さを調査して、その実態を世界に公表して一定の評価を得た人であった。そして、ホロコーストへの疑念としてアメリカ人女性教授への訴訟を起こすというものです。私が興味を持ったのは、彼が触れることのタブーになっている「理念規範」への挑戦であると素朴に感じたからでした。裁判の結果は、だれも想像しうるものでありますが、変人として言論界から疎外されても、それを行う勇気に畏敬の念禁じ難いものがあります。そしてそれが発揮できたのは、彼が英国という勝者にいたことでもあり、それ故の一方の良心のありかたという点に興味を持ちました。敗者という「捕囚」としての「理念規範」のくびきがあっても、見るべき考えるべき焦点をしっかり見て置くことの価値を失うべきではないという心情責任を感じるからであります。つまり「形而上学的責任」とはという課題になりそうです。 ポーランドの旅はどうなるか、覚束ありませんが、旅の報告は後日いたします。
~~~~~
参考まで
この朝日記に関連がある過去の朝日記は以下です。;
1. ホロコーストに関連したもの
記180112 映画「否定と肯定」 見るまえと見たあと
2. 朝日記で触れたハンナアーレント
2-1. 朝日記180517 ハンナ・アーレント「全体主義の起源」を斜め読みすることと ...
17時間前 - 朝日記180517ハンナ・アーレント「全体主義の起源」を斜め読みすることと今日の絵きょうは以下ハンナ・アーレントがテーマです。今日の絵は(さらわれたあねこ)です。 徒然ことハンナ・アーレント「全体主義の起源」を斜め読みしてみること ...
2-2. 朝日記131113 ハンナアーレントのこと と今日の絵 - Yassie Araiのメッセージ
朝日記131113ハンナアーレントのことと今日の絵おはようございます。まもなく日付がかわります。徒然こと1「ハンナ・アーレント」の映画を見て「ハンナアーレント」という映画がいま岩波ホールで上映中です。アーレント(1906-1975)は「全体主義 ...
2-3. 朝日記140325 <偶感二題> 映画『ハンナ・アーレント』 - Yassie Araiの ...
2-4. 朝日記140325<偶感二題>映画『ハンナ・アーレント』と山本七平『空気の研究』 偶感一「ハンナ・アレント」の映画を見てその1アレント「ハンナ・アレント」という映画が昨年( 2013)の秋に話題になりました。アレント(HannahArendt1906-1975) ...
朝日記140326 <偶感二題>偶感二 山本七平『空気の研究』からおもうこと
2-5. 朝日記180529 Ruth Benedict 「菊と刀」をななめによむことと今日の絵
我々のなかにある価値原理つまり個人としての倫理と集団としての道徳律(社会倫理)に
ついて考えるテキストとしてあげておきます。この辺は、たくさんの日本の著書があります。 和辻さんあたりからもう一度出発するもよし。学徒動員で戦地に赴いた人たちのポケットにカントの哲学書のあったことをときに思いを馳せます。
朝日記180529 Ruth Benedict 「菊と刀」をななめによむことと今日の絵
https://blog.goo.ne.jp/gooararai/e/a780fcd27163a4b5e01b433161d7c83d
2-6.ハンナ・アーレント 朝日記の画像
以上

















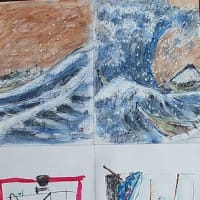








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます