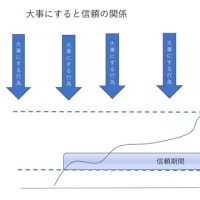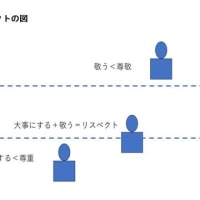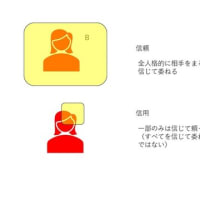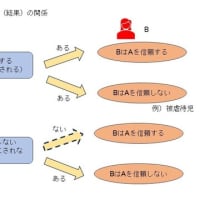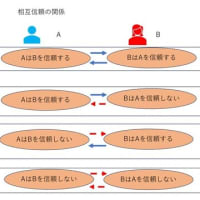2024年12月6日~2025年1月23日にかけて、Soarさん主催「ウェルビーイングをつくりあう対話の実践を考える」に参加しました。
このコースについて、詳細は割愛しますが、以下のような内容で構成されていました。
(以下の解説に一部上記の案内を引用して再構成)
・第1回 12月6日(金)テーマ:「オープンダイアローグ」
精神科医でオープンダイアローグのトレーナーである森川すいめいさんが講師。「オープンダイアローグ」はフィンランドの精神科で生まれたメンタルヘルスケアのアプローチ。実際にミニダイアローグの実践がありました。
・第2回 12月17日(火)テーマ:「トラウマインフォームドケア」
児童精神科医で一般社団法人Everybeingの共同代表である小澤いぶきさんに、トラウマインフォームドケアと人のウェルビーイングの関わりについてお聞きしたのと、ウェルビーイングカードなどを用いて参加者が対話しました。
・第3回 1月7日(火)テーマ:「当事者研究」
「当事者研究」は、個人が自分の困りごとや生きづらさについて研究者となり、周囲の仲間たちと語り合って、理解を深めたり、自分とのよりよい関係性を探求する試み。2001年に北海道にある社会福祉法人浦河べてるの家から始まり、今では全国に広がり、現在様々な場で実践されているということです。実際にセミナー運営側スタッフを当事者として当事者研究の手法を使ったデモンストレーションがありました。
第4回 1月15日(水)テーマ:「システムアウェアネス/ワールドワーク」
システムアウェアネスは、プロセスワークをベースに、日常のアクションにより結びつきやすい形に再構築したものだそう。システムアウェアネスコンサルティング代表の横山十祉子さんが講師。オンラインでどのようにプロセスワークを行うのかというところが興味深かったのですが、演じる人物をホワイトボードに配置し、参加者が自由に移動したり発言することである程度リアルの場での再現ができる仕組みになっていました。
第5回 1月23日(木)テーマ:「ジャーナリング」
情報学研究者のドミニク・チェンさんが講師。一般的にジャーナリングとは、頭に浮かんでくる自分の思考、感情、経験を自由に書き出すことをいうわけですが、ドミニクさんが大学で行っている授業では、単にテキストを書き出すということを超えた様々な演出手法が展開されていて興味深かったです。
さて今回の5回のセミナーでの体験で、自分が共通して感じたコンセプトは次の3つ。
1)オープン性、オープンマインド
心も脳も開いていくということ。自分自身にも開かれ、相手にも開かれるとき、自分が拡張していくのだなと思いました。そのためには、そういうオープンマインドしても大丈夫である環境づくりが重要になってくるということ。
2)探求
自分が探検したことのない未知の領域を意識して体験していくこと。
特に当事者研究やジャーナリングの回には、探求という立ち位置の重要性を感じることができました。例えば深刻な悩みがあったとしても、それを探求する対象としてしまうことで、深刻さやネガティブ感情を抜きにして解決へ向かうこともできると・・・
3)俯瞰
探求するときに個人の個に入り込めば深堀っていけるけど、ある意味、視野狭窄に陥る危険があります。自分を高い位置から俯瞰して客観的になれることもまた重要。
それぞれの回のエッセンスを思い出したり使ってみることで、より探求的な自分に出会えるような気がしています。